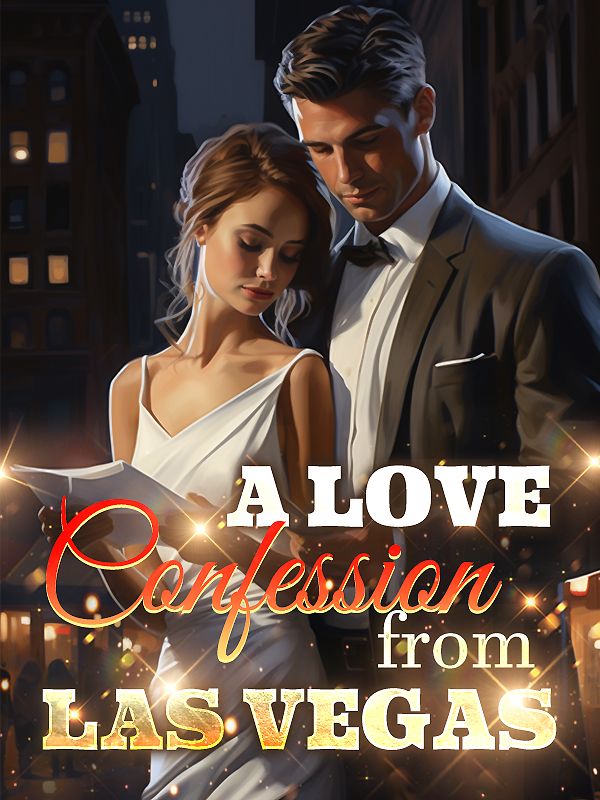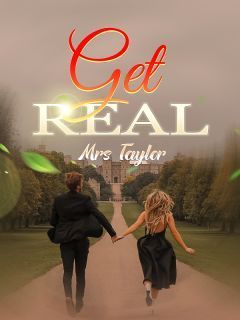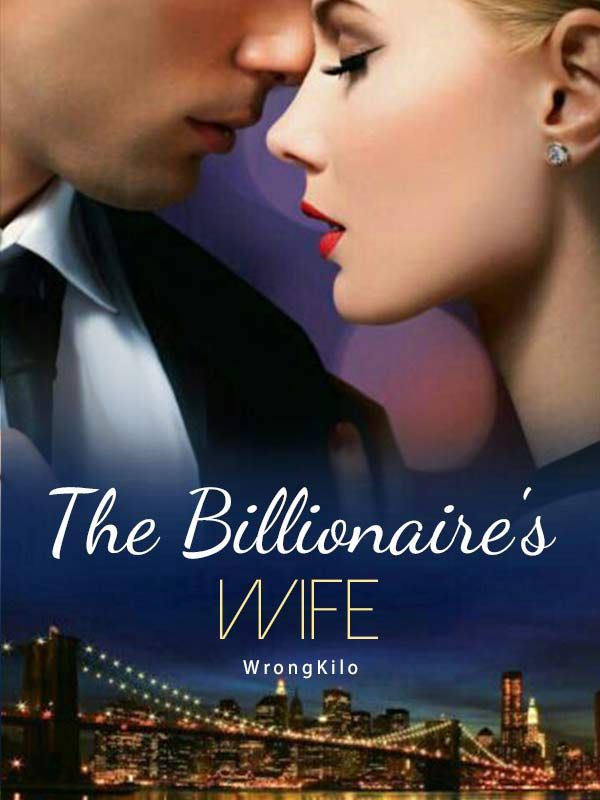いつもの日とは違う、すごく良い天気だった。太陽の光がいつもと違って見えて、なんか変な感じがしたんだ。
昨日の夜、あんまり寝れなかったんだよな。それが原因かも。記憶が邪魔して、全然眠れないんだ。
彼女の夢を見るのは久しぶりだったのに、まだ頭から離れないんだ。最近は彼女の夢ばっかり見るし、夢の中の彼女は裸で現れて、俺をからかってるみたいなんだよ。
「おはようございます、ワイルダー先生」病院のロビーに入ると、ハンナが挨拶してきた。
彼は頷いて挨拶を返すと、その子は顔を赤くした。ハンナが何か言おうとしたけど、電話の音に遮られた。
誰からかかってきたのか見て、ため息をついた。なんで電話してきたのか、もう分かってる。
昨夜も何回か電話がかかってきたけど、全部無視したんだ。電話に出たくなかったけど、今回はそうもいかないって分かってた。
「昨夜、デートをドタキャンしたのはどうして? 今どこにいるの?」母親がすぐに尋ねてきた。
「病院だよ」
「また?」
「俺、医者なんだから、ママはさ---」
「そうあるべきよ」母親は言った。彼女の声から嫌悪感が伝わってきた。
「おかしいわ、ワイルダー。もう我慢できないわ。あなたが好きなものにコースを変えるのを許したけど、もうすぐ最初の学位を取得できるのに、あと一歩のところだったのに。」
母親が怒るだろうことは分かってたんだ。
「会社のCEOになれたかもしれないのに。私達はあなたの選択に賛成はしなかったけど、応援はしてたの。でも、今回はもう許さないわよ。結婚して家族を持った方がいいわ。私が用意したお見合いを断ることはできないわ。また夕食会をセッティングするから、絶対来なさい---」
「行けないよ、ママ」
「どうして?! あの子のことなの? いい加減にして、もう5年も経ってるのよ、ワイルダー! 前に進みなさい! 彼女はクレイジーな女だったし、あなたの人生からいなくなってくれて本当に良かったわ。あなたがあの道に進むきっかけになっただけでも十分だわ!」
彼は唇を尖らせて、深呼吸をした。
「彼女はクレイジーじゃないよ、ママ」
「それなら、あなたがあんな風に生きていたら、私がクレイジーになるわよ。落ち着きなさい! あなたの年齢なら、結婚して、家族と子供がいるべきよ! 私の友達の中で、孫がいないのは私だけよ!」
彼は黙っていた。母親が孫を欲しがっていることは知っていた。話すたびに、それについて話していたから。
「まだ準備ができてないんだ、ママ---」
「準備ができてない? それとも、まだあの女の子を待ってるの? いい加減にして、息子。彼女はあなたにふさわしくないわ。前から言ってたけど、彼女はクレイジーだった---」
母親の言葉に、彼は歯ぎしりした。彼は精神科医で、心の病気を専門としていて、それについての啓発活動をしているのに、母親は精神疾患が本当だと信じず、嫌なことを言う。
「もう行かなきゃ」そう言って、電話を切った。
失礼なことはしたくないけど、ママとも喧嘩したくなかったんだ。
何年も、このことばかりなんだよ。
「ワイルダー!」誰かに呼ばれて、彼はハッとした。
「あっ、ワイルダー先生だ!」
「ちゃんと呼びなさいよ、リジー!」隣の男がからかった。
「ワイルダー・カラザール先生!」
彼らは彼の方向に歩いてくると、彼は首を振った。
「まだ朝なのに、なんか悪いことでもあったみたいな顔してるね?」
ワイルダーは首を振った。
「悲しい顔してても、やっぱりかっこいいね。あんたとは違うよ、カイル。何も変わらないもん。悲しい顔してても、嬉しい顔してても、同じ。全然かっこよくない。」
「ったく、よくもそんなこと言えるな?」
「本当のことじゃん! ね、ワイルダー?」
「やめなさいよ、二人とも。まるで喧嘩してるカップルみたいだね」
二人は全然賢くないんだよな。リジーは顔を赤くして、カイルはゴクリと唾を飲んだ。
彼はニヤリとした。明らかに、お互い好きなのに、照れくさくて言えないんだよな。
「あ、あの、どういうこと? ワイルダー?」彼はぎこちなく笑った。
「そうだよ、ワイルダー。何言ってるの? カイルは俺のこと好きだよ。彼は君のファンボーイなんだ。彼はゲイだって確信してるよ」
「先生!」
ミナに声をかけられた。
「先生のオフィスに子供がいるんです。駄々をこねてて、どうやって入ったのか分からないんです。叫んでるし、先生の物を壊してるんです!」
オフィスに行くと、二人は子供の姿に口をあんぐり開けた。
「あれは子供? それともリトルモンスター?」カイルが尋ねた。
ミナは本当のことを言った。子供は彼の書類を投げまくってて、中には患者さんの秘密が書かれたものもあったけど、今は床に落ちて、くちゃくちゃになって濡れてるんだって。
「どうやってここに入ったんだ?」
子供は彼らの方を向き、眉をひそめて、唇を突き出している。
リジー、カイル、ミナは顔をしかめたけど、ワイルダーだけは違う。
「ヘイ…」彼は子供にすごく慎重に話しかけた。
ゆっくりと近づく。子供は紙をくちゃくちゃにするのを止めた。
「イヤ!」子供は彼らが自分をオフィスから追い出すことを知っているみたいで、ワイルダーは微笑んだ。彼女は天才的な子だけど、彼はそんなことしない。
「名前は何て言うの?」
子供の目はキラキラ光って、言葉を発した。
「ノナ」
「ママはどこ?」
彼女は首を振った。彼はひざまずいて、彼女の丸い茶色の瞳を見た。ある人によく似ている子供を見て、彼はタバコを吸うのをやめられなかった。
「やあ、ノナ。僕はカラザール先生。ここは僕のオフィスだよ。パパとママが見つかるまで、ここにいる?」
小さな女の子は頷いた。
「いい子にしてられる?」
彼女は尋ねた。「これで遊んでいい?」
「それはおもちゃじゃないけど、」彼は本棚のミニテディベアに手を伸ばした。彼にとってすごく大切なもので、彼が唯一愛した女の子からのプレゼントだった。誰にも触らせなかったのに、今回は、まぁいいか。子供に触らせてあげたんだ。
小さな女の子はワイルダーの回転椅子に座って、彼がくれたもので遊んでいた。
「スタッフと警備員に連絡して。子供の両親がまだここにいるかもしれないから」ワイルダーはミナに言った。
彼女はすぐにワイルダーの言いつけ通りにした。
「わあ、先生、優しい!」リジーが言った。
「先生って、女の子に、子供にまで、違う効果があるんですね!」
「うるさいよ、カイル」
「冗談だよ! ノナ、可愛いね!」彼は笑った。