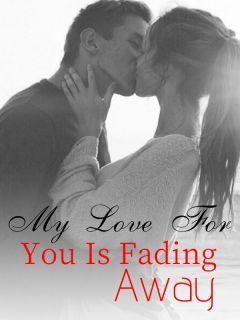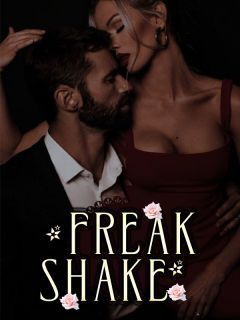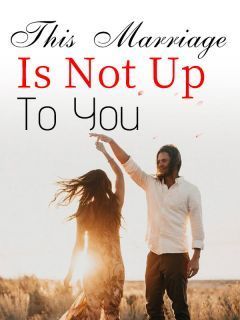母の声が名前を呼ぶ音で飛び起きた。朝が苦手なのはうちでは有名で、これはいつものモーニングコール。完全に目が覚めたけど、ベッドから出ないで、母がドアの外で少しの間叫び続けるのを待った。
「カタリーナ、マジで?」 部屋のドアを開けた母の息を切らした声が聞こえた。唸りながら頭を起こし、母の鋭い青い瞳と視線を合わせた。
私の明るい青い瞳は、美しくも厳しい母から受け継いだ数少ない特徴の一つだった。妹は、スレンダーな体型、カールしたブロンドヘア、日焼けした肌、高い頬骨と、ほぼ瓜二つだった。「家族のいいとこ取り」と母は、私が聞いていないと思ったときに言った。父も見た目が悪いわけではなかったが、がっしりとした体格で、何年も前にパックを守るために負った顔の傷があった。私の家族の女性陣は皆スレンダーなのに、私の体は曲線的で、胸とヒップは成長を続けたが、それ以外は変わらなかった。髪は父と同じチョコレートブラウンで、ピンのようにまっすぐで、肌も同じように青白い。顔に血が上ると赤くなるだけだった。髪の唯一の救いは長さで、夏にずいぶん伸びて、今では腰をはるかに超えている。私の顔は丸くて若々しく、実際の年齢よりずっと若く見えた。
身長は別の問題だった。私の家族の女性は男性よりも背が高い傾向があり、母は父より数インチ背が高かった。私は身長遺伝子を完全に逃した。わずか5フィート3インチで、母も父も私よりずっと背が高かった。妹も何年もかけて私を追い越してしまった。成長するにつれて、両親は私が彼らが想像した娘ではないことに気づいた。頑固で反抗的で、従順でない。それが母が私のことを説明するときに使った言葉だった。兄のヴァレン、パックの将来のベータは、私の頑固さを隠された強さとして見ていた唯一の家族だった。彼らは妹のアリアがいることに幸運を感じていた。母はしばしば、良いメイトにふさわしい完璧なお嬢様だと彼女を褒めていた。
「起きてるよ」と私は溜息をつき、今日は忙しい一日になることを恐れた。
毎年、ムーンボールは別のパックの領土で開催される。今年は私たちのパック、つまり私の家族が所属するブルー・ムーン・パックの番だった。ムーンボールは、若いオオカミたちがメイトを見つけるのを助けるために設計された、精巧でロマンチックなイベントのはずだった。私は今まで毎年イベントを首尾よくスキップしていたが、今年は逃れようがなかった。
心配するのはやめた。恐れることは何もない。ただボールに出席し、誰も見ていないときにこっそり抜け出して、残りの夜を一人で過ごすつもりだった。私のオオカミのローズは、私がメイトを見つけることに無関心なのを見て目を丸くした。彼女も私の考えにためらいを感じていたが、私の理由は理解していた。これまでのことを考えると、私が熱い狼のメイトになることはあり得なかった。
「起き出して着替えなさい!ヴァレンはすぐに来るわよ!」 母は私に鋭い視線を向けながら、きっぱりと言った。アリアが部屋をのぞいていた。
ヴァレンのことをほとんど忘れていた自分を叱りながら、母をなだめるために着替えるふりをしてベッドから出た。最後に不賛成の視線を送ると、母はため息をついて後ろでドアを閉め、私にいくらかのプライバシーを与えた。
ヴァレンは、隣のパックを訪問していたときにメイトを見つけた。数ヶ月間一緒に過ごした後、彼はついに私たちに紹介するために帰ってきた。彼にまた会えると思うと、興奮を抑えきれなかった。私の家族の他の人たちとは異なり、ヴァレンは私の性格を欠点とは見なさず、単に「やんちゃな妹」と見ていた。
あまり考えずに、黒いオフショルダーのトップスと破れたデニムのショートパンツをつかみ、急いで着替えながら、2人の親友にテキストを送るために携帯電話を取り出した。グループチャットを作成し、ヴァレンについてメッセージを送った。2人とも彼を歓迎したかっただろう。
*私 - 10:55
-みんな起きてる?ヴァレンはすぐそこだよ!
*レイヴン - 10:56
-当たり前じゃん!みんながみんな一日中寝るわけじゃないんだから!
*私 - 10:57
-何て言うか、私はベッドと真剣交際中!
*ギデオン - 10:58
-クソッ、まだ来てないんだよね?5分で行くよ!プリンセス、本気のやつあげられるよ ;)
*レイヴン - 10:59
-キモっ!!!私も行く!
携帯をもう一度確認せずに、使い古した靴を履いて階段を半ばよろめきながら降りた。朝食を食べ損ねたことをよく知っていたので、パントリーからブルーベリーマフィンをつかんで食べ始めた。甘い美味しさにうめき声を上げそうになったとき、友達のいつもの声が聞こえた。
「レイヴン、ギデオン!寄ってくれてありがとう!」 母の過度に甘い声がリビングルームから響き渡った。目を見開くのを抑えながら、私はリビングルームに向かい、顔に広がる笑顔を止めることができなかった。私の親友2人がそこに立っていて、私を家から連れ出そうとしていた。
レイヴンとギデオンは、私が覚えている限り、ずっと私の親友だった。レイヴンは甘くて従順な女の子に見えるかもしれないが、彼女にはワイルドな面があった。彼女の茶色の目はいたずらっぽく輝くことが多く、小さな唇は何か無謀なことを考えているときはいつでもニヤリとした。ギデオンは、女性が男性に完全に従順であることを期待しない、私たちのパックの数少ない男性の一人だった。レイヴンとギデオンはどちらも年々見た目がよくなり、多くのパックメンバーの注目を集めていた。しかし、このパックでは、女性がメイトなしの男性と友達になることは良くないとされていた。
ギデオンとレイヴンを初めて家に連れて行ったとき、母はほとんど気が狂いそうになった。彼女は2人が去った後、1時間も叫び続け、もっと責任感を持って、将来のメイトを尊重することの重要性を私に説教した。私のメイトは、私がメイトなしの男性と友達になることについてどう思うだろうか?メイトに会うまで、他の男性の誘惑に抵抗できるだろうか?私はこれらすべてを思い出し、目を丸める衝動を抑えた。過去の経験から、男性の誘惑に抵抗することは、あまりにも簡単になっていた。確かに、ギデオンはフレンドリーだったが、それは無害で、彼は誰にでもフレンドリーだった。
リビングルームに入ると、ギデオンとレイヴンの顔が明るくなった。レイヴンの目にいたずらっぽい顔色に気づき、彼女が何を計画しているのかと疑問に思ったが、あまり嫌なものでなければいいと思った。
「みんな、外に行って!ヴァレンは数分で来るわよ!」 母は興奮してさえずり、長男と将来の義理の娘の到着を待ち望んでいた。母や階段を下りてきたアリアをもう一度見ることなく、私の友達と私は外に出た。
私たち3人は、過去何年にもわたって何度もそうしてきたように、玄関の階段に座った。私は、レイヴンの声が私の思考から私を引き離すまで、無意識のうちに階段の剥がれた白いペンキをつついていた。
「このボールには本当に行きたくないんだよね?」 レイヴンは笑いながら、細い眉毛を上げ、私の顔のしかめっ面を見ていた。
「うん、本当に行きたくない。前半は出ると思うけど、スピーチが終わったら、逃げるつもり」 私はうなずき、笑顔の親友にニヤリとした。
「もしよかったら会えるよ。私も今年はボールにあまり興味ないんだ」 ギデオンはしかめ面をし、レイヴンと私からの困惑した顔を無視した。
ギデオンは過去2年間、文句も言わずにボールに出席していたが、この夏何か変わったのだ。
「いつからボールに行きたくなくなったの?」 レイヴンは彼を疑わしげに見つめながら尋ねた。ギデオンが答えを考えている間、私たちは皆数秒間沈黙していた。彼の顔の表情と、彼が私に送った視線から、彼が説明しないことがわかった。
「いいよ、森で会えるよ。ローズは足を伸ばすのは嫌じゃないだろうから」 私は肩をすくめて沈黙を破った。私のオオカミのローズは、ムーンボールを見逃すことを考えて顔をしかめたが、走るのが大好きだということに同意した。
「まあ、勝手にすればいいけど、私はメイトに会うのが楽しみ」 レイヴンは私たち2人に舌を出してからかった。
「それで頭を下げて、完璧に従順なメイトとしての義務を果たし始めるの?」 私は母のスピーチを真似して、レイヴンにニヤリとし、レイヴンはいたずらっぽい顔をしていた。
「たぶん、そこまでは行かないけど、いくつかの秘策はある」 レイヴンはウインクして答え、私が彼女のコメントにむかむかしているふりをして笑った。
「ああ、カタリーナ?」 甘ったるい声が聞こえ、私はため息をついてから、母の生き写しに顔を向けた。
「アリア、何か用?」 私は穏やかな口調を保って答えた。彼女は私のボタンを押すのが大好きで、私がひどく反応したら母のところへまっしぐらに走り、私の残酷さの犠牲者を演じるだろうことを知っていた。妹との関係は緊張していたが、ヴァレンとは正反対だった。彼は私の暗い時期に私を支えてくれて、私の深い秘密を信頼していた唯一の人だった。ギデオンも、私が完全に頼ることができる人だった。彼は私が過去から立ち直るのを助け、私の秘密を守ってくれた。
「お母さんが、明日の夜のボールをスキップしようと少しでも考えることを忘れないようにって言ってたわ。彼女はあなたを鷹のように見張るつもりよ」 アリアは、自慢げな笑顔で、日焼けした手を腰に当てながら言った。
彼女が私たちの会話を聞いていて、母に密告したことに気づき、顔が熱くなった。怒りが私の中にこみ上げてきて、私のオオカミのローズの静かな興奮を反映していた。しかし、その怒りはすぐに冷たい現実に変わった。私はこのばかげたボールに出席しなければならないことになったのだ。
メイトを見つけ、奉仕の人生に閉じ込められることを考えると、ゾッと身震いした。あらゆる方法で使われるという考えは私を怖がらせ、呼吸を困難にした。
「さよなら、アリア」 ギデオンは苛立ちを込めて、私のスパイラルな思考から私を引き離した。アリアの青い瞳はギデオンの口調の鋭さに少し見開かれたが、彼女はメイトなしの男性に挑戦する勇気はなかった。彼女はフンとため息をつき、古い網戸のドアが後ろでバタンと閉まり、家の中に突進した。
「クソッ」と私はつぶやき、熱いおでこに冷たい手を当てた。
「もしかしたら、メイトに会えないかもしれないよ、カタリーナ」 レイヴンは優しく言い、慰めるように私の腕に手を置いた。2人とも、私がなぜメイトを見つけることに反対しているのか知らず、私は真実を伝えることができなかった。
真実を明かすことは、何が起こったかを追体験することを意味し、私はもう一度自分自身を経験させることはできなかった。悪夢は以前ほど頻繁ではなくなったが、起こったことを考えると、それらは復讐とともに戻ってきた。
「そうじゃないことを願うよ」と私は言い、他に言うことを見つけることができなかった。重いものが胃に定着し、鉛のように私を引きずり降ろした。こんな気持ちになったのは、以前一度だけ、何かひどいことが起こる直前だった。
「明るい話題として、今日は誰が私と一緒にドレスを買いに行くと思う?」 レイヴンは明らかに、メイトという話題から会話をそらそうとして、甲高い声で言った。
「えーっと、アリア?」 私は彼女に半ば冗談めかしてニヤリと笑い、彼女の目は嘲笑して見開かれた。
「いや、面白かったけど、違う。あなたよ!」 彼女はニヤリとした。レイヴンは私が買い物が好きではないことを知っていたが、私がしたくなかったのは、強制的に出席させられるボールのためにドレスを買うことだった。
「私も一緒に行くことになったみたいだね?」 ギデオンは、あまり嬉しそうではない表情で、奇妙な光を瞳に宿しながら、加わった。
「もちろん、男性の視点も必要だよね」 レイヴンは笑った。
その瞬間、私たちの注意は、空いている場所に黒いセダンが入ってきたときに、駐車場に向けられた。胃の結び目が一時的に忘れられ、兄に会えるという考えに興奮がこみ上げてきた。