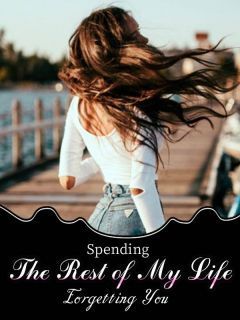ええと、どうしようかなって思ってるんだ。クララが入院してる病院に行って、まだ払ってないデポジットのせいで追い出されるリスクを冒すか、それとも行かなくて、潜在意識が、妹をよそ者に任せて自分だけ助かろうとした罪悪感で私を殺しにかかるか、どっちかだよ。
バカでもないし、冷酷でもない。もちろん、妹のところに行くよ。でも、その前に何か食べとかないと。昨日はシフトから帰るのがすごく遅くなって、食べるの忘れちゃったんだよね。帰ってきてすぐ寝ちゃったし。冷蔵庫はほぼ空っぽで、チーズと牛乳が少しあるだけ。あれはもうすぐ賞味期限切れだろーな。
昨日給料日だったのを思い出して、50ドル取り出して食料品を買いに行くことにした。クララと私のために何か料理しないとね。手作りのご飯は、今の私たちにはすごくいいはず。ここ2週間くらい、冷凍食品とテイクアウトばっかりだったから。ピザにも飽きてきたし、あーあ。
食料品の袋を持ち上げようとしたら、雷が鳴って、苦しそうなうめき声が口から出ちゃった。雨が降り出す前にウォルマートに着けるといいんだけどな。髪の毛、絶対変な臭いになっちゃうよ…
傘を探し始めたんだけど、壊れてたのを思い出した。マジで詰んだ。もう、恥ずかしい選択肢しかないんだ。シャワーキャップしかない。
急いでバスルームから持ってきて、ミニツイス全部を中に入れた。よし、準備OK。
スマホを後ろポケットに入れて、家を出た。空はすごくどんよりしてる。雨は絶対ひどくなるだろうな。
今日は最悪なスタートだ。家から一歩出た瞬間に、雨が激しく降り始めた。もう、引き返すには遅すぎる。まるで自分の命がかかってるかのように走り出した。いや、ある意味、そうだよ。こんな雨の中に長くいたら、ひどい風邪をひいちゃうかもしれないからね。
雨の鞭で何千年もの間打たれ続けたような気がして、やっとウォルマートのドアにたどり着いた。
ありがたいことに、エアコンは入ってなかったから、すぐに凍死する心配はない。レジの人に挨拶して、ファストフードのコーナーに向かった。値段のせいで、どのコーヒーにしようか迷ってる時に、チョコレートと甘いものがいっぱい詰まったカートが横に倒れてきた。
なんでこんなに甘いもの食べるんだろ?別にジャッジするつもりはないけど。私には関係ないことだし。
やっと欲しいコーヒー、いや、買えるコーヒーを選んで、振り返ったら、何かが私に強く当たって、つまずいてしまった。地面に倒れて、突然、今まで見た中で一番美しい青い目を見上げることになったんだ。
彫刻のような顔立ちと、鋭い青い目がすぐに私を惹きつけた。彼の黒いウェーブのかかった髪は、顔の左側に少し落ちていて、すごくルーズなのに完璧な感じだった。彼は、パリッとした白いTシャツと、お金持ちのにおいがプンプンするジョガーパンツを着ていた。身長は190cmくらいで、引き締まったアスリート体型。Tシャツは彼の上半身にぴったりフィットしてて、腹筋のラインがくっきり見えた。私は腹筋フェチじゃないんだけど、マジで!これはなんか違う、ただのラインを見ただけなのに。
私の24年の人生で一度も頭に浮かんだことのない考えが、どこからともなく根を張り、翼を広げ始めた。頭といえば…私の頭!思わず顔をしかめて、おばあちゃんみたいなシャワーキャップがまだ頭にあることを思い出した。クソッ!第一印象ってやつだね。助けて!
彼はジェントルマンで、私を助けてくれるのかな?そうしたら、ちょっと話して、何か…
「拾って」。深みのあるビロードのような声が、私の白昼夢から私を引き戻した。
「え?」
彼は指で、横倒しになったショッピングカートを指さした。中にはチョコレートがいっぱい。たくさん。
あー、彼はさっきのカートの持ち主だったんだ。でも、なんで私がそれを拾わなきゃならないの?彼が私を転ばせたのに、私が悪いってこと?冗談でしょ。過去2分で芽生えた恋心は、すぐに消え去り、怒りに変わった。このイケメン野郎の神経。
私は床に手をついて、少し後ろに寄りかかった。彼とカートを交互に見て、笑い出した。
一瞬、ほんの一瞬、彼の目が痙攣した。面白がってるのか、怒ってるのか、私にはどうでもよかったけど。
「何がおかしいんだ?」。彼は私と同じくらい面白くはないという口調で尋ねてきた。
「あなた。すごく面白いわね。コメディアンになるの、検討したら?私を転ばせたのに、謝りもせずに、自分のものを片付けろって言うんだから。冗談でしょ」。笑い声は顔から消えた。私は地面から立ち上がり、手を払った。
ゆっくりと彼に近づき、髪の毛を後ろにねじった。
「あなたの性格は、あなたの好みと正反対ね」
私は彼から背を向けて、床からコーヒーを拾うためにかがんだ。やっぱり固形物か何かを手に入れないと。彼がまだそこに立っていると、今度は彼のよそよそしい顔が冷たくなった。別にいいけど!さっさと消えろ。
何日か生き残れそうな食料品を手に入れて、レジに向かった。私の前にいる人が終わるのを待っていると、突然白いTシャツが視界を遮った。あ、さっきのクソ野郎だ。
彼の前にいた人たちのことなんか気にせず、彼はチョコレートや、この店にあるあらゆる種類の甘いものが詰まったカートを落とした。あいつはすぐに糖尿病治療を受けることになるだろう、私の言葉を覚えておけ。
私の目の前で、図々しいレジの人が彼の品物をチェックし始めた。ふざけんな!
「おい!私の方が先だったのに。おかしいでしょ。それに、私のものは彼のものよりずっと少ないのに」。私はレジの人に文句を言いに行った。彼女は彼に夢中になっていて、私の言うことなんか全然聞いてない。
「奥様、すぐに終わりますから。落ち着いてください」。ビッチはまだ彼に笑いかけてる。正直、気をつけないと誰か殺すかもしれない。
「今すぐ答えなさい。彼の顔と、彼とヤリたいっていうあなたの欲望のせいだけじゃないの?」。それだけ言って、彼女の空想から彼女を現実に引き戻した。
殺すことができる目があったら、私は今ごろ地下に埋まってるだろう。「誰にそんな口をきいてるの?」。彼女は唸った。
「欲張りビッチ。でも本気で言うと、私が去った後にいつでも彼をヤレるでしょ。まあ、彼があなたの絶望の匂いに気づかなければだけど」。このひどい一日にうんざりして、彼女が私に対応する気がないこともわかってたから、カートをカウンターに投げつけた。
「バイバイ、フェリシア!」。私が去る時に誰かの視線を感じた。誰なのかは見ないようにした。あの女の子は激怒してるだろうな。そろそろマクドナルドに行かないと。今日は病院には行けそうにない。彼らは私の気分をめちゃくちゃにしちゃったんだから。