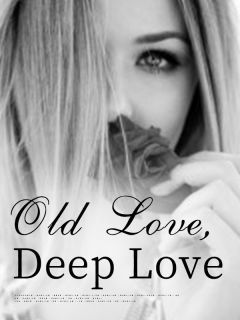あたしの心の声が聞こえる能力が目覚めた日、何年も世話になってる先輩が考えてたんだ。「くそ、あたしのお風呂場にカメラ仕掛けとけばよかったな…」って。
彼はイケメンで、お金持ちで、性格も優しい。
聞き間違いかと思ったけど、次の日、あたしのバスルームに小型カメラが見つかったんだ…
凍り付いたあたしの家には、ピンポーンってチャイムが鳴った。半年もあたしを追いかけてる純粋な後輩、マークがパン屋さんのかわいい箱を手に立ってたんだ。
「もう飽きた。また断られたら、あの子に薬盛ってしまえ」
あたしの頭の中は騒がしくて、震える手を抑えながら、無理やり笑顔を作って彼を家に入れた。
彼はソファーに座って、ちょっと恥ずかしそうに微笑んだ。
「先輩、あたしの大好きなポップタルト買ってきたんだ。」
彼はあたしにそのお菓子を渡してくれた。その時の、照れくさそうでありながら純粋な瞳は、ほとんど抵抗できないくらいだった。
あたしの心の声が聞こえる能力は、いつも使えるわけじゃないんだ。
マークが入ってきた瞬間、聞こえなくなった。
マークが入ってきた瞬間、聞こえなくなった。
背筋がゾッとした。
平静を装って、あたしはそのお菓子を受け取って、ダイニングテーブルに置いた。
「ありがとう。今日はどうしたの?」
彼のベビーブルーの目は、いつものように可愛らしく笑った。「先輩のためなら、いつでも空いてるよ…」 その言葉は、ドライアイスの上をシロップが這うみたいだった。
いつものように、彼はあたしに、付き合ってくれるか試すように尋ねてきた。
あたしはとっさに断ったんだけど、彼の目には落胆の色がちらっと見えた。
ドアを開けた時に聞こえたことを思い出すと、急に不安になった。
「やっぱりだめか」彼はため息をついて、話題を変えた。「このポップタルト買うために、ずいぶん並んだんだ。まず食べてみてよ。」
また断ったら、本当に何かされるんじゃないかって怖くて、あたしはポップタルトを手に取って一口食べ、美味しいって言った。
マークはあたしをじっと見つめて、意味深な笑顔を浮かべた。「本当?」
ポップタルトは、あたしの舌の上で灰になったみたい…マジでヤバイ…
ブリン、ブリンー
マークが安全な仮面を脱ぎ捨てて、その捕食者の目があたしをロックオンした瞬間に、あたしの携帯が鳴った。あたしは慌てて、2つ目のポップタルトを落として電話に出た。
「明日、クラブでイベントあるんだ。」 ポールのベルベットボイスが受話器から聞こえてきた。あたしの白馬の騎士。「設営を手伝ってくれないか?」
「あ、うん。ありがとう。」 あたしの手のひらは、スマホケースに湿った跡を残した。
マークがいつの間にか隣に座っていたことに気づかなかった。
彼の強い腕があたしを囲い込んだ。「チャンスくれないか?」 彼の唇があたしの耳に触れ、まるで子犬みたいに甘えた声だった。「本当に好きだよ…」
「ポールが下に待ってるからー」
「ジャクソン?」 彼の腕の力が一層強くなった。あたしは彼の胸を突き飛ばそうとしたけど、彼の腕はあたしの喉に巻きつき、ソファーに叩きつけられた。
「もう我慢できない。お前はいつも彼とばかり。好きなのか?」
お前ら、どっちも同じ穴の狢だろ…
「違う、ただの先輩だよ! 離して!」
言い終わらないうちに、激しく血まみれのキスに、あたしは呆然とした。あたしの爪が彼の肩を引っ掻き、酸素不足で彼が顔を離した。「こんなにずっと追いかけてきたのに…」 彼は腫れた唇に息を吐き出した。「どうすればいいんだ?」
お父さんの葬式のバラがまだ悪夢に現れる頃、ポールが現れた。セラピストのような目で、計算された笑顔を見せる、頼りになるお兄様。彼はいつカモミールティーを持ってくればいいか、どのシェイクスピアのソネットが悲しみを突き刺すのか、正確に知っていた。今では彼の優しさの下にあるチェス盤が見える。
「どうして、君の唇は…切れてるんだ?」
ポールはクールな外見だけど、優しい声だった。彼のフェニックスの瞳は、それを見た人々の心をいつも高鳴らせた。
彼はあたしの唇をまっすぐに見つめた。
「暖房。」 あたしは嘘をついた。後でバスルームの鏡は真実を映し出した。砕かれたラズベリーのように咲いた、切れかけた唇を。
後輩が噛みすぎたせいで、あたしの唇はまだ痺れていた。
ポールはあたしに何かを悟ったような表情で、それから無言で車を運転した。
クラブに着くと、あたしはまずトイレに駆け込み、数分間口をすすいだ。
設営は、ついに夕方になって終わった。
「家まで送ろうか」 ポールが突然現れて言った。
あたしは丁重に断った。
彼は何も言わず、早く寝るようにだけ言った。
あたしは家には帰らなかった。マークがまだいるかもしれないと思ったから。
今、カメラがあったらいいのに…あれ?
「くそ、あたしのお風呂場にカメラ仕掛けとけばよかったな…」
つまり、ポールは他の場所にカメラを設置していて、あたしはバスルームのカメラだけを外したってことだ。
どうりで、彼の電話がこんなに都合の良い時にかかってきたわけだ…
ブリン、ブリンー
ポールから電話がかかってきた。
なぜか、嫌な予感がした。
あたしは何度か電話を鳴らしたまま放置して、ホテルを見つけてそこで夜を過ごした。
次の日の学校は、全てが平和に見えた。
でも、平和であればあるほど、あたしは不安を感じた。
授業の後、友達からマークが入院したと聞いて、お見舞いに行かないかって誘われた。
あたしは言い訳をして行かなかった。
家に帰ると、ポップタルトの箱がまだダイニングテーブルに置いてあった。
昨日、一つ食べただけでちょっとクラッてした。全部食べなくて良かった。
午前3時47分
ヘビの夢を見た。あたしの肋骨に巻き付くウロコ、二股の舌が息を奪う。あたしは内腿に指紋の痣が咲き乱れて起きた。そして、それをやった記憶は全くなかった。
理由がわからなくて、モヤモヤした気持ちで授業に出た。
授業後、サンドラが興奮した様子であたしに駆け寄ってきた。
「ポール先輩とそんなに長い付き合いなんだから、絶対付き合うと思ってたよ。」
あたしは首をかしげた。
あたしの反応を見て、彼女は不思議そうに尋ねた。「知らないの?」
「何を知らないの?」
「ポール先輩、次の学科のアンシュと付き合ってるの!」
あたしが彼の電話に出なくなってから、連絡は途絶えていた。
まさか、彼がまた新しい恋を始められるなんて思ってなかった。
正直、あたしは寂しさとか空虚感とか、色んな気持ちが入り混じってた。
2年間、彼はいつもあたしを気にかけてくれていた。もちろん、裏があったけど、すぐに彼を避けることもできない。
あたしが彼に対して抱いている感情が、ロマンチックな愛ではないことはよく分かっていた。
あたしは、頼る人がいないと生きていけないバカみたいだった。
どうして、こんな風になっちゃったんだろう?
…ポールのせい?
あたしの考えは、ポールの着信音で遮られた。
躊躇しながら、あたしは電話に出た。
「サラ・キム?」 ポールの声は、相変わらずあたしの鼓動をバクバクさせた。
あたしは複雑な「うーん。」って返事をした。
「クラブで数日後に合コンがあるんだけど、来る?」
正直、彼の顔は見たくなかった。
「ううん、論文に集中しなきゃ。」
相手は数秒間沈黙した。
「じゃあ、いつか食事でもしない? 彼女を紹介するよ。」
あたしは色んな感情でいっぱいだった…
「近いうちには時間がないかも。」
「待ってるよ。」
なんで、彼女に会わなきゃいけないんだ? 会わなかったら死ぬのか?
あたしはため息をついて、精神的に疲れ切っているのを感じた。
ホテルに泊まってから、あたしは引っ越すことを考えていた。
数日後、ついに新しい場所を見つけた。
この近所は、前のところより安全だった。
あたしはクラブを辞めるための書類を提出した。これは、あたしにとって大きな安堵だった。
ポールは、クラブに入っていれば人脈ができて、卒業後も楽になるって言ってた。
だから、あたしは2年間クラブにいたんだ。
正直、社交的なのは全然楽しくなかった。
あの頃、あたしは忙しくして、お父さんのことを考えないようにするために、ポールの勧めで入会したんだ。
辞表を提出してすぐに、ポールから電話がかかってきた。
「なんで?」 彼の声は、いつもより冷たく聞こえた。
「辞表に書いてある。」
「会長の座…」
ポールは、辞めることのデメリットと、続けることのメリットを延々と話した。
でも、あたしの決意は固かった。
彼は渋々認めた。「まあいいや。辞めたければ、辞めろ。」
…
授業中、サンドラはまたゴシップを囁き、先生をちらりと見た。
あたしは黙って聞いていたけど、突然表情が硬直した。
「いつも先輩に近づいて、先輩があたしを好きなんだって言ってるんだよね。もうポール先輩に彼女がいるんだから、相当ムカついてるだろうな、爆笑。」
「ポール先輩と話すきっかけがなかったら、あたし、サラみたいな勘違い女とこんなに長く友達でいられなかったのに…」
丸めた指が強く拳を作った。あたしは机の上の教科書を見つめて、苦笑した。
この突然の心の声が聞こえる能力は、本当に厄介だ。
あたしがいつ、ポールがあたしを好きだって言った?
それとも、わざと近づいたって?
次から次へと、あたしに濡れ衣を着せる。
「サラ…サラ?」
あたしは顔を上げてサンドラを見た。彼女は困った顔をして言った。「話しかけてるんだけど、聞こえないの?」
あたしは彼女を静かに観察してから、視線を外した。
彼女は不機嫌そうにあたしをつついて、「どうしたの? ポール先輩のこと? 落ち込まないで。前にあたしを追いかけてた後輩もイケメンだし…」
あたしは感情を爆発させないように我慢して、彼女の言葉を遮った。「ポールとあたしはただの友達だし、それに、もう彼氏がいるんだ。」
彼女は驚いた顔をした。「彼氏? どうして? いつも彼氏いないじゃん。」
あたしは適当な話をでっちあげた。
あたしが全然ポールを好きじゃないと知ると、彼女の表情はさらに重くなった。
この時、心の声が聞こえる能力は消えた。彼女がそんな顔をする理由が分からなかった。
まあ、深くは考えないことにしたけどね。
その夜、また夢を見た。
この夢は変だった。映像はなくて、音だけなんだ。
その声の主は、あたしの名前を何度も呼んでいた。
急な呼吸は、熱い空気をあたしの耳に送り込むようだった。
何かがあたしを押し付けていて、あたしはそれを振り払うことができなかった。