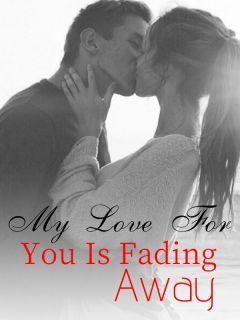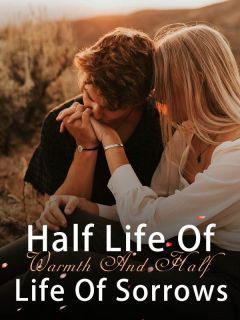サマーの視点
ドアをノックする音がした。お父さんから外出禁止をくらってから、ほとんど部屋から出てない。それからお父さんに会ったのはほんの数回。聞いた話だと、境界線が不安定で、攻撃があるかもしれないって。昔は待ち伏せとか、奇襲とか大好きだったんだけどな。もうそんなことしなくなるんだ。
「入って」って言った。
マルセラが私の部屋に入ってきた。一瞬顔をしかめたけど、すぐに笑顔に戻った。
「可愛いサマー、良い知らせがあるの」
「そうなの?」
「ええ」また顔をしかめた。
私は笑いをこらえるのに必死だった。湿った木の匂いが彼女にはきついのかな。私は慣れたけど、時々ネズミが出てくるのもね。
「今夜は夕食を作らなくていいの!」彼女は手を叩いた。
「どこか行くの?」って聞いた。
「そう…行くわよ」
私たち? マルセラは私を家族のことにほとんど入れない。私は彼女の旦那の娘だけど、ここではメイドみたいなものだ。
「どこに行くの?」って聞いて、クイーンサイズのベッドから足を降ろした。
マルセラは歩き回って窓の下に立った。「冬のロッジよ、町から20分くらいの場所にあるの。シフトのためにね。女の子たちといつもそこでシフトしてるの。あそこは、ここの荒野よりずっと静かなの」
「へえ、よさそう。いつ出発するの?」
マルセラは胸に手を当て、頭を後ろに傾けて笑った。「あら、ハニー。私たち女の子は日が沈む前に出発するの。あなたにも来てほしいんだけど、もちろん、あなたの状況が残念なのよね」
私はうなずいた。やっぱり、私をからかいに来たんだ。
「じゃあ、楽しんでね。お父さんも一緒に行くの?」
「もちろんよ。家族でするの」
また、私はよそ者だってことを思い知らされた。
「わかった、マルセラ。良いシフトを」
マルセラは壁をしかめて、私にニヤリとした。「また今度ね、でしょ?」
私は舌を噛んでうなずいた。彼女は地下室から出た途端、汚い辞書に載ってる言葉を全部使った。お母さんに電話しようか考えたけど、しちゃダメだったんだ。これは、事件以来初めてのシフト。時間が過ぎて、家が空っぽになっていくのを聞いていた。
日が完全に沈んでから、私は二階へ行った。肌に月の光を浴びて、冷たい夜風が肌を駆け抜けるのが恋しかった。裏口を開けて、階段に座って空を見上げた。私はバカだけど、もしかしたらって思ってたんだ。
ドアを閉めた。上位メンバーの家はほとんど森に繋がってる。私は自分の奥深くに手を伸ばして、見慣れた友達を呼んだ。希望に目が眩んだのか、それとも何かあったのか。私は森をかき分けて、できるだけ月の光を浴びた。月の光には、適切な雰囲気では癒しの力があるって読んだことがある。
遠吠えが次々と夜に響き渡った。私の心は痛み、持っていた希望はすべて消えた。私はバカだったんだ。でも私は振り返らずに歩き続けた。人間として、この生活に慣れることは決してないだろう。遠吠えは吠え声に変わり、体が地面にぶつかる音が聞こえた。
「よくないな」って私はささやいた。
オオカミの戦いが、私のすぐ近くで繰り広げられた。私は後ろに下がった。もし見つかったら、私はおしまいだ。戦いはさらに激しくなった。オオカミがひどい痛みにうめき声をあげていて、死ぬのかと思ったけど、足が地面に当たった音がした。私は振り返って走り出した。奴らには追いつけないから、賢くならないと。私は円を描いて走り、自分の匂いをまき散らした。
家の中に駆け込み、ドアに寄りかかった。鋭い息を吐き出した。
「あなた」
私は頭を上げて顔を上げた。ツバを飲み込んだ。
裸の男がキッチンに入ってきた。顔に熱が走った。刺青とブロンズの肌の男が私をにらんだ。
「ここで何してるの?」って私はか細い声で言った。
「それを聞くのは僕の方だ」彼は私たちの間の距離を縮め、私の体にぶつかってきて、ドアに押し付けられた。彼の手が私の首に巻き付いた。私は彼の肌に爪を立てたけど、彼はびくともしなかった。
「レッドクローの一味だな?」彼はあざ笑い、掴む力を強めた。
「ふざ…けんな」って私は息をした。
「エズラ」お父さんが怒鳴った。
「何だ?」
「彼女を放せ。私の娘だ」
彼の掴む力が弱まり、私は床に落ちた。私は首を押さえて彼をにらんだ。
「18歳の娘がいるのか?」アルファ・エズラが尋ねた。
お父さんは肩をすくめた。「20歳だけど、ああ」
お父さんの肩から血が流れて、床に滴り落ちた。
「お父さん、怪我してる」私は彼に駆け寄った。
彼は私を追い払った。「大丈夫だ。部屋に行け」
「傷が深いから、手伝わせて」
彼は救急箱を手にした。
彼は唸り声をあげて、ダイニングルームに足を踏み入れた。
「攻撃されたのか?」私はエズラの方を向いた。
彼はくすくす笑った。「まだ君を信用してないんだ。僕のパックにどれくらいいるんだ?」
「サマー!」お父さんが叫んだ。
やばい、エズラは私の名前を知ってしまった。私は急いでダイニングルームに向かった。彼は救急箱を私の胸に押しつけた。
「黙ってろ」って彼はヒソヒソ言った。
「え?」
「僕に話させておけ」って彼は命じた。
「はい、わかりました」
エズラは黒いパンツを履いて部屋に入ってきたけど、彼の日に焼けた筋肉質の腹筋は丸見えだった。彼は私より10歳くらい上のはずだ。
「早くしろ、サマー」お父さんが命令した。
私は消毒液を綿に注ぎ、何の予告もなくそれを傷口に擦りつけた。彼は唸り声をあげ、オオカミの本能が出てきた。
「なぜ彼女のことを教えてくれなかったんだ?」エズラが尋ねた。
私は開いた傷に視線を向けたままだった。
「彼女はここに長くいない。もっと大事なことがあったんだ」とお父さんはぶつぶつ言った。
「僕のパックを通過する者は誰でも僕を通さなければならないって知ってるだろ。君の娘として、彼女も僕に忠誠を誓わなければならない」
お父さんは下唇を噛んで顔を背けた。「彼女がここにいない場合でも?」
私の心臓が大きく跳ねた。彼は私を追い出すつもりなのか?
「関係ない。明日、パックハウスで待ってる。わかったな?」
お父さんは唸り声をあげた。「はい、アルファ」
「よし。確認することがある」
アルファ・エズラが出て行くまで、私たちは沈黙したままだった。お父さんは椅子から飛び出して罵った。
「どうすればよかったんだ?君たちがここにいるなんて知らなかったんだから」って私は聞いた。
「いや、マルセラと女の子たちはどこだ?」
「行った。私は誘われなかった」
「クソったれ、サマー。一緒に行くべきだったんだ。新しいアルファに忠誠を誓うのがどういうことか知ってるのか?」
「ちょっと言葉を言って、少し痛いけど、おしまい?もう隠れる必要もないんだ」
彼は顔に手をやった。それが正しくないことはわかってる。
「君はローグじゃないんだ、サマー、逃亡者なんだ。エズラがそれを知ったら、君を引き渡す義務がある。どんなペナルティか知ってるだろ、スイートハート」
「私のせいじゃないのに」
「明日捕まらないように願うことだ」
「どうして?」
「逃亡者の印がつくことになる」
お父さんは階段を上がった。数ヶ月前に起きたことは私のせいじゃないけど、まだ私は標的になってるんだ。エズラはすでに私を疑っていて、逃亡者の印は私を地獄に真っ逆さまにするだろう。