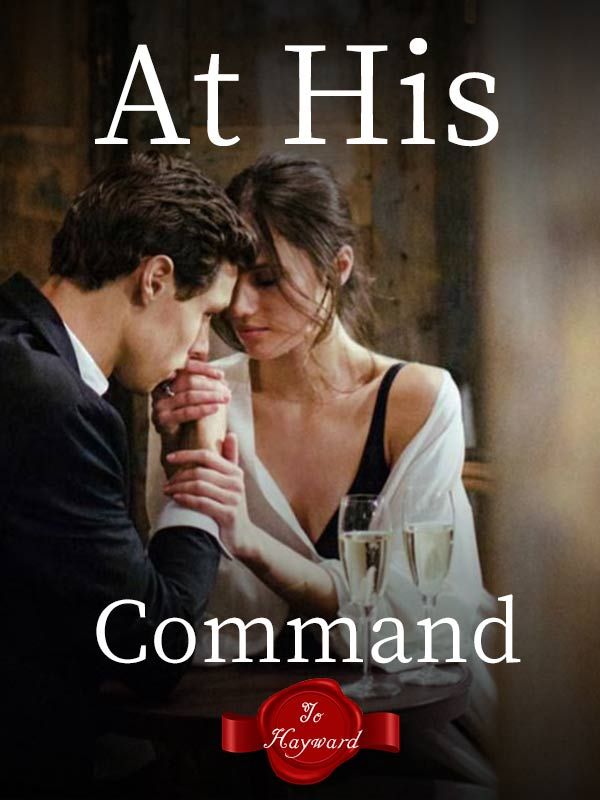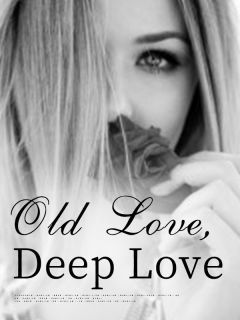「イーサン・シールズ!」メルが、リンと一緒に、ニヤニヤしながらこっちに向かってよちよち歩いてきた。
ザックが僕の腕の中でくすくす笑ってる。今話してたお姉さんが僕から離れて行ったんだ。
兄の方を見て、僕は喉のつかえを飲み込み、今日は何か面白いことでも考えようと試みたんだ。
ザックは興奮して両親を呼び、僕は彼を降ろして、彼がそっちに走っていくのを見てた。
「やあ、みんな。どうしてこんなところに?」僕は笑顔で挨拶した。
「相変わらずだな、兄貴」リンカーンがくすくす笑った。
「何が?」
「甥っ子を使ってデートしてるんだろ。この二人が仲間入りしたら、一体どうなるのか想像もつかないよ」メルは赤ちゃんの膨らみを撫でながら言った。
「おいおい、みんな、俺のこと分かってるだろ。今は、ここのおいしいクロワッサンを教えてくれる、美しいシンディーの話を邪魔しただけだよ」僕は不機嫌そうに言いながら、金髪美女を探した。
「まあ、メルと彼女の食欲のことだからな」リンカーンは奥さんを見て、彼女がプラムを一口食べて、僕との口論を忘れ、純粋に楽しんでいる様子を見て言った。
「行こうか」リンカーンは彼女の手を取って言った。
「ちょっと待って、私のチョコレートを取りに行かないと」彼女は懇願するような表情で言った。
「少しだけな」リンカーンはため息をつき、僕は彼を見て笑った。
「兄貴みたいなやつにはなりたくないな」僕はにやにや笑った。
彼女を見た瞬間、僕はその言葉を取り消した。ザックが彼女に駆け寄り、あの愛らしい笑顔で抱きしめたんだ。彼女の笑顔は瞬時に僕の世界を明るくしたんだ。彼女はひざまずいてザックを抱きしめ、頬にキスしたんだ。彼女の黒い瞳は笑いで輝き、ザックの言葉に笑ったんだ。彼女の明るい褐色の肌は、まさに誘惑そのものだったし、彼女のカーブについては語り始めないでほしい。彼女はただ…完璧だったんだ。
彼女は顔に笑顔を貼り付けて、僕らのところへ歩いてきた。
「タリア、元気?」メルは彼女を抱きしめようとしたけど、二人とも笑い、彼女の膨らみが邪魔した。
「元気だよ、メル。学校で会うのは久しぶりだね」
「ごめんね、今、自宅謹慎中なの」彼女はリンカーンをにらみつけた。
「大丈夫だよ。行かないと。また電話するから、近況報告しようね」彼女はリンカーンに微笑みかけ、僕を完全に無視し、近づくなというような視線を送ってきたんだ。
次に感じたのは、腕に走る痛みだった。メルが僕を殴ったんだ。
「何だよ!」僕は痛む腕をさすったんだ。
「私の友達に何をしたの?」
「何にも、何にもしてないよ」僕は降参して両手を上げた。
メルが僕に向けた視線は、瞬時に僕の腹の内をすべて吐き出させた。彼女の唇は笑顔に変わったんだ。
「払って」彼女はリンカーンの方を向き、彼は財布から100ドルの札を取り出したんだ。
「混乱してるでしょ、ダーリン」メルはリンカーンがザックを抱き上げながら言った。「あなたがいつもザックの学校に熱心に行くのは、そこに何か興味のあるものがあるからに決まってるの。この場合はタリア・クイーンね。彼女の反応からすると、あなたは彼女を夢中にさせようとやりすぎたわね。リンカーンは私がタリアのことだって言った時、信じなかったのよ、それで賭けをしたの。そして今日、あなたは私にお金をくれたのよ」彼女は生意気な笑顔で言ったんだ。
僕は顔をしかめた。リンカーンとメルは大笑いし始め、周りの人たちが振り返ったんだ。彼らの警備チームのメンバーがドアを開けてくれたので、僕らは店から出た。
「猫に舌を掴まれたか、兄貴。こんなに静かなお前は初めてだ」リンカーンが言った。
「ほっといてくれよ、兄貴」僕は不機嫌そうに言った。
メルは心配そうな表情で僕を見て、立ち止まって、みんなに止まるように合図したんだ。「ちょっといい?」彼女は夫に優しく言い、彼は理解したようにうなずいたんだ。
「本当に彼女のこと好きなんだね?」
「その…その…」
「何をしたか正確に教えて」
「いつものことだよ…」
-----
僕は過去一週間、ザックを彼の教室まで迎えに行ってたんだけど、今日は彼女にデートに誘う日だったんだ。
「やあ、スウィーティ」僕は挨拶し、彼女は僕にむかって目を回し、ザックはさよならを言った。「君と僕、映画、最高の一夜ってわけだ」僕は生意気な笑顔で言ったんだ。
「結構です、シールズさん」彼女は僕から顔を背けた。
「わかった、映画はなしにして、僕の家で親密なディナーでもどう?」僕は最高の笑顔を見せたんだ。
彼女は鼻で笑い、僕から顔を背けた。それから、僕はザックを迎えに行くたびに、彼女は疫病神のように僕を避けるようになったんだ。
-----
「痛い」僕はもう一度腕をさすった。「なんでそんなに乱暴なんだ、ホルモンのせい?」
「あなたはバカだ。彼女が、あたのベッドに入りたがってる他の女たちと同じだって、本気で思ってるの?」
僕は首を振った。
「さて、あなたにしてほしいことがあるの。彼女にピンクのバラを買ってあげるの。ピンクよ、聞こえてる?」
「はい、奥様」
「彼女は4時に仕事が終わって、バスで帰るの。お詫びとして、送ってあげなさい。それだけよ。わかった?」
「はい、奥様」僕は満面の笑みで言った。
「そしてイーサン、お願いだから、変なナンパの言葉とか、安っぽいコメントはやめてね」
「はい、奥…」
「もう一度奥様って呼んだら承知しないわよ」彼女は脅した。
「はい、メル。ありがとう」僕は彼女を抱きしめ、頬にキスした。
「もし失敗したら、私にアドバイスを求めに来ないでね。ガソリンは渡したから、あとは火をつけて、燃え続けるようにしなさい」
「ありがとう、ありがとう、ありがとう」僕は彼女から離れ、車に向かって歩きながら、バカみたいに笑ったんだ。