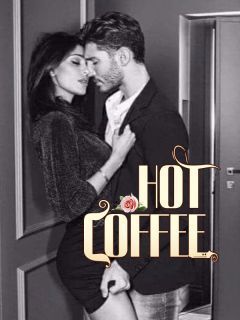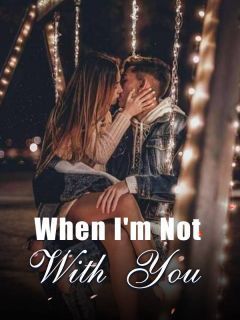マリシャ、マジでブチギレて顔真っ赤だった。最初めっちゃいい感じだったのに、人生で一番最悪な日になっちゃったよ。
ずっと待ってたんだよね。自分をやり直すために。長すぎるくらいに。新しい名前でさ、過去の汚れを全部洗い流せるような名前で生きていきたいって思ってた。
今日こそは、社会の仲間入りを果たす最高のチャンスだったのに。でも、朝の出来事のせいで、奇跡でも起きない限り無理だ。
だから、うん、キレてる。
4年間も頑張ってきた努力が全部水の泡だし、誰に腹立ててるのかもわかんない。自分に?それとも、あいつが余計なことしたから?
なんでいつもこんなに大変なことばっかりなんだろう?もし、あいつがいなかったら、もし、他の誰かだったら、マリシャは絶対、こんなにひどいことにはならなかったって確信してる。
なんであいつは、あたしをイライラさせるのがそんなに楽しいんだろ?答えは出ないけど、全部あいつのせいだって、やっと決めたんだ。
「うがああ!」 マリシャは叫んで、イライラして髪の毛を引っ張った。
「一体全体、誰が朝っぱらから乗馬なんてするのよ!」 マリシャは、誰もいないアスファルトのハイウェイの脇にある道を歩きながら、ブツブツ文句を言った。
天気が良くて、景色も最高だったんだけどね。普通だったら、景色を眺めて、自然の恵みに浸ってただろうけど、今のマリシャにとっては、その景色が嘲笑ってるみたいに見えた。気分をさらに落ち込ませるような感情が込み上げてきた。
それでも、ポプラの木は風に揺られ続けてるし、ヤシの木は堂々と立って、朝日に向かって枝を振ってる。遠くには、巨大な都市のシルエットがキラキラ光ってる。高い、ガラス張りの高層ビルが、緑の海の中にそびえ立ってるんだ。
それが、マリシャが向かうはずだった場所。
マリシャは鼻で笑ったけど、自分の行動で、その美しさを消し去ることはできなかった。都市の美しさも、西に何リーグか行ったところにある、キラキラ光る青い湖の美しさも。
それが、ウルブの湖。ヴェテルムの首都の宝石なんだ。そこにある別館に行く予定だったのに、あいつのせいで、何度もつまらないことばかりして、新しい仕事の面接に遅刻しちゃったんだから。
マリシャは、あの時のことを思い出して、顔をしかめた。
「あいつらは何者だったの?」 マリシャは、あいつと、もう一人の宿敵、ジェネヴィーヴ・マザーズの周りに集まっていた女たちのことを思い出しながら、つぶやいた。
「あいつの友達?それともハーレムの一部?」 マリシャは、激しい口調で付け加えた。あいつが自分に言った言葉をまだ覚えていて、それがマリシャをイライラさせた。
「誘惑?冗談でしょ!」 マリシャは鼻で笑った。怒りが爆発しそうなくらいで、それが、現実逃避のいい口実になった。だって、マリシャはそういう人間なんだもん。責任を負うとか、自分の行動の結果を甘んじて受け入れるとか、そういうことは大嫌いなんだ。
他のことを考えるより、ヴェテルムのゴシップの世界で何が起こるかを考えるより、ずっと楽だった。マリシャはそう決めて、怒りの道を歩み始めた。
「誘惑?」 マリシャは、その言葉を繰り返した。そのことを考えると、他のことを考えなくて済むから、ってだけなんだよね。
「あたしがそんな低レベルなことするわけないでしょ。あいつはあたしのこと、どれだけ落ちぶれてるって思ってんのよ?」 いろんなことがあったけど、マリシャにとって、自分の信条はまだ大事なものだったし、あいつがあたしのことについてそんな風に考えてるって知って、むかついたんだ。
あいつの言葉だけじゃなくて、あの朝の出来事のイメージが頭から離れなくて、マリシャは首を振ったけど、考えは止まらなかった。
つらくて、考えれば考えるほど、イライラしてうめき声が漏れてしまう。髪の毛を引っ張るのを我慢するのが大変で、精神的な攻撃のせいで、顔にはっきりとイライラ感が表れていた。それでも、「今からどうしよ?もうどうしようもない状況を、どうにかする方法なんてあるのかな?」 マリシャは、今歩いているきれいな灰色の舗装路とは対照的に、泥だらけになった片方の靴を見つめながら、考えた。
もうどうしようもないんだ。マリシャは、ついに負けを認めた。結果から逃げることなんてできないし、今回は、4年前のあの時よりも、もっと大きなスキャンダルになるだろう。
「なんで、あのスカーフを放っておけなかったんだろ!」 マリシャは呪うように叫び、片方の赤い靴でまた別の石を踏んだ。小石が飛び出して、ハイウェイに散らばった。
「そして、あのむかつく風!」 マリシャは、激しい口調で言い、裸足と、ヒールが壊れた片方の赤い靴を引きずりながら、舗装された狭い道を歩いていた。
マリシャの格好自体が、あの時の試練の証だったし、あの朝のひどい気分を考えれば、当然のことだった。それに、マリシャが歩くたびに、たくさんの石が飛んでいくのも理解できた。
道に誰もいなかったのは、運が良かった。いつもそうなんだけど、あの朝の不幸な出来事のせいで、マリシャは、自然までもが自分を困らせようとしているんじゃないかって疑ってた。
「自然がお前を困らせようとしてるって?」 声が嘲笑った。
その声には笑い声が混じっていて、そして、一番聞きたくないような舌から、いたずらの匂いがした。
「今じゃない…」 マリシャは心の中でうめいた。「こんなことまで加わったら、もう耐えられないよ。」 マリシャは心の中でつぶやいた。
「もしかして、本物の人間が話してるのかな?」 マリシャは顔を上げて期待した。
「あたしだよ、バカ!」 その声が付け加えた。マリシャは、自分の悪い運に本当に信じられなかった。 「なんでいつもわかんないんだろ。こんなバカなことばっかりして、何の意味があるんだ?」 その声が文句を言い、マリシャの心はもう限界だった。
驚き。展開。あの朝に起こったことは全部、ポジティブな感情を暗い深淵に突き落とすためだけに用意されたみたいだった。
「無視しろ。無視しろ!」 マリシャは、自分に必死に言い聞かせたけど、いつもみたいに、良心は勝手に動くんだよね。
「恥ずかしくないの?」 その声は、マリシャを責めた。「鏡でちゃんと自分の顔を見なよ。自分の姿だけじゃなくて、まあ…」 それは、何かを考えているかのように、ちょっと止まった。
「まあ、結局、全部自分の姿なんだけどさ、本当に、両親のこと考えたことある?マリシャ、お前はもう終わりだよ!」 突然、その声は笑い出し、マリシャの心臓は一瞬止まったみたいだった。マリシャは、まるで時間が止まったかのように、その場に立ち尽くし、過去の記憶や、両親の反応を頭の中で巡らせた。
今まで、現実逃避してきたから、そういうことは考えないようにしてたんだ。記憶も、良心も、全部置いてきた。この小さな悪魔はいつも、マリシャをさらにイライラさせるために、何をすればいいのかを知ってるんだよね。
一撃で、マリシャの壁は崩れ、抑制がすべて消えてしまった。そしてついに、パニックに陥った。あの朝、すべてが始まった時からマリシャを苦しめていたパニックに。