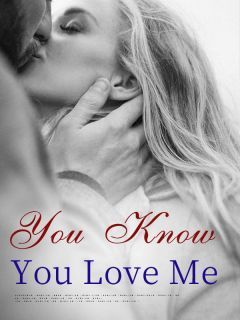小さな、ピオニーみたいな繊細な姿が、マフィアの王女であるオーロラの10歳の誕生日パーティーの隅っこに座っていた。
色んなグループの人たちが、まるで何年も冷戦状態だった後にようやく築かれたハーモニーの錯覚のように、お互いに穏やかに話していた。まるで彼らはついにウェイロンズの統治下で団結するという認識を持ち、彼らに忠誠を誓ったかのようだった。
ローズ・カッタネオは、カッタネオのマフィア一族のリーダーであるヴィンセントの一人娘であり、1世紀以上続く犯罪組織の遺産を受け継ぐ若い王女なのに、場違いに見えるまだ12歳のシャイな女の子だった。
ピンクのマカロンを一口食べながら、彼女は両親が皇帝自身と話しているのを見ていて、側に美しい女性を従えたその男性にどうしても圧倒されてしまった。
彼女はそのカップルを困惑した様子で見つめていたが、その女性がマフィア皇帝の最愛の女王だと気づいた。だから、そこに座っているだけで、彼女はすでに王室の半分に会っていたことになる。それから、彼女の目は、パーティー全体が行われている人物を探した。
王女はいつも両親と一緒にいなければならないんじゃないの?それに、王子はどこにいるの?
「ねえ!そこのあなた…」ローズは、まるでヘッドライトに照らされた鹿のように目を見開き、ほぼ席から転げ落ちそうになった。そして後ろを振り返ると、小さな指が紫色のベルベットのカーテンを分け、茶色の頭がカーテンの間から顔をのぞかせていた。
「カップケーキの皿をちょうだい」その子は自分より小さかったが、目をパチクリさせずに見つめてくる強気な態度で、か弱いローズを緊張させた。ローズは慎重に皿を持ち上げ、周りを見回してから、それをつかもうと出てきた手に渡した。
「あ、あのね、ゼリーサンドイッチも食べてみて、あ、私の大好きなんだ」ハチミツ色の目がローズの茶色の目に深く見つめられ、その子はうなずいた。
「わかった」しかし、今度はローズがサンドイッチの皿を渡した時、彼女の全身が前に引っ張られ、2人の少女の繊細な姿が紫色の装飾が施された柱の向こうに消えてしまった。
ローズは不満そうに唇を尖らせ、恥ずかしそうに指をいじっていた。彼女はその女の子が奇妙な場所に行くのを止めようとした。彼女は、自分がパーティー会場からずっと出てしまい、宮殿のような別の建物に向かっていると確信していたため、そこが自分が入ることを許されていない場所だとある程度確信していた。
「あ、誘拐されてるのかな?」彼女は花の真ん中で立ち止まり、地面を走る白いふわふわした雲をいくつか見ることができた…あれは犬?現状に集中するために頭を振って、ローズはただ不満そうに立っていた。
「誰かに誘拐されたら可愛く振る舞って、それで何?ホットチョコレートを一杯くださいって頼むの?」
「い、嫌!」美しい大切な天使は不満そうにむずかり、頬がピンク色に染まった。
「それなら、私についてきて、弱虫」
「ねえ!私の方が年上だし、あ、あなたより背も高いの!」
「あなたの方が私よりナイーブだもんね」その少女は先に歩き、ローズは知らず知らずのうちに2度うなずき、それが頭の中に登録されるまでぼんやりしていた。
「いや!私の方が頭がいいの!」
「それはもっと賢いじゃなくて、もっと頭がいいって言うんだよ」
ローズ「……」
_________________________________________________________________
「部屋のその側には魔法があるの」
「魔法?本当?」ローズは、新しくできた友達と一緒にその場所を見ることにかなり興奮した。今まで、彼女たちは屋敷の半分を歩き回り、ローズは楽器がいっぱいの部屋を見たし、他には洗練されたジムもあった。彼らを通り過ぎるガードたちは奇妙に見えたけど。
彼らは半分困惑し、少し不安そうに見えたが、なぜ何も話したり、彼らを止めたりしなかったのだろう?マフィアの王と女王の個人的な空間を歩き回るのは大丈夫なんだろうか…
「博物館みたいにしてあるのかな」純粋な天使は、隣の女の子がお腹を抱えて大笑いするのを聞いただけで、彼女の背中を叩いた。
ローズは、自分が妹のような友達にとってどんなにばかげたことを言っていたのか、その時は全くわからなかった。そして今、彼女が扉の向こうに魔法があると答えたとき、ローズはまるでスペクタクルだった。
「ある種の境界線を破るべきじゃないわ、いくつかの謎と秘密は王族の心に近く、彼らは私たちが邪魔するのを望まないでしょう。私たちはもうこんなに深く入り込んでるし…戻りましょう、両親が心配するから」
「あなたって、年の割にすごく賢いわね」その少女は、その日何回目かのローズを観察するように頭を傾けた。
「でも私の方が年上だし、もちろんもっと賢いでしょう」その柔らかい言葉は単なる事実であり、その少女は誰か戻ってくる人を求めてあたりを見回していた。
「そんなわけない、私より同い年で賢い人はいないもん、私天才なんだから」その小さな茶色の目の可愛い子は、息を潜めてそうつぶやき、部屋の扉を開けると、中に座っていた人物はローズを恐怖で凍りつかせた。
彼女の茶色のチョコレート色の瞳と出会う緑色の虹彩は暖かく思いやりがあったが、恐怖はローズを動けなくし、彼女はよろめいた。
「パパ…この子はローズ、私の親友。ローズ、これが私のパパ」中に座っていた壮大な男は王だった。しかし、エイジャックス・ウェイロンがこの少女の父親であるなら、彼女は…「オーロラ姫!」
「あ、お、お詫び申し上げます、本当にごめんなさい」エイジャックスは、転ばないように少女の肩を抱いたが、ローズは目の前に彼がいるのを見て驚き、恐怖を感じることさえできなかった。
「気をつけなさい、娘よ」純粋な少女は、自分が思っていたこととは反対に、皇帝が自分にどれだけ温かく接してくれたのかに泣きたかったが、混乱が彼女を支配し、涙が顔を伝い始めた。
だから、パーティーの隅に座っていた一人の子供は、オーロラと一緒にブリトーのように包まれ、凍える冬の夜にホットチョコレートを飲みながら、エイジャックスが2人の子供にネバーランドの海賊の本を読んでいるのが見つかったのだった。
『フラジャイル』のチャプター1