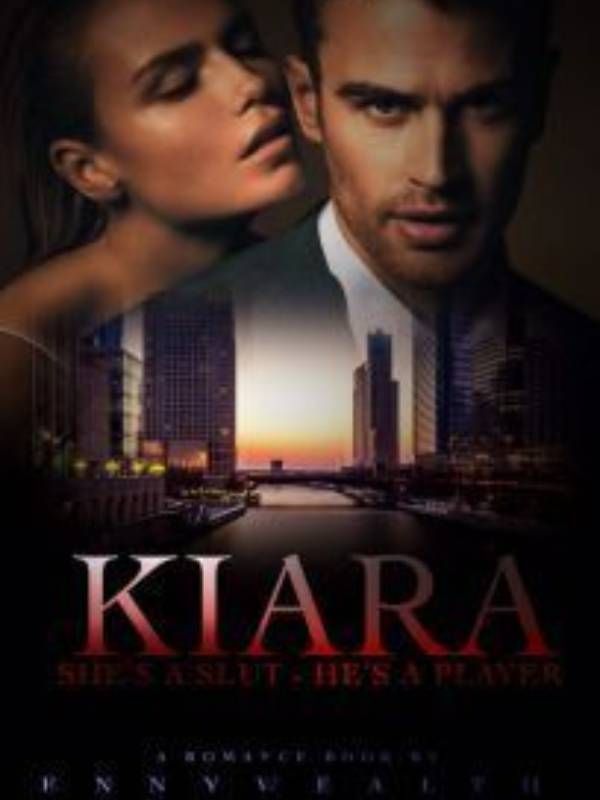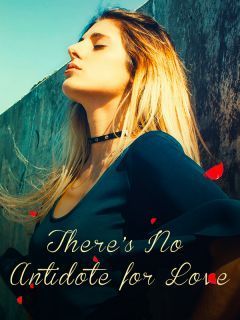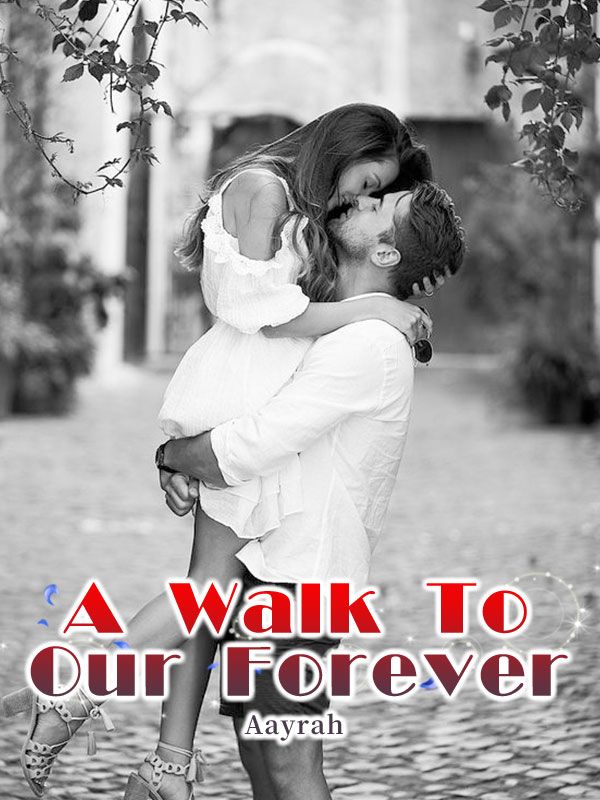Somewhere_in_Arizona
キアラの視点
鏡の前に立って、顔にちょっとだけメイクを足したんだ。そうしてたら、ベッドの上で彼が私を誘うように見つめてるのが目に入った。
「キアラ、本当にいいね」 また褒めてくれた。もう10回目くらいかな。
私はただニヤリとして、黒いクラッチにメイク道具を戻した。
「もう、君のアカウントにいくらか振り込んだよ」 彼はそう言って、私の顔にスマホをかざした。
ベッドの横に置いてあったスーツケースを持ってきて開けて、私に現金を差し出した。
え?
私は混乱して彼を見つめた。
「なんでまたお金をくれるんですか、旦那様?」 私はちょっと囁くような声で尋ねた。
「ああ、もう、キアラ!」 彼はベッドから飛び降りる前にそう叫んだ。
「君の甘い声を聞いたら、またベッドに連れて行きたくなったよ」 彼はそう言って、私の肩から腕にかけて優しく触ってきた。
「うーん… リチャードさん、今夜の私のサービスはもう終わりましたよ」 私は彼の金色の瞳を見て言った。
本当にイケメンだし、しかもめちゃくちゃお金持ちなんだよね。
「でも、もし君と独占契約を結びたかったら?」 彼は近づいてきて、私の耳元で囁いた。
え?
「君の素晴らしい体を独占したいんだ」
彼はようやくちゃんと立って、私の小さな体をじっと見下ろした。
「それで、どう思う?」
「全部よくわかりません、旦那様」 私は落ち着いて、彼の顔から視線を外して言った。
彼は軽くため息をついて、私の手を取った。それで私は彼を見た。
「キアラ、僕の愛人になってくれないか。一生後悔させないから」 彼はすごく熱心に言ったから、私は思わず鼻で笑ってしまった。
冗談でしょ?
うーん…
私はそっと手を引っ込めた。
「リチャードさん、オファーありがとうございます。でも、残念ながら興味ありません」 私はきっぱりと言って、すぐに彼の横を通り過ぎた。
「でも、なんで断るんだ…?」
「必要になったら、いつでも呼んでください、旦那様」 私は彼の言葉を遮って言った。ベッドの上のお金を取って、彼の方を向いた。
「本当にありがとうございます」 私は彼の驚いた顔にお金を掲げた。そして、そうして部屋から出て行った。
ため息をついて、手元のお金を見た。
結構な額だ。私はニヤリとして、クラッチにしまった。
それから、静かな通路を歩き始めた。ヒールがマーブルの床をカツカツ鳴らす。
エレベーターから降りて、もう少し歩くと、レセプションに着いた。
私を見ると、受付の人がにこやかに微笑んだので、私も微笑み返して、さよならを言った。
「良い夜を、奥様」 入口の警備員が軽くお辞儀をして言ったので、私はうなずいて彼の横を通り過ぎた。
ホテルのガレージに着いて、車のイモビライザーを押して、開けて乗り込んだ。
クラッチと携帯電話を助手席に放り投げて、すぐにエンジンをかけた。
「疲れたな」 私は独り言を言いながら、素晴らしいホテルから車を出した。
アレクサンダーの視点
テキサスのどこか
「ああ、アレク」
「ああ、もう」
「もっと強く、ベイビー」
「もうすぐ…」
「お願い、やめないで」
彼女のうめき声が部屋中に響き渡り、私は彼女を激しく突き刺した。ビッチ!
ついにオーガズムに達した。長い時間、彼女を乗り回した後だった。私はすべてを彼女の中に注ぎ込みながら、うめき声を抑えた。
「あー… すごく熱かったわ、アレク。味見してもいい?」 彼女は誘惑的に言い、私の胸に人差し指を這わせた。
「俺は…」
「もう遅いよ、アレク。おばあさんが電話をかけ続けてる」 マックが部屋の外で言った。
私はすぐにベッドから降りて、床に落ちていたブリーフとズボンを拾い、着始めた。
「もう行くの?」 彼女は子犬のような目で尋ねた。
「でも、まだ始まったばかりだと思ったのに」
彼女の小さな手が私の腰に巻き付き、ネクタイを結んでくれた。
「連絡先、教えてくれない?」 彼女は私の背中に頭を乗せて言った。
「いや」 私はきっぱりと答えた。
「え?」
彼女は私の背中から離れて、私の前に立った。
「あんなに頑張ったのに」 彼女は不満そうに言った。
「俺が決めることだ」 彼女の肩はすぐに落ちた。私は振り返って、ドアに向かって歩き始めた。
「近いうちに君のアカウントにお金が振り込まれるよ。また必要になったら電話する」 私は彼女にそう言って、ちらりとも見ずに、出て行った。
「どれだけ待たせたか、わかってるのか?」 マックの声が背後から聞こえてきて、私は思わずビクッとした。
振り返ると、彼はドアの前に立っていた。
「びっくりしたよ、マジで」 私は軽く息を吐いた。
彼は鼻で笑って、私に近づいてきた。すごく怒っているように見える。
「あの時、部屋に突入しそうになったんだぞ」
「お前はそんなことしないだろ。それに、なんでお前も女と遊んでなかったんだ?」 私はズボンのポケットに手を入れて尋ねた。
「気分じゃなかったって言っただろ」 彼は半分叫び、私は唇をひくつかせた。
「それは俺のせいじゃないな」 私は平然と言い、彼は私を睨んだ。
「うーん… 俺の携帯は?」
「おばあさんの電話、出たのか?」 彼は私にスマホを渡しながら尋ねた。
「ああ、出たよ」
胸がドキドキして、私は彼の顔を素早く見上げた。
「何て言ったんだ、マック?」
「他に何が言える?」
「もちろん、お前が何をしてたか言ったよ」 彼は無頓着に言い、歩き始めた。
私は彼の襟を掴んで引き戻した。
「まさか、本気で言ったんじゃないだろうな?」 私は鼻で笑った。
「もう放してくれよ」 彼は歯を食いしばった。
ポケットの中で電話が鳴り、私は彼を乱暴に突き飛ばして、急いで電話を取り出した。そしてまた、発信者番号を見て、心臓が震えそうになった。
おばあさんだ。
私はしばらくスマホの画面を見つめて、考えた。
「俺は車に行く」 マックはそう言って、私を置いて出て行った。
クソ野郎。
私はスマホの画面に視線を戻した。
いや、出ない… 私は首を横に振って、またポケットに電話を入れた。もう家に帰ろう。
慎重にリビングに入った。周りを見回すと、ありがたいことに彼女はいなかった。それだけでなく、私は安堵のため息をつき、階段を上り始めた。
「おかえりなさいませ、ご主人様」 メイドの声に驚いて、私は目をきつく閉じて手すりにつかまった。
マジかよ!
「おばあさんは?」 私は彼女に苛立たしげに尋ねた。
「お休みになられました、ご主人様」 彼女は丁寧に答え、頭を下げた。
ああ、神様。なんて安心だ!
私はメイドを追い払い、残りの階段を上った。廊下に出て、つま先歩きを始めた。彼女の睡眠を邪魔したくなかった。
それから、自分の部屋のドアノブを回すと…
「おかえり、孫」 彼女の冷たい声が背後から聞こえてきて、私はすぐに心臓が落ちた。
言い訳を考えながら、ドアノブをしっかりと握った。
「やあ、おばあちゃん」 私は明るい笑顔で彼女の方を向いたが、驚いたことに、彼女はすでにすごく近くに立っていた。
私は顔をしかめた。
「いつ… ここに、おばあちゃん?」 私はどもりながら、彼女の厳しい視線を避けた。
「どこから帰ってきたんだ!」 彼女は叫んだ。私は不安でドアに張り付いた。
ああ、いや… メイドは彼女が寝たって言ってたのに?
「仕事からだよ、おばあちゃん」 私は嘘をつき、頭を下げた。「このクソガキ!」 彼女は怒鳴り、私の耳を引っ張った。
「マジかよ、おばあちゃん、痛いよ」 私は痛みにうめき声を上げた。
「お前の秘書に電話したんだ。もう夕方からオフィスを出たって言ってたぞ」 彼女はまだ私の耳をひねりながら言った。
あのクソビッチめ!
明日、覚悟しておけ。
「信じてくれ、おばあちゃん、本当のことなんだ」 私は彼女の手を握りながら、弱々しく言った。
彼女は私の部屋のドアを開けて、私を乱暴に押し込んだ。
「次、こんな時間に帰ってきたら、耳を引っ張って食わせてやる」 彼女は激しく脅した。
私は何度も瞬きして、ゴクリと唾を飲み込んだ。
もう一度も私を見ずに、彼女は部屋を出て行った。
私は指を、彼女が引っ張ろうとした耳に当てた。すごく痛い。
クソ!
燃えるように痛い。
顎のラインが引き締まり、ネクタイを緩めた。
全部、秘書のせいだ。
明日、あいつは死ぬぞ… 私は心の中でうめいた。