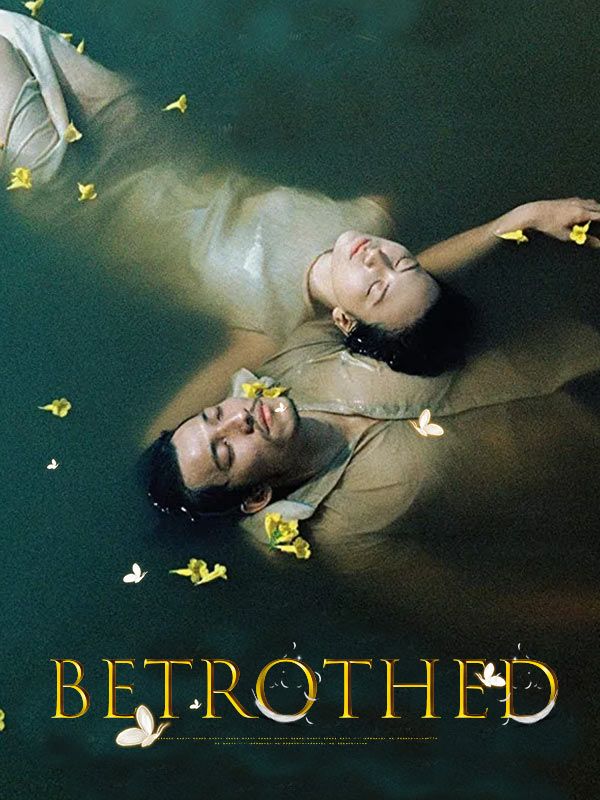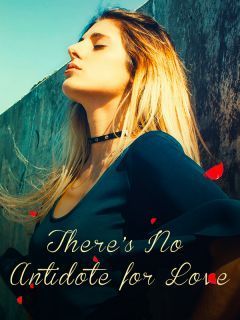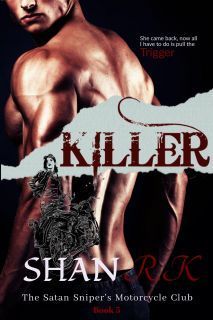「シャイエンヌ!」リビングからジョシュが怒った声で呼んだ。あたしはダッシュで駆けつけた。
「あ、うん?」あたしはどもった。
「今日、お前が話してた男は誰だ?」ジョシュは怒って聞いてきた。顔が真っ赤になってる。
あたしはジョシュのこと大好きだし、ジョシュもあたしのこと大好きだった。唯一の問題は、ジョシュがすごく心配性で嫉妬深いところ。過保護だし、意味もなく過剰反応したり怒ったりするんだよね。
「高校の同級生だよ、ハニー。なんでいつも嫉妬するの? 落ち着いてよ。」
ジョシュはちょっと頷いて、不快そうにおでこを擦ってる。もう立ってるし。
「ごめん」ジョシュは言い出した。「ただ、お前がいずれ俺からいなくなるんじゃないかって不安なんだ」
「そんなことしないよ、ジョシュ。もう言ったじゃん。あんたは仕事もある大人の男でしょ。ティーンエイジャーみたいなことやめなよ。もう違うんだから。」
ジョシュは髪をかきむしって、また座った。
「わかってるよ、ダーリン。ただ、いつだって、若い男どもがお前を狙ってるような気がしちゃうんだよ」
ジョシュは大げさだし、あたしはムカついた。でも、理解しようとはした。あたしはスタイルもいいから、ほとんどの男はあたしに言い寄ってくるんだよね。ジョシュと一緒にいると、まるで家族の白人のおじさんとか、お父さんの同僚といるような感じだったし。
ジョシュはイケメンじゃないし。ちょっと太ってるし丸いし。友達もジョシュのことそんなにカッコいいとは思ってないけど、あたしは大丈夫だった。欠点があっても愛してた。たとえば、ジョシュがお酒を飲みすぎるとか。
あたしはまだ、ジョシュを変えようとしてた。
あたしは今、ジョシュにどんなことを伝えようか考えてた。
「あのさ、ジョシュ?」
「ん?」ジョシュがあたしを見た。
「もうお父さんとお母さんには話して許可ももらえたから、あたしの計画についても話そうと思って」
「どんな計画?」
「映画の撮影と脚本を専門に勉強したいんだ。もう大学も見つけて、願書も出した。専門課程は3年かかるんだけど」
ジョシュは信じられないって顔であたしを見てる。ジョシュが認めてくれないのはわかってたから、もう内緒で全部やっちゃってたんだよね。
「は? シャイエンヌ、なんで? 結婚するまで一緒にいたいって言ってたじゃん」
「来年だよ、ジョシュ。あんたは仕事してるんだし、あたしは専門の勉強をして仕事に就きたいんだよ」
「俺の会社で仕事を紹介しただろ」
「あたしは映画制作とか脚本とか、撮影とか、そういうのに全部関わりたいんだ。合格したんだよ」
「でも…」
「お願い、ダーリン、大人になってよ。あたしはあんたのこと大好きだし、あたしのこと好きなら、あたしの夢を叶えさせてくれるでしょ。お願い。」
ジョシュは黙ってあたしを見てた。そしたらびっくりしたことに、テーブルの下からウォッカの瓶を取り出して、がぶ飲みし始めた。怒ってるんだ。
「ジョシュ、やめて」あたしは瓶を取り上げようとしたけど、ジョシュはあたしの手を払った。
「やめさせない。お前は好きなことをやるんだから、俺も好きなことをやる。」
「わかったわ」あたしは怒ってハンドバッグを取った。
「どこに行くんだ?」ジョシュはもう酔ってる。「
「お父さんとお母さんの家。今日夜9時にケイシャと一緒に出発するんだ」
ケイシャはあたしの親友。ジョシュの目が大きく見開かれた。
「旅行?」ジョシュは呟いた。
「うん。大学はニューヨークにあるんだ。本当は円満に別れたかったけど、あんたはお酒飲んでるし。まあ、ボストンからニューヨークまでは数時間だし。遊びに来てもいいよ。」
あたしはドアに向かって歩いて、またジョシュの方を向いた。
「着いたら部屋番号をメールするね。ジョシュのこと大好きだよ」あたしは呟いた。
ジョシュはあたしに背を向けて、お酒を飲んでる。
「ジョシュ?」あたしは呼んだ。
ジョシュが振り返った。運良くジョシュが投げた割れそうな瓶を避けることができた。
「出て行け!」ジョシュはあたしに叫んだ。
涙が目に溜まる。ジョシュはいつもこうだ。あたしは顔をしかめて家を出た。ジョシュのこと大好きだけど、ジョシュの悪いところは変えられない。
*
ジョシュのせいで、あたしの今日は台無しだった。最悪な気分。ジョシュはいい人だけど、自己中心的すぎる。ジョシュのこと好きすぎて、もう後戻りできない気がした。
***
あたしは3時に両親の家に着いた。
「ジョシュと話した?」お母さんが聞いてきた。
「うん、全然良くなかった」
「大丈夫よ。ジョシュはただ愛してるだけなのよ」
あたしは顔をしかめた。両親はいつもジョシュの味方だった。ジョシュが何しても。両親は厳しい人で、時には不公平だった。友達と遊びに行く許可をもらうのに何年もかかったんだ。あたしは「閉じ込められた」女の子だった。大学のおかげで、少し自由を知ることができた。でも、キャンパスに住んでなかったから、そんなに自由じゃなかったけど。両親は、授業が終わったらあたしを家に送ってくれる人を雇ってた。
パーティーとか、そういうのは一度も行ったことない。でも、今回は違う。ケイシャと旅行するし、両親から何時間も離れるんだ。本当の自由。やっとだ。
「そうね。じゃあ、荷造りしよっかな」あたしはそう言った。
「わかったわ、ダーリン」
***
その夜、両親に見送られて(ジョシュは来なかったけど)、ケイシャとあたしはニューヨーク行きの飛行機に乗り込んだ。大都会。あたしはまだ経験したことのないことをたくさん経験するだろう。それに、パーティーガールのケイシャがいるんだから、必然的にそうなる。
「さあ、これからあたしと一緒にパーティーに行くのよ、ハニー。もうボディガードはいないんだから。これから、あたしみたいに自由な黒人ガールとして生きるのよ。お嬢様みたいな生活じゃなくてね」ケイシャは笑った。
ケイシャはいつも、あたしの両親はまるで王族みたいだって言ってた。あたしも、そんな生活は嫌だった。高校ではいつも後ろの方に座って、友達がアーバンダンスのレッスンに行くのを見てた。あたしはクラシックバレエを強制的に習わされてたから、本当に退屈な経験だった。
-
「うん。あたしも、今までにないような生活を送ってみるよ」
「楽しい生活ね」ケイシャは微笑んで、あたしも笑った。もうワクワクが止まらない気持ちだった。