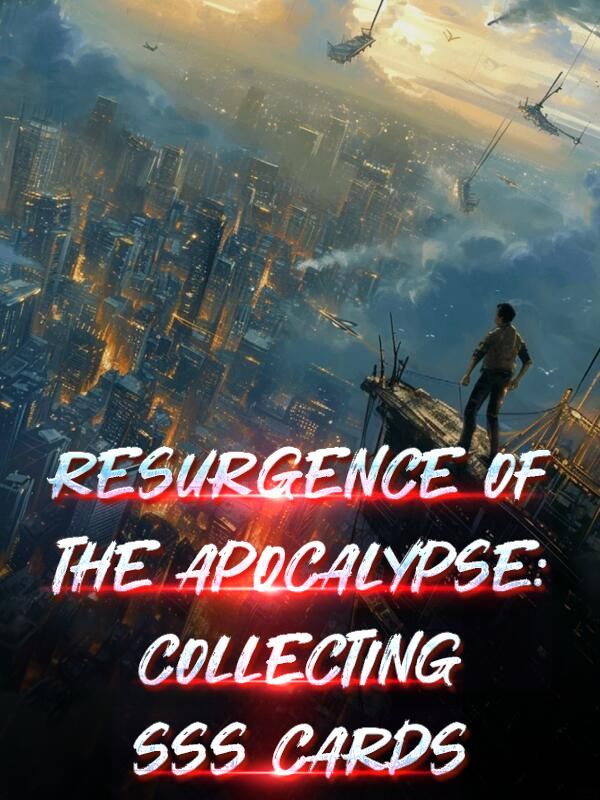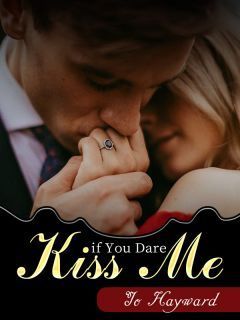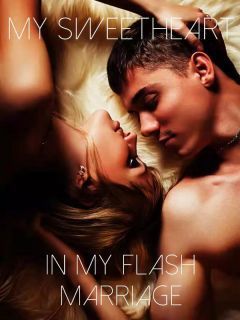「アリス……!」
「アリス!起きて!」
「オースティン!死んでも離さないからな!」
「ヘンリー、お前が生きてる時だって俺の相手じゃなかったのに、死んだら怖い? ふん、自分の女も守れないような力なんて、ゴミと何が違うんだ?」
「オースティン!ぶっ殺してやる!」
「死ね!」
……
……
ヘンリーは、狭くて窮屈な借り部屋で、バッと勢いよく起き上がった。
シャツも寝具も汗でびしょ濡れで、荒い息をしながら、充血した瞳には怒りが満ちていた。
でも、すぐにその怒りは困惑に変わった。
自分のコミュニティは敵に襲われ、仲間も友達も女もみんな殺されて、自分も撃たれたはずなのに、なんで急にこんなところにいるんだ?
「ここは……一体どこなんだ? 五年前の俺が住んでたアパートにそっくりだけど?」
ヘンリーは呟き、枕元の古いスマホに目を落とすと、それをタップして表示された時間を見て固まった。
「2077年7月3日……」
「7月3日?!」
終末が始まる前日だ!
「俺、生まれ変わったのか?!」 ヘンリーはちょっと信じられない気持ちと興奮を覚えた。
窓の外には、果てしなく続く人々の流れと車、そして甘いパンの香りが漂っている。
ヘンリーは自分が夢を見ていないことを確認するために、丸々五分間を費やし、エクスタシーの中でスマホのローン、クレジットカード、ファンドなどを開き、そこにある三十数万ドルのすべてを借り出した。
十二時間もすれば、世界の終わりが来る。そうなれば人間の文明は完全に破壊され、終末の法則に置き換わる。お金は自然と最も役に立たないものになる。
でも、その前に、このルーズなお金はまだ少しは役に立つ。
「ヘンリーさん、お出かけですか。焼きたてのクリームパン、いかがですか。」
階下のパン屋のスコットが、ヘンリーに声をかけた。
ヘンリーは足を止め、一見忠実そうに見えるが、実は腹黒いパン屋の主人を前にして、その瞳にはかすかな陰険さがよぎった。前世では、スコットに殺されそうになったからだ。
「前世では、俺は本当に馬鹿で、アホみたいな真似してたな。今度は違うぞ。」
そう思いながら、ヘンリーは少し笑みを浮かべ、「スコットさん、あなたのピックアップトラックを貸してくれませんか。」
スコットは何も考えずに鍵を放り投げた。「いいよ、どうぞ。」
ヘンリーは数歩歩き、振り返って言った。「夜になったら、たくさんのカードを拾ってくれよ。特に色のついたやつをな。」
スコットは少し首をかしげて、どんなカードなのかと尋ねようとしたが、ヘンリーはすでに車を運転して行ってしまった。
……
ヘンリーは六時間かけて買い物をし、さらに六時間かけて無理やり休息を取り、あっという間に午後11時50分になった。
手に持っていたタバコを落として踏み消し、リュックを胸にかけ、新しいマウンテンバイクを肩に担いだ。
スターシティ中心部の歩行者天国は、スターシティで最も賑やかな場所だったが、この時間帯では、すでに早朝で、道にはほとんど人がいなかった。
時間が十二時を指すと、地球外から聞こえてくるようなビープ音が鳴り響き、その直後、激しい雨が降り始めた。
過去と違うのは、過去の雨はただの雨だったのに対し、今の雨はトランプサイズのカードだったことだ。
これらのカードは、散らばり、密集していた。
カードには様々な色があり、白、緑、青、銀、金……
「金色のカードだ!」
ヘンリーは数十メートル先の金色のカードを鋭くロックオンし、目をギラギラさせて、全力で駆け出した!
予想通り、ヘンリーはスムーズに金色のカードをポケットに入れ、ジャケットのポケットに直接詰め込んだ!
「これは何だ? どうなってんだ?」
「ポーカーを輸送する飛行機が爆発したのか? でも、何も飛んでるものは見えなかったな。」
「このカードは何に使うんだ?」
歩行者天国周辺の住民が家から出てきて、困惑した目でカードの雨を見ていた。
この瞬間、ヘンリーは夢中でカードを拾い集め、何も選り好みせず、どんな色のカードでも、すべて登山バッグの中に詰め込んだ。これらは非常に重要な戦略的資源であり、他にないものなのだ!
すぐに登山バッグはカードでいっぱいになり、何千枚ものカードがあった。
ヘンリーは、カードでいっぱいのリュックを車の後部座席にかけ、新しいバッグを取り出して、同じ行動を繰り返した。
カードを拾いながら、銀色以上のカードがないか観察していた。それらは終末で生き残るために、優先的に拾わなければならないものだったからだ。
「え? あれは……?」
突然、ヘンリーの瞳孔が収縮した。空から降ってくるカードの雨の中で、鮮やかな光を放つカードがあり、前に向かって漂い落ちていたのだ。
「カラフルレジェンドカード!」
ヘンリーはゴクリと唾を飲み込み、レジェンドカードに向かって走り出し、空中で飛び込み、そのカラフルなカードをしっかりと掴んだ。
……
カードの雨は、一時間後についに止み、ヘンリーも何とか十三個のバッグにカードを詰め込んだ。歩行者天国全体が、ほぼ彼一人でカードを独占したようなもので、大雑把に見積もっても一万枚以上はあるはずだ。
ピックアップトラックの荷室が膨らんだ登山バッグを見て、興奮しないわけがない。こんなにリッチな戦いは、今までなかったからだ。
ますます多くの人々がカードを拾いに外に出てきたため、ヘンリーは人目を避けるために歩行者天国から車を走らせ、朝早く予約しておいたホテルに行き、次々と登山バッグをプレジデンシャルスイートに運んだ。
「これで十分だろう。あとは日の出を待つだけだ……」
ヘンリーはベッドに横たわり、激しく呼吸していたが、突然スマホが鳴った。スコットからだった。
「ヘンリーさん、どこにいますか?」
「どうしたんですか、スコットさん?」
「あのカードは何に使うんですか?」
「たくさん拾ったんですか?」
「ええ、あのカードはカラフルで綺麗です。」
ヘンリーは起き上がり、少し驚いた。「カラフルなカードがあるんですか?」
「はい、カラーのカードが一つ、金色のカードが一つ、銀色のカードが三つ、白と緑のカードがほとんどで、百枚くらいはあります。」
「ホテルにいます。カードを持ってきてください。何かお話があります。」
「はい、でも、タクシーを呼ぶには時間がかかります。遅刻しそうです。」
「待ってますよ。急がないで。」
午前3時40分。
スコットは部屋のドアをノックして入ってきた。使い古された古いスクールバッグに入ったカードは、ほとんど半分、数百枚ほどだった。
「あんまり拾ってないな。」
スコットはニヤリと笑い、「ヘンリーさんが教えてくれたから拾えたんだよ。そうでなければ、どうやって拾ったことか。ヘンリーさん、これは一体どういうことなんですか?」
スコットの心は疑問でいっぱいだった。
ヘンリーは呟いた。「君は、カラーカードを俺にくれる気があるのか?」
「ああ。」 スコットはポケットからカラーカードを取り出し、ヘンリーに渡した。
ヘンリーは深呼吸し、レジェンドカードをしまい、真剣な口調で言った。「スコットさん、朝八時まで待て。世界の終わりが来る。このカードは効果を発揮する。君がレジェンドカードをくれたから、そのお返しに、一つ提案させてほしい。まだ時間があるうちに、カードを拾い集めるんだ。拾えば拾うほど、終末で生き残れる可能性が高くなる。特に色のついたカードを。」
スコットは自嘲気味に笑った。「ヘンリーさん、そんな顔で見られると、ちょっと怖いですよ……終末って、本気で言ってるんですか?」
「冗談じゃないよ。」
スコットは、隅に置かれた十数個の登山バッグをちらりと見て、何も言わずに出て行った。その貪欲な視線をヘンリーは目に焼き付け、ただ不気味に笑っただけだった。
時間が過ぎ、東の空は魚の腹のように白く染まった。
午前7時30分。
世界の終わりまで、あと30分。
スコットが再び部屋のドアをノックし、息を切らして入ってきた。「ヘンリーさん、戻りました。この二人は私のいとこです。」
スコットの後ろには、18歳か19歳くらいの若い男が二人いた。
ヘンリーは警戒することなく頷き、三人を部屋に入れ、その隙にドアを閉めた。
「ヘンリーさん、ずいぶんたくさん拾いましたね、すごい。」 スコットはニヤリと口を開けた。
ヘンリーはかすかに笑った。「ああ。」
「兄貴、俺たちにも何パックか分けてくれないか。俺たちは家を出るのが遅かったから、カードはほとんど拾えなかったんだ。」
左側の若い男が笑いながら口を開き、わざとシャツをまくり上げて、ズボンのウエストバンドに刺された短剣を見せた。
ヘンリーは凍りつき、恐怖した。「スコットさん、どういう意味ですか?」
スコットは少し陰険な笑みを浮かべた。「ヘンリーさん、誤解しないでください。他の意味はありません。ただ、いくつかカードを借りて使いたいだけなんです。さっき三人で外をうろうろしていたんだけど、収穫は全然だった。」
「つまり……俺を強盗したいと。」
「強盗なんてきつい言い方はやめてくれよ、借りるだけだよ。そんなにたくさん持ってるんだから、きっと構わないだろ。」 スコットは両手を広げた。
「分かったよ。お前たちにそれぞれ一パックずつ分けてやる。」
ヘンリーはため息をつき、自分のリュックを取りに行こうとした。
若い男がそれを掴もうとしたその時、冷たいサーベルが突然、彼の喉を突き刺し、若い男は反応する間もなく、喉が瞬時に切り裂かれ、血が勢いよく噴き出した!
彼は目を見開き、片手で喉を抑え、もう片方の手で空に向かって何かに掴みかかりながら倒れた。
「リード!」
「ハリス!」
スコットは息を呑み、信じられない様子でヘンリーを見た。「お前……殺したのか?」
ヘンリーはまるで別人になったかのように、ぼんやりとした表情で、まるで人を殺すのが食事や飲み物を取るのと同じくらい簡単なことであるかのように見えた。
「お前がこうなることは、予想していた。」 ヘンリーは無造作にサーベルについた血を自分の服で拭い、落ち着いた口調で言った。