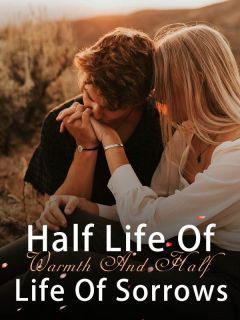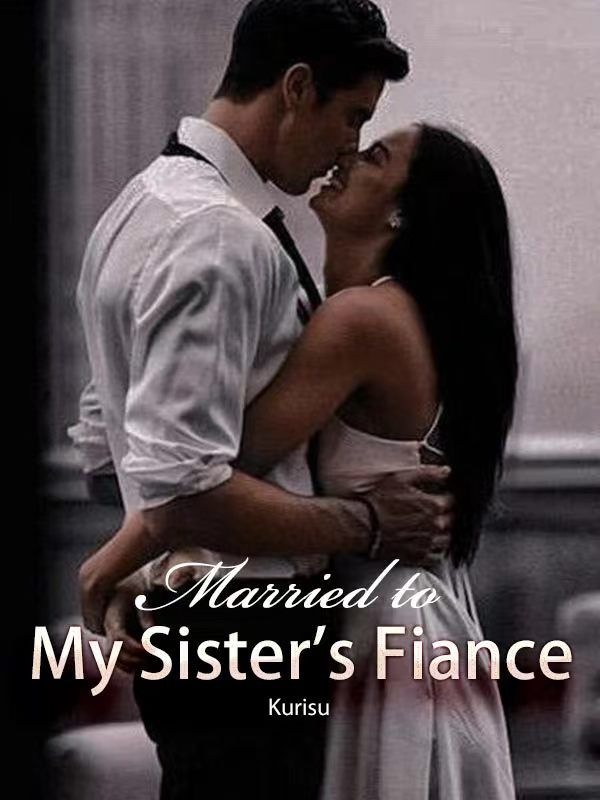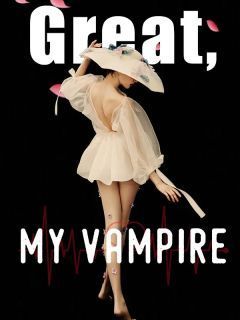10年前。
ガブリエラ。
エルが私を嫌ってるのはいつも分かってたけど、私を傷つけるためならどこまででもやりかねないって知って、本当にゾッとする。数週間前にあったことのせいで、私はいつも不安で、彼女が次にどんな嫌がらせをしてくるのか、私を傷つけるためだけにどんなことするのかって考えてる。彼女との衝突は避けるようにしてるんだけど、変なことに、彼女は私たちの喧嘩を少し楽しんでるみたいで、私を侮辱してイジメる口実を作るために、積極的に仕掛けてくるんだよね。
フラッシュバック(2週間前)
「ガブリエラ、本当に子犬を飼ってあげた方がいいよ。そうすれば、いつも家で一人ぼっちだって感じないで済むからさ」私の親友で唯一の友達、マーティンが気の毒そうな声で言ってきて、私は顔をしかめた。
「もう言ったでしょ、子犬は飼えないの。ママが許してくれないから。ペットがいるのは嫌いだし、エルも嫌いなのよ。それに、あの2人が家をほぼ支配してるって分かってるでしょ」って彼に念を押したら、電話の向こうで彼がため息をつくのが聞こえた。
「お前の家族は、お父さん以外はみんなクソみたいな奴らだよな。お父さんは家にいないのか?」って彼は聞いてきた。
「何か用事があるらしくて、出かけたの。それに、つまんないからって、いつもお父さんに構ってもらうわけにもいかないし。お父さんはすごく仕事があるし、私がつまんないからって邪魔するのは不公平だし」って私が返事したら、彼はまたため息をついた。
「ガブリエラ、他の人と友達になる努力をしろよ。一生、人との付き合いを避けてちゃダメだ」って、私がつまんないとか一人ぼっちだって不平を言う度に、いつも同じことを繰り返すんだよね。
「訂正します、マーティン。私は人を避けてるんじゃなくて、人が私を避けてるの。双子の妹が、酷い性格で意地悪だって広く知られてる女の子と友達になりたい人なんていないでしょ」って、私は彼にまた念を押したら、彼はきっと今、目を回してるだろうな。
「だったら、自分を主張して、お前のバカな妹を恐れてお前を避けるのはフェアじゃないって、みんなに分からせろよ」って彼は返事してきた。私はため息をついた。彼は、本当に簡単なことみたいに言ってるけど、実際はそうじゃないんだよ。
ガブリエラは私を嫌っていて、みんなにもそう感じてほしいから、私と友達になろうとする人は、彼女の気に障って、誰もそんなこと望んでないんだよね。
「もう、いい加減…」って私が言いかけたら、突然、私の部屋のドアが開いて遮られた。
「話があるの」って、エルがいつものようにイライラするような口調で言ってきて、知らないうちに苛立ちのため息が漏れた。
「また電話するね」って、私はマーティンに急いで言って、電話を切った。
「何がしたいの、エル?」って私は疲れた声で聞いた。
「そんなに私をここに居させたくないって顔しないでよ。私も別にいたくないんだけど、友達の誕生日パーティーに行く準備をしてて、ママがあなたを誘ってって言ったの」って彼女は言ったので、私は顔をしかめた。
「なんでママが、あなたのパーティーに私を誘うように頼むの?」って私は明らかに信じられないって感じで言い返すと、彼女は目を回した。
「あなたにもっと外に出てもらいたいらしくて、私の方があなたより明らかに活発な社交生活を送ってるから、仕方なくあなたを連れて行けって言われたの」って彼女は言ったけど、私は信じてなかった。
「嘘でしょ、エル。私が知ってるエルなら、絶対断るはずだから、私を巻き込まないで、あなたのやりたいことに」って私は疲れた声で警告したけど、彼女は出て行こうとしない。
「いいから、あんたなんか誘うつもりもないわよ。だって行ってもらいたくないもん。でも、ママは私を外出禁止にするって脅してきて、あなたのせいで外出禁止になるわけにはいかないの。信じられないなら、ママに聞いてきてもいいわよ。でも、1時間で準備してよね、わかった?」って彼女は怒って脅してから、私の部屋から出て行った。
私は実際にママに確認したら、ガブリエラは嘘をついてなくて、ママにパーティーに行きたくないって言ったら、ママは私が1日中家にいるせいで、社交生活を奪ってるって、ものすごく怒ったんだよね。
マーティンに話したら、彼は驚いたことにママに賛成したけど、双子の妹は信用できる人間じゃないから、気をつけろって付け加えるのも忘れなかった。
それで、私は今、ケリー・ジョーンズの巨大な豪邸の前に立ってて、彼女は16歳の誕生日パーティーを開いてて、大音量の音楽、派手な照明、それに、この子達が吸ってるものが何なのか分からないけど、酷い悪臭から判断すると、このパーティーは私にとっては絶対ロクなことにはならないだろうな。そこにいる人の半分以上は、私の友達の基準に合わないだろうし、正直、私はここにいることにあまり興奮してないんだよね。
「よく聞いてなさい、ガブリエラ。中に入ったら、あんたは自分のことだけ考えなさい。あんたに何が起きても、それはあんたの責任であって、私の責任じゃないから、わかった?」エルが警告してきて、私はしぶしぶ頷いてから、彼女の少し後ろをついて行くのを見てた。
当然だけど、彼女はすぐに友達に囲まれて、私がすぐそばを通り過ぎても、誰も気づいてないみたいだった。
ものすごく大きな音楽が私に激しくぶつかってきて、もうすぐ吐いてしまいそうだった。私と同年代の女の子達が、恥ずかしげもなく、音楽に合わせて体を官能的に揺らしてて、何人かは男の子達とイチャイチャすることに夢中だった。
私は静かな場所を見つけて座ったんだけど、そこはキッチンで、こういうパーティーで出される飲み物は普通信用してないから、何も飲まなかった。
携帯を取り出して、大親友のマーティンにテキトーにメールを送ったら、すぐに返事がきた。
M:大丈夫?
G:うん、退屈してるだけ!
M:何か楽しもうとしたりした?それとももう可能性を断念した?
G:…
M:?
G:ただ退屈してるだけ。
M:(ため息)大丈夫だよ、アルコール入りのものは飲まないでね。
マーティンに返事をしようとした時に、ルーカス・ギャロウェイってやつが私を遮ったんだけど、彼は学校で一番人気がある奴の1人で、ずっと前から私がすごく夢中になってる奴でもあるんだよね。バカだって分かってるんだけど、まあいいや。
「やあ、ガブリエラだよね?」って彼は聞いてきて、私はポーカーフェイスになった。
「うーん、そ、そう、やあ、私はガブリエラ」って私は緊張して返事した。
「会えて嬉しいよ、ガビー。俺はルーカス。こんなことして悪かったんだけど、飲み物を飲もうとしてて、ちょっと君に惹かれたから、ただ挨拶したかったんだ」って彼は返事して、いつものように、私の舌は突然凍り付いて、次に何を言えばいいのか分からなくなった。
「何か飲み物いる?」って彼は、気まずい沈黙を破って聞いてきた。
「うーん、別に」って私は返事した。まだ明らかに恥ずかしそうだった。
「水はどう?俺は何か飲んで、君が何も飲んでないのは変だと思うから」って彼は言って、私は実際は何も飲みたくなかったんだけど、しぶしぶ水をもらうことにした。
彼と私は、数分間、すごくどうでもいいことを話した。彼はフットボールが好きだってこと、クラブのスター選手でいることがどんなことかってことを教えてくれたり、自分の好きなこと、嫌いなこと、興味のあることについても話してて、私は別に面白い話もなかったから、ただ聞き役に徹することにしたんだよね。
私は突然疲れてきて、目眩もしてきて、2秒ごとに疲れたようにあくびせずにはいれなかった。
「退屈?俺の話、長すぎた?」ルーカスは顔に妙な表情を浮かべて聞いてきた。
「ううん、別に。ただすごく疲れてるだけ」って私は返事したら、私は明らかに彼が珍しい笑みを浮かべるのを見た気がした。
「眠いの?部屋をとってあげようか?」って彼は聞いてきたんだけど、私が返事する前に、私はすでに彼の手に首を抱えられて、どこに向かうのか分からないけど、上の階に連れて行かれてた。
酷い頭痛をますます悪化させる大音量の音楽以外、ほとんど何も見えなかったし、聞こえなかった。私は目を開けていることすらできなくて、突然、私はルーカスのものと思われる男性的な手に、ベッドだと思う柔らかい場所に置かれたのを感じ始めたんだ。
「ここはどこ?」って私は疲れて言ったけど、彼は私を黙らせて、寝るように促してきて、私は目を閉じて眠りたい衝動を必死に抑えようとしたんだけど、突然の疲労感からは逃れられなくて、最後に覚えてるのはルーカスの顔が一瞬見えたことで、その後はすべて真っ暗になってブラックアウトした。
****
1時間後…
自分の体が知らない場所に横たわっていることに気づいた瞬間、私の目はパッと開いた。私は何が起こったのか、どうやってこの部屋に来たのかを思い出そうとしたんだけど、その瞬間に、私の心は落ちた。
自分の体に何か変化がないか確認しようとしたんだけど、服も下着もまだそのままだったから、ほっとため息をついた。
部屋のドアが開き、疲れた様子のルーカスが部屋に入ってきて、すぐにドアに鍵をかけた。
「な、何をしたの?」って私は恐怖に震えながら、何が起こったのか、何か理にかなった説明があるといいんだけどって祈って言った。
「俺が何かしたように見えるか?」って彼は言い返してきた。
「じゃあ、なんで私がここにいるの?」って私は激しく問い詰めた。
「ガブリエラ、正直に言うと、お前が起きててくれて感謝してる。手短に言うと、俺はお前の命を救ったんだ。信じるか信じないかは別としてな。お前の妹はお前に薬を盛って、お前が気絶してる間に、イタズラするつもりだったんだ。でも、俺はそういうやり方はしないから、お前に触らなかった。そうすることで、他に実際にやりたがる奴を見つけさせない方がいいと思ったんだ。つまり、お前はレイプされることから救われたんだ」って彼は説明して、私は完全にポーカーフェイスになった。
「レ、レイプ?あ、あたしにそれをしろって頼んだの?」って私は、信じがたくて、そう尋ねると、彼が説明を再確認したので、私の心はさらに落ちた。
「忠告するけど、お前は俺達が何かあったように振る舞った方がいい。そうすれば、お前の妹が、お前に襲いかかってくる他の奴を見つけなくなるからな。お前の妹は、お前が涙を流してここから出ていくのを見たいって思ってるんだから。気をつけて」って彼は急いで付け加えて、私が助けてくれたことに感謝する前に部屋を出て行ってしまって、私は自分の妹がどれほど酷い人間なのかを考えなければならなくなったんだ。