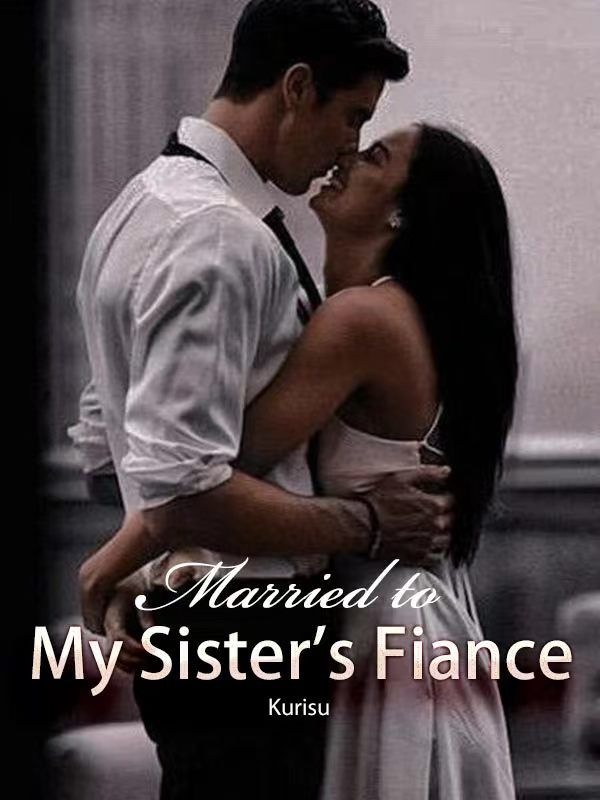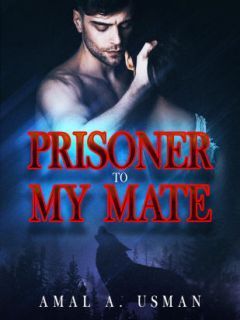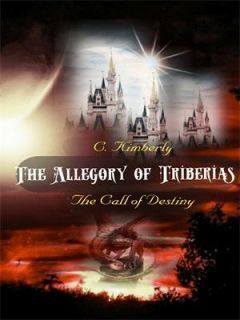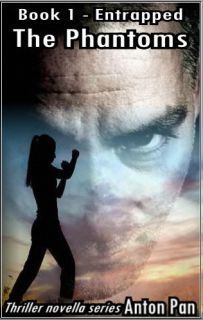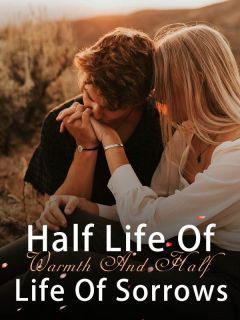ヤッシーの視点
ああ、全然眠れなかった夜だった。めっちゃクラクラするし。
階段から落ちたせいで体がめちゃくちゃ痛くて、昨夜は全然グッスリ眠れなかったんだよね。
階段掃除してたら、オーブリーにぶつかられて、あれってオーブリーがやったって認めないんだもん。あれは事故だったってさ。運良く、あの時、階段の五段目にいて、一番上じゃなかったから良かったけどさ。でも、あの段でもマジで体にキツかったんだよね。
ヒップと肩をチェックしてもらうために、クリニックに連れてってくれるのかなって思ったけど、それはただの夢だった。
この家にいる家族は、あたしのことなんて全然気にかけてくれないから、あたしは感じてる痛みを全部我慢するしかなかった。
昨夜は眠れなかったし、体調も良くないんだけど、れでも、あたしに割り当てられた仕事、つまり家の掃除をしない言い訳にはならなかった。
それで、あたしの持てるすべての力を使って、ベッドから起き上がって、家事を始めたんだ。
皿を洗っていたら、大きい声で、苛立った声で、あたしの名前を呼ぶのが聞こえたんだ。
「ヤッシー?!ヤッシー!」
それがグレンダおばさんの声だって気づいた瞬間、体が震えたんだよね。
あたしはおでこに汗をめちゃくちゃかき始めて、また何か悪いことしちゃったのかなって思ったんだ。
お皿を持ったまま、あたしの手は震えて、心臓が胸の中でドキドキしてた。
足音が近づいてくるのが聞こえて、おばさんの声がずっとあたしの名前を叫んでるんだ。
「ヤッシー!!!」
それから、オーブリー、つまり娘が、あたしを連れて彼女の顔が現れたんだ。
「ヤッシーがいるわ、お母さん。」オーブリーはあたしを悪魔みたいに見ながら言ったんだ。
オーブリーは脇に寄り、グレンダおばさんはあたしの方に近づいてきて、あたしの顔を平手打ちしたから、あたしは床に倒れたんだ。
「あーっ!」あたしは苦痛で叫んで、頬を涙が伝って、唇の端に血の跡を残したんだ。
「グレンダおばさん?」あたしは彼女を見て尋ねた。
「ネックレスをちょうだい!」彼女はあたしがまだ話している最中に言ったんだ。
ネックレス?グレンダおばさんはネックレスについて話してて…あたしはそれについて知らなかったんだ。
「ネックレス?グレンダおばさん、どんなネックレス?」あたしは頬を押さえながら彼女を見て言ったんだ。
「ああ、ヤッシー、冗談はやめてよ!」あたしが言ってること理解してないみたいなフリはやめて!「今すぐネックレスを渡しなさい!」
「あたしは何を言ってるのかよくわからないんだけど…」
「嘘つき。」オーブリーはグレンダおばさんの後ろで呟いて、静かに笑ったんだ。
グレンダおばさんの足があたしの頭に着地して、あたしは背後の壁にぶつかったんだ。
「ごめんなさい、グレンダおばさん、でもそのネックレスがどこにあるのか全然わからないんです。」あたしは言ったんだ。「持ってないんです。」グレンダおばさんがあたしの言うことを聞いてくれるといいんだけどって思ってた。
彼女は雑巾を取って、あたしの顔に投げつけたんだ。
床に座りながら、あたしは体をまっすぐにし、手で顔を拭いたんだ。それからすぐ、痛む腕に強烈な一撃を感じて、グレンダおばさんは食器用洗剤を取って、あたしに投げつけたんだ。
「お願い、グレンダおばさん、落ち着いてください。あたしは持ってないんです。」あたしは懇願して、彼女に傷つけるのを止めてくれるように頼んだんだ。あたしは完全にエネルギーを使い果たしたんだ。食べ物もなくて、ただアザと疲れた体だけだった。あたしは、もうその痛みに耐えられないんじゃないかって思ったんだ。
彼女はあたしの痛む腕を引っ張って、立たせようとしたから、あたしは叫んだんだ。
「あーっ!」
彼女はあたしの顎に右手を押さえつけて、あたしの顔を彼女に近づけたんだ。恐怖と寒さで唇が震えたけど、あたしはどうしても彼女に真実を説明しようとしたんだ。
「グレンダおばさん、あたしはそのネックレスのことを知らないって言ってるの、信じてください…」
「あんたは完全な嘘つきだわ!あんたみたいな女を誰が信じるって言うのよ?!そのネックレスがオーブリーにとってどれだけ貴重か、よくわかってるでしょ。今日はキング家がオーブリーとジェイス・キングとの結婚のために来る日なんだから!あれを使うはずだったのに、なくなってるじゃない!」彼女は歯を食いしばって叫んだんだ。
「わかりました、グレンダおばさん…」
「あたしたちの日を台無しにしようとしてるんでしょ!死にたくなければ、ネックレスを返しなさい。」あたしが本当にネックレスを盗んだかのように結論づけたんだ。あたしだけじゃないのに、メイドもいるのに、なんであたしだけが疑われてるんだろう?
「かわいそうな泥棒。」オーブリーは同情して首を横に振って言ったんだ。
でも、あたしがもう持っていないものって、一体何があるの?
「あたしはネックレスを盗んでないって誓います、グレンダおばさん。」もしあたしを殺したとしても、ネックレスは見つからないわ。「持ってないんです。」あたしは深呼吸して言ったんだ。
彼女はあたしの顎を押して、あたしはバランスを崩して、一歩後ろに下がったんだ。
「クソ野郎!ネックレスを渡さなかったら、間違いなく死ぬわよ。どれだけ高いか、あんたは知ってるでしょ!そして、あんたはそれに興味を持ったに違いないわ。でも、そんなことしないで!ネックレスを返しなさい。さもないと、一生後悔することになるわよ。」
オーブリーは前に出て、「なんで認めないの?ネックレスを盗んでないって否定するのはやめてよ。あなた以外、誰もそんなことしないわ。」って言ったんだ。
あたしは、マジで聞こえてる?あたしは色んなこと我慢してこのヴィラにいるのに、まだあたしを疑う気?
「探してみます。」あたしは言ったんだけど、それはその時のあたしが出来る唯一の選択肢だったんだ。あたしを信じてくれないだろうし、グレンダおばさんはあたしがそのネックレスを見せれば、やっと文句を言うのを止めるだろうし。
「行け、バカ!見つけて、渡しなさい。30分だけあげるわ。もう待てないわ。キング家の人たちはすぐ来るんだし、うちの娘にそれを着せたいんだから。」
30分?死が待ってる?どうやって見つけたらいいの?まだ、どこにあるか見当もつかないのに。マジで最悪!
彼女たちがあたしの言い分を受け入れないのは分かってたから、あたしはただ頷いたんだ。