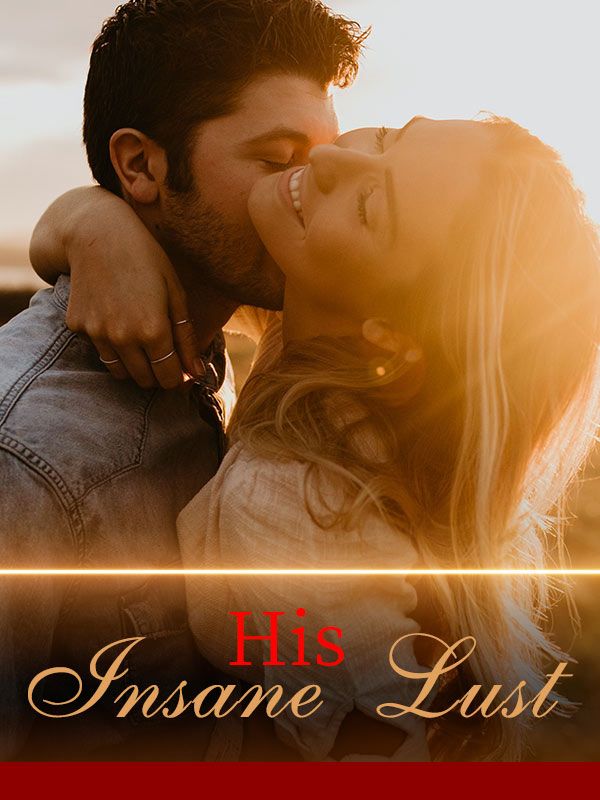「アンナ!まだいる?おじさんが来たよ」おばあちゃんの階下からの叫び声を聞いて、現実に戻った。
「ちょっと待って」って返事した。前に終わらせておくべきだった荷造りを始めてから、時間がゆっくりになってたんだ。
瞑想するたびに、時間の流れなんて意識してない。まるで子供の頃みたいに、ここで遊んでただけだったような気がするんだ。部屋全体をぐるっと見回した。今日出発する日だって考えると胸が痛い。たくさんの思い出、嬉しかったり悲しかったりしたこと。だって子供の頃から、この家がずーっと憧れだったんだから。おばあちゃんと一緒に、お母さんとお父さんの死っていう、人生で最悪の悲劇が起きてから、ずいぶん経ったなぁ。
あの恐ろしい出来事を忘れようとするけど、何度も蘇ってくる。そして、私が唯一縋り付くのは「正義と復讐」って言葉だけ。
荷物を運び始めた時、別に大変じゃなかったから楽だったんだ。階下に降りるとすぐ、おばあちゃんがいつものハンモックで、ぼーっとしてた。
なんだか胸が締め付けられるみたいで、すごく悲しくなった。だってさ、悲しくない人なんていないでしょ?両親が長い間支えてくれた人から離れなきゃいけないんだから。
目にじわじわと涙が溜まってくるのを感じた。自然と、持ってた荷物を置いて、おばあちゃんに近づいたんだ。ぎゅーって抱きしめたかったけど…やめたんだ—もしそうしたら、もっと辛くなって、ここから離れられなくなるって分かってたから。
「おばあちゃん」って、おばあちゃんのそばに行った。いつもの特別な笑顔をしてた。誇らしげな笑顔—その笑顔は、私にとってすごく特別だったんだ。それを見るだけで、胸の中に閉じ込められてた悲しみが全部消えていくようだった。
「誇らしいよ、孫…」って、優しく言った。涙が止まらなかった。
「おばあちゃん、これどうしたらいい?」って、大きく約束した。無理やり笑顔を作って、頬を伝う涙を拭った。
「おばあちゃんはいつもあなたをすごく愛してるってこと、忘れちゃだめだよ。たとえ世界があなたを拒絶しても、私はあなたのそばにいるからね。いつも孫を愛して、決断する前に自分の心と頭の声を聞きなさい。すごいね、アンナ」って、おばあちゃんは私の髪を耳から出した。
「いつも覚えておきなさい。『人を尊敬できないなら、ペットのベンズみたいに愛しなさい』」その言葉も言った。おばあちゃんはいつも私にそう言ってた。人に意地悪になったりする私に—特に私を尊重してくれない人に対してね。この言葉は変だけど、私にとっては意味があるんだ。
おばあちゃんの手を握った。「おばあちゃん…寂しくなるよ」って、真剣に言った。おばあちゃんの手を強く握った。前よりずっと大きくなってた。小学校に連れて行ってもらった時、私の手を握ってくれた、あの滑らかで柔らかい感触をまだ覚えてる。今はシワシワで、血管が浮き出て見える。おばあちゃん、年を取ったんだね…私が20年間してもらった良いことを、今度は私が返したい。
「私も寂しくなるよ…また来る?」って、優しい口調で言った。
「うん、約束だよ、おばあちゃん」って、おばあちゃんの手の甲にキスした。おばあちゃんの今の気持ちが、すごく重く感じる。目に涙が溜まっていくのが見えたし、どんなに辛いのかも感じた。もし、いつもみたいに、そばにいられたらいいのに。でも、そうじゃないんだ—自分自身で自立することも学ばないといけないし、一生懸命働いて生きていかないといけないし、みんながいる世界に飛び込まないといけない。
「あら、ドラマは終わりよ。おじさんがずいぶん待ってるわよ」って、おばあちゃんは席を立って、私が置いていった荷物のところに行ったんだ。
「大丈夫?重くない?アンナの荷物」って、おばあちゃんはカバンを一つ持った。私は3つのバッグしか持ってない。大きいのと、お金とか貴重品が入ってる中くらいの、あと服用のキャリーバッグ。
「大丈夫だよ、おばあちゃん、できる!」って、すぐにバッグを一つ持って肩にかけた。おばあちゃんは私を玄関まで見送ってくれた。おじさんはもう待ってた—少し前に、退屈そうだったんだ。
「おばあちゃん、ここで気をつけてね、無理しないでね」って、一つずつ荷物を三輪車に積む時に言ったんだ。
「あなたもね、私のことなんか気にしないで。おじさんと従兄弟たちがいるから」って返事した。三輪車に乗って、おじさんがエンジンをかけた。
「大好きだよ、おばあちゃん!」
「私も大好きよ!」車がゆっくり動き出して、おばあちゃんが見えなくなるまで手を振った。微笑んで、目の前の小さな鏡を見た。
これは、お母さん、お父さん、あなたたちへ。心の底から愛してる気持ちを表現する言葉は、足りないくらいだよ。
数分経って、バスの駐車場に着いた。おじさんに運賃を渡そうとしたけど、受け取ってくれなかった。
大丈夫だよ、って、押しが強いんだから—私が自分の金に足せばいいって。自分が持ってるお金を前に、躊躇しちゃったんだよね。
小学校からの友達のアルシアと話したんだ。彼女のマンションは、私がホテルで働く場所に近いから、一緒に住もうって誘われたんだ。
最初は断ったんだけど、マンションを借りるだけとか、恥ずかしいし、彼女も納得しなかったみたい。一緒にいないのは変だとも言われたし。それで結局、私も賛成したんだ。
「ヘネラル・トリアスカビテ!」って、バスの車掌さんが、サインを持ちながら、白い五つ星バスを指差して叫んだ。すぐに荷物を持って移動した。
マノンがバスに近づくのを手伝ってくれた。乗客は少なかったんだ。真ん中の席を選んだ。後ろの方も好きじゃないんだよね、イライラするかもしれないから。
結局、乗り心地もよくて、ゆっくり進んでいくうちに、前の大きなテレビの番組が気に入らなくて。すぐにイヤホンをバッグから取り出して、長い旅のためにサウンドトリップを始めたんだ。