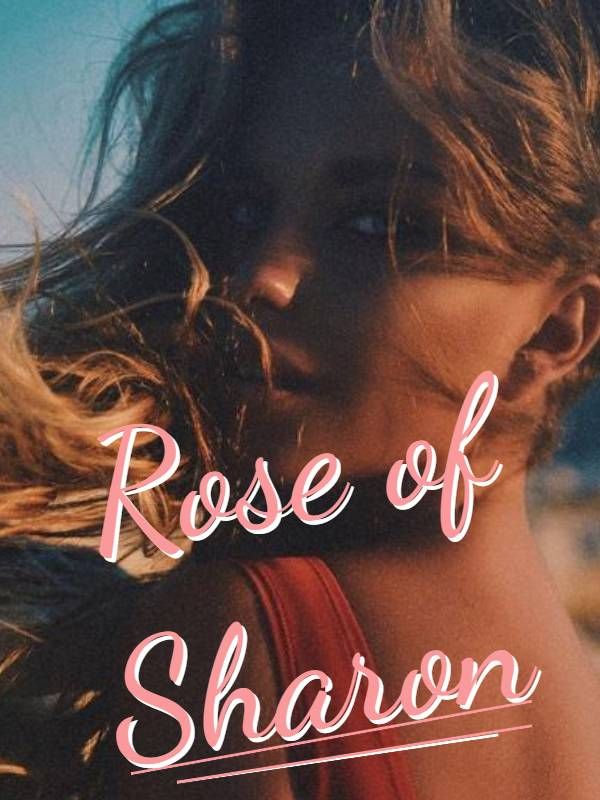紹介
目次
紹介
都合の良い結婚に閉じ込められた、デヴォンシャー公爵の氷のような相続人であるアリシアは、傲慢で腹立たしいほどハンサムな従兄弟、ウィリアム・キャヴェンディッシュと結婚することになる。 家族は彼らの結婚を定め、家の遺産を守ろうとしたが、アリシアは夫を望んでおらず、特に子供の頃から彼女を苦しめてきた悪名高いプレイボーイはなおさらだった。
独立心を保つことを決意したアリシアは、奇妙な取り決めを確立する。つまり、奇数日は夫婦の義務を果たし、偶数日は至福の孤独を過ごす。 しかし、気乗りしない花嫁に魅了されたウィリアムは、彼女の冷たい外見を打ち破り、その下に隠された情熱的な女性を目覚めさせようと決意する。
結婚が進むにつれて、彼らの強制的な近さは禁断の欲望の嵐を巻き起こす。 リージェンシーイングランドの華やかな舞踏会と厳格な社会慣習の中で、アリシアとウィリアムは意志の戦いを繰り広げ、義務は誰も否定できない愛と衝突する。 彼らの型破りな取り決めは悲劇につながるのか、それともウィリアムはデヴォンシャー公爵の氷のような相続人の心を溶かすことに成功するのだろうか? 情熱がすべてのルールに逆らう、燃えるようなスローバーンロマンスに浸ってください。
もっと読む
すべての章
目次
第1章:非常に不都合な結婚
第2章:結婚の夜
第3章:夜明け
第4章:二夜目
第5章:奇数日の特異性
第6章:三夜目
第7章:順応
第8章:条項
第9章:七回の合意
第10章:抱擁
第11章:反撃
第12章:返答
第13章:欲望
第14章:ソネット
第15章:空想と弱点
第16章:告白
第17章:最も動揺するキス
第18章:さらに狂おしい取り決め
第19章:ファンタジー
第20章:結婚
Chapter 21: The Portrait
Chapter 22. Hot and Cold
Chapter 23. Observation
Chapter 24: Lessons
Chapter 25: A Cousin's Plaything
Chapter 26: The Revels
Chapter 27: Return to London
Chapter 28: In Which a Wife Takes Her Leave
Chapter 29: Conjugal Matters
Chapter 30: A Fit of Pique
Chapter 31: A Most Unwelcome Suitor
Chapter 32: The Cravat and the Cad
Chapter 33. A Most Grievous Grudge
Chapter 34: Progress
Chapter 35: Contraception
Chapter 36: A Most Unreasonable Jealousy
Chapter 37: Tolerance No More
Chapter 38: A Most Improper Arrangement
Chapter 39: Moving House
Chapter 40: Married Life
Chapter 41: Blessings
Chapter 42. Finis
Chapter 43: Progeny
Chapter 44. The Hunting Season
Chapter 45. The Thrill of the Chase
Chapter 46. A Most Singular Understanding
Chapter 47: Another World
Chapter 48. The Dream
Chapter 49: The New Year
Chapter 50. The Age of Innocence
Chapter 51. Of Misdiagnoses and Missives
Chapter 52. Of Reunions and Rather Uncomfortable Carriages
Chapter 53: Letters and Farewells
Chapter 54: A Scarred Victory
Chapter 55: Of Journeys and Jitters
Chapter 56. An Unexpected Inheritance
Chapter 57: The Eldest Son
Chapter 58: Daughter
Chapter 59. The Angel
Chapter 60: William & Alicia