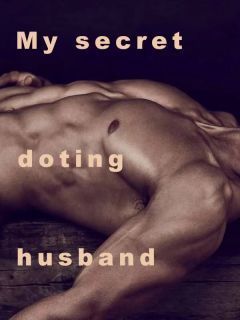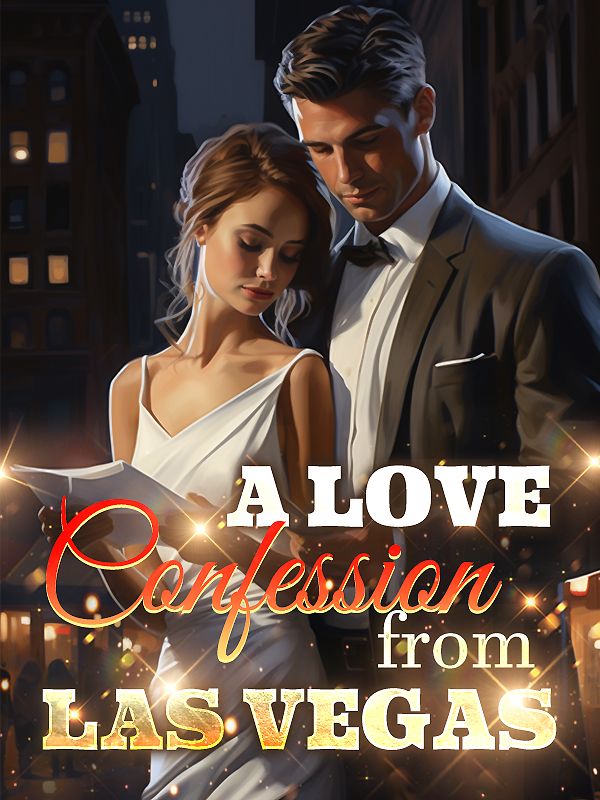年に一度の会社の夏のパーティーで、会場は色んな人たちでごった返してた。伝説とか神話がテーマだから、フォーマルな感じじゃないはずなのに、お堅い人たちはすぐピリピリし始めるんだよね。ペタルズ化粧品と製薬会社の共同経営者が主催者だけど、会社の顔であるピーター・トーレスさんのほうが人気あるんだよね。彼のパートナーなんて、ほとんど誰も知らないんじゃない?だって、世界中を旅してばっかりなんだもん。
「トーレスさん、このパーティー、素敵ですね!全部完璧に仕上がってる。イベントプランナーさんの連絡先を教えてください!」カレッタは褒めちぎって、あっちを見たり、こっちを見たりしてた。
「あいつ、新しいダイヤのネックレスをみんなに見せびらかしたいだけよ」ピーターの奥さんのレジーナは、長女のジャクリーンに囁き、ジャクリーンは口元を隠してクスクス笑った。
「ありがとう、カレッタ。でも、全部ジーナ(レジーナ)が企画したんだよ。彼女に話しかけてみて。ちょっと失礼」ピーターは軽く会釈して、スマートに退場。レジーナは彼に「意気地なし」と口パクして、彼はウインク。最高にセクシーな笑顔を見せた。彼女は小声で文句を言いながら、カレッタに最高の作り笑顔を向けた。
男たちはエスコートを連れて出入りし、愛人や奥さんたちも一緒。テーマのおかげで、女性たちは好きなだけ露出度の高い格好ができるんだよね。胸元も露わだし、日焼けしたお腹や背中、金髪に派手なメイク。生バンドはスローワルツにぴったりのソフトな曲を演奏してて、みんなの腰が揺れてた。
突然、音楽が止まり、みんなの視線は、ある男性が入ってくる入り口に釘付け。モデルみたいな女性を連れた、めっちゃ魅力的な男。嫉妬深い女たちの視線は、彼に無邪気にもたれかかってる女を食い入るように見てた。そのミステリアスな男は、右目に黒髪を垂らしてるんだけど、その悪い笑顔が会場全体を魅了したんだ。
「リチャード、会えて嬉しいよ」ピーターは大声で叫んで、ハグしようと近づいた。リチャードのほうが背が高いのに。リチャードはセクシーな低い声で笑い、兄弟みたいにピーターの背中を叩いた。
「ただいま、ピート。あ、失礼!ピート、こっちはローレン。僕のデート相手。ローレン、こっちは…」
「ピーター・トーレスさん。誰でも知ってるピーターさん」ローレンが言い切って、頬を赤くした。
「うわ!僕のこと、いないことになってるじゃん。ジーナはどこ?会いに来たのに、あんたじゃなくて、おばさん」
「ここにいるわよ」ジーナが現れて、夫の親友からフレンチキスを受け取るために顔を左右に傾けた。お決まりの挨拶の後、彼女は彼をみぞおちパンチ。彼は痛そうなふりをした。
「ジーナ、また何したんだよ?」リチャードは、ぷっくりしたピンクの唇を尖らせて聞いた。
「私のベビーシャワーも、子供の誕生日も、結婚15周年も、会社の15周年も…全部すっぽかしたくせに!最低!」彼女はもう一発お見舞いしようとしたけど、彼はうまく避けた。
「ちょっと待った!今ここにいるだろ?何とか埋め合わせするから、約束する。で、僕の可愛い子たちはどこ?」リチャードは話題を変えた。彼が旅に出てる理由は、彼だけが知ってることだし、それが一番いいんだ。
「こっちはクリスティン、私たちの長女」ジーナは紹介し、赤面してるクリスティンに誇らしげな笑顔を見せた。
「はじめまして、ロッシさん。来月18歳になります。優等生なんです」彼女はきちんと言った。彼女は母親の自慢の娘で、父親の知恵も受け継いでるんだよね…
「綺麗で優秀、最強の組み合わせだな」リチャードはクリスティンの手の甲にキスをして褒めた。彼女は完璧な金髪を後ろに流し、母親の後ろに立った。ジーナは周りを見回して、ダンスフロアの人たちの間をキョロキョロしてた。
「ジャクリーンはどこ、クリス?」ジーナは尋ねた。
クリスティンはイライラしたように目を回した。「捕まえられなかったの。あの子のこと、分かってるでしょ」
ピーターはため息をつき、しわの寄った額を指で揉んだ。この娘には本当に手を焼くんだよな。
「ごめん、誰を探してるんだっけ?」
「次女のジャクリーン、つまり私たちが呼んでる「トラブル」。クリス、彼女に電話して。一体何してるんだか…」ピーターは本当に心配してた。ジャクリーンは本当に変わった子だったから。歳相応の行動はしないし、適切な格好もしないし、彼女の一番好きな遊びは、運転手を置いて地下鉄に乗ることだった。ベビーシッターはみんな辞めていったけど、彼女には全然効果がなかった。ピーターは彼女を祖母のところに送ろうと思ったけど、変な行動で高齢の祖母が早死にしそうで怖かったんだ。
「電話するわ。また変なことして、携帯切ってないといいんだけど」クリスティンは、スマホの画面を叩きながら批判した。彼女は画面を見て軽く笑った。ジャクリーンの名前を「リトルインプ」って登録してるんだ。彼女は番号をダイヤルしたけど、電話はジーナのバッグの中で鳴った。レジーナはイライラして咳払いした。ジャクリーンは明らかにまた冒険に出かけてるんだ。彼女は鳴ってる電話を取り出して、ピーターに渡した。
「またよ、ピート。この前あんなに言ったのに」
「あいつのワイルドさはどこから来るんだろ。女の子なのに、まだ16歳なのに」
突然、リチャードが笑い出して、激しく震えた。「どこから来るか分からない?ピート、お前のクレイジーな時代を忘れちゃったのか?あ、ジーナと一緒になる前のことだよ。あの頃のお前は、マジでやばかった。ジャクリーンはちょっと自由にさせてあげればいいんだよ。16歳は二度と来ないんだからな」
ピーターは不満そうに鼻で笑った。「もちろん、お前はそんな乱暴な行動を擁護するだろうな。だって、お前はろくでなしなんだから」
みんなはリチャードをからかって楽しんだ。
「とにかく、会う前に、写真を見せてあげるよ」ジーナは彼の顔にスマホを押し付け、彼はそれを受け取った。リチャードは、全身黒革の服を着た可愛い女の子を見た。彼女はピクシーカットで、ブロンドの白髪が耳の後ろでカールしてる。ゴシックモデルみたいで、引き締まった長い脚は、タイトな革パンツで強調されてた。マスカラは、彼女のほとんど透明な目に注目を集めてた。彼女は…生まれつき美しい。クリスティンとは正反対で、クリスティンは上品だけど、現実離れしてる感じだったんだ。
「ふむ、可愛い娘さんたちだな、ジーナ。ピートの悪い遺伝子が二人には受け継がれなくて良かったよ」リチャードは冗談を言い、また笑い声が響いた。