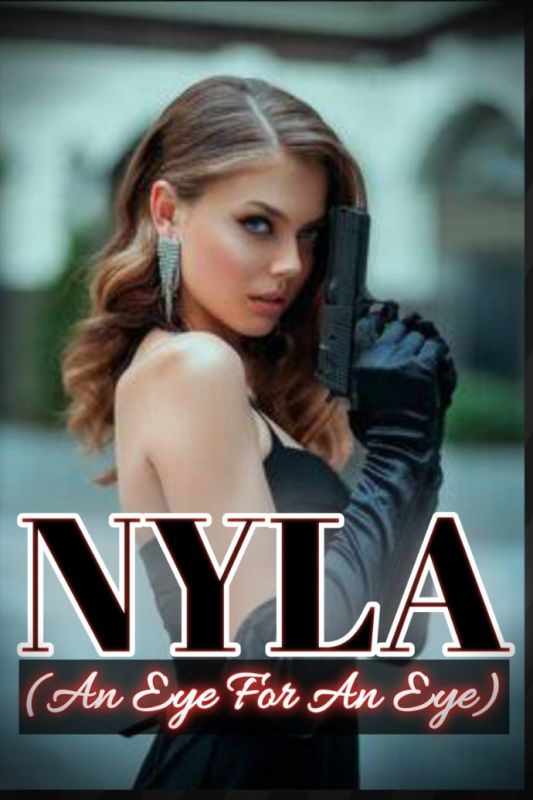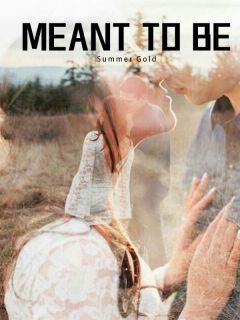ドアのところに立って、もう一度聞いた。案の定、その音は部屋から聞こえてきた。彼らのうめき声と、お尻を叩く音が聞こえる。彼女はドアを開けて、不健全で不浄な光景を目にした。そこに、ベッドの上には、彼女の婚約者であるはずの人が、見知らぬ女性とイチャイチャしていたんだ。彼らはその行為に夢中で、彼女がいることに気づいていない。
「もっと強く、ベイビー」と、その女性のうめき声が聞こえた。
エミリーはもう我慢できなかった。床を足で強く踏みつけた。それが彼らの注意を引いた。ジェイデンは、食べ物に入ったハエを見るような目で彼女を見た。彼らは隠そうともしなかった。
「一体どうしたんだ?」ジェイデンは怒って尋ねた。
「マジで!ジェイデン?」エミリーは返した。
ついに、ジェイデンはズボンをはくという分別を見せた。彼はベッドシーツをその女性に投げつけ、彼女も覆うように指示した。
「邪魔しないでくれる?」ベッドの上の女性が尋ねた。彼女は、億万長者との時間を邪魔されたことに明らかに怒っていた。
「出て行け」ジェイデンは素っ気なく言った。
「出て行くべきなのは私ではなく、彼女よ。私はあなたの婚約者なんだから、ジェイデン」エミリーは怒った。
「婚約者だって」その女性はあざ笑った。「あなたは何様?ジェイデン・メーソンと結婚しようとしている底辺の貧乏人?彼はあなたと結婚するかもしれないけど、決してあなたを愛することはないわ。自分の立場をわきまえなさい。」
エミリーはジェイデンに向き直った。
「少しは私を尊敬してくれない?結婚式はあと2日後よ。」
「それで…」その女性は言い始めた。
「…黙りなさい」エミリーは遮った。「あなたは黙って、自分の愚かさを恥じるべきよ。誰とでも関係を持ったりして。」
「ジェイデン。彼女が私をいじめてるの!」その女性は、愛嬌のあるフリをしながら言った。
「エミリー、出て行け」ジェイデンは再び言った。
エミリーは、ジェイデンが彼女ではなく、婚約者であるその女性を擁護したことに苛立った。
「あなたとはもう結婚しないわ」彼女はきっぱりと言った。
ジェイデンは微笑んだ。「なんだって?そんなことできないだろう。」
「見てなさいよ」エミリーは答えた。
「もし僕が君を拒否したら、誰も君と結婚しないよ。誰もそんなことしない。大人しくして、今すぐ出て行け。優しくしてるうちに。さもないと、後悔させてやる」ジェイデンは脅した。
エミリーは彼の言葉を考え、それが真実だと悟った。ジェイデン・メーソンほど力のある男に拒否されたら、誰も彼女と結婚しようとしないだろう。彼女は向きを変えて、部屋を出た。しかし、結婚を進めるつもりはなかった。
エミリーはタクシーを呼んで家に帰った。彼女は静かに座り、涙が頬を伝った。彼女はまだ21歳の若い女の子だった。それでも、彼女が生まれてから、運命は彼女に微笑んだことはなかった。両親は彼女を軽蔑し、家では決して安らぎを知らなかった。彼女は自活するために働かなければならなかった。それにもかかわらず、家族はまだ彼女を経済的自立と豊かさを得るために利用したがっていた。彼らは彼女を血の一滴まで利用する決意だった。彼女の母親、父親、そして妹はすべて罪を犯していた。誰も、誰も残らなかった。彼女は誰も味方ではなかった。彼女の罪と、そのような酷い扱いを受けるに値する彼女がやったこと、彼女は知らなかった。
「はい」親切な運転手が彼女にティッシュペーパーを差し出した。その時、彼女は自分が泣いていたことに気づいた。彼女はティッシュを受け取り、無理やり笑顔を作った。
「ありがとう」彼女は丁寧に言った。少なくとも、今日、彼女に親切にしてくれた人が一人いた。もし彼女の両親も彼女に優しくすることを学べたら…
「着きましたよ」運転手が告げ、彼女を考えから現実に引き戻した。エミリーは深呼吸し、車から降りた。彼女は地獄のような家に帰ってきた。
彼女はドアを開け、極度の敵意を抱いて彼女を見つめる三組の目に遭遇した。
「こんばんは、お母さん、お父さん」彼女は挨拶し、自分の部屋にこっそり行こうとした。
家族は夕食をとっていた。彼女の姉、ローズは彼女に目をむいた。
「なんで家にいるの?メーソン家の豪邸で夜を過ごすべきでしょ」と、母親のオリビア・グラントはすぐに指摘した。彼女は自分の声の残酷さを隠そうともしなかった。彼女はどんな犠牲を払ってもエミリーを追い払いたかった。
「彼とはもう結婚しないわ」エミリーは答えた。
「何!」オリビアとローズは同時に叫んだ。
「冗談でしょ。私はあなたにこの家族のチャンスを台無しにさせるつもりはないわ。私たちを恥ずかしくさせないでよね。そうよ。させないわよ。さあ、急いでメーソン家に戻りなさい」オリビアは嫌味を込めて言った。
エミリーは動揺しなかった。オリビアは驚いた。エミリーはいつも生涯従順だったから。
「違うわ、お母さん。私は結婚しない…」
ローズは彼女の言葉を遮り、平手打ちをした。「よくも私たちの母親に逆らったわね?お父さん?」ローズは父親に助けを求めた。
ウィリアムズ・ハーパー氏は沈黙して見ていた。彼は、エミリー、つまり彼の末娘のために少し心を痛めた。エミリーも父親に頼った。彼は彼女の最後の希望だった。
「お父さん、私はジェイデンと結婚できないわ。彼は私を大切にしてくれないわ」彼女は泣いた。
「大切にするだって。あなたはもっといいものは受け取らないわ、使えない子!」オリビアは吐き捨てた。
エミリーは、自分の母親からこれらの言葉を聞くのに心を痛めた。彼女はそれに慣れていたが、毎日のコメントは彼女に異なる影響を与えた。父親に懇願するのは無駄だった。彼は彼女にわずかな同情を抱いていたが、彼の妻と彼女の母親も彼に大きく影響を与えていた。彼は妻を見て、彼女は彼に死の睨みを送った。彼は口を開き、エミリーに言った。
「エミリー、お母さんの言うことを聞きなさい。メーソン家に戻りなさい。」
いつも同じ古い話だった。いつも「従う」。エミリーにはその家で発言権はなかった。彼女は涙と怒りの中で自分の部屋に入った。
ローズと彼女の母親は互いに視線を交わした。
「お母さん、彼女を行かせないといけないわよね?たくさんのお金と幸せな人生を送るチャンスを失うわけにはいかないわ。名声、富、力、そしてそれに続く幸せのことを考えてみて。行かせられないわよね?」ローズは尋ねた。
「確かに。彼女は結婚しなければならないわ。でも、彼女は頑固なのが証明されつつあるわ。結婚式は2日後。そして、今夜彼女は彼の家にいなければならない。間違いを犯してはいけないわ。さもないと、彼らは考えを変えてしまうかもしれない。どうすればいいの、私の可愛い子?」オリビアは答えた。
ローズはしばらく考え、言った。
「私に任せて、お母さん。彼女が自分で行くか、私が彼女を行かせるわ。薬を盛って送り込むだけでいいの。」