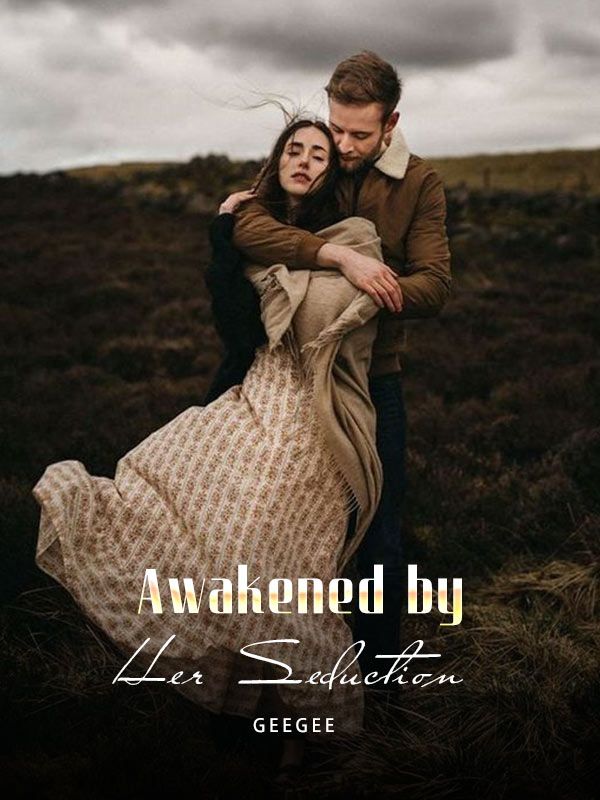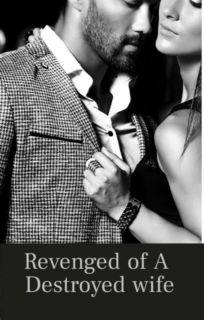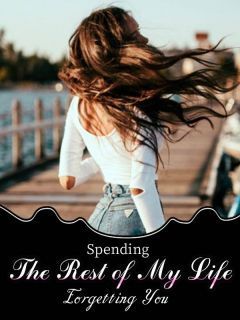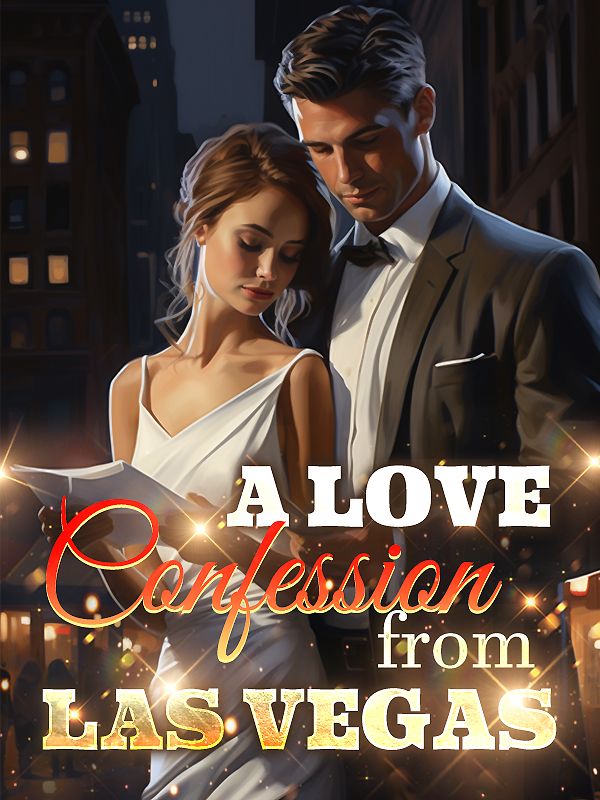プロローグ
走って疲れ果てて、彼女はどうしても息を整えるために崖っぷちで止まらざるを得なかった。三日間も追跡され、逃げ場がなくなった彼女が、ここにしか逃げ場はないと思った。
窮地にあった彼女は、ある男を呼び出した。子供の頃から婚約していた男、心を捧げた男に、この悪夢から助けに来てほしかったのだ。
あの男、そして彼の「家族」に騙されていたと知っていたら、自分の居場所なんて教えなかっただろう。自分の愚かなミスが原因で、彼女は男が顔を歪ませて近づいてくるのを、不安と恐怖を感じながら見守っていた。
こんな日が来るとは想像もしていなかった。逃げ場はもうどこにもなく、すべての選択肢を使い果たし、彼女を待っているのは死だけだった。
「君の存在は、俺がこれほどまでに努力してきたすべての邪魔になる。だから、すまない、これが最後だ」と男は冷たく言い、引き金を引いた。
響いたのは、少女の胸を貫く銃声だけだった。その衝撃で若い少女はよろめき、崖から転落した。
彼女の顔には笑顔が張り付いていて、唇から血が流れ、胸からは血が滲み出ている。これが終わりだと彼女は悟っていた。初めからそうすべきだった。なぜなら、甘やかされて育ったにもかかわらず、彼らは彼女と時間を過ごそうとしなかったからだ。
家族を幸せにするために、彼女は彼らが血を吸うたびに耐えた。子供時代の記憶がなくても、彼女は何も求めず、ただより良い未来を願った。
もし疑って答えを求めていたら、これは痛みのない死だっただろう。この死は、彼女が十数年来、家族が隠し続けてきた暗い秘密を初めて知ってから、認めようとしなかった一つのことを証明した。彼女はただ、彼らの子供のクローンだったのだ、そしてそれは本当に辛かった。
-----
三年後
部屋は少し暗く、月明かりだけが部屋の唯一の光源だった。時間を見れば午前二時頃だったが、その巨大なプラットフォームの上には、二つの体が隙間なく絡み合っていた。
女性のうめき声と叫び声はとても魅力的で、まるでサキュバスがその家の男を夜に訪れたかのようだった。男は目の前の女に夢中で、彼女の叫び声をもっと聞きたくて、彼女の涙を舐めたくて、余計に頑張って仕事をした。
どうしてこうなったのだろう?若い女性は、まるで飢えたニンフや猛獣のように振る舞いながら、自問自答していた。何が起こっているのか嫌いなわけではなかった。実際、彼女はそれを楽しんでいて、もっと欲しかった。しかし、初めてのことが、上司に、酔っ払っているわけではないけれど、ハイになっているときに奪われるなんて、想像もしていなかった。
もし彼が次の日に起きて、荷物をまとめて出て行けと言ったら?彼女には行く場所がなく、この仕事を得るために一生懸命働いてきたのに、今は、ある狂人が上司に媚薬を盛ったせいですべてが終わってしまうのか?
しかし、この男がベッドでどれだけエネルギッシュだったかを思い出すと、彼女はすべてを許した。彼が彼女に強要したとしたら?この男は彼女に親密さのエクスタシーを体験させてくれた。彼は素晴らしい恋人で、彼が彼女を何度もオーガズムにさせたことを考えると、顔が赤くなる。男は彼女の赤くなった顔を見たら驚くだろう。
これまで多くのことを経験してきたヴァニティは、ただ波に乗って、それが続く間、その瞬間を楽しむことに決めた。そんな野獣に奪われることは、もし彼女がまた別の男と一緒になることを考えるなら、間違いなく彼女の基準を上げるだろう。
空からのそんな無料の食事で、彼女は自分の仕事を窓から投げ捨てるかもしれない。彼女は前の三ヶ月でたくさんお金を貯めた。
チャンドラーは、このサキュバスの顔の変化に気づき、安堵した。彼女は読みやすいが、彼は彼女が多くの秘密を隠していることを知っていた。一方、誰が秘密を持っていないというのだろうか?
彼は慈悲を見せないことに決めた。なぜなら、彼女はショーを続ける気があるからだ。彼は、彼にそんな強力な薬を渡すような大胆な人間は、きっと大いに報われるだろうと確信していた。
彼はヴァニティが長い足を彼の腰に巻きつけ、別の誘いだと受け取り、まるで狂人のように彼女に飛びつくのを見た。自分自身を完全にコントロールできる人が、こんな風にコントロールを失うとは、薬だけのせいではなく、目の前のこの女の子のせいでもあるだろう。
彼女の体のすべてが、奪われることを叫んでいて、暗闇の中でも見える咬み跡は、彼が彼女をどれだけ狂ったように求めているかを示していた。彼は、彼女と何時間も一緒になった後も、止まる気配を見せなかった。チャンドラーは、人生で初めて、この女の壁の中に埋もれたいと願った。あの壁は彼を吸い込み続け、閉じ込めて、彼が彼女を容赦なく荒らし続けることを可能にするのだ。
彼はただ、彼女が彼の深い中で一緒に死ぬのを見たかっただけだ。このすべての試練が終わった後でさえ、彼は彼女を離すつもりはなかった。
チャンドラーは、彼女の足の一つを取り、肩にかけ、彼女に突進し続けた。彼は彼女に飛び乗り、涙を浮かべたあの揺れる瞳を見て、彼女に情熱的にキスをした。
彼はあまり経験がなかったが、これほどの親密さの後、近づいていっている。こんなに素敵な人が見過ごされてきたことは、彼に彼女に対する独占欲を感じさせた。彼女は彼のものだ、そして誰も彼女を彼から奪うことはできない。
***
ヴァニティは、ものすごく体が痛くて目覚め、あの野獣のような男を心の中で何度も呪った。目を開けると、まだチャンドラーのシャツを着て、彼のベッドの中にいることに気づいた。部屋にはまだ二人の愛し合った匂いが漂っていて、夜明けまで二人の間に何があったのかを思い出し、顔を赤らめた。
どうすれば、男は彼女を何時間も拷問するほどのスタミナを持てるのだろう?もし彼が薬を盛られたときはいつもこんな反応をするのなら、彼女はすべての薬を奪って燃やし、将来のために自分用にいくつか取っておきたくなる。
たとえ彼女の体がひどく痛くても、彼女はそれだけでは死なないだろう。彼女が望まない限り、誰も彼女を殺すことはできない。ベッドから抜け出すのに苦労した後、彼女は自分が掃除に使っていただけのマスターベッドルームを見回した。数秒で、彼女はパニックに陥り始めた。壁の時計は午後二時頃を示していて、つまり彼女は寝坊したということであり、彼はそれを許したということだ。
彼女は頭を振って、まずトイレに行った。自分の姿を見て、言葉を失った。全身にキスマークだらけなのに、どうやって自分の部屋に行けばいいのだろう?彼はいったい、彼女にこんなことをするほど冷酷だったのだろうか?
ヴァニティは、体を覆っていたシャツを引っ張り、もう一度叫んだ。まるで彼が彼女にタトゥーを入れたかのようで、彼は彼女の一番プライベートな部分さえも残さなかった。これは完全に彼女を当惑させたが、彼女はそれに耐え、おそらくそれがなかったかのように振る舞うしかなかった。
彼女は自分の窮状に夢中で、遠くの音を聞き取る能力も失われていた。誰かが彼女の部屋に一緒に入ってきたことにも気づかず、鏡に別の影が現れるまで気づかなかった。
「マジでビビったわ!」ヴァニティは、自分の裸体がさらされていることも気にせず、思わず叫んだ。
「俺の従業員があんなに汚い口をきくとは思わなかったよ。お前が汚い言葉を喋りまくって、俺にやらせろって懇願するまでは。そんな喋り方好きなのか、愛しい人?」チャンドラーはゆっくりとした口調で彼女に話しかけた。
これを聞いたヴァニティはパニックになり、彼の顔を見て、悪魔のような笑顔を浮かべた。彼女は人生で多くの残酷な人間を見てきたが、この男は間違いなくトップにいるだろう。
彼に対してそんなことを言った今、彼は彼女を許すのだろうか?二人の間に何があったかを秘密にするために、彼を殺して処分するのだろうか?
「私…これ…」ヴァニティは何も考えることができず、目の前の獣をただ見つめていた。ただ彼を見ているだけで、体がゾクゾクし、彼のタッチをもう一度求めて、下腹部がむず痒くなるのを感じた。