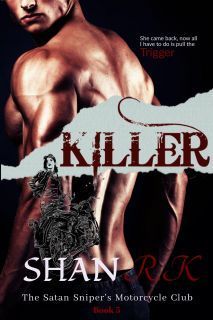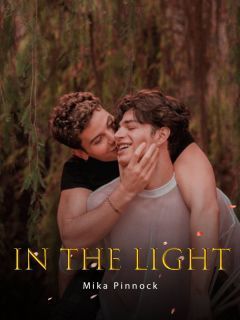「カイリヤ、おしゃべりは終わりにして、ご飯が冷めないうちに食べちゃいなさい。食べるまではおしゃべり禁止って、何度も言ったでしょ。なのに、全然聞かないんだから」 マリアムお母さんは、2歳児みたいに娘を叱った。カイリヤと兄弟たちは、ご飯も忘れて話し込んでいたんだよね。
「でも、お母さん、サビルにスマホで見せてただけだよ。ずーっと『見せてくれ』ってうるさくってさ…」
「で、まだ話してるってわけね?」
しょうがないから黙ってご飯を食べ続けたけど、お母さんはまだ文句を言い続ける。いつもの説教が始まった。
「一体、何回言ったら、こんなもの(テーブルのスマホを指して)をここに持ってくるのをやめるの?」
「あんたたちは、それしかできないんだから。ご飯食べ終わってから、永遠にスマホでもいじってなさい」
カイリヤと兄弟たちは顔を見合わせて、首を振った。お母さんは、一番上から一番下まで、ご飯中に話したりスマホをいじったりすると、いつも叱る。もう慣れっこで、やめられないんだよね。黙ってご飯を食べ続けていたら、またお母さんが何か気づいた。
「ちょっと、お嬢さん。何してるの?」
カイリヤは飲んでいたコーラの瓶を置いて、お母さんがまた何に怒っているのか不思議そうに見ていた。
「上品さのかけらもないの? 女性は瓶から直接飲んだりしちゃダメでしょ。コップに入れて、優雅に少しずつ飲むの。ストローを使うのもいいわね。男の人だってそんなことしないわよ。みっともないから。やめなさい」
兄弟たちは笑いをこらえきれず、大声で笑い出した。カイリヤはイライラした。別に瓶から飲むのは変だと思わないし、つまらないコップに入れるより美味しいんだもん。お母さんは、ずーっと前からそんなことばっかり注意してくるけど、もう血みたいなものだから、やめられないんだよね。
「ごめんなさい、お母さん」 カイリヤの優しくて優しい声にお母さんは微笑んだ。
「大丈夫よ。今度はコップを使いなさいね」
カイリヤは不機嫌そうに口を尖らせたけど、お母さんは笑った。
「どうしたの、ベイビー?」
「お母さん、そういう呼び方は嫌いだよ。もう赤ちゃんじゃないもん。もう立派な女の子なんだから」
お母さんは心から笑い、男の子たちもそれに続いた。
「でも、あんたは私のベイビーよ。いつまでもそうよ。ずっと、永遠に、お母さんのベイビーなのよ、可愛い子」
「やめてよ、お母さん。私、23歳だよ? 見てよ、こんなに大人になったんだから、あのベビー時代はとっくに卒業したんだから」 カイリヤはドラマチックに肩に手をかけた。お母さんはもっと笑った。今、二人は超高級なリビングルームの王様の椅子に座っている。サビルとイブラヒムは部屋に戻って、お母さんとお気に入りのカイリとサディーの三人だけになった。
「サビルがいなくなっても、あんたはまだ私のベイビーだったわよ。だって、可愛くて甘えん坊だったもん。いつも私のそばにいたし。男の子たちは、お腹が空くまで私を探そうともしなかった。今でもそうよ。大人になったのにね。だから、あんたはまだ私の甘えん坊なの」 お母さんはカイリヤを抱きしめて、カイリヤは母親の肩に頭を預けた。
「お母さん、でも、私がベイビーより近かったんだよ。赤ちゃんが来るまではね、私が自分の場所を無理やり取られたんだから」 サディーは胸に手を当てて、悲しそうなふりをした。
「お兄ちゃんは、ベイビーには大きすぎるでしょ」 カイリヤはからかった
「それは昔のこと。あんたはいつもあっち行ったりこっち行ったりで、全然家にいないから、私が一緒に過ごせる時間なんて、もう覚えてないよ。一緒に1週間まるまる家にいたことなんて、いつが最後だったかな」 お母さんの目に少しだけ悲しさが浮かんだ。
カイリヤは、お母さんがいつもあちこち旅行に行っているから、どうやってみんなと時間を過ごすんだろうって不思議に思った。お母さんはすごく忙しい人で、家族のために使える時間はあまりない。少しは仕事に、ほとんどは旅行に使っている。それでも、短い時間でも一緒に過ごすことができて、みんな感謝していた。それなのに、サディーが一緒にいないって文句を言ってる。
「まただよ、お母さん。私がどれだけお母さんと一緒にいたいか分かってるでしょ。でも、仕事でほとんど時間取られちゃうんだよ。それに、お母さんの方が忙しいんだから、私たちも時間がないんだよね。休暇が重なる時だけなんだよ、一緒にいられるのは。ほら、それが理由だよ。でも、みんなで一緒にいるのが大好きだし、家が賑やかになるのも本当に好きだよ」 サディーはソファで伸びをして、足を組んだ。
「大丈夫よ、私もいつも忙しいし。旅行が好きで、世界を探検したり、新しい人に会うのが好きなの。でも最近は、あんたたち子供たちと一緒の時間を増やすために、それを減らさないといけないわね。サディー、ここで結婚しなさいよ。そうすれば、孫たちが近くにいてくれるから。可愛がりたいんだから」 カイリヤとサディーは顔を見合わせて、黙って笑った。
マリアムお母さんは、何回目かの姿勢を直して、椅子の端に座った。カイリヤは立ち上がって、クッションを取って、お母さんの隣に置いてあげた。お母さんは、その優しくて愛情深い仕草に微笑んだ。
「そういえば、この前あんたが行ったアイシャ・タンブワルさんの娘さんに会ったんでしょ?」 サディーに尋ねた。サディーは、その言葉に急に居心地が悪くなった。
「うん、会ったよ。ちょっと部屋から何か取ってくるよ。すぐ戻るから」 母親の完璧なお見合い講座が始まる前に、彼はすぐにリビングから出て行った。
「どこに行こうとしてるの? 戻ってきて、詳しく話してよ。今回は、前回みたいに私をガッカリさせないでよね?」 カイリヤは母親に笑った。
「お兄ちゃんが、ああいうのどう思ってるか分かってるでしょ。女の子に会うように言われるのは、すごく嫌なんだよ。すごく居心地悪そうにするんだから」 カイリヤは母親の手に触れて、理解を求めようとした。
「もちろん分かってるわよ。でも、もう若くないんだから、そろそろ紹介されたたくさんの女の子の中から選んだ方がいいと思うの。なんで、あの素敵な女の子たちが彼の心を奪わないのかしら」 お母さんは首を振って嘆いた。
「そうだね、お母さんもそう思うよ」 カイリヤは、お兄ちゃんが母親がすごく信じているお見合いを嫌っていることをよく知っていた。母親は、相手を選ぶのは、同じような上流階級の人たちが一番だって思っていた。彼らにふさわしい相手は、物質とかお金とか、贅沢な生活とかじゃなくて、愛が基盤じゃないといけないのに、たまに忘れてしまう。
サディーは数分後にリビングに戻ってきた。母親は顔を上げて彼を見た。
「逃げるのは終わり? ようこそ、さあ、女の子との出会いがどうだったか話して」
サディーはくすくす笑った。「まあ、うまくいったよ。でも、いつものように、こういう出会いはいつも僕にとってはああいう風に終わるんだ。だから、全部順調だよ」
「どういうこと? 女の子は気に入らなかったの? 綺麗じゃなかった? それとも、あんたのタイプじゃなかった? 何か問題があったの?」 お母さんは驚いて尋ねた。
「女の子は良かったよ。ただ、興味がなかっただけなんだ。そう言ったら、彼女もそれでいいって言ってたから。彼女には好きな人がいるからね。それでいいんだよ。問題はないよ」
「あの女の子をあんたにすごく勧めたかったのよ。彼女以上の人には、もう会えないかもしれないって思ったから。弁護士だし、すごく教育も受けてるし、育ちもいいから、良い妻にも良い母親にもなるわよ」 お母さんは話し続けた。
カイリヤは何か言おうとしたけど、やめた。彼女は親友のスハイラを通してその女の子を知っていたから、母親にその女の子のことを教えるのは、本当はカイリヤの役目だったんだ。だって、母親は、その女の子のことをよく知らないみたいだったから。その女の子は一人っ子で、すごく甘やかされてて、母親が言うほど礼儀正しくないし、全然違うんだ。結婚する準備もできていないみたいで、自分はそれくらいすごいからって思ってるから、近づいてくる男の人たちを見下してるんだよね。あの女の子は、全然良い妻候補じゃないんだよ。なんで、お兄ちゃんがあんなのと結婚するんだろう?
カイリヤは立ち上がって、スマホを取って、階段を上がって部屋に行った。シャワーを浴びて、気持ちよく昼寝するしかない。母親と、サディーが全然興味のない女の子の話をしているのを残して、彼女は行った。
ドアを開けて入ると、バーガンディ色のシーツとカーテンがぴったり合っていて、キングサイズのベッドが完璧に整えられていて、すぐに横になりたくなった。でも、シャワーを浴びないと。服を脱いで、タオルを巻いて、広々とした、すごく素敵なお風呂場に入った。シャワーを浴びて、ゆったりしたガウンに着替えて、温かいベッドに飛び込んだ。もうすでに目が閉じてしまいそうだった。
********
ウムル・カイリ・アブドゥルワハブ・ダンゴテ。みんなからカイリヤと呼ばれている23歳の女性。彼女は、外科医のマリアム・サイド・アブバカールの娘で、その国の非常に強力で裕福な実業家の一人である、有名で影響力のある石油ガス億万長者のマグネット、アブドゥルワハブ・ダンゴテの娘だ。彼女には3人の兄弟、サディー(28歳)、イブラヒム(26歳)、サビル(18歳)がいた。
生まれたときから金のさじを持っていて、裕福な実業家や、医者やよく教育された弁護士で構成された王族の親戚がいる裕福で恵まれた家族から来た。ウムル・カイリは、世界を自分のポケットに入れているように感じている女の子で、誰もが人生で望むであろうすべてを持っていた。彼女のクリーム・デ・ラ・クリームの背景の完璧な定義だった。彼女は頼んだものはすべて瞬く間に手に入れたが、甘やかされてはいなかった。彼女は人生がどういうものかを知っていて、両親をいつも誇りに思わせるために正しいことをするようにしていた。
彼女は、世界で最も名誉ある大学の1つを卒業し、ファッションデザインの学位を取得した後、修士号を取得した。子供の頃から、彼女は絵を描いたり、テディベアのために小さなドレスを縫うのが大好きな創造的な子供だった。ファッションデザインは、大人になったら彼女の夢だった。それを実現するために、彼女は大学でそれを勉強し、ナイジェリアで非常に評判の高いファッション会社と「カイリのデザイン」と呼ばれる成功したファッションラインを設立した。
彼女の母親は彼女の学位を「役に立たない」と見なし、時間の無駄だと見なしていたにもかかわらず、ウムル・カイリは、何よりもそれを愛していたので、気にしなかった。彼女は自分が望んでいるものを達成したことを誇りに思っていた。カイリヤがファッションデザインの最初の学位を取得したいと知ったとき、母親は彼女に、それを諦めて、彼女と彼女の背景に合った「影響力のある」コース、例えば医学や法律を勉強するように懇願した。彼女の母方の家族全員が専門としている。
カイリヤは、判事、弁護士、弁護士、小児科医、外科医、医師でいっぱいの家族は退屈だと感じたので、それからの少しの逸脱は大丈夫だった。彼女の母親は、ウムル・カイリは頑固すぎると感じ、娘に何を勉強したいかを勉強させるしかなかった。そして、彼女の父親が彼女に全面的なサポートを与えたとき、カイリヤはファッションデザインを勉強した。それは彼女の夢だったからだ。彼女の父親は、自分の最愛の娘が望むものを拒否することはできなかった。彼はただできなかったのだ。彼が彼女に対して持っていた愛は非常に大きかったので、彼は彼女に適切な方法ですべてを手に入れさせた。彼女のパパの女の子であることと、彼が祝福された唯一の女の子であることの特典だった。彼はいつも、娘が独立した強い女性であることを誇りに思っていた。