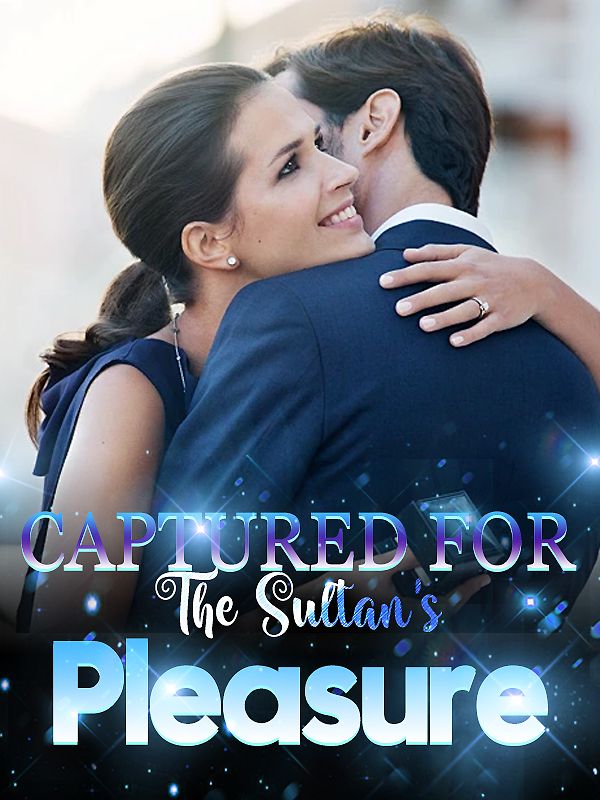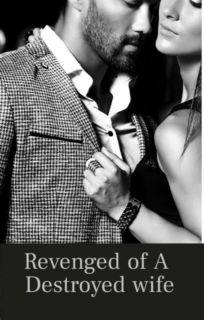ロクソラーナは足を止めて、笑顔で左側を見た。しゃがんで、嬉しそうに咲いている忘れな草の匂いを嗅いだ。紫色の花びらは太陽の輝きのように輝き、紫色の間に散らばる白い斑点が、まるで純粋な生命が呼吸しているかのように見えた。恥ずかしがり屋の花嫁が踊るように、左から右へ、そして前後に優しく渦巻いていた。
その花は、周りに咲いているすべての花の中で、ロクソラーナのお気に入りだった。そして、それらの花の中には、ユリ、赤いバラ、ハイビスカス、コーンフラワー、デイジー、ヒマワリなどがある。蝶や他の野生生物を引き寄せるミルクウィードもあった。他の女性なら誰でも見つめていたかもしれない。ロクソラーナ以外は。彼女のメイドでさえ、彼女がなぜそんなに花を愛しているのか尋ねることがあった。
彼女が小さかった頃、父親が彼らの新しい定住地を探しに行くと、忘れな草をいくつか摘んで、彼女が寝ているときにベッドの横に置いてくれたことを思い出した。彼女は翌朝、それらがそばにあるのを見つけて目を覚まし、父親がしばらくの間いなくなったことをすぐに知った。しかし、彼の愛のジェスチャーは、花を通して感じられた。
ロクソラーナは、ダル・シラと呼ばれる部族に属していた。彼らはいつも世界中をさまよっている人々のグループで、最近チャドに定住地を見つけた。彼らが定住した他の場所と比較して、これは部族がとどまっていた最長の期間だった。
ロクソラーナは、今回彼らが家にしたスルタン国を見た。海からそれほど遠くなかったので、常に新鮮な水と海の獣が利用できた。何よりも場所を美しくする花が十分に咲いていた。スルタン国全体に小屋が散らばっており、それぞれが美しく、他のものとは異なって見えた。彼らが新鮮な獲物と果物を狩る木の森が南にあった。
北の地域には訓練場があり、すべての男がそこで訓練していた。女性は地面の近くに入ることは許されていなかったが、ロクソラーナだけは例外だった。男たちが訓練している間、女性は他のことをしているのが見られた。料理、掃除、洗濯、花の剪定、子供たちの世話など。何人かは座って物事や時々男についてゴシップをしていた。
子供たちの何人かは遊んだり、お互いを追いかけたりしていた。何人かは、両親のためにネズミなどの小動物を捕獲するための罠を仕掛けた。他の人は、単に両親の日々の仕事を手伝っていた。訓練するのに十分な年齢の男の子は訓練場にいて、戦いの基本原則を学んでいた。
彼らはいつも放浪者だったわけではない。彼らのルーツはもともとスーダンの土壌にあった。彼らは、それが彼らに影響を与える場合を除き、世界の出来事に関与したことのない平和な人々だった。彼女の父親はいつも彼女に、世界が統一し成長できる唯一の方法は平和であり、人々が信じている戦争ではないと話していた。
ロクソラーナは、特に母親が1947年に亡くなった後、部族がなぜそんなに長く一か所に留まることができなかったのか理解できなかった。彼女の父親であるセリム・バヤジドは、彼らがかつて知っていた唯一の家から部族全体を移動させた。彼女は当時まだ10歳で、弟のアバーンはわずか5歳だった。何度尋ねても、父親は単にそれが部族にとって最善の利益になると言った。
彼女の父親は部族のスルタンだった。そして、他のほとんどのスルタンとは異なり、彼女の父親はすべての部族メンバーから愛され、尊敬されていた。そして、なぜそうでないのだろうか、その男は常に自分のニーズよりも、自分の家族よりも先に、人々の利益を優先するのだから。母親が全能のアッラーの咲き誇る場所で安らかに眠ったときでさえ、父親は他のスルタンとの平和交渉に出かけていた。
ロクソラーナは、胸の間で安らかに休んでいるネックレスを指でなぞった。母親の死後、彼女はそのネックレスを相続した。それは、特に彼女が緊張しているときに、母親とのつながりを感じるのに役立つ。そのネックレスは、父親から母親への愛の証として贈られたもので、母親は亡くなる直前にそれを彼女に譲った。
他のスルタンがハーレムを女性で飾る一方で、彼女の父親はそれを一つも作らなかった。彼は彼女が生きている間、彼女の母親にしか目を向けていなかった。彼女の死後でさえ、その男はまだ忠実だった。ロクソラーナは、一緒にいるかどうかに関係なく、いつも彼女を愛してくれる父親のような男を見つけたいと思っていた。
彼らの家は、父親がスルタンであるため、周りの他の家とは少し違っていた。しかし、使用人は最小限に抑えられ、スルタンの家族のメンバーからは家族のように扱われた。彼女の父親は、それぞれが別々に住む小屋を持ち、タバコのパックのようにまとめられないようにした。
遠くから聞こえてくる太鼓の音は、ロクソラーナを考えから現実に引き戻した。彼女は自分の本来の使命をほとんど忘れていた。彼女の顔に笑顔が浮かんだ。結局のところ、それは彼女が一年で唯一、自分が最も得意なことをする日だったのだ。
「ロクソラーナ様、急がないと遅れますよ」と、彼女の女性の一人が言った。
「じゃあ、急ぎましょう」とロクソラーナは、足が運べる限り速く走りながら叫んだ。
男たちが会場に急いでいるのが見え、女性たちはヒジャーブとキモルンを着て小屋に急いでいた。ロクソラーナは開いた頭を撫で、父親が彼女にどれだけの自由を与えて、自分で決断できるようにしてくれたのかを考えた。彼女は一人で微笑んだ。
「急いで」とロクソラーナは護衛に言った。
殿堂と呼ばれる場所は、スルタン国の端にあった。ロクソラーナは、メイドたちが彼女に追いつこうとする無駄な試みに笑った。彼女は、彼らが決してそれをすることができないことを知っていた。結局のところ、彼女は7年前に母親を奪った事件以来、ずっと訓練を受けていたのだ。彼女の父親は、彼女が勤勉で、決して訓練を欠かさないようにした。
ロクソラーナは、殿堂のドアのそばに立っている人物にほとんどぶつかりそうになり、足を止めた。彼女は顔を上げて、アスリームが感情のない人形のように立っているのを見つけた。
「いつになったら走り回るのをやめるんだ、お嬢様?」とアスリームは彼女に尋ねた。
ロクソラーナは全身が熱くなった。アスリームは、彼らの部族のイェニチェリの一員だった。言い換えれば、彼は部族の軍隊を形成するエリートの一員だった。そして、単なるメンバーではなく、彼は将軍だった。彼の父親は彼女の父親の親友であり、ロクソラーナは彼らが2つの家族間の結婚の可能性について話し合っているのを聞いたことがあった。
彼女は気にしなかった。彼女は若い頃からずっとアスリームが好きだった。他の人が単に彼女を楽しませるだけだったとき、彼だけが彼女と一緒に訓練することを気にしなかった。彼は、彼女が適切に練習するためにズボンを履くことを許可するように父親を説得するのを手伝ってくれた。それは彼女の宗教が嫌うことだった。それは、彼女が自分自身を守ることをよく学ぶという彼女の父親の弱点を利用して、忍耐力で勝ち取った戦いだった。
「あなたは今の格好でパフォーマンスをするつもりですか?」とアスリームは彼女に尋ねた。
彼女は言われた服を見て顔をしかめた。彼女はまたズボンを履いていた。それは彼女のせいではなかった。年月が経つにつれて、彼女は単にそれらが女性の服よりもずっと快適であることに気づいたのだ。
「はい」彼女は単に答えた。他のことを言えば、何についてでもっと議論が起こることを知っていた。「私の存在を知らせて」と彼女は彼に言い、彼が持っているかもしれない議論を終わらせた。それは将軍としての彼の義務ではなかったが、ロクソラーナは彼をからかうのが好きだった。