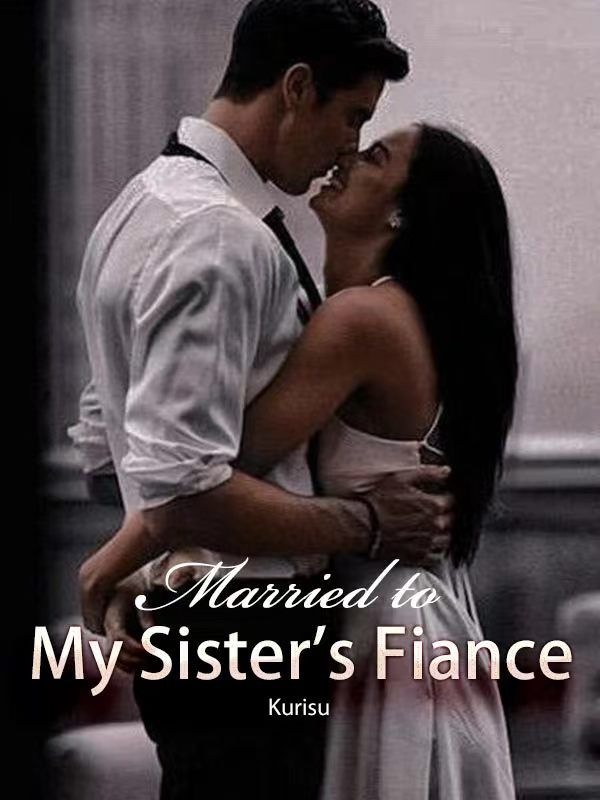ここにいて大丈夫?一人で?私と一緒に住めるよ。お屋敷は私たち2人でも十分広いし。」
彼の声は優しかったけど、心配そうなのが伝わってきて、思わず笑っちゃった。叔母が私を面倒見たくないって決めてから、彼はずっと私がどうしたいか聞いてくれてたんだよね。すべての決定、些細なことまで…彼はいつも私に選択肢を与えてくれた。最初は圧倒されたよ、そんな風に気遣われるのは。今でも、時々そうなるけど。
でも、自分の場所が欲しいって伝えたら、彼は私に反対しなかった——ただ、過保護な鷹みたいに、2日に1回くらい現れるだけ。別に嫌じゃないんだけど。誰かが心配してくれるって分かってるのは、心強いんだよね。
明日から大学。新しい生活、新しい章…そしてどうやら、彼と同じ学校に通うらしい。また監視する口実を見つけたって感じ。彼の過保護ぶりに少し呆れる気持ちもあるけど、正直?気に入ってるんだよね。誰かが私を見ていてくれる——それは彼がこんなに気前よく申し出るまで、私が必要だとも知らなかったことなんだ。
「デイモン」って、私はため息をついて、首を傾げた。「まだ子供扱いしないでよ。一人でも大丈夫だから。」
私が言わなかったのは、それに、迷惑かけたくないってこと。デイモンはもう十分すぎるくらい背負ってくれてたから。何かあるとしたら、その負担を少しでも減らしたいのであって、増やしたくはない。
「分かった。何かあったら言ってね、いい?」彼の視線が優しくなり、唇が細く引き締まってから、彼は譲った。
「もちろん——あ!ちょっと待って!」彼はドアの方を向いたんだけど、私は駆け寄って、彼を捕まえた。考えもせずに、彼を抱きしめてた。彼の体は驚いて固まったけど、すぐにリラックスした。温かい。見慣れた。安心。正直、私は彼にご機嫌取りしてたんだ。彼が断らないのは分かってたから。
「何?」彼はくすくす笑った。
「あの青い髪の男の人——空港で私たちを拾ってくれた人…」彼の眉が上がった。ああ。彼はもう、私が何を言いたいか分かってたみたいで、それだけで私はもっとニヤけた。
「私…ちょっと、彼のことが好きなんだ。」
それが出た——オープンに。私の心臓はドキドキして、神経はニヤケ顔の下で沸騰してた。彼の表情はあまりにも長い間読み取れなくて、私は次に来るであろうお説教かからかいに備えた。
「まだ先週会ったばっかりなのに、もう好きなの?」デイモンは、信じられないって顔で髪をかきむしって唸った。私は目を丸くして、めげなかった。
「えー、デイモン!ただ紹介してほしいだけなの。彼はあなたの友達だし、お昼から授業後まであなたと一緒なんだから、少なくともお互いを知るべきでしょ。」彼の眉間のシワは深まり、私の論理に明らかに感心してないようだった。
「彼はミースト・トリゴン・シュナイダーって言うんだ」彼はまるで、その名前だけで私を怖がらせるべきだって言わんばかりに呟いた。「それに、彼はもう好きな人がいるんだ。」
その言葉は冷たい水しぶきのように、一瞬私を落ち込ませた。他に誰か?やったね。でも…まだ結婚してないんだよね。ってことは、まだチャンスはあるってこと。
私は姿勢を正し、ニヤリと笑った。「分かった!ありがとう、デイモン!」私は可愛らしく返事をして、彼にこれ以上お説教される前に踵を返した。
ミースト、ね?ちょっと待って——私があなたのものにしてあげるから。
私はディベッカ・マリアンヌ・ラッシュウッド・ダンクワース——デイモン・ルシファー・ダンクワースの唯一の妹。でも、アメリカでは、ほとんどの人は私をディマリア・ラッシュウッドとして知ってる。なんでこの名前がモデルを始めたときに定着したのか分からないけど、そうなったんだ。今となってはどうでもいいけどね。
デイモンが私を見つけたとき…私は彼を選んだ。あの世界を置いて、ここで勉強を終えることを選んだんだ、物事が少しだけ現実的に感じる場所で。もう少し私らしく。
次の朝、私は早く起きて、興奮でそわそわしてた。あるランダムなメロディーを口ずさみながら、床からほとんど飛び跳ねて、そのメロディーは暖かい水が私に降り注ぐバスルームに響き渡った。今日…私はまたブルーに会えるんだ。
うん、ブルー。それが私が頭の中でミーストって呼んでること。彼には何かあるんだよね——何か警告なしに私を惹きつける、磁石みたいなものが。確かに、彼は年上。彼らは私の先輩。それが何?年齢差なんて、私には関係ないんだよね。彼を好きになること?それが本当に私を驚かせること。誰かを好きになることなんて滅多にないのに、私は今、恋に落ちたティーンエイジャーみたいに振る舞ってる。情けない…それとも愛らしい?愛らしいにしよう。そうしよう。
シャワーの後、私は服を着て、短い髪をとかした。長く伸ばしたことは一度もないんだよね。なんでか分かんないんだけど——ただ…それを伸ばすっていう考えが怖いんだ。一度、自分で冗談で言ったんだよね、もし失恋したら伸ばすって。皮肉だよね?ほとんどの女の子は傷つくと髪を切るんだよね。私は?どうやら、その逆をするみたい。別に傷つくつもりはないけどね、ごめん。
鍵をジャラジャラさせながら、私はデイモンがくれたピカピカの車の運転席に滑り込んだ。甘やかされてる?もちろん。でも文句はないんだ。デイモンはずっとそういう感じなんだよね——フロースもね。私たちの従兄弟、デイモンが悲劇で人生を奪われた後、養子にした…彼らは私のすべて。正直?彼らを世界と交換したくないんだよね。
お昼時までには、私の脳みそは別の次元に迷い込んでた。授業はぼやけてたし、私の心は、髪が違反行為であるべき人に固執してた。私は交流することすら面倒じゃなかった——私には一つの使命があったから。デイモンを見つけること。ミーストを見つけること。どちらも建築学科の4年生。デイモンはちょっと年上だけど、ホームスクーリングと…まあ、高校時代に休学せざるを得なくなった深刻なことがあったから。彼はそれについてあまり話さないし、私も追求しないんだよね。
キャンパスのホールをナビゲートして、私はついに建築学科の近くで彼らを見つけた——背の高い姿が、難なく人々の注目を集めている。笑い声が紙吹雪みたいに空中に舞い、女の子たちは彼らの前でほとんど気絶しそうになってた。彼らを責められないけど。デイモンとミーストが一緒?それは視覚的なオーバーロードだもん。映画スターみたいなルックス、たやすい魅力…みんなの憧れの的、2人ともね。
そして確かに——もしデイモンが私の兄じゃなかったら、もっとその人気を理解するかもしれないけど、うわ。キモイ。マジ勘弁。私は自分の正気を大切にしてるんだよね。私の視線は、いかなる謝罪もなく、ミーストに釘付けになった。ああ、彼の青い髪は違法だよ。パンティドロッパー、私は思ったよね、ニヤケ顔を抑えながら。しっかりして、ディベッカ。
でも正直?彼があんな風に見えたら、どうやって冷静でいられるっていうんだ?
私は明るい笑顔で彼らに挨拶した——半分は興奮、半分は彼らを獲物として見つめている捕食者のように彼らを見つめている女の子たちのグループをイライラさせるために。そう、見続けて。私は彼らと一緒に立ってるんだから。
ミーストは私の方を見て…笑った。彼の唇の端が小さく、ほとんど分からないくらいに曲がったんだけど、私の心は反逆して、まるで胸から逃げ出そうとしているみたいにドキドキした。本能的に、私は下着のウエストバンドを引っ張った——それは突然、脱げそうに感じたんだよね。マジで?しっかりして!
本当に私に笑ったの?私に?
「デイモン!ミースト!」私はどもって、彼らに追いついた。「会えて嬉しいよ!」
デイモンの眉は上がり、明らかに楽しそうだった。やったね。笑ってよ、お兄ちゃん。
「ミースト」デイモンは、私の方に首を傾けて言った。「妹のディマリアのこと覚えてる?彼女も一緒にいるんだ。それでいい?」ミーストの視線が再び私に注がれた。
「ああ、いいよ」彼は簡単に答えた。
ああ、神様。私はその場で爆発しそうになった。彼は嫌がってない!彼は私がそこにいることを許してる!彼も私を好きなのかも?いや——落ち着いて、ディマリア。先走らないで。クールに振る舞って。氷のようにクール…彼の視線の下で溶けていく氷——やめて!
私は彼らと一緒に歩き、幸せが胸の中で泡立って、私はミーストをチラチラ見てた。正直、運命——または私の不器用さ——が介入しなかったら、私は目をそらさなかっただろうな。
ドスン!
「ああ、神様!」私はよろめき、人間の姿をしたレンガの壁みたいのを見て、瞬きした。
「ごめんなさい!」
私の前では、デイモンとミーストは会話に夢中で、私の即興的な衝突に全く気付いてなかった。うわ、ありがとう、みんな。あなたの味方だって分かって嬉しいよ…って、違うか。
私はぶつかった人を見た——うわあ。背が高い。肩幅が広い。真面目で、威圧的になりそうなほど。彼の鋭い視線は私の上を滑り、クールで無関心で、まるで私が彼が無視するほど迷惑な虫であるかのように。まるで、さらに悪いことに、彼は自分が汚染されたかのように制服を払った。痛い。
私は彼のIDをちらっと見た。工学部生。当然。彼の態度は——厳格で正確——「無駄話禁止」って叫んでるみたい。デイモンと同じくらいの年齢に見えたけど、それが最初の危険信号だったはず。私の兄は、とても陰気な炎に蛾のように惹かれる人たちを引き寄せるんだよね。
「ごめんなさい…」私は再び呟いて、今回は少しだけ謝罪の気持ちが薄れてた。彼の反応?何もない。うなり声すらなし。靴の向きを変え、一瞥する価値すらないかのように、さっと逃げただけ。うわあ。失礼。
私はもう少しの間そこに立って、彼が歩いていくのを見て、眉を寄せた。彼は何なの?彼には何かあった…私の思考の端で、何か不穏なものが引っ張られたんだよね。あの種の冷たさを認識するべきみたいに。それとも、ただランダムな衝突に深読みしすぎただけかな。
どちらにせよ。私は残りの変な感じを振り払い、デイモンとミーストを追いかけた。彼らはついに私がいないことに気づいた——もうとっくに。2人とも私の方を振り返った。デイモンの上がった眉は、遅かったね?って言ってるようだった。
私は息を吹き返し、追いついた。キャンパスの嫌な奴にぶつかっただけよ。文字通り。
「何?」デイモンは私を見て尋ねた。
「ああ、誰かにぶつかっただけ」私は気楽に答えて、笑顔を向けた。デイモンは肩をすくめ、ミーストとの会話に戻った。いい会話だね、お兄ちゃん。
私たちがカフェテリアに着くと、ミーストは私たちの食べ物を注文することを申し出た。なんてジェントルマン。私は彼が歩いていくのを見て、そして気づいたら——
「君は、彼をまるでむさぼり食うように見つめてるな」デイモンは真顔で言って、楽しそうに口元を歪ませた。「君はそんなに友達のこと好きなの?」
私は彼を睨んだ。「それがどうしたっていうの?彼はクールで面白いんだよ、いい?彼の青い髪、彼の態度全体——もっと知りたいだけなんだよ——」
私の言葉は途切れ、カフェテリアのざわめきが変わり、視線は入り口に引き寄せられた。本能的に、私の視線もそれに従った——そして、彼がいた。
さっきぶつかったあの男と同じ人。彼の制服は、「ドレスコード」っていう概念にほとんどしがみついてなかった——上のボタンは3つ外れてて、袖はカジュアルにまくられてて、手はまるで自分の場所だって言わんばかりにポケットに突っ込んでた。彼のそばを歩くのは、ランウェイから出てきたような背が高くて見事な女の子。他の2人の男たちが彼らに付き添い、それぞれが同じようにゴージャスな女の子たちを連れていた。
そして、その瞬間、デイモンとミーストを夢中にしていた女の子たちは、そのレーザーフォーカスを彼に向け直した。特に彼に。空気が変わり、まるで彼が重力を引きずっているようで、誰も試すことなく、すべての人の注目を集めた。
あの男は誰?
私たちの目が合った。短い。鋭い。彼は眉をひそめた——また——そして目をそらし、全く無関心った。失礼。一貫性はあるけど、失礼。
「誰のこと見てるの?」デイモンの声が私を現実に引き戻した。
私はニヤリと笑い、自分の楽しさを隠すこともなかった。「さっきぶつかった人を見ただけ。あなたみたいに、不機嫌で冷たい人だよ。」
デイモンのしかめっ面が深まった。「あれはハンター・マルティネスだ」彼は小声で言った。「それに、私と彼を比較しないで。」
ハンター・マルティネス。その名前は頭の中で転がった。革と悪い決断に包まれた問題、って感じ。
「それで、彼のこと知ってるの?!」私は思わず、たぶんちょっと大声で言ってしまった。何人かの頭がこちらを向き、好奇心がわいた。デイモンは鼻を摘んだ。
「もちろん知ってる」彼は不満そうに唸った。「彼はここで一番手ごわいライバルなんだ。それに、私の名前を彼の隣で聞くのは本当に嫌なんだよ。」
ライバル?ああ、これ面白くなってきた。
私はデイモンのライバル関係の発言を流して、ミーストの方を見た。彼は一瞬見て、私たちの目が合ったとき、私は彼に明るい笑顔を向けた。笑ってよ——たった一度だけでいいから。
そして彼はそうした。しかめっ面も、冷たい視線もなし——彼はうなずいた。私の心臓はドキドキした。勝利!
しかし、私の幸せが花開いたのと同じくらい早く、それは枯れた。
女の子が彼のそばに現れ、彼のパーソナルスペースにシームレスに入り込んだ。彼女の腕は彼の周りに絡みつき、彼女の頭は彼の肩にもたれかかっていたんだけど、まるでそれが彼女の当然の場所であるかのように。そして——ああ、やめて!——彼は彼女の頬にキスをした。
マジで?
私の気分は落ち込んだ。私が抱いていた希望の火花は消えてしまった。一体彼女は誰?
まるで、宇宙が傷口に塩をすりこみたいかのように、その女の子はテーブルで私とミーストの間に座った——戦略的に、私が彼の隣に座るのを邪魔するように。うう!
「妹さん?デイム?」その女の子は、歯が腐りそうなほど甘い声で尋ねた。私は心の中で顔をしかめた。確かに、デイモンと私は特徴を共有しているけど、本当に気づくには表面を通り過ぎる必要があるんだよね。
「ああ、彼女はディマリアだよ。ディミー、こっちはミーストの大切な人、ヴァレリーだよ」デイモンは紹介した。
大切な人。その言葉は私の心にこだまして、重く沈んだ。私は彼女を見た——背が高く、落ち着いて、紛れもなくゴージャス。彼女のエレガンスは、たやすいものだった。当然、彼女はモデルみたい。私もそうだったんだけど、彼女の何かは彼のタイプって叫んでるみたいだった。
でも、なんで彼女なの?
それでも、私は自分の唇を笑顔に——偽物だけどまあ許容できる——伸ばし、会話に加わった。たとえ私のすべての繊維が別の次元に目を回したいと思っていたとしても。
最終的に、ヴァレリーはトイレに行くことを許し、デイモンは電話に出るために離れ、私をミーストと二人きりにした。
私はジュースをすすり、彼が食べるのを見てた。ああ、彼が噛む姿でさえ魅力的。私の頬に顎をのせて、私は微笑んだ。「本当にヴァレリーのこと好きなんだね?」
彼は食べるのを止めて、私を見て、答えた。「うん。」
イタイ。プライドに直撃弾。
「どうして?つまり…なんで彼女なの?」その言葉は、私が引き戻す前に滑り出た。スムーズ、ディマリア。本当に控えめだね。
ミーストは肩をすくめた。「なんでいけないんだ?」
いい着眼点だ。私の心には最悪だけど、いい着眼点だよ。私は喉を清めて、目をそらし、首の後ろに熱が忍び寄るのを感じた。隅から、彼が私を観察しているのに気づいた。それから——彼はため息をつき、首を横に振った。それはどういう意味なの?
私が考えすぎる前に、ヴァレリーとデイモンが戻ってきた。私たちは食べ終わり、すぐに彼らは1時の授業に出た。
私は自分の建物に向かったけど、途中——自然が呼んだ。完璧なタイミング。私は一番近い共用トイレに駆け込み、個室に滑り込み、座って安堵のため息をついた。
でも、それから——ちょっと待って。
何かが…変。
かすかな音が響いた。最初はかき消されてた——それから、紛れもなく。うめき声。大きい。謝罪なし。
鳥肌が立った。ああ、冗談でしょ。
私は急いで、できるだけ早く終えて、服を直した。手を洗い、それを聞いたふりをしようとした。ティッシュをつかんで、私はドアに手を伸ばした——
カチッ。
隣の個室が開いた。女の子が出てきた——間違いなく、私の学科の人。彼女の髪は完璧で、制服はきちんとしてて、唇はつややかだった。彼女は恥ずかしげもなく私を見て、スカートを整えて、何事もなかったかのように歩いて行った。
一体何が——
私は鏡に戻って——凍りついた。
ハンター・マルティネス。
さりげなくシンクにもたれかかって、腕を組んで、彼の姿は私の目とロックされた。彼の視線——鋭く、読み取れない——私をその場に釘付けにした。彼のスターリングアーモンドグレーの目は私を捕虜にし、太い眉はすべて鋭い角度とたやすい傲慢さの顔をフレームに収めていた。あの貴族的な鼻、あのよく定義された特徴——西洋的で不当に魅力的。
呼吸して、ディベッカ。呼吸して。
私は唾を飲み込み、指をティッシュに締め付けた。なんで彼は私をそんな風に見ているの?私の鼓動が耳で鳴った。
「ごめんなさい…また」私はどもって、かろうじてささやくような声で言った。「さっき…えーっと、今も。」
彼は動かなかった。瞬きもしなかった。まるで私がその絵に合わないパズルのピースであるかのように、私を見守り続けただけ。空白。無関心。苛立たしい。
私はティッシュをゴミ箱に投げ込み、首にぶら下がっている彼のIDをちらっと見た。ハンター・ダクストン・マルティネス、土木工学科の学生。
それから——彼は話した。
「なんでデイモン・ダンクワースと一緒にいるんだ?」
その質問は私を困惑させた。なんで彼は気にするの?
「私は彼の妹です」私は用心深く言った。「なぜ?」
ゆっくりと、いたずらっぽい笑顔が彼の顔に広がり——イライラするほど得意げ。この人は一体なんなの?!
答えずに、彼はドアの方を向いた。しかし、彼がそれに達したとき、彼は一時停止した。振り返って、彼の視線が私にもう一度ちらついた。
「何も聞こえなかったふりをしてくれ」彼は言った。一拍。それから——「謝罪は受け入れた…ディベッカ。」
彼は出て行き、ドアは彼の後ろで閉まった。
待って。
ディベッカ?
私の息が止まった。どうして彼は私の名前を知ってるの?
私は自分自身を見た。目に見えるIDはない。私のものはまだ発行されてない——来週まで来ないんだ。
それでどうして…?
悪寒が私の背骨を這い上がった。何が起こってるの?