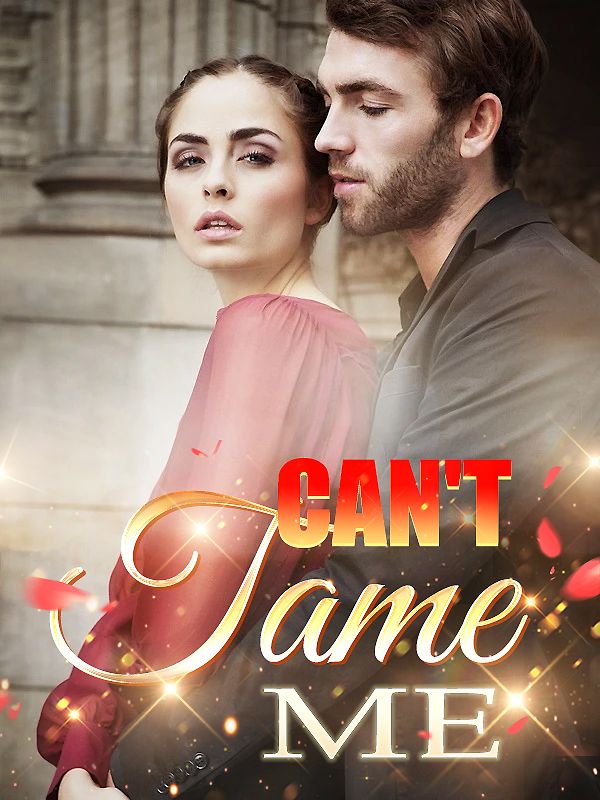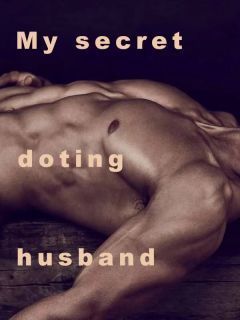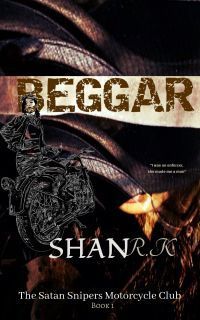「ライラ、急いで!お客さん、待ってるんだから!」
あたしは、**秘書のばか**の手から荷物をひったくって、自転車に飛び乗るために走り出した。
あたしはニューヨークでメッセンジャーのバイトをしてて、このバカのせいで貴重な時間を無駄にしたんだ。ちゃんと梱包できてなかったせいでね。
時間は金なんだから、無駄にする時間なんてないんだ。
今日、もう1000キロ以上走ってるんだけど、できればあと2、3回くらい配達して、今日の給料を増やしたいんだよね。
目標を達成するために、あたしは交通ルール無視して車の間を縫うように走ったり、バスとかタクシーに便乗してスピード出したりする。
次のお客さんはマンハッタンのど真ん中。
**ヴェローニ**のビルに行かなきゃいけないんだけど、ここはビッグアップルのビジネス街。
あたしの仕事のせいで、足を踏み入れたことなんて一度もないんだよね。
だって、ここはちょっとバンパイアな地区で、そういうの専門の下僕みたいなのを呼ぶ傾向があるから。
でも、あたしにとっては全然問題ない。
お金は匂いも、人種も、国籍も関係ないんだから。
どこから来ようと、恥ずかしげもなく受け取るだけ。
GPSを片目で見て、周りのビルを見ながら、どんなところなんだろうってぼんやり考えてる。
あたし、今まで人間じゃないやつらに会ったことないし、他の人たちみたいに興味もなかったし。
幸いなことに、バンパイアは一番危険なやつらだから、自分の種族しか住んでない地区に住んでるけど、それなりに知識はあるんだ。
まず、昔はあたしたちみたいなのを食べ物として狩ってた時代があったってことを知ってるから、基本的な協定で守られてるのは嬉しい。
それは、他の個体を許可なく狩ったり食べたりすることを禁止する、不干渉条約。
あたしを守ってくれる正義とか法律を信用したことはないけど、いつもいる近所からこんな遠くまで配達するっていうことで、会社がボーナスくれるから、ちょっと油断しちゃう。
もし何かあったら、おしらせするよ。
まあ、自分の身を守るのは初めてじゃないからね。
自転車を壁に立てかけながら、結局、人間っぽい二足歩行のやつらはみんな同じに見えるから、別に他のやつらより怖がる必要はないんだって自分に言い聞かせる。
完璧な窓と、目が眩むようなラインのビルを見上げて、中のほとんどの人は、自分のブランドイメージに気を使ってるに違いないって思う。
配達員を食べちゃうのは、多分まずいんじゃない?
キャップを頭に押し込んで、荷物を腕の下にちゃんと挟んでから、自動ドアをくぐって、頭の中から不安を追い出しながら受付に向かって小走りで向かう。
**入り口の女性**は、あたしのぼろぼろのジーンズと**カビゴン**のTシャツを見て、厳しい顔で見てくる。
もうとっくにポケモン世代じゃないのはわかってるけど、世間の目なんてどうでもいいんだよね。
それに、あたしはファッションショーをしに来たわけじゃないんだから。
ちょっとでも口出しされる前に、あたしはすぐに話しかける。
「**ミスター・ヴェローニ**宛ての荷物です。上に上がらないといけないので、急ぎなんです!」
彼女は上の階に行くのをためらって、嫌そうな顔をしてあたしを見つめてる。
あたしが何だって言うんだ?
ビルに落書きしに来たって思ってるのか?
「まあ、最悪、あなたに荷物を預けることもできますよ!」
あたしは肩をすくめる。
あたしにとっては問題ないもん。
「お客さんが時間通りに受け取れなかったら、あなたのせいですよ」って言っておく。
彼女は唇を噛んで、心配そうにファイルをいじりながら、良いことと悪いことを天秤にかけてる。
あたしは踵を返したふりをする。
「いいわよ、いいわ!」
結局、彼女は不機嫌そうに答えた。
メッセンジャーナンバーワンの戦略:歓迎されないときは、平静を装い、相手に自分の立場を危うくするってことを匂わせる。
これはあたしのお気に入りのテクニックの一つ。
ちょっと偉そうな部署のリーダーが、傲慢さから恐怖に変わるのを見るのが大好きなんだよね。
ニヤリとして、彼女が指先でバッジを渡すのを見る。
「出る時に返却して!」
彼女はあたしに吐き捨てるように言い、すぐにパソコンの画面に向き直った。
「冗談でしょ!」
あたしは嫌味な口調で言う。
「あたしがコレクションを始めたかったのに!」
あたしは彼女が怒ったような横目で睨むのを見ながら出て行く。
意地悪は必須じゃなかったけど、面白かったから追加したんだよね。
エレベーターのドアをくぐると、ダークなスーツを着て、きっちり身なりを整えた男女の集団の中に挟まれてしまった。
ほとんどは血を吸う連中なんだろうけど、誰だかわからないし、別にどうでもいいや。
あたしは自分の報酬のことだけを考えて、その間、隅っこに滑り込んで、彼らをよく観察してる。
結局、指定されたオフィスに急いで向かい、返事も待たずにドアをノックして入る。
結局、早く終わらせれば、この居心地の悪い場所から早く出られるんだから。
焦っていたせいで、背の高い、黒髪のスーツ姿の男と真正面からぶつかってしまった。
デカすぎるやつらに対して文句を言いながら、あたしは一歩下がったんだけど、彼があたしの腕を掴むまで、ほとんど動かなかった。
「君の匂い、すごくいいな…」
彼は夢見るような声で言いながら、鼻孔を広げてる。
あたしは怪訝な顔をして、正気じゃないんじゃないかと思った。
眉を上げて、訳が分からず、ここで何をしているのか説明しようとする。
「**ミスター・ヴェローニ**宛ての荷物です!」
彼はあたしを離さず、黒い瞳であたしを見つめ、あたしの魂に入り込もうとしている。
「俺だ!」
彼はそう言いながら、歪んだ笑顔を浮かべている。
なんて偶然!
あたしたちは運命共同体だったってことか…
あたしは、すごく重いことになりそうな彼の返事を遮って、荷物をちょっと乱暴に彼の胸に押し当て、サインをしてもらうためにタブレットを渡す。
「ここにサインしてください」
あたしは冷たく返事をして、まだしっかりと掴んでいる腕を離すように促す。
ついに彼が腕から手を離し、反射的に荷物を掴むと、あたしは画面とサインする場所を見せる。
何があっても、プロでいなくちゃ。
配達員向けの戦略ナンバーフォー
このテクニックは、レベルの低いチャラ男とか、めちゃくちゃイライラしてるペーパープッシャーには効果がある。
残念ながら、今回はゲームの一部なんだ。
彼は動かずにあたしを見つめていて、まるで荷物以外の何かを待っているかのよう。
荷物には全く興味がないみたい。
彼の目は、何か意味のあることは何も教えてくれない輝きを放ってる。
早く終わらせたいと思って、全ての恐怖が現実になるように感じながら、あたしは冷静さを保とうと試みる。
「**ミスター・ヴェローニ**、荷物、欲しいんですか、いらないんですか?」
あたしはしつこく尋ねた。
予想外なことに、もう一つの嘲笑する男の声が少し離れたところから聞こえてくる。
「おい、ボス、もうフェロモン効かないのか?」
あたしは、自分の間抜けなクライアントの後ろをよく見るために、頭を前に傾け、大きなウォールナットの机に座っている男を発見した。その男は、あたしたちを見て笑顔を浮かべている。
彼は突然、自信たっぷりに、まるであたしが彼の魅力に溶け込むように、獲物を狙うような足取りで近づいてくる。
あたしは目を細め、黒いスーツと奇妙な対照をなす、この背の高い金髪で肌が青白い男を観察する。