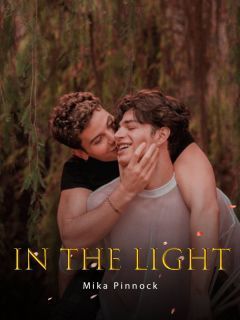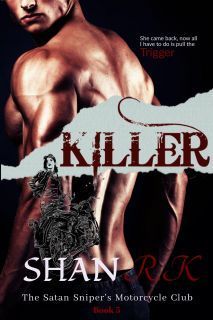「ねえ、どうしたの?なんで顔シワシワなの?」って、返事する代わりに、クシャクシャになった紙をテーブルに投げつけたんだ。
教頭の部屋から出てきたとき、すぐに顔をしかめた。イライラしてたから。
「落第?試験に落ちたの?」
私は目を回した。「当たり前じゃん、トシ?」
「落ち着けよ、ベイビー。ただ聞いてるだけ。なんで困ってるの?サーはそんなに悪くないよ。サー・タモアはここの先生でしょ?あのじいさんをからかってるんじゃないの?」
「それが問題なの。ミセス・サタンがもう先生じゃないんだから!」
「マジ?知らなかったな」
「一緒にいるときは、いつも口で話してるんだからね」トシはニヤリとした。
「なんで?話すよりキスの方がずっといいじゃん、セリザ」私の唇を見てきた。
「それに、この会話は退屈なんだよね」彼は前に乗り出した。
「やめてくれない?無理だって!あの試験のせいでストレスなんだよ。ミセス・サタンが、彼女のクイズと試験に合格しなかったら、落第させて卒業できなくなるって脅してきたんだから!」
うわー!
「で、信じてるの?」
「えー?!もちろんあの意地悪な先生を信じるよ!前に留年した生徒をたくさん落第させたんだから!」
「ミセス・サタンの先生じゃなくてよかったね!」
「あの意地悪な先生は本当にムカつく!それだけじゃないはずだよ。私より優れてるから、嫉妬してるんでしょ!私より可愛いし!美しくあるのは本当に大変なんだから!」
「美しさを正しく使ってないから大変なんだよ」トシが言った。私は眉をひそめた。
「どういう意味?」私はニヤニヤしたトシを見つめ続けた。彼はバスケットボールの練習で忙しいのに、どうやってクラスで一番になったんだ?知る限り、そんな時間はないはず。それに、トシはすごく怠け者なのに、どうして一番になれるんだ?
「なんで俺が勉強好きじゃないのに、こんなに成績いいのか、不思議に思わなかったの?」
「思ったよ、さっきお前がそう言う前にな。で、秘密は何?カンニングコードとかあるの?先生を買収してるとか…」
「俺のこと見くびってるの、セリザ?」私は目を回した。
「笑わせないで、トシ。どっちもやったことあるって知ってるし、学校のルールを破ったのは、私たちだけじゃないでしょ」
「よく知ってるね、ベイビー」彼はそう言って、私の唇の横にキスをした。
「からかうのはやめて、トシ。どうしたら試験に合格できるか教えて?順位はどうでもいいの。ただ合格して、ミセス・サタンに黙っててほしいだけなの!」彼の友達はさらに大きな声で笑った。
「だからミセス・サタンが燃えてるんだ!」ヒーローが言った。
「確かに、彼女はサタンの妻だよ。本当に悪いからね!どれだけの夢を潰してきたの?先生は生徒をサポートするべきなのに、足を引っ張るんだから。彼女がやってるみたいに。めちゃくちゃだよ!」
私はあの教室に入るたびに、自分の血が沸騰するのを感じる。まるで先生が私に個人的な恨みを持っていて、私が何か悪いことをするのを待ちきれないかのようだ。ちょっとしたミスやミスに対して、厳しいお説教をされ、それが私を疲れさせている。
私は完璧じゃないことは知っているけれど、先生は私にそうあってほしいと思っているようだ。私がミスをするたびに、私は何か犯罪を犯したかのような気分になる。そして、私だけではなくて、先生はクラス全体をターゲットにしているようだ。私たちはいつも何かで叱責されていて、それは話すのが多すぎるとか、注意を払わないとか、そういうことだ。
本当に私を困らせるのは、先生が私たちを叱るときに使う口調だ。まるで私たちが、居場所を知っておく必要がある言うことを聞かない子供たちのようだ。そして最悪なのは、先生がそれがどんなに落胆させるかを理解していないようだ。叱られるたびに、私は小さくなっていくような気がして、自分は十分に良くないと感じる。
私はわざと授業を邪魔したり、トラブルを起こそうとしたりしているわけではない。時々、他のティーンエイジャーのように、退屈したり気が散ったりするだけだ。しかし、私たちを夢中にさせようとしたり、クラスをもっと面白くしようとしたりする代わりに、先生は私たちが何か間違ったことをするのを見つけることに集中している。
私は教師が大変な仕事をしていて、教室で秩序を維持する必要があることを知っている。しかし、規律と絶え間ないお説教の間には違いがある。まるで先生は私たちが自分の決定をしたり、自分のミスから学んだりすることを信頼していないようだ。その代わりに、私たちは自分たちがどれだけ及ばなかったかを常に思い出されている。
この絶え間ないお説教が私にどれだけ影響を与えているのか、先生が理解してくれればいいのにと思う。毎日のように失敗しているように感じるのに、1日を乗り越えるのは難しい。もしこれが続くようなら、どうすればいいのかわからない。私は絶え間ないプレッシャーとネガティブな感情に耐えられない。
「トシと一緒にいる時は、どうやって合格するんだ…」
「うるさい、ヒーロー。何も役に立ってないんだから、黙ってて」
「わかったよ!」彼はそう言って立ち上がった。
「ベイビー、落ち着いて」トシが私の肩を揉んだ。
「どうしたら落ち着けるのよ?!トシ、落ちるんだよ!卒業できないんだから!」
「さっき言ったこと、覚えてる?」
「たくさん言ったけど、どれのこと?」
「自分の美しさを使うんだ」
「え?!サー・タモアがもう先生じゃないって、わからなかったの?私のささやかな笑顔やメイクは効かないよ!今回は、私の可愛い顔は使えないの。この可愛い顔のせいで、私は落第したんだから!それが主な理由なのに、どうすればもっと使えるの?」
トシは首を振った。
彼は優しく私の顎に触れ、正しい方向を真似した。
「彼らに自分の美しさを使うんだ」私は眉をひそめた。
食堂に並んだオタクたち。
「なんで彼らに自分の美しさを使うの?」
「私を見て、セリザ」
「何を持ってるの?」
「俺はハンサムでしょ?」
「で?」
「女の子たちは、俺に気づいてもらおうと何でもするんだよ。特に、あいつらみたいなオタクはね。俺がちょっと笑うだけで、宿題をやってくれるんだ」私は口を開けた。だから彼の成績はあんなに高いのか!あのオタクのせいだったんだ!
「あそこの女の子を見て」私はオタクを見つめた。
「あのオタクより私が優れてるって言いたいわけ?私の成績とあのオタクの間にどんな関係があるの?意味がわからないわ」
「彼女は俺の宿題とプロジェクトをやってくれるんだ」
「え?」
「彼女が俺の試験やクイズに答えてくれるんだ」なんで気づかなかったんだ?
彼氏と付き合って数ヶ月になるんだけど、正直言って、彼が学校でどうしてあんなにうまくやっているのか、ちょっと混乱しています。つまり、誤解しないでほしいんだけど、彼は賢い男だけど、いつも本を読んでいるタイプではないんだ。でも、どういうわけか、一生懸命勉強してたくさんの努力をしている私よりも、高い成績を上げているんだ。
最初は、彼は生まれつき才能があるか、写真のような記憶力を持っているのかもしれないと思った。しかし、彼を観察すればするほど、彼は私ほど学校に熱心ではないことに気づいた。彼は授業ではほとんどノートを取らず、宿題もほとんどしないのに、どういうわけか、試験で高得点を取っているんだ。
率直に言って、これは苛立たしいことだ。私は、これだけ一生懸命勉強してストレスを感じて、やっと追いつこうとしているのに、彼は簡単に乗り越えているようだ。どうすればいいのか、彼に尋ねようとしたこともあるけど、彼はただ肩をすくめて、「どうにかなる」と言うだけなんだ。
何か見落としていることがあるのではないかと、考えずにはいられない。もしかしたら、彼は密かに自分で勉強しているのかもしれないし、私よりも情報を保持するのが得意なのかもしれない。しかし、私の中には、彼は公平にプレーしていないと感じざるを得ない部分がある。彼は私にはない、何らかの不当な優位性を持っているような気がするんだ。
一方、私はただ考えすぎているだけかもしれない。彼が本当に生まれつきの才能を持っているだけかもしれないし、彼のことを喜ぶべきなのかもしれない。結局のところ、競争ではなく、私たちが学校でうまくいっていれば、それが重要だ。
それでも、何か裏で起きているような気がしてならない。もしかしたら、もっと彼を注意深く見て、彼の秘密を突き止める必要があるかもしれない。どちらにしても、同じ努力をしていないように見える人に追いつくために、一生懸命働いているように感じるのは、苛立たしいことだ。
「彼女にちょっと微笑めばいい。彼女は俺の言うこと全部やる。セリザ、お前もそうしろ。それが美しさの力なんだ。誰だって、この学校で一番ハンサムな男を喜ばせるためなら、何でもするだろ、セリザ。きっと彼らも、この学校で一番ゴージャスでセクシーな女の子にも同じことをするだろうさ。あのオタクたちは、お前のために何でもするよ」
私は、オタクとその知能とやらについて、ずっと疑いを持っていた。確かに、彼らは本に詳しくて、コンピューターや科学のことはたくさん知っているかもしれないけど、それ以上のことは本当にできるのか?つまり、彼らが事実や数字を覚えるのが得意だからといって、必ずしもその知識を現実世界の状況に応用できるとは限らない。
そして今、その理由がわかった。
オタクが主導権を握ったり、問題を解決しようとしているのを見るたびに、懐疑的にならざるを得ない。彼らは本当にこれを処理できるのだろうか?それとも、単に自分自身を理解しすぎて、混乱させるだけなのだろうか?
彼らの知性や彼らの興味を尊重していないわけではないが、実用的なスキルや常識に関しては、疑いを持っている。もしかしたら、それは私自身の偏見や不安が話しているだけかもしれないが、オタクは時々、実際にそれを有効に活用することよりも、知識で他の人を感心させることに集中ているような気がする。
テーブルを離れる前に、トシが言ったことからどうしても頭が離れなかった。
ベアとアンがちょうどいいタイミングで来た。私たちが食べ終わった後も、彼の言ったことは頭から消えなかった。
私が可愛いから、何でもしてくれるだろう。それは知ってたけど、あのオタクたちとは何もしたくないんだ。
「ビッチ、ずっと深く考えてたの?インフェアネス、考えてるじゃん!」
私はため息をついた。
「今はやめて、ベア。困ってるの」
「何が問題なの、ベイビー?金?お金が必要なら、いつでも私の財布がここにあるわよ」
「違うよ、今はあなたのお金は必要ないの。でも、質問があるの」
「全部話しちゃって!」
「オタクの男の人を知ってる?」
「マジで、セリザ?ファッションセンスのない、頭のいい人たちのグループの一員に見える?」
「ただ聞いてるだけ、ベア」課題が出るかもしれない。でも実際は、彼女は課題をやらなかった。彼女のエッセイは、導入、本文、結論のそれぞれに3つの文章しかなかったからだ。
「誰も知らないわ、いいわね」
私はため息をついた。
この数学の宿題を手伝ってもらう必要があるのはわかっているけど、友達に迷惑をかけたくないんだ。彼らはみんな自分の仕事で忙しいし、それに、私がバカだったり、苦労していると思われたくないんだ。だから、私には選択肢が1つしかないみたいだ。オタクに頼むんだ。
でも、まるで困っているみたいに見せたり、必死に見せたりせずに、どうすればいいんだろう?適当な男の人に歩み寄って、「ねえ、数学を手伝ってくれない?」なんて言うのは、ちょっと変だし。
もしかしたら、宿題の話をさりげなく持ち出して、彼らが手伝ってくれるかどうか様子をうかがう方法を見つけられるかもしれない。あるいは、数学関連の話題について彼らの意見を求めて、彼らの反応を測ることもできる。もし彼らが知識があり、喜んで手伝ってくれるようなら、彼らに助けを求めることができる。
でも、もし彼らが断ったらどうなるだろう?もし彼らが忙しすぎたり、私を手伝いたくなかったりしたら?それは恥ずかしいし、がっかりすることになるだろう。私は、自分をさらけ出して、そして拒絶されるようなことはしたくない。
一方、もし彼らが「いいよ」と言ったら?もし彼らが本当に役に立って、私が宿題を理解できるようになるなら?それは大きな安堵感になり、私の肩から重荷が下りるだろう。
たぶん、鍵は自信を持ってそれにアプローチし、助けを求めることを恐れないことだ。結局のところ、助けを必要とし、それを求めることに何の問題もない。そして誰にもわからないけど、もしかしたら、私も何か新しいことを学んで、少し数学オタクになるかもしれないんだ。
私は周りを見渡した。私の課題に喜んで答えてくれるオタクは他にどこにいるんだろう?
ランダムなオタクを選ぶのは好きじゃない。
だって、彼が本当に賢くないかもしれないから。
そうしたら、私たち両方とも失敗するでしょう!
私は誰か騙されやすい人を探してるんだ。
私の笑顔にすぐに惹かれるような人を。
私は純粋なオタクが必要なんだ。私の視線は、ベアと私のそばを通り過ぎた男に止まった。彼はすぐに私の目を避けた。
「ベア」
「またなの?」
「あれは誰?」私は彼の方向に口を動かした。
「どこ?」
「あー、マグナス・モリソン」
「マグナス…」彼の名前はセクシーな響きだけど、正直言って逆なんだよね。私は彼を完全にスキャンした。彼は分厚い丸メガネをかけていて、ポロシャツをだぶだぶの四角いパンツにしまっていた。古くは見えないけど、時代遅れなんだ。
「そう、マグナス、彼だよ」
「前にも彼の名前を聞いたような気がするわ」
「セリザ、知らないわよ。あなたがオタクに興味を持ったのは初めてだもん」
「彼のことをもっと教えて」