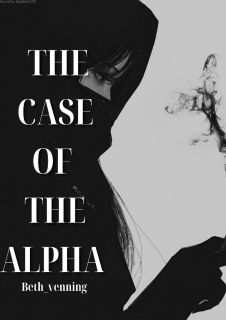紹介
目次
紹介
'The Nerd Can Fight'シリーズの2冊目
*これを理解するには、最初の本を読む必要があります*
アダムの記憶喪失後、ケースは愛する人を守るために距離を置こうと苦労した。
今回は、彼女は危険な戦いを戦うことをもはや選択できない。愛する人々のために、彼女は自分の命を危険にさらし、頂点を目指して戦うことを余儀なくされる。
ケースは高校を生き残ったが、彼女の物語がそこで終わると誰が言えるだろうか。問題は山積みになり、彼女は一掃し始めることを決意した。
これは、他の誰もが彼女を抑えようとしたとき、彼女が持っているすべてで人生を戦い抜いた少女の物語である。
*警告:大量の冒涜表現があります。自己責任でお読みください*
もっと読む
すべての章
目次
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章
第11章
第12章
第13章
第14章
第15章
第16章
第17章
第18章
第19章
第20章
第21章
第22章
第23章
第24章
第25章
第26章
第27章
第28章
第29章
第30章
第31章
第32章
第33章
第34章
第35章
第36章
第37章
第38章
第39章
第40章
第41章
第42章
第43章
第44章
第45章
第46章
第47章
第48章
第49章
第50章
第51章
第52章
第53章
第54章
第55章
第56章
第57章
第58章
第59章
第60章
第61章
第62章
第63章
第64章
第65章
第66章
第67章
第68章
第69章
第70章
第71章
第72章
第73章
第74章
第75章
第76章
第77章
第78章
第79章
第80章
第81章
第82章
第83章
第84章
第85章
第86章
第87章
第88章
第89章
第90章
第91章
第92章
第93章
第94章
第95章
第96章
第97章
第98章