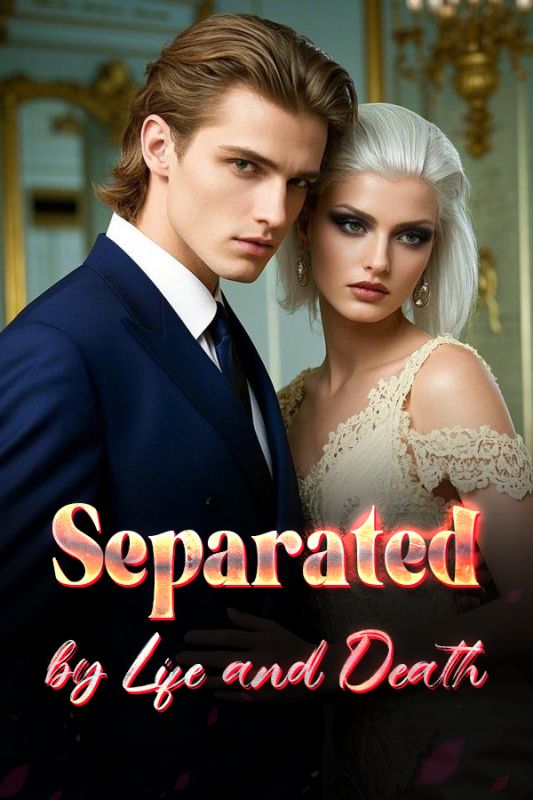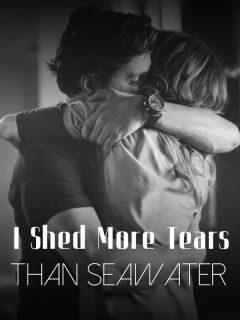暗闇の中で、サラは次の車線にハンドルを切ると、自分のところにスピードを上げてくるヘッドライトのペアを見た。彼女はシャーベット状のものが自分と小さな車を横切って、対向車線に突入するのを感じた。意識がなくなる前に彼女が言った最後の言葉は、「クソッ!」だった。
それから20年ほど経ち、彼女は一番下の娘のベッドに座り、「もうこんなの、嫌だ」と心の中で思った。一番下の娘が成長して、自分の荷物をまとめているのを見ていた。
「ねえ、ちゃんと全部詰めた? 忘れ物しちゃって、どうしても手放せないものがなかったら、大変でしょ」サラは上の空で、一番下の娘が友達と引っ越す準備をしているのを窓の外を見ながら言った。
彼女が判断する限り、娘はすべてを把握しているようだ。立派な仕事も決まっている。でも、大きな街でうまくいくか心配せずにはいられない。ドレスの綿の折り目を何度も指でなぞっていた。もしここで仕事を見つけてあげていたら、大きな街でうまくいくか心配しなくても済んだのに。
「分かってるよ、ママ。ほとんど全部詰めた。残りは全部リサイクルショップに持っていく。それ以外は大丈夫だけど、パパはいつ来るか知ってる? 仕事が終わってから出る交通渋滞に巻き込まれないように、早く来ようとしてるって言ってたんだ。5時に高速道路で渋滞に巻き込まれたら、グランドラピッズは地獄だって知ってるでしょ」ノラは心配そうに、最後に全部見渡しながら言った。
「ううん、実は、ここ数ヶ月、彼とは話してないの。最後に話したのは、あなたが引っ越すって分かった時。彼なら、コネを使ってあなたに仕事を見つけてあげられるかなって思ったんだ。もちろん、うまくいかなかったけど、少なくとも試してみたかったんだ。」
ベッドから降りて部屋を出ようとすると、ノラが彼女に駆け寄り、きつく抱きしめた。「ママ、すごく怖い。いつも私のために全部してくれた。これからは、自分で全部しなきゃならないんだ。アリスのワンダーランドのウサギの穴に落ちていくような感じ。」
「大丈夫、あなたは決して一人じゃないわ。私はいつもあなたのためにいる。もしそこに着いて怖くなったら、遠慮なく電話して。うまくいかなかったら、家に帰ってきて。一緒に考えましょう。絶対にあなたを見捨てたりしないってことだけは知っててほしいの。私はあなたのママで、いつもそうよ。愛してるわ」サラはそう言いながら、涙が一筋、目の端にたまった。
そう言うと、ドアベルがけたたましく鳴り、サラは、自分の可愛い娘が巣立ちの時を迎えたことを悟った。
「最高。パパはいつもタイミングが悪いんだから」ノラはサラに微笑みかけ、それから二人は一緒に玄関に向かい、ジョージを迎えた。サラはジョージを通り過ぎて、外の使い古された引っ越しトラックに気づいた。「これが現実なんだな」と心の中で思った。
その日の午前中と午後のほとんどをかけて、二人はノラの家具や、彼女の持ち物でいっぱいの箱をトラックに詰め込んだ。そして、すべてが梱包され、準備が整ったとき、ジョージはドアを閉めて乗り込んだ。ノラはサラの方を向き、少し躊躇してから言った。「ママ、愛してる。着いたらすぐに電話するね。」
ノラはもう一度彼女を抱きしめ、それから自分の可愛い娘が大人としての人生を歩み始めるのを見送った。その後、彼女は家に戻り、冷蔵庫の中を見て夕食を作るものがないか探した。頭をかきながら、誰もいない部屋に「まあ、私はに出かけるしかないわね」とつぶやいた。
出かける準備を終えた後、彼女は突然寂しさを感じ、それがとても辛くて、ほとんど泣きそうになった。「私、どうしちゃったんだろう? 子供が初めて家を出たみたいに振る舞ってるわ」彼女は誰もいない部屋にそう言い、首を振って、お腹が痛み出す前に、もう出かけた方がいいと決めた。
数分後、彼女はスーパーの私道に入り、駐車場はほとんど満車で、後ろに1つのスペースしか空いていないことに気づいた。それで、彼女は中に入り、自分の赤いビュイック・ルセイバーから出るのに十分なスペースだけを残して駐車した。まだ結婚していた頃からの懐かしい車だ。足早に中に入り、カートを借りて、ハンドバッグからリストを取り出した。
通り過ぎる際、彼女は肉のカウンターのそばにいる男に気づき、しばらく見つめていた。すると、彼の輝く青い目がすぐに彼女の目に吸い寄せられた。彼は微笑んで彼女にうなずいた。サラも微笑み返しながら、「今夜、彼と仲良くなりたいな」と思った。
その時、彼女は彼をどこかで知っていることに気づいた。でも、どこで? 最近のことだったら、絶対に覚えているはずだ。
「夕食に来ないかって誘ってみようかな?」彼女は、結婚指輪を探しながら、彼の手に目を向けた。
「今夜、何か美味しそうなものを作ってるみたいだね」彼は、自分の食べ物ではなく、彼女の胸を見ていることに気づいた彼女に言った。
彼は顔を上げ、彼女が自分の動きをすべて見ていることに気づくと唇を舐めた。そして、「あの美しい胸の間で抱きしめられて眠りたい」と心の中で思った。
「ええ、まあ、お腹がすいてる時に店に来ちゃいけないんだけど、冷蔵庫に何も良いものがないことに気づいたの」彼女は気まずそうに笑いながら続けた。「それに、あなたのカートを見てると、手作りの料理が必要だわ」サラは彼にちょっかいを出しながらも、同時に気分が悪かった。
そこに立っていると、彼のカートに入っているのは缶詰スープとデリのフライドチキンだけだった。
「君に料理してもらって、美味しいものを食べられたらいいんだけどな」彼は笑顔でそう言い、それから自分の時計を見てため息をつき、「もう行かなきゃ、じゃないと仕事に遅れちゃう。みんな請求書を払わなきゃいけないのが残念だよ」彼は笑い、それからこう付け加えた。「また会えることを願ってるよ。ところで、僕の名前はサム。君の名前は?」彼は彼女の手を取って自分の唇に近づけ、彼女の柔らかく滑らかな肌をなぞった。それはたちまち彼女の背筋を震え上がらせ、息を呑ませた。彼も同じだった。どうしたらいいか、何と言ったらいいか分からず、サラは口を開けたままそこに立っていたが、それに気づき、ついに答えた。
「サラよ。また今度、何か作ってあげられるかも」彼女は、言葉の中にすべての約束を込めたが、実際には、そんな機会はないことをよく知っていた。
「絶対に。まあ、行かなきゃならないんだけど、仕事が待ってるんだ」
彼は腕を広げたので、彼女は友好的なハグでお別れを言おうとしているのだと思い、快くそれに従った。しかし、彼が彼女を抱きしめるとすぐに、彼の腕は彼女の脇をくすぐった。彼女は少しの間笑った後、解放され、彼の肩を軽くパンチした。
「何それ?」彼女は、一体何が起こったのかまだよく分からないまま尋ねた。
「君がくすぐったがりか知りたかったんだ。僕はくすぐったがりの女性がフェチなんだ」彼の笑みが大きくなり、目に光が宿った。
彼女がもっと何かを言う前に、彼は向きを変えてレジに向かった。まもなく、彼は夜の中に姿を消した。その後、サラは買い物を続けたが、サムは彼女のすべての思考を悩ませた。「くそっ! 彼の電話番号を聞けばよかったわ」彼女はレジを済ませながら、つぶやいた。
家に帰る途中、彼女は彼の唇が自分の肌に触れた感触を何度も頭の中で繰り返した。彼が触れた瞬間、彼女の神経は生き返り、彼女は突然すべてを感じた。キスのような単純なことに、自分の体が反応するのは本当に素晴らしいことだった。もちろん、彼に二度と会えないかもしれないのに、なぜそんなことを考えているのだろうか。
彼女は首を振り、ため息をつき、それからイグニッションからキーを取り出し、家に入って食事を作った。彼を見つける方法があるに違いない。
家に帰る途中、彼は心の中でつぶやいた。「なんで彼女の番号を聞かなかったんだろう? 彼女は他の人とは違うかもしれないのに」寂しげな声で、空っぽの家に帰るために運転した。