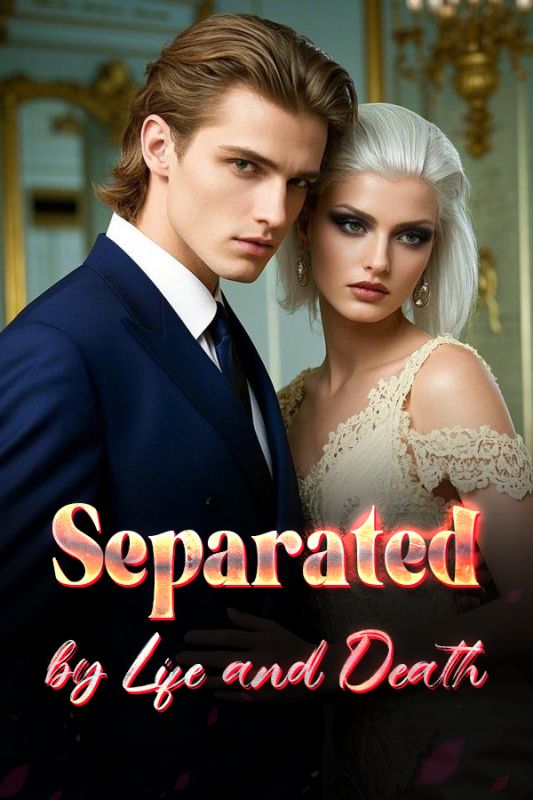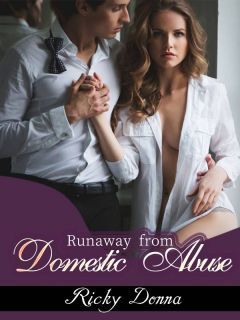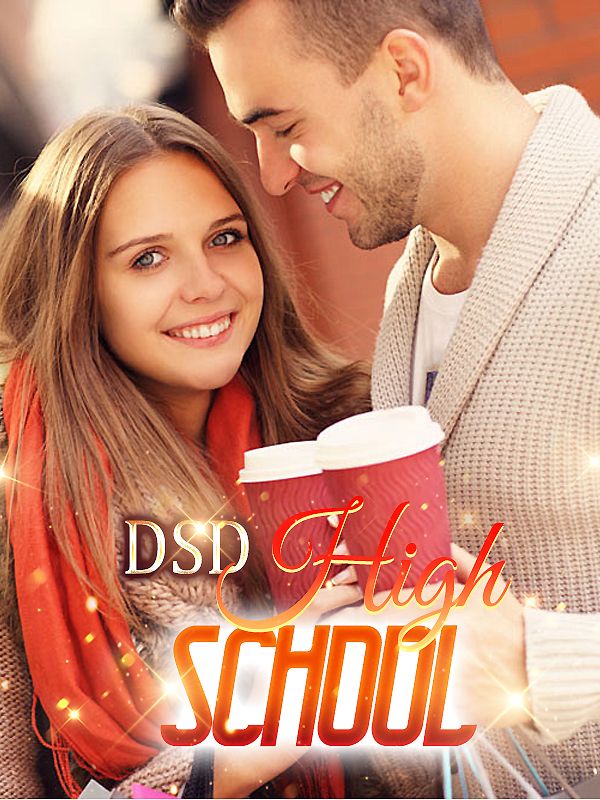今日は【ケビン】の22歳の誕生日。あたし、愛するあの人のために、半月も前から色々準備してたんだ。
なのにさ、まさかの展開。
あたし、アイツが他の女に甘い言葉を囁いてるの、聞いちゃったんだよね。
「【リサ】のこと? あの子はさ、ビジネス界のお姫様でしょ。あたしみたいな、ただの一般人とは全然違うじゃん」
女の言葉には、明らかに嫉妬が滲み出ててさ。あたしを貶めようとしてるのが、まるで【ケビン】の口を通して伝わってくる感じ。
その瞬間、心臓がドキッとした。
【ケビン】の返事が、すごく楽しみでもあり、すごく怖くもあった。
2秒後、予想通り、皮肉たっぷりの口調で【ケビン】が言ったんだ。
「姫? 男に媚びへつらう姫がいるのかよ」
二人の声は遠ざかっていく。あたしの心に開いた傷が、また痛み出した。
無理やり笑顔を作って、心の中で自分を責めた。
答えは分かりきってたのに、あたしはまだそれを求めてたんだ。これって、まさか、マゾズム?
でも、あたしは【ケビン】を12年も好きで、彼に優しくするのが習慣になってた。もう、簡単に壊せるもんじゃないんだよね。
「【リサ】、なんでここにいるんだ?」
【ケビン】の口調は冷たくて、その瞬間、また心臓がドキッとした。
ゆっくり振り返ると、アイツは別の女と絡んでる。
「あたしは…」
あたしの言葉は、【ケビン】の苛立ちに遮られた。
「あたしに縋り付いて、関係を認めてもらおうとして、結婚を迫ろうとしてるんだろ。なんでそんなに必死なんだよ、一体」
その日の終わり、あたしは、どんなみじめな姿でそこから追い出されたのか、覚えてない。
でも、分かってた。あたしは、【ケビン】のせいで、最後の自尊心まで失ったんだって。
半月後、あたしは、22歳になった【ケビン】を、あたしの父の50歳の誕生日のパーティーで見た。
アイツはさらに大人になってて、輝くように魅力的になってた。
抑えきれず、あたしは飲み物を勧めるために近づいたんだけど、アイツはそれを巧妙に避けたんだ。
「悪い。【リンダ】がすごく厳しくてさ、知らない女の人とあんまり話すなって言うんだ」
【ケビン】の笑顔は、何か思い出したように明るくなった。
「知らない女の人」って言葉が、あたしにはとてつもなく辛かった。
【ケビン】とは、一緒に育ったんだ。一度は、あたしのことは好きじゃなくても、あたしはアイツの中で特別な存在だと思ってた。
でも、違った。あたしは、自分を過大評価してたんだ。
「そっか…」
パーティーの間中、【ケビン】は、あたしをまるで疫病神のように避けてた。アイツから、心の底からの軽蔑が伝わってくる。
三度目、あたしがうっかり触れてしまった後、手を拭いた時、あたしはついに口を開いた。
「そんなに、あたしのこと嫌いなの…? 触るのも嫌なくらい?」
【ケビン】は、本能的にあたしの後ろを見た。誰もついてきてないのを確認して。
苛立ったように頷いた。
「分かってるなら、もっと賢く、あたしから離れてろよ」
あたしは、やっとのことで「なんで」って言葉を絞り出した。
心は痛い。でも、わざともっと痛みを求めて、【ケビン】に言葉を投げつけ、自分の手でまたあたしを刺させた。
「なんで? 【リサ】、あたしにそんなこと聞くなよ。お前が【リンダ】との仲を邪魔したから、今、あいつはあたしに会おうともしないんだろ? あいつはあたしの人生の愛なんだ。一緒になれないなら、お前を許さないからな」
【ケビン】の言葉は強烈で、あたしはほとんど言葉を失った。
涙が滲んでくる。
半月前、あたしの秘書が【リンダ】の過去を調べたんだ。
【リンダ】は、叔母に教えられたずる賢いやり方で育ってて、何人ものお金持ちの若い男を騙して、心と金を奪ってきたらしいんだ。
あたしは【ケビン】に忠告しようとしたんだけど、アイツはそれ以来、あたしをますます嫌うようになった。
その日、アイツが最後に言ったことを覚えてる。
アイツは言ったんだ。
「たとえ【リンダ】が嘘をついてたとしても、あたしはそれでも構わない。お前、【リサ】、覚えておけ。あたしは、この先、一生お前を愛することはない」
「この先、一生」って言ったんだ。
もちろん、あの男の傲慢さは、すぐに自分に返ってきた。
【リンダ】は、【ケビン】に嘘をついて株を譲らせて、手に入れた途端に逃げたんだ。
オーストラリアに逃げて、別の男と幸せに暮らしてる。
ちょうど、【ケビン】の父の家で、権力を握ろうとする人が現れて、すごく大変な時期だったんだ。
あたしは、【ケビン】も、ついに目を覚ますと思った。
でも、次の日、両親から、アイツが国外に出たって聞いた。
全てを奪った女、【リンダ】を探しに行ったんだって。
【ケビン】の父は、心臓発作で、半月も入院した。
【ケビン】はそれを無視して、ただ【リンダ】のことだけを考えてた。
【ケビン】の母が、個人的に海外から連れ戻したんだ。
あたしは、その日、たまたま病院にいた。
再会した時、【ケビン】は迷わず、あたしを平手打ちしたんだ。
「ビッチ、全部お前のせいだ。お前が、【リンダ】とのチャンスを奪ったんだ… 全部、お前のせいだ」
【ケビン】の旅はうまくいかなかったみたいで、以前は美しかった目は、今ではくぼんで赤くなっていた。
あたしは、【リンダ】が何を言ったのか、そんなことどうでもよかった。あたしは、アイツが全てをあたしのせいにしてるってことだけ分かってた。
その瞬間、あたしは自分の気持ちを表現できなかった。顔は青ざめ、無力で、ちょっと面白くもあった。
「それで? あたしを殺すつもり?」
【ケビン】がナイフを持っていたら、躊躇なくあたしの胸を刺しただろうって、確信してた。
「そうしたいのは山々だけど…」
【ケビン】の母の言葉が、見事にアイツを黙らせた。
「あんたはバカね、全部あんたが甘やかしたせいよ。こんな冷たくて身勝手な人間にしちゃったんだから」
それから、誰も【ケビン】のことなんか気にしなくなった。
3メートル先のオペ室では、まだ赤いランプが点灯してた。 【ケビン】の父が、その夜を乗り切れるかは、運次第だった。
でも、【ケビン】は父の命のことなんか、まるで気にしてない様子で、決して繋がらない番号に電話をかけ続けてた。
「まさか… 【リンダ】はまだあたしのこと愛してるはずだ。あたしを置いていくわけがない」
【ケビン】の母は、アイツが鬱陶しくて、病室に一人で追い出したんだ。
午前3時か4時頃、丁度【ケビン】の父の手術が成功した頃、病室の看護師たちが驚きの声を上げたんだ。
【ケビン】は、自分を捨てた身勝手な女に追い込まれて、あのビルから飛び降りたんだって。
幸い、そんなに高い階じゃなかったから、軽傷で済んだ。
もしそうじゃなかったら、【ケビン】の両親は、若くして息子を亡くす悲しみを味わうことになっただろう。
変なことに、目が覚めた【ケビン】は、あたしを小馬鹿にし続けた。
でも、あたしの心は、全く揺れなかった。
まるで傍観者のように、あたしは、あの男が狂っていくのを見て、滑稽だと思ったんだ。
「【リサ】、お前の魂胆は分かってるんだぞ。お前は、【リンダ】と一緒にいられないようにすれば、あたしが、お前を好きになるとでも思ってるのか? バカげてるよ、絶対にないからな」
幸いなことに、あたしも今は同じ気持ちだった。無理だ。
3ヶ月後。
【ケビン】の父は、あたしに、自分の株の20%を譲るっていう取引を持ちかけてきたんだ。
あたしは良い条件だと思って、株主総会でホワイト家を助けることに同意したんだ。
でも、最後の最後に、二人の招かれざる客が事務所に現れたんだ。
「【リサ】、ホワイト家を助けられるのは、お前だけだと思うのか? 【リンダ】だってできるんだぞ。今回のために、ステータスを勝ち取るために、あたしのために、海外に行ったんだからな」
【ケビン】は特に得意げで、あたしの視線に気づくと、その女をさらに強く抱きしめた。
でも、そんな光景は、今のあたしにはただ愚かで滑稽にしか見えなかった。
あたしは、【ケビン】の父に丁寧に頭を下げて、退場した。あの「英雄」に舞台を譲って。
【リンダ】が、なぜ突然帰ってきたのか、あたしには分からなかったけど、良いことじゃないってことは確かだった。
幸い、あたしはもう、この渦から抜け出せてた。こんな痛みは、もうあたしのものじゃない。
【ケビン】が気に入ってるなら、ゆっくり楽しめばいい。
偶然か、運命のいたずらか、あたしが【ケビン】の父のお見舞いに行った時、【ケビン】と【リンダ】が言い争ってるのを見かけたんだ。
【リンダ】みたいに欲深い女が、株の20%だけで満足できるわけがない。
あの女は、ホワイト家の財産の全てを欲してたんだ。
【ケビン】が全てを黙認したって聞いた時、父だけでなく、あたしまでぞっとした。
自分の息子で、20年以上も育ててきた人が、よそ者を助けて、自分を陥れようとしてるんだから。
昔だったら、そんな裏切りは、天罰ものだろう。
【ケビン】の父が協力しようとしないのを見て、【リンダ】はパニックになって、無理やり彼の手に契約書を書かせようとしたんだ。
あたしは、ただの部外者で、邪魔をする権利なんてない。
同情心があふれたのか、邪魔をしただけでなく、このクソ女を警察に突き出そうとしたんだ。
でも、全てがあまりに速く起こって、あたしが反応する前に、血の海に落ちてた。
【ケビン】だった。あたしが警察に通報して、【リンダ】を逮捕させたから、あたしを殺そうとしたんだ。
小さなナイフが、正確に、あたしの心臓に突き刺さったんだ。
意識を失う前に、あたしは、頭上の白熱電球に最後の視線を投げかけた。
これが、この人生で最後に見るものになるかもしれないって。
人生の思い出が、映像のマラソンのように、目の前を駆け抜けたんだ。
でも、【ケビン】だけにある思い出は、無理やり引きずり出されたみたいに、灰色のぼやけとして残った。
涙が、頬の端を伝った。
【ケビン】とあたしは、本当に、もう終わりなんだ。
ICUで半月後、あたしが目を覚まして最初に聞いたニュースは、ホワイト家の所有者が変わったってことだった。
結局、【ケビン】の父は、愛する息子の手によって死んだんだ。
【ケビン】の母は、その衝撃に耐えきれず、気が狂ってしまった。
その時、あたしは、かつて【ケビン】が、あたしに語った、骨の髄まで染み付いた嫌悪感を理解したんだ。
その感情は、実際に、それを考えるだけで、身体的に不快になるってやつだ。
それが、今のあたしが【ケビン】に対して抱いてる気持ちなんだ。
でも、あたしはかつて、【ケビン】と【リンダ】を酷く「台無し」にした。
そんな女が、このチャンスを逃して、あたしに嫌味を言わないわけがないよね?
だけど、あの女の計算には、一つ抜けがあったんだ。あたしの心には、もう【ケビン】の居場所なんてなかったんだから。
二人は手を取り合って現れた。薬指には、同じ指輪が光ってる。
「【リサ】、そういえば、お前は、【リンダ】とあたしをくっつけたキューピッドみたいなもんだな。来月の婚約パーティーには絶対来いよ」 【ケビン】は、「婚約パーティー」という言葉をわざと強調したんだ。
あたしが恥ずかしがるのを見たかった。あたしがアイツに夢中になって狂うのを見たかったんだ。
そうすれば、アイツは道徳的に優位な立場に立って、あたしが他の人の関係を邪魔するようなバカだって非難できるんだから。
でも、あたしはそうじゃなかった。まるで、重要じゃないニュースを聞いてるみたいに、最後まで冷静だったんだ。