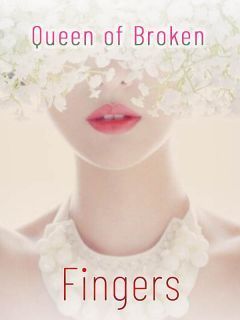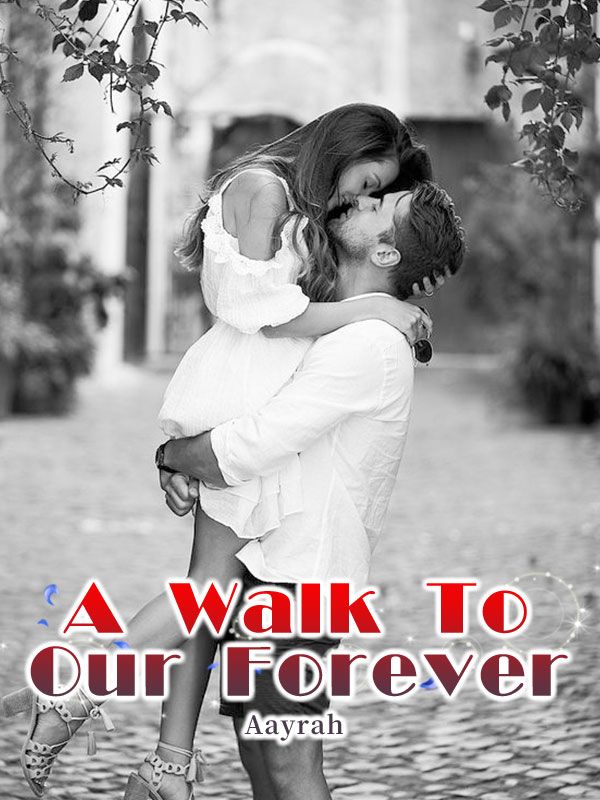紹介
目次
紹介
ルアナ・カサビアは、雇い主の息子に代わって尊敬される貴族と結婚するなんて考えもしなかった。
特に、漆黒の瞳を持つ男が、ルアナの薬指に指輪をはめたときでさえ、非常に鋭い視線で彼女を見たときには。
ルアナがこの男と結婚するという決断は正しかったのだろうか?もしルアナが単なる代理人なら、本物の花嫁になれるのだろうか?
もっと読む
すべての章
目次
1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
33
35
36
37
40
41
42
43
44
46
47
49
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
65
66
68
69
70
71
72
74
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
109
111
112
48
92
45
76
88
24
20
38
75
9
50
101
5
14
28
39
58
67
86
108
34
64
73
110