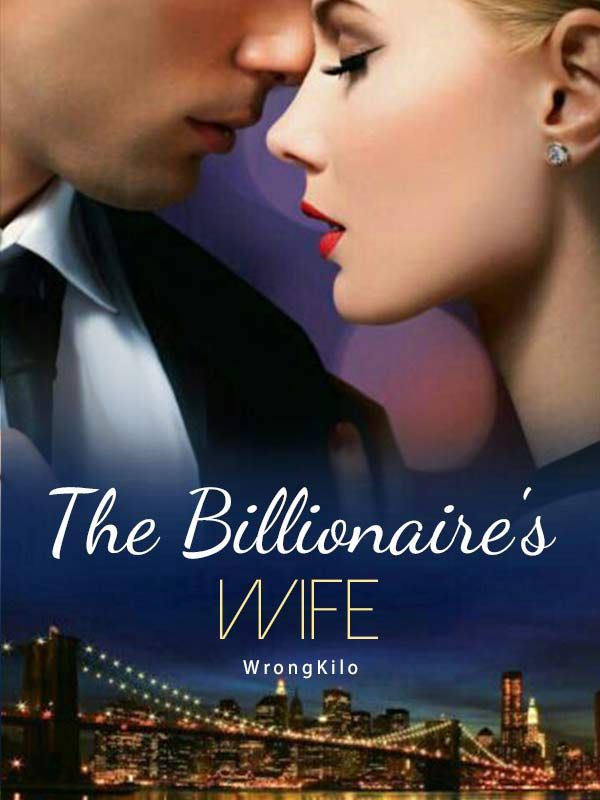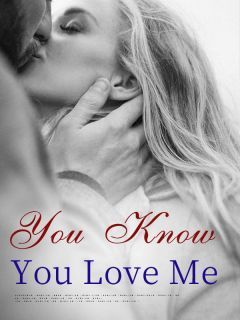やっと、何日も何日も頑張った末、俺たちの先輩の年の試験が終わった。 あいつらが地獄だって呼んでる場所から解放されたんだ。 また彼に会って、俺たちの人生を永遠に変えるニュースを伝えたくて、すっごくワクワクしてた。 俺たちは未来について、まだ何も計画してなかったんだよね。 今まで、俺たちのメインの焦点は、ありがたいことに終わった、これから先の試験だけだった。 でも結局、物事は俺たちの願いとは反対に進んで、神様が俺たちにベイビーを授けてくれたんだ。 もう少し我慢すれば、俺たちの小さな家族に、小さな喜びの塊が加わることになる。 妊娠七週目で、赤ちゃんは健康なんだ。 最初は、なんかウイルス性の病気にかかったのかと思ったんだよね。 責めないで! 眩暈と吐き気で、昨日までそう思ってたんだから。 彼の子供を俺の子宮の中で育ててるってことが、俺の心を喜びでドキドキさせたんだ。 叫びたかったよ、大声で「私は正式に彼のものになるんだ! 俺たちは新しい家族の仲間を歓迎するんだよ!」ってね。 困ったことに、俺は大学のキャンパスにいたから、生徒たちを怖がらせたくなかったんだ。 彼はどんな反応するだろう? マジで、彼の顔が見たかったんだ。 彼の表情が見たか���た。 口をあんぐり開けて、自分が聞いたことが本当なのか、それとも自分の耳が想像を裏切ってるのか、信じられないような顔をしてるところを見て、笑いたかったんだ。 多分、ビデオを撮って、将来を思い出すための思い出としてとっておくことになるだろうな。 それとも、彼が成長した俺の小さなベイビーに、彼の反応を見せてあげようかな。 そして、彼がまだ石像みたいに立ってたら、「そうだよ、本当なんだ。 俺たちは自分たちの家族を持つことになるんだよ」って言って、彼の頬をつねってやろう。 全ての瞬間を楽しみたいんだよね: 彼が近づいてきて、俺を腕の中にきつく抱きしめて、この赤ちゃんを持つことができて最高に嬉しいって言ってくれる。 彼は、自分の魔法の王国から出てきたら、どうするんだろう? きっと、俺の頬に指をそっと当てて、親指で俺の涙を拭ってくれて、「大丈夫だよ、何があっても俺はここにいるから」って言って、安心した笑顔をくれるに違いない。 「もし彼がそのニュースを喜んでくれなかったらどうしよう?」 俺の良心がまた尋ねてきた。 昨日の朝から、この疑問が頭から離れなかったんだ。 「いや。」 彼の妹のレイチェルが妊娠を打ち明けたとき、彼はすごく喜んでたんだから。 彼は、どうやって赤ちゃんの面倒を見るのか、どうやって甘やかすのかについて話し合ってたんだ。 レイチェルは、昨日、医者から性別を確認した後、彼女の子供は男の子だって教えてくれたんだ。「心配しないで、スウィーティー。 パパがお前の面倒を見るからね」って、俺はお腹を優しくさすりながら、俺の小さなピーナッツに言ったんだ。 一晩で、この赤ちゃんにすごく愛着が湧いちゃった。 赤ちゃんは、俺たちの愛から生まれたんだ。 俺は自分の深い思考の海に溺れてるんだけど、俺の彼氏が口笛を吹きながら、車のキーを人差し指で回しながら、駐車場の方へ歩いていくのを見逃さなかったんだ。 間違いなく、彼は史上最高のパパになるだろうね。 私はニヤリと笑い、夫の美しさにうっとりした。 彼は、白いTシャツと黒いジーンズを着てて、すごくかっこよかったんだ。 彼の髪は乱れてて、何度も手でかき上げてたみたい。 彼の顔は輝いてて、薄い笑顔を浮かべてたんだ。 多分、俺のこと考えてたんだろうな。 彼は俺が他の日と同じように、駐車場にいるって思ってたはずだよ。 あ、しまった! 遅刻しちゃった。「ケイイッシュ!」 私は彼の名前を呼んだけど、彼の耳には届かなかった。 私は彼を追いかけて、ペンギンのように駐車場に向かって走り出した。 足の感覚がなかったんだ。 正直言って、すごく疲れてて、歩くことさえできなかったんだ。 私は彼の前に立って、激しく息を切らした。 落ち着くまで、少し時間がかかったよ。 彼が俺を見て、ものすごくニヤリとして、俺を抱きしめてくれたんだ。「試験はどうだった?」彼は尋ねた。「よかったよ。 あなたは?」 私は必死に息を切らした。「いつも通り。」彼は肩をすくめた。 私は彼に微笑んだ。 彼は、俺たちの大学のトップだったんだ。 この試験は、彼にとっては子供だましだったんだ。「どうしたんだ、リヤ?」 彼は、俺が結婚指輪をいじってるのに気づいて尋ねた。 緊張すると指をいじるのが、俺の癖だったんだ。「ケイイッシュ、私…あなたに何か伝えたかったの」 私は、まだ結婚指輪をいじりながら、神経質に彼に言ったんだ。 彼は俺の顎を手に持ち、俺は彼の触れ方に身を任せた。「リヤ、俺も君に何か伝えたいことがあるんだ」 彼は言って、俺は眉をひそめた。 彼は俺に何て言うんだろう? 「別れよう。」彼は言い放った。「え?」 私は彼を見て、顎が床に落ちそうになった。 自分の愚かさを抑えきれず、私は吹き出してしまった。「ケイイッシュ、私はあなたに良い知らせを伝えに来たんだけど、あなたは冗談を言ってるのね」 私は彼の肩を軽く叩いた。 別れるなんて、俺たちの辞書にはないし、彼はいたずらのためにも、こんな言葉は使わないんだ。 彼は俺に微笑む代わりに、腕を組んで胸の前で組み、眉を上げた。「どう見える? なんで、これは一種のジョークだと思うんだ、ミス・カデル?」 彼は眉をひそめた。 彼がいつものように「ベイビー」とか「ワイフィー」って呼ぶ代わりに、俺の苗字で話しかけてきた瞬間、俺はそこに凍り付いた。 何かおかしい、彼の遊び心はすっかり消えて、彼は真剣モードに戻ってたんだ。「ケイイッシュ、もういいよ。 やめて。」 私は涙でいっぱいになった。 なんで彼は俺をからかってるの? 彼にとって、これが面白いことなの?「まあ、ミス・カデル。 俺は本当のことを言ってるんだ。 良い彼氏のフリをするのはもう飽きたんだ。 もっと正確に言うと、良い夫のフリをするのはね。 俺は誰かと結婚することに、一度も興味がなかったんだよ。ましてや、君とね」 彼は俺に指を指した。 私は彼にもう一度笑ってやりたかったけど、怖かったんだ。 もし彼が本当のことを言ってるって考えたら、怖かった。「なぜ?」 私は尋ねた。 涙が頬を伝って流れ落ちた。「覚えてる? 2012年1月2日」 彼は、俺の心臓に冷たいものが走るような、いつものような口調で尋ねたんだ。 その瞬間、まるで俺が氷山に投げ込まれたみたいに感じて、心臓が胸に激しく打ちつけた。 なんで、彼は今こんなこと聞いてくるんだ? それは、俺たちの最初の出会いで、上手くいかなかったんだよね。「お前はみんなの前で俺を屈辱させたんだ。 お前は俺にキスしただけで、クソみたいな野郎が俺を平手打ちしたんだ。 あの日、俺は自分に誓ったんだ。お前を俺のものにして、お前の人生をめちゃくちゃにしてやると」 彼は吠えた。「でも、お前は俺に身体を触らせなかった。 だから俺は、お前をダメにするために結婚したんだ。 この結婚は俺にとって何の意味もない、お前の正気を手に入れるための鍵に過ぎないんだ」 彼の言葉一つ一つが、俺の心を刺したんだ。「お前の体が欲しいんだ、お前じゃない」 彼は俺の耳元で囁いた。 俺の体は完全に麻痺し、足が震えてた。 彼は本気じゃない。 彼は俺のケイイッシュじゃないんだ。「今、俺は復讐を果たしたから、このドラマから解放されたいんだ」 彼は、ズボンのポケットから封筒を取り出して、それをビリビリに破いた。「これ…これが、俺たちの結婚の唯一の証拠だ。 持ってろ」 彼はその紙切れを俺の顔に投げつけた。「まあ、お前は俺に良いニュースを伝えたいんだろ? もう良いニュースじゃないことを願うよ」 そう言って、彼は俺の唇を攻撃的に叩きつけた。 彼の触れ合いにひるんだのは、これが初めてだったんだ。 それは情熱的なキスどころか、彼が俺に対して感じてる怒りと憎しみすべてを投影したキスだったんだ。 彼はキスを終えて、俺を見た。「今日、俺は出ていくから、俺を探すために時間を無駄にするな」 そして彼は踵を返して、自分の車に飛び乗ったんだ。 しばらくして、タイヤの擦れる音が聞こえて、彼が俺を置いていったんだってことがわかった。 彼は行ったんだ。 俺を一人ぼっちにしたんだ。 俺たちを一人ぼっちにしたんだ。 私は、そこでほぼ1時間立ち尽くしてた。 じゃあ、今まで彼は俺を愛してるふりをしてただけだったんだ? そして、彼は血まみれの復讐のためだけに、そんなことをしたんだって? なんで、私はこんなに世間知らずになってしまったんだろう? なんで、私は彼が俺の気持ちを弄んでるって気づかなかったんだろう? でも、彼は偽ってる間に考える暇を与えなかったんだ。 私は彼の愛は本物だって感じてたから、でも彼は俺が間違ってると証明したんだ。 私は彼のせいで両親を捨てたんだ。 私は彼を信じすぎたんだ。そして今、俺は使い古された紙切れだってことに恥ずかしさを感じてる。 彼の使い古された紙切れ。 俺の心は、彼が出て行ったっていう事実を受け入れようとしなかった。 俺たちの甘い思い出が全部、頭の中に蘇り始めたんだ。 彼が俺にしたことを考えると、それがまだ甘い思い出になるのかどうかわからないんだ。 頭の痛みはひどくなって、いつ爆発してもおかしくないって感じたんだ。 そしてすぐに、周りに黒い点がちらつき始めたんだ。 次の瞬間、俺はベイビーと俺のことだけを考えて、意識を失ったんだ。 俺のベイビー。 彼は、それを知るに値しないんだ。