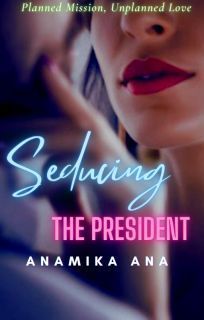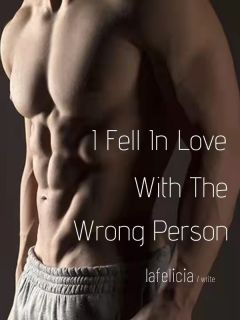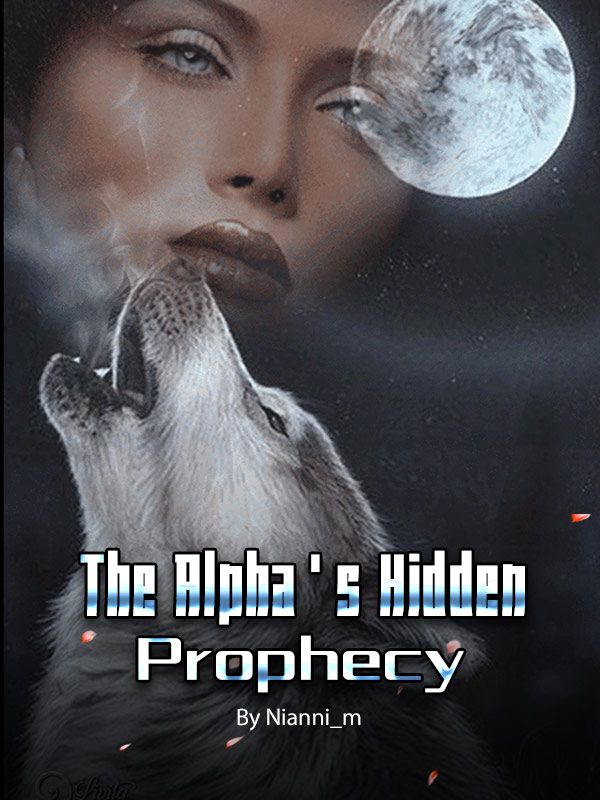ローレン・ジョーンズの手が寝室のドアに触れる前に、部屋でセックスしている音が聞こえた。あるウーマンの深い唸り声と、男の低い喘ぎ声が混ざっていて、ローレンはそれによく聞き覚えがあった。
ローレンは顔をしかめ、手を引っ込め、ドアを蹴り開けた。
部屋の中の絡み合った二つの体がローレンを吐き気にさせ、嫌悪感で顔を背け、口と鼻を覆った。
ベッドの上の痩せてハンサムな男は止まり、ドアの前にいる招かれざる客を冷たく一瞥し、自分の下のウーマンのふっくらとしたお尻を叩いた、「出て行け」。
ウーマンは誘惑的に彼の体に寄り添った、「アルフレッド、私を置いていかないで…」
男は我慢がならなくなった。彼の声は冷たく、容赦なくなった、「出て行け!」
ウーマンはもう一言も言えず、服を手に取り、適当に包んで、部屋からよろめき出た。
ローレンのピンク色の唇はきつく閉じられた。夫を長い間見つめた後、彼女は冷たく言った、「私の気分を台無しにしているのかしら?」
アルフレッド・ケントの冷たい目は深い軽蔑を露わにした、「いつも台無しにするのが得意ね」。
彼は服を着る気さえせず、ベッドに直接寄りかかってローレンを見ていた。「実家に帰るなら、もう少し長くいてくれない? 厄介者!」
彼は裸のまま彼女に向かって、こんなにあからさまに尋ねた。
「アルフレッド・ケント!」ローレンが必死に抑えようとしていた感情が少し抑えきれなくなった。「自分を隠そうともしないの? 本当に気持ち悪いわ」。
「気持ち悪い?」アルフレッドの声は低く冷たかった。彼の顔は無関心でいっぱいだった。それから彼は突然立ち上がり、服も着ずにローレンに近づいた。
彼の冷たい視線に、ローレンは無意識に二歩後ずさった。それから彼女はよろめいて地面に倒れた。
痛みを全く感じないうちに、彼女はアルフレッドに抱きかかえられた。彼は彼女の腕をきつく掴み、痛みを伴って彼女を掴んだ。「金のために他の人を別れさせた。私が病気だって?よく言うわね」。
ローレンは目に涙を溜めながら、「別れさせたのは私じゃないわ。おじい様たちが決めた婚約なのよ…」
その婚約が原因で、アルフレッドは彼の愛するガールフレンド、キャリー・グリーンを失い、ローレンと結婚することになった。
ローレンは、彼と結婚することを知った時の自分の歓喜をまだ覚えていた。彼は、少女の頃に夢見ていた彼女のプリンス・チャーミングだった。そして彼は本当に彼女の夫になった。彼女はウェディングドレスを着ながら微笑み、急いで彼の世界に入った。しかし、彼は彼女に近づくにつれて冷たくなっていった。
彼は、キャリーを追い出したのはローレンの策略だと思っていた。
ローレンは人が物事をコントロールすることはできないと言ったが、アルフレッドは物事は常に人が作り出すものだと信じる傾向があった。彼は、これを計画したのは、長年彼を愛してきたこのウーマンだと信じていた。
彼女の顎は容赦なく掴まれた。ローレンはもう涙を抑えることができなかった、「アルフレッド、本当にあなたたちを別れさせようとしたわけじゃないの…」
彼女の言葉はアルフレッドをさらに攻撃的にさせた、「ああ、なぜ? あなたのような高貴なウーマンが! ノア・ケントがあなたと親しくなったとき、彼の願望だったに違いないんでしょう?」
「本当に…」
「もうたくさん! 今になって、そんなビッチだったのに否定するの? 本当に嫌だわ」。
彼女は彼の言葉をはっきりと聞いた。すべての言葉がローレンの心にナイフのように突き刺さった。
彼女は口を開けたが、一言も発しなかった。彼女の涙は徐々にアルフレッドの手に落ち、人々は冷たく寂しい気持ちになった。
アルフレッドは皮肉っぽく鼻を鳴らし、振り返ってローレンをベッドに投げつけた。彼の背が高く頑丈な体は彼女の華奢な体に押し付けられ、彼女はほとんど息をすることができなかった。
「売春婦はお金持ちと寝るのが好きだって聞いたことがある。今日は俺の気分を台無しにしたけど、ちょうどいいタイミングだった。お互い必要なものを手に入れるんだ」。
彼はそう言って、ポケットから財布を取り出し、ローレンの顔に叩きつけた、「こんなに大金を与えるんだから、お前みたいなビッチを喜ばせてやらなきゃな」。
ローレンは涙を滲ませながら彼を見た、「アルフレッド、あんた最低ね」。
アルフレッドは一言も言わず、彼女の服を容赦なく引き裂いた。彼は彼女を誘惑し、傷つけ、怒りをぶつけ、彼女の尊厳を踏みにじった。
ローレン・ジョーンズのことになると、彼は彼女をひどい方法で屈辱を与え、傷つけることを気にしなかった。彼が望んでいたのは、彼の愛するガールフレンドとの別れの原因となったウーマンが全身にアザを作るのを見ることだけだった。
彼は彼女のデリケートな体、乳房、汗と格闘の跡に覆われた白く柔らかい肌を見つめた。これらすべてが彼女をより魅力的に見せた。アルフレッドは目を細め、ためらいもなく彼女の中に入った。
ローレンは彼の圧力の下で縮こまり、すでに呼吸する力も失っていた。彼女はまるで果てしない痛みに閉じ込められているように感じた。その痛みは、体からではなく、血が滴り落ちそうな彼女の心から来ているようだった。
どれくらいの時間が経ったのか分からなかった。彼女は意識があるのか、気絶寸前なのか、アルフレッドが止まったことをぼんやりと感じた。それから彼は立ち上がり、何の慈悲もなく去っていった。
彼にとって、それは欲望を示すことではなく、怒りをぶつけることだった。
ローレンがようやく再び目を開けたとき、朝の光が部屋に入ってきた。
夜明け、仕事に行く時間だ…
彼女は苦笑し、仕事への情熱を少しだけ尊敬した。しぶしぶ汗で濡れた体を支え、足をひきずって身支度を整えるために立ち上がった。
下腹部に痙攣が起こり、バスルームの床に少し血がついていた。