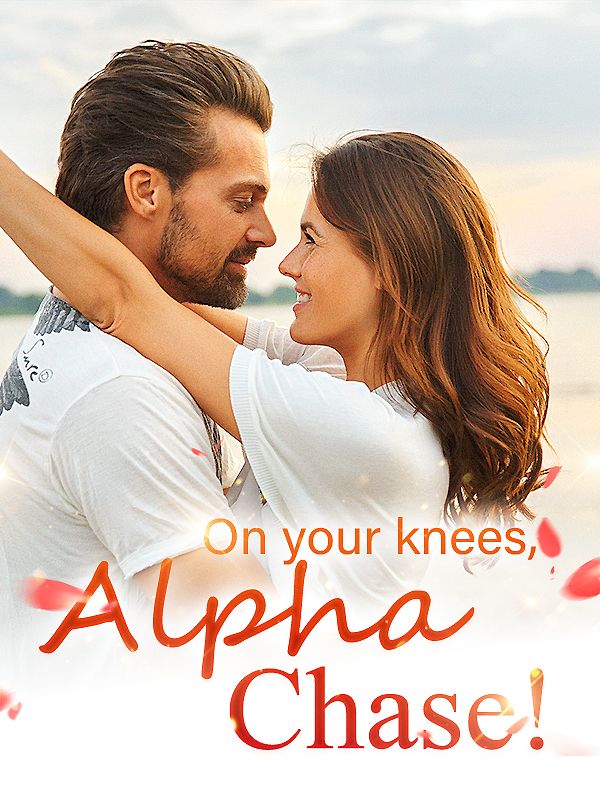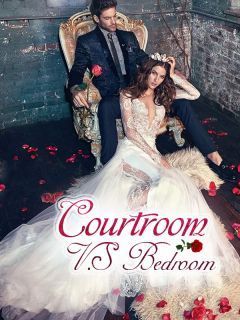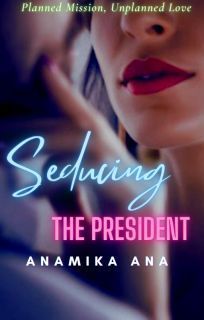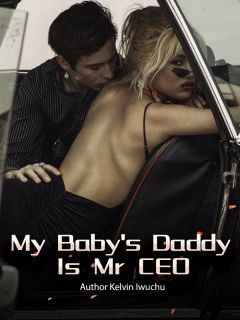紹介
目次
紹介
大統領である彼女が、自分よりも年下の男の子を追いかけるとは、どんな気持ちだったのだろうか?
彼女は彼に豪邸を送ったが、彼はそれを気に入らなかった。
彼女は彼に高級車を送ったが、彼はそれを必要としなかった。
彼女はドローンを使って愛を告白しようとしたが、彼は彼女がお金を使いすぎていると思った。
成功したビジネスウーマンが、そっけなくシャイな美少年をどのようにして手に入れたのか、一歩ずつ見てみましょう。
もっと読む
すべての章
目次
Chapter 1: 成功したビジネスウーマンの気前の良さ
Chapter 2: プロポーズ
Chapter 3: 「物乞い」から王子様へ
Chapter 4: 私にちょっかい出してるの?
Chapter 5: あなたはもう私のもの
Chapter 6: 猫とネズミの駆け引き
Chapter 7: 彼が私の好きな人
Chapter 8: 一歩ずつ
Chapter 9: シルビアの家探し
Chapter 10: 恋人のフリ
Chapter 11: ママの協力
Chapter 12: 結婚許可証を手に入れた
Chapter 13: 元彼氏の突然の登場
Chapter 14: 私と赤ちゃんが欲しいんじゃないの?
Chapter 15: 元彼氏の執拗な嫌がらせ
Chapter 16: 忠実な若い夫
Chapter 17: なんて大きな誤解
Chapter 18: 小さなオオカミ犬が嫉妬した
Chapter 19: 邪悪なオオカミ犬
Chapter 20: 私の夫は最高だった
第21章:ワインテイスティングコンペ
第22章:私の男は私次第
第23章:悪意のある宴会
第24章:私の男を盗もうと?
第25章:素晴らしい夜
第26章:夫のために「裏口を開けた」
第27章:強さから語る
第28章:小さなトリックに手を出すな
第29章:嫉妬からの罰
第30章:デートのあらゆる瞬間を掴む
第31章:インターンの陰謀
第32章:彼に教訓を
第33章:私の情熱的な小さな狼犬
第34章:全体的な手配を開始
第35章:私の愛する人
第36章:許すタイプではない
第37章:元彼が台無しにする
第38章:私の男は私を誤解した
第39章:私たちは口をきいていなかった
第40章:エリアスが消えた
第41章:彼はどうしてそんなに冷酷になれたのか?
第42章:ハニートラップは成功した
第43章:彼を忘れる決意
第44章:子供が生まれた
第45章:成功したビジネスウーマンはシングルマザーになった
第46章:エリアス・シルバが帰ってきた
第47章:男は私にとって足かせにしかならない
第48章:私の名前で呼ばないで
第49章:エリアスとの夕食会
第50章:恋のライバル
第51章:また私と一緒になりたいの?
第52章:妻を取り戻すのは難しい
第53章:遅ればせながらの愛情
第54章:ここから出て行け
第55章:私の子供は私ではなく見知らぬ人を助けた
第56章:嫉妬の嵐
第57章:エリアスは哀れな顔をした
第58章:あなたのことが心配です
第59章:彼は神のように現れた
第60章:皮肉にまみれて