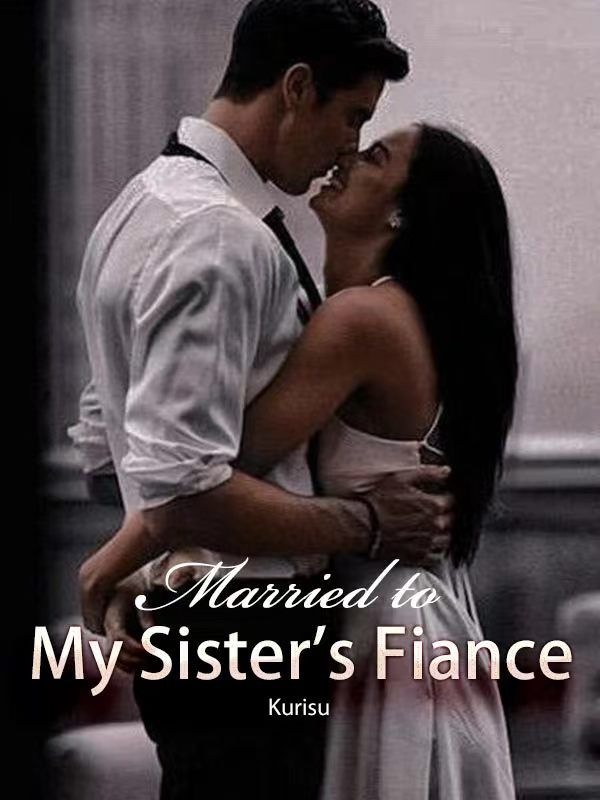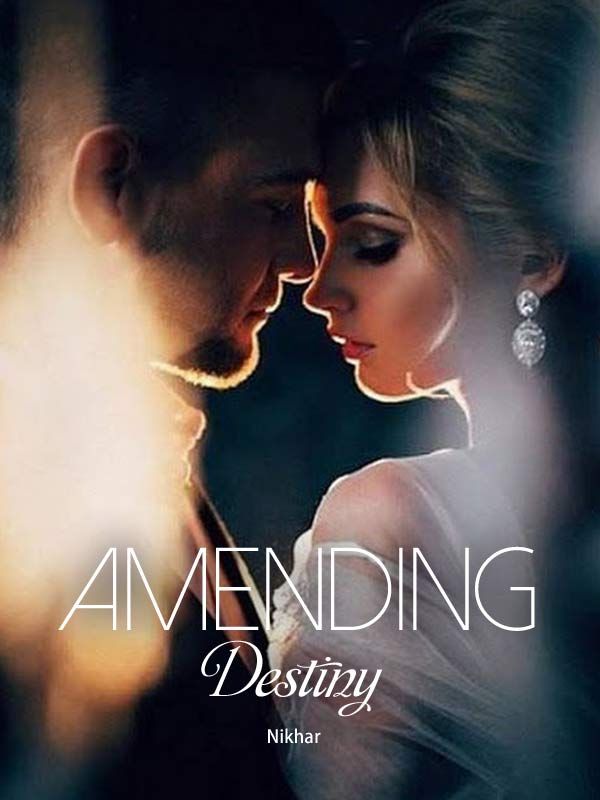## ウェッジ
胸が苦しい…熱い…頭がクラクラする…もう無理…窒息しそう… アイ・ルオは後ろ手に縛られた両手がすでに感覚を失い、涙もすっかり乾いていた。まだ少女の彼女は、初めて死の恐怖を感じていたが、同時に、誰かが早く自分の命を終わらせてくれることを願っていた。死を待つのはあまりにも辛いからだ。9歳のアイ・ルオは、黒いスーツケースの中に10時間以上も閉じ込められていた。電車に乗せられ、座席の下に押し込まれたのがわかる。人々が彼女の横を通り過ぎ、周囲には笑い声と食べ物の匂いが漂っている…しかし、300人以上の人間が同じ車両にいるのに、彼女が誘拐されたことに気づく者はいない。誰も彼女を見つけない。最初は、スーツケースの揺れで何か気づいてくれるかもしれないと、必死に体を揺らした。何かおかしいと気づいた人もいたが、彼女を誘拐した女は「ただの犬よ」という言葉で簡単に誤魔化した。すべてが無駄だった。今、彼女には抵抗する力も残っていない。もしかしたら、このままスーツケースの中で死んでしまうのかもしれない… アイ・ルオは無力に目を閉じた。薄い空気と狭い空間の圧迫が彼女を打ちのめし、体の機能は死の淵で苦しんでいた。彼女が呼吸を続けることを支えているのは、ただ強い生存への願望だけだった。夜が更け、静かな車内には、いびきと電車の音だけが響き渡る。車輪の回転する音は、まるで死の足音のようだ。意識が朦朧とし始めたアイ・ルオは、眠ってゆっくりと休みたいと思っていた…まさにアイ・ルオが限界に達しようとしたその時、電車は小さな駅に停車した。ブレーキの慣性で、彼女の顔はスーツケースの中の金属製のタイロッドにぶつかり、その痛みで再び目が覚めた。ショートカットの女は車内を見回し、ほとんどの人が眠っているのを確認すると、アイ・ルオが入った箱を慎重に取り出し、急いで電車を降りた。駅の外の薄暗い路地裏で、女はスーツケースを開け、縛られた少女がまだ息をしているか確認した。新鮮な空気が流れ込み、10時間以上も濁った空気に耐えてきたアイ・ルオは、元気を取り戻し、大きな鼻孔から純粋な酸素を貪欲に吸い込んだ。「生きててよかった、今回は儲かったわ」まだ元気そうな彼女を見て、ショートカットの女は安堵のため息をつき、再びスーツケースを閉めた。「また閉じ込めたら、本当に死んじゃうよ!」暗い隅から、レンガの壁に寄りかかってタバコを吸う若い男が「親切に」忠告した。ショートカットの女は、声を発した金髪の男を警戒して見つめた。少しの間葛藤した後、彼女はついに手に入れた「獲物」を諦め、逃げることを選んだ。人身売買には慣れており、今回の失敗は気にならないが、見知らぬ場所で捕まれば大変なことになる。彼女にとって最も重要なのは、自分の安全を守ることだ。「チッ、臆病者め」
金髪の男は角から現れ、月光が彼を照らし、彼の白い肌に神々しい輝きを与え、白い背景に金の縁取りのスーツは彼を神のように見せた。しかし、彼の外見の神聖さは、単なる隠れ蓑かもしれない。彼の深紅の目は、月光の中で2つのルビーのように輝き、彼の優しい顔とは全く異なる、獰猛な光を放っている。ゆっくりとスーツケースの前に歩いていくと、若い男はまるで薄い紙を破るように簡単にスーツケースを引き裂き、アイ・ルオの縛りを解き、彼女を抱きかかえ、先ほどの誘拐犯を追いかけた…男の腕の中で意識が徐々に鮮明になったアイ・ルオは、まず彼の口元の血の色、自分のドレスについた血、そして遠くで倒れ、すでに干からびた死体となった誘拐犯を見た。アイ・ルオが目を覚ましたのを見て、青年は彼女に微笑んだ。「怖い?」
怖い?彼の牙と唇についた血のこと? アイ・ルオは優しく首を横に振り、男の口元の血を拭いてあげた。スーツケースに閉じ込められた時の無力感や絶望感に比べれば、この赤は何だというのだろう。「俺は吸血鬼だけど、怖くないのか?」男は驚いたように尋ね方を変えた。アイ・ルオはまだ首を横に振った。吸血鬼って何?幼い彼女には分からなかった。ただ、目の前の青年が自分を助けてくれたことだけを知っている、それだけだ。男は優しく微笑んだ。彼がアイ・ルオを見る目は、獲物を見るようなものだったが、今は父親が子供を甘やかすようなものになっている。「面白い子だ、まあいい、今日はもう満腹だ」金髪の青年はアイ・ルオをそっと地面に寝かせ、振り返って路地の奥へと消えていった。「賢くして、また捕まらないように」
路地の反対側からは、男の心配そうな声が聞こえた。アイ・ルオは心が温まり、深く頷いた。吸血鬼?彼女は恩人の名前を思い出した。ゴーストメイク、邪悪な笑顔、低く気だるい声、レースだらけの黒いドレス…テレビのトーク番組で、自らを有名な「ダーク小説家」と称するゴシック系の少女が、司会者との質疑応答形式で話している。司会者は口を開き、尋ねた。「…アイ・ルオさん、なぜあなたの小説を「ダーク」と呼ぶのですか?私の意見では、あなたの小説は、一般的に言うところの「怪談」や「ホラー文学」と大差ないと思いますが。」
ルオ・チーは、中国の一流女性司会者として、常に知的な女性の代表であった。彼女のメイクは繊細で甘く、魅力的な笑顔を浮かべているが、少女の目には完全な不寛容と軽蔑が込められている。しかし、彼女はまだ成長途中の少女で、いくつかの退屈な吸血鬼小説を書いて、わけもなく全国的に人気を集めている。これは、芸能界で10年以上も活躍しているルオ・チーをいくらか納得させないものであり、番組の雰囲気はいくらか硬直し、火薬庫のようになっていた。番組の最初から相手が示した敵意を察知したアイ・ルオは、大きな目で優しく瞬きし、わざと素朴で賢く見えるように装い、真剣に答えた。「ホラー小説や怪談は、通常、血なまぐさく、主な表現は、人々を恐怖させ、恐怖によってもたらされる快楽を利用して売ることです。私のオリジナル小説「ダークファミリー」は、明らかにそれとは異なります。私の小説の主人公のほとんどは、吸血鬼、人狼、ゴブリン、モンスターなどです。人間は昼行性の動物であり、これらのキャラクターは夜の生き物であり、人間は光を、彼らは闇を象徴しています。「ダーク・ディビジョン」は主に、闇の生き物の生活と、彼らと人間の間の愛憎の絡み合いを描いています。人間から抑圧されていても、彼らはまだ必死に太陽と希望を求め、人間との平和を維持し、自分たちの種族を発展させようと努力しています。これらの葛藤と対比は非常に感動的です…」
アイ・ルオの長話に、ルオ・チーの表情は明らかに苛立ち、彼女は目を回し、その口調は甘く柔らかいまま、彼女の言葉を遮った。「しかし、それらのキャラクターはフィクションであり、それは怪談と全く同じです。フィクションのモンスターで読者を感動させる。あなたの高い販売部数は長く続かないのではないかと心配です…」
自分の失語症に気づいたかのように、ルオ・チーはすぐに口調を変え、心配しているふりをして続けた。「先輩として、同じ分野ではありませんが、あなたの将来の発展にはとても関心があります。ご存知のように、人々は新しいものを好み、古いものを嫌います。あなたのような良い子が、最初はあまりにも鋭敏であるために、一部の人々によって追い出されるのではないかと心配しています。あなたは、次にどのように名声を維持するか考えたことがありますか?」
「考えていません。私はまだ新人なので、何も知りません」アイ・ルオは不本意そうな顔で答えた。ルオ・チーは、気づかれにくい嘲笑を見せた。「中国の有名な芸術家の傑作と、中国文化の幅広い精神を参照することをお勧めします。吸血鬼が人気がなくなったら、中国文学を研究し、やり直すこともできます。」
「私は一生「ダーク」小説を書きます。誰も賛成しなくても、私はそれを貫きます」アイ・ルオの忍耐力はほとんど尽きたようで、顔色が変わり、ささやいた。「しかし、純粋な文学作品を創造したいなら、このファンタジーテーマは間違いなく時代遅れです…」
「もうたくさんだ!」アイ・ルオは低い声で叫び、鋭い矢のように司会者のルオ・チーの顔を睨みつけた。「ファンタジーテーマは汚いことと同等なのか?!西遊記、封神演義、山海経の文学的価値を、そんな言葉で否定するのか?!」
少女が突然顔色を変えるとは思ってもみなかった。ルオ・チーの眉はひねくれ、彼女は焦った。「私はそれらの古典作品の価値を否定していません!それに、あなたの作品を西遊記と比較することなどできません…」
彼女が自分の作品を軽蔑した口調で「あんなもの」と呼ぶのを聞いて、アイ・ルオはついに我慢できなくなった。彼女は番組グループが用意した質疑応答カードを手に取り、カメラの前に歩み寄り、カードをカメラの前に突き出し、怒鳴った。「このカードには、司会者のルオ・チーが尋ねるべき質問と、私が答えるべき答えが書かれています!今、あなたが見ているように、この女は、質疑応答カードの質問に従って質問するのではなく、皮肉な言葉で私を挑発しました!」
そう言って、アイ・ルオは質疑応答カードを取り除き、カメラに映し出されたのは、彼女の困惑した涙、目がかすんだメイク、そして非常に怒った顔だった。「あなたは私の作品を軽蔑しています!しかし、私は血族をフィクションのキャラクターに分類するやつを許すことはできません!ここで、テレビの前の血族に現れるようお願いします!私は自分の血をあなたの夕食として提供し、高貴な血族にこの世界から私を連れ去ってくれるようお願いするだけです!一体全体、この番組は何なんだ!もう収録しない!私は、あなたのような偽善的な人間にはもう我慢できません!私は自分の命を使って、血族の真実を証明するつもりです!
「私の住所はBTAストリート月光アリュールコミュニティ、X棟1403号室です!首を洗って、あなたを待っています…」
「こいつ、キチガイだ、CMに飛ばせ!」
誰が叫んだのか分からないけど、カメラが何度か揺れて暗転した。数秒後、テレビ画面には粉ミルクのCMが映し出された。