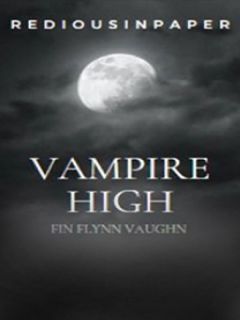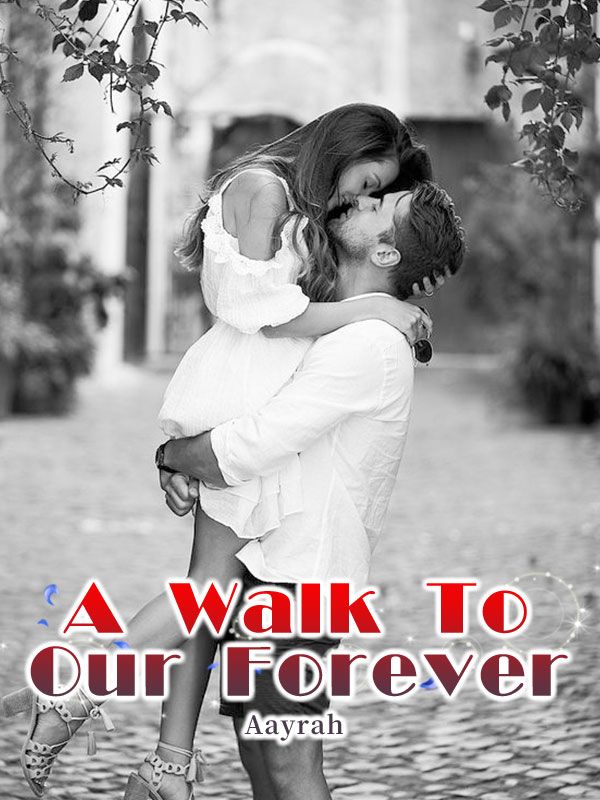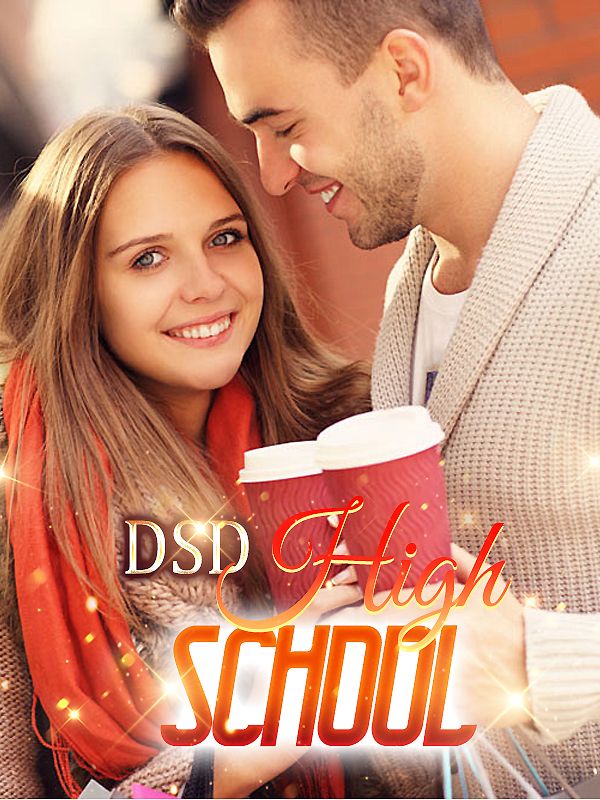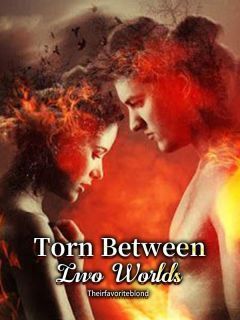紹介
目次
紹介
"レクシー、やめて!"
女性は苦々しく目を拭った。彼女は建物から出て、入り口近くの自分の車に向かって歩く。
車のドアを開けると、彼女は建物から大股で出てきた男の叫びを無視した。
"レクシー!" 男は苛立ちながら髪の毛をつかんで叫んだ。
"ブレット..." 小さな声が色っぽく呼びかけた。
ブレットは振り返り、目の前の女性を怒りと嫌悪感で見た。彼の冷たい目は大きく見開かれ、唇は嫌悪感で逆さまに曲がっていた。彼は女性を殺意を込めた目で見た。彼の目は一瞬赤く光り、歯ぎしりをして頭をそらした。彼女以外ならどこでも見ていた。
彼は爆発しないように、拳を握ったり開いたりして、自分を落ち着かせようとした。
しばらくして、彼は「出て行け」と言い、ナイトホテルの入り口で凍りついている女性を振り返ることなく、赤いアウディ車に向かって歩いた。
アヴィラはブレットの車が視界から消えるのを見て歯ぎしりした。しかし、先ほどレクシーが彼らを見たときの反応を思い出し、彼女の顔には不吉な笑みが浮かんだ。
"ブレットは私のもの。ゴミはゴミでしかないわ" 彼女の目は邪悪になり、暗い空を見つめた。
もっと読む
すべての章
目次
Chapter 1: レクシー
Chapter 2: なぜ?
Chapter 3: ソフィア
Chapter 4: バン!
Chapter 5: 誰がいる?
Chapter 6: お願い
Chapter 7: ごめんなさい
Chapter 8: 毒
Chapter 9: 解毒剤
Chapter 10: ブラックリバーギャング
Chapter 10: バスタードチャイルド
Chapter 11: 妊娠
Chapter 13: ウォッカ
Chapter 14: 私のものですよね?
Chapter 15: 結婚したい
Chapter 16: 無駄!
Chapter 17: ママ
Chapter 18: 彼は返事しない?
Chapter 19: ファーザーレス
Chapter 20: 冷酷
第21章:これ、もらってもいい?
第22章:動かないで!
第23章:すごく怖い!
第24章:騒がしい
第25章:彼は当然だ
第26章:妻
第27章:中国
第28章:罰
第29章:パリ
第30章:ロシア
第31章:ニュージーランド
第32章:フィナーレ