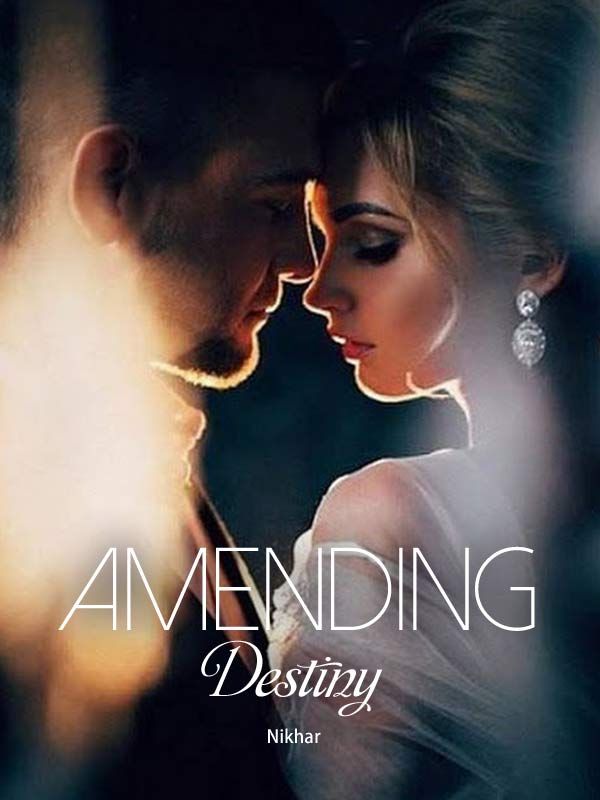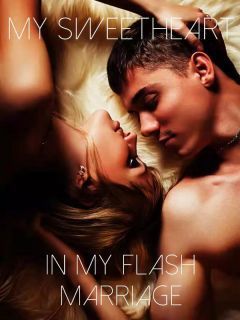免責事項:物語に登場する名前、場所、人物は、生きている人や死んでいる人とは一切関係ありません。これは完全にフィクションです。
______________________________________________
ハイヒールのカチカチという音は、この街、この時代では珍しいものではなかった。
入り口で屈強な男たちが手の甲に押す赤いスタンプの濡れたキスは、気分を良くすることだけが唯一の選択肢である狭い通路への、苦労して得たパスだった。
吸い込む。
中からの音楽の柔らかい音が聞こえてきた。
吐き出す。
視線を前に向け、彼女の長く黒く磨かれた爪がクラブの両開きのドアを押した。コールで裏打ちされたチョコレート色の眼窩が、意図を持って部屋をスキャンした。彼女の神経は振動し、端でつながっていたが、彼女はなぜこのような場所に来たのか、その理由にしがみついていた…再び。
彼女は、このような種類の場所に足を踏み入れることは決して繰り返さないと誓ったが、人生で二度目にクラブに立っていた。まるでバーに入った最初の時のような、うるさく、あらゆる種類のアルコールの匂いがし、もだえ苦しむ体。唯一の違いは、その日彼女の世界が崩壊したことだった。
彼女のじっとりした手は、着るのにすべての勇気が必要だった小さなドレスを滑らかにした。彼女の服はとても黒く、光が全く跳ね返らなかった。それは彼女の体を最も親密な方法で抱きしめ、さらにネックラインが非常に低く落ち込んでおり、彼女の胴体全体を露出しそうになり、スカートの裾は彼女のお尻のすぐ下にあった。彼女は裸で無防備だと感じたが、これを選んだので、やり遂げる。
黒く、まっすぐな、絹のような髪が、彼女の青白い脚がクラブの奥へと進むにつれて揺れた。
彼女はもう一度そのエリアをスキャンした。部屋は、中にいるすべての人を誘うように見える、踊るストロボライトで薄暗かった。ずっと薄着を着た人々が彼女を通り過ぎた—彼らは笑うか、大きな音楽のビートに合わせて飛び跳ねたが、全体的に楽しさの典型であった。真ん中のもの—彼女が推測したステージ—は、アップビートな曲に合わせて動く、脈打つ体でいっぱいだった。
点滅する光の攻撃から身を守るために手を使った彼女は、探している人を見つけようと試み、幸運にも彼女の目は彼に着地した。
彼女が殺すことになっていた人。
彼女は彼に向かって歩き、その間ずっと自分の考えと戦った。彼は悪い男で、彼を排除することで世界を少し助けているけど、もし彼に子供たちがいたら—家族がいたら?
彼は、娘の手を握っている父親を無表情に頭に撃ったとき、それを考えなかった。
そうしたら、あなたも彼と変わらないことになるのでは?
多分そうだけど、これは報復であり、同時に金でもある。一石二鳥—というより弾丸。
彼女の目は、標的のすぐ近くに立って、何気なく行動している男の一人の腰に巻き付けられた銃に引き寄せられた。別の男は、Uziを露骨に自慢している。
彼女は、その男が彼女に作戦を中止するようにかすかに促すほど、自分を納得させるためにその男がした嫌なことを考えた。
「今、怖気づかないで、ヤングブラッド。」彼女のコムの声がヒューヒュー言った。
彼女はそれを確実に保つために、小さなイヤホンを軽く耳に押し込んだ。今夜は誰も怖気づかない、サー。
彼女は、お尻に取り付く魔法の手を引っ張り出し、酔って彼女ににやりと笑うだけの大学生をにらんだ。
何もせず、ペーパーワークをし、動かない物体で射撃と訓練をすることだけで過ごした2年間が、ついに報われた。彼女は最初のフィールドワークを手に入れた。
ゲームフェイスを決めろ、タリア!
神様、私が殺そうとしているのは悪いやつで、殺されないようにしてください。
彼女が彼らを通り過ぎると、女性たちの笑い声が耳に響き渡り、飛び跳ねて回転する体の塊。
彼女は、立ってセックスをしようとしているカップルの周りをスケートした。
「ポジションについた。あなたのことをやって、ヤングブラッド。」彼女のイヤホンから声が聞こえた。「覚えておいて、撃って去れ。」
彼女はそれらが見えることを知っていたのでうなずいた。了解。
タリアは、彼女から数フィート離れて座り、頭の髪と同じくらいカールした胸毛が明らかになる3つ以上のボタンを外した白い長袖ポロシャツを着た黒い肌の男をじっと見つめていた。彼は両腕にビキニボトムしか着ていない女の子を抱いていて、明日がないかのように笑っていた—非常に明らかに酔っていて、他の何かにも酔っていた。彼女が飲み物を取ろうと手を動かすと、彼女の指のそれぞれに巻き付いている厚く、ダイヤモンドをまぶした金の指輪に光が跳ね返った。
彼の視線が彼女にロックされるのに時間はかからなかった。その男の濃い茶色の目は、彼女に彼に歩み寄るように手招きした。
彼女が彼の注意を完全に引いたと確信して、彼女は笑顔を描いた。
「かわいらしい笑顔、タリアは犬のような笑顔ではない。」別の声が彼女のコムで聞こえた。
彼女は彼に近づき、彼の耳に身をかがめた—彼女の黒いレースの下着と胸をあまり見せすぎないように注意しながら。「あなたを見ていたの。」彼女は音楽の轟音にもかかわらず、聞こえるように言った。
「もし君を早く見ていたら僕もそうしただろう、チキータ。」彼はささやき返し、メキシコなまりが明らかになり、彼の口ひげが彼女の頬をくすぐった。彼は一緒にいた女の子たちを解雇し、彼女を彼の膝に引っ張った。「それで。」彼は下唇を噛み、ためらうことなく、彼女の胸に触れた。
彼女は顔をしかめるのを抑えた。「知っているわ。」彼女は彼の髪をいじりながら言った。「私のホテルに行って話すこともできるわよ。」彼女は完璧な白い歯に舌を通した。
彼は笑顔を返した。「できないんだ、ベイビー、僕はクラブを経営しなきゃいけないんだ。」彼は、自分が何について話しているのかを彼女に示すかのように、手を振った。「でも、僕のオフィスに行ってビジネスをすることもできるよ。」と彼は提案し、彼女の胸を撫で続けた。
豚!彼女は彼の手を叩きのけ、大声で叫び声を上げ、または彼の髪を引っ張るために戦った。
彼女は、そのペットネームを聞いた後、逃げ出そうとする震えを抑えた。「そうすることもできるわ。」彼女は微笑んで彼から降りた。彼も立ち、彼女を彼のオフィスに案内し、座っていた黒い革のソファーのすぐ後ろから、赤いベルベットのロープが吊り下げられた小さなポールの両側にいる2人の大柄な用心棒に守られていた。
「彼がドアを閉めたらすぐに、YB。」
はい、サー。
彼女は、彼がオフィスに入ったらすぐに取り出して準備が整っていることを確認するために、サイレンサーが装着された小さな銃を黒い財布の中に忍ばせた。私はこれを持っていた。
彼女のむずむずする、倒錯的な指を持つ巻き毛の男が後ろでドアを閉めると、サバイバルナイフがどこからともなく現れ、彼の頭蓋骨を貫いた。男が床に倒れ死ぬ前に、血が傷から流れ出す機会さえなかった。永久的なショックと恐怖が彼の顔に刻まれていた。
彼女は一歩後退し、驚きと恐怖の表情が彼女の顔を傷つけた。タリアは、彼女が自分で殺そうと計画していた死んだ男の無気力な視線に目が固定されたように見えたので、彼女の喉から逃げ出そうとする叫びを抑えた。
映画で死体を見るのと、実際に会うのでは、全く違うシナリオだった。
ああ、やばい。吐きそう。
「ジェシー、あなたが彼を倒したの?」タリアは床を占めている血を避けて後退しながら尋ねた。
彼女が返事を受け取らなかったとき、彼女は仲間を見つけるために周りを見回した。誰もいない。
「サー?」彼女は再び呼んだ。
タリアはパニックになり始めた。彼らは彼女を置いて行ったの?クソ!
彼女の不規則な考えは、彼女のすでに激しく鼓動する心拍数を3倍にした首の後ろの息吹を感じたときに止まった。
「ロドリゴ・ペレス」その声はうなり声をあげ、非常に深く、彼女の膝を折って、ほとんど降参させた。
いや、ありえない。こんなことはありえない。「ここで何をしているの?」彼女はかろうじて聞こえる声で尋ねた。彼女はあえて動かなかった。