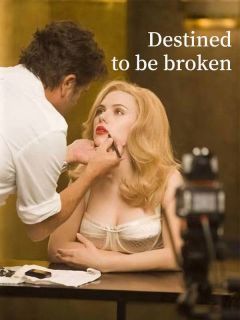ジェイドの視点。
燃えてた。あいつの触れ方が私にしたことを表現できるのは、それしかなかった。
手に水をためて、まるで冷たい水の痛みが私の血を燃え上がらせる火を消してくれるかのように、顔にぶっかけた。
あいつの匂いが私にまとわりついて、今まで以上に必要で、ムラムラする気分にさせた。あいつの触れ方は天国だったし、自分がどれだけ飢えていたか、どれだけそれを求めていたか、その瞬間まで気づかなかった。まだあいつの筋肉が私に押し付けられていた感触、あいつの興奮の匂い、そしてあいつが私を強く抱きしめたときに私のシステムを駆け巡った快感物質が、私の胸の中の空虚さをまだ満たしていた。
あいつの声はマジで神々しくて、安心させてくれる。何度も何度も聞きたかったし、あいつの手が私の喉に触れるのを感じたかったし、あいつが頭の中で考えているすべての汚いことを私にしてほしかった。全部めちゃくちゃクレイジーだった。
「しっかりしろよ」と私は鋭く言い放ち、自分の頬を強く叩いた。私は怒っていた。それが私が関連付けられる唯一の感情だった。すべてが起こった後、そして時間が過ぎた後では。あいつは二度と顔を出すべきじゃなかった。私を解放した後では。
私は、自分が運命を共にする男と出会った後、鏡に映る自分を見つめているまで、それに怒っていることに気づかなかった。
アストラは、ジェイドを見つけたら二度と離さないだろうと言っていたのに、あいつは私を戦うことさえせずに手放した。あいつは私の後を追ってこなかったし、私を離さないと誓ったにもかかわらず、私に手を伸ばしてこなかった。全部ウソだったんだ。
私が去ってから一週間後、そして私が完全に奴をシャットアウトする前に、私はあいつが私を迎えに来るだろうと予期していた。でも、あいつがそうしなかったとき、まるで今まで私に言っていたことは、今まで捕らえていたすべての人に吐いていた単なる嘘の束だったかのように、自分が望まれていないように感じた。そしてそれは痛かった。思った以上に。私が奴を拒否したのに、拒絶されたのは私の方だったような気がした。
いつも通りだった。見られず、望まれず、そして私はそれを受け入れていた。ただ、あいつが戻ってきて、今出てきたことが、私が慎重に築き上げてきたすべてを台無しにしようとしている。
顔を拭い、深く息を吸った。あいつが私の人生にのんびり戻ってきて、今回私を自分のものにすると主張するのは簡単じゃないだろう。私はそれを許すつもりはない。あいつは私のマスターじゃない。私たちの関係は終わったんだ。私はもうエトラにはいないし、あいつに私のテリトリーを侵略する権利はない。
私は、もしあいつが私の前に現れたら殺すと脅し、奴がまだ私の捕虜であった間、エトラを焼き払うことさえ誓っていた。しかし、私はそれらのどれも実行していなかった。すべて、あいつが言ったように、私が臆病者みたいに逃げ出したからだ。
そろそろ逃げるのをやめて、正面からあいつと向き合い、奴を破壊する前に奴から必要なものをすべて奪う時かもしれない。
鏡に向かってニヤリと笑い、胸の中で心臓が激しく鼓動し、初めてマジで生きていると感じた。
私は今もっと強くなった。だから、もし私がただ服従して、あいつのやりたいことをすべてやらせると思っていたら、ディアリルはまた何か違うことをやってくるだろう。
あいつは私に挑戦することに決め、私があいつのメイトだと主張したにもかかわらず、私のライバル側に立つことにした。代わりに私を選んだのではないのか?でも、また、私が私を選ぶ必要はなかった。
その考えに私の心は痛みでよろめき、私は疲れ切ったため息をついた。すべては変化のせいだった。あいつを求めて走りたいのか、それともあいつを遠ざけたいのか、たとえあいつを嫌っていたとしても、決めることができなかった。
それでも、私の中の何かがあいつを必要とし、求め、あいつの触れを感じたい、そして奴を破壊すると誓っているにもかかわらず、すべて私が彼のもとに行き、あいつに自分の匂いを私中に注ぎ込んで、頭の中のもやと心の中の痛みが、少し前まであいつの腕の中にいたときのように和らぐのを感じてほしかった。
「もうたくさん!」私は叫んだ。「誰も必要ない。自分でできる…ジェイドはディアリル・ヴォーン・ライアルを必要としない」私は鏡に映る自分に向かって叫び、心臓は肋骨に激しく打ちつけた。
鏡から離れ、私はバスルームを出て行った。怒りと性欲はまだ私の中でくすぶっていた。
何かを粉々にしたかった。特にディアリルが現れて私をめちゃくちゃにしたことに対して。シモーヌとフランコはすぐに私のそばにいたが、まるで存在しないかのようだった。
「大丈夫か、ドン?」シモーヌが尋ね、私は立ち止まり、彼の方を向いた。
「いいえ、大丈夫じゃないわ。あいつはあの男たちの前で私を屈辱させた。私はそれを見過ごすつもりはないわ。あいつは自分のやったことの罰を受けるべきだわ」
「命令するだけでいいんだ、ドン。そしたら死体袋に入れるよ」
「ダメ」私は言い放った。「ディアリル・ヴォーンは自分で始末する。これは個人的な問題だけど、お前らにも役割がある。エドワード・ジョーンズと一緒にいた男たちを全員殺したい」
二人はうなずいた。「アレスについてはどうする?救出作戦を計画するのか」
私はそれを考えたけど、ディアリルはアレスを取り戻すことが私にとって重要であることを知っているので、アレスを監視して、極めて厳重に警護するだろうとわかっていた。
「私がやるわ」私はそう言って、個室から出て行った。
カジノはまだ人でいっぱいだった。出口に向かって歩いていると、ディアリルの匂いがして、壁際に立って飲み物を手に持ち、私を見つめているのが見えた。
私たちの間に距離があったにもかかわらず、彼の視線から熱を感じた。彼がグラスを口に上げて一口飲むのを見て、私は手を握りしめた。あいつの目は常に私に釘付けになっていた。飲み物を飲み込み、喉が動き、唇は液体で濡れて赤かった。
女性が通り過ぎようとして私にぶつかった。私はディアリルしか見えなかったから、彼女の謝罪の声は聞こえなかった。
彼の視線がに長くとどまるほど、私はマジで燃えた。私の中のすべてがあいつに引き寄せられている。私は彼の方向に二歩進み、そして止まり、代わりに建物を後にした。
私の要塞に戻る道は、ナイフで切り裂けそうなほどの緊張感で満たされていた。
着くと、私は車から出て、彼らに何かあっても邪魔しないでくれと命令した。
リビングルームに入ると、レクシスが私に挨拶するために立ち上がり、顔にしかめっ面をしていることに私は立ち止まった。
彼女を見て、ヘイデンのことを思い出し、それが私の気分をさらに悪くした。
「ヘイデンを傷つけた」レクシスは私にゆっくりと近づきながら言った。「彼がいつもやっていたことは、ジェイドを喜ばせようとしていたことだけなのに、どうしてあんなことしなきゃいけないの」
「あなたの質問に答える必要はないわ。あなたが許可なく私が置いた家を出た…」
「ふざけるな!お前はルールを作っても、自分では守らない。お前はヘイデンのマスターなのに、あいつがどれだけの痛みを受けたら十分になるのか知らない。医者は彼が永久的な傷を負うって言ってたけど、お前は気にしないんでしょ?だって、お前はマジのモンスターなんだから」彼女は叫び、涙が頬を伝った。
私は彼女を見つめた。彼女が私を呼んだ言葉は、核心を突いていた。「家に帰りなさい」私はそう言って、彼女を通り過ぎた。
「彼を解放して!」彼女は叫んだ。「彼がジェイドを諦めることはないわ。ジェイドが彼を解放しない限り。彼はジェイドがどう思っているか知ってるから、ジェイドの世界のように彼を見ている人がいることだけを求めて、ジェイドは彼に固執してきたの」
「何を言っているのかわからない」私は怒鳴り、レクシスの方を向いた。私が間違っている可能性があることに非常に怒っていたので、彼女の頭を壁に叩きつけたいほどだった。
「本当?なら、なぜ、彼を求めていないなら、彼を解放しないの?ジェイドは彼がジェイドを愛していることを知っているのに、少しの愛情をジェイドに示して、彼がジェイドに対して何かを感じているかもしれないという希望を持たせて、甘やかす。でも、ジェイドと私は、それが決して実現しないことを知っているわ。だって、ジェイドは愛という言葉に対する心を持ってないんだから。ヘイデンをきっぱりと解放してあげて。私は彼を愛しているし、彼が傷つくのを見るに耐えられないわ」彼女は告白し、私は不意を突かれた。
私たちは沈黙の中で立っていた。私はヘイデンを傷つけたし、彼女が言ったように、私はヘイデンのふさわしい方法で彼を愛することができない、彼女はまた、私は彼をぶら下げたままにして、私が彼に少し愛情を示したときを待って、それによって彼に私が彼に何かを感じているかもしれないという希望を与えた、しかしヘイデンを断ち切ることは恐ろしかった。彼は私にどれほど夢中になっているのかを恐れずに示した唯一の人だった。もし私がそうするように言ったら、彼は私のためなら死ぬだろうと私は知っていた。彼にとっては不公平だった。私はマジで自己中心的で、過去にはそれが気にならなかったとしても、今は気になった。ヘイデンはあんな風に扱われるに値しない。
「わかった。じゃあ、彼を解放するわ」
レクシスはまばたきし、私の口から出た言葉を信じられないようだった。
「え?」
「彼に、彼は自由で、何でも好きなことができるって言ってあげて。私はもう彼を楽しませるつもりはない」私はそう言って、部屋に行こうとした。これまで以上に疲れを感じた。
「本当にそう思っているなら、自分の言葉で言ってあげないと」彼女は私に呼びかけた。「私から聞いても、彼には意味がないから、自分が言ってあげないといけないわ」
私は彼女の方を向いた。「なんで私が彼のもとに行かなきゃいけないの?」
「だって、ジェイドはヘイデンをめちゃくちゃに叩いたから、歩くことさえできないんでしょ。ジェイドは彼の愛人として彼を世話するべきなのに、そういう愛人じゃないんでしょ?ジェイドは自分の快楽のことしか考えてない」
「十分よ。あなたは出て行っていいわ。私が行って、すべてを終わらせるわ」私はそう言って部屋を出た。レクシスの視線が私の背中に感じられ、彼女の憎しみも感じられ、そして恐怖、不安、そして彼女が何か悪いことを計画していると私に語る不吉な闇も感じられた。
私は彼女の方を向いた。彼女の顔の怒りの表情は、私が彼女に追いつくほど早く消えなかった。
関係なかった。彼女が計画したことは、私が1マイル先からキャッチできないものは何もなかった。