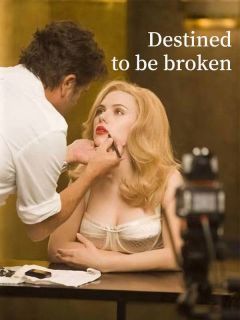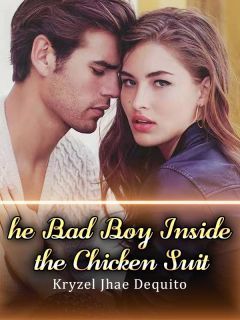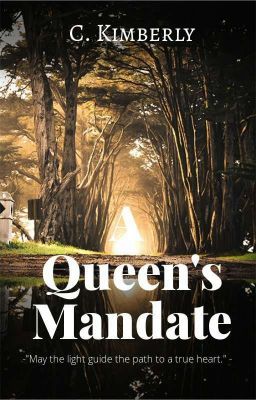叫び声が聞こえる空の下で、彼女は固まって、何が起こったのか理解しようとしていた。 百回目くらいになるだろうか、彼に対してまつげをバタバタさせて、現実じゃないみたい、頭がおかしくなってるのかもって思った。 彼は咳払いをして、彼女に眉をひそめ、中に入るように合図してきた。 説明できないような恐怖が彼女の心を支配し始めた。 彼の暗い瞳は悪意に満ちて輝いていた。 彼女は右側の細い道を見て、すぐにどうするか考えた。
大きく息を吸い込み、喉の奥で大きな塊を飲み込み、彼女は覚悟して走り出した。
車のドアがいくつも開く音が聞こえて、彼女の血管にパニックが走った。
彼女はまるで自分の命がかかっているかのように走り出し、木にぶつかり、いつも顔を引っかいていた。
**サーシャ**はキラーヒールを蹴り飛ばして路地に入ったけど、砂利の鋭い石に足を踏み入れてしまった。 石の角が彼女の足を切りつけ、彼女の息は喉に詰まった。 白い塊が視界を覆い、彼女はめまいを感じた。 彼女は意識を取り戻そうと最善を尽くした。
彼女は背後をちらりと見て、4人の影のある男が彼女の足跡を追っているのを見た。 彼らは走っていた。速かった。
彼女は角に追い込まれ、ゴミ箱の後ろに隠れた。 猫と嘔吐物の匂いが彼女の鼻孔を突き刺し、彼女はすぐに吐き気を催した。 この場所はめちゃくちゃで、文字通りいくつかの嫌な匂いが立ち込めていた。 ゴミが溢れ出すゴミ捨て場と非常階段が彼女の周りにあった。 彼女は腐ったゴミの匂いが彼女の体に侵入するのを防ぐために、手で鼻と口を覆い、そこにじっと立っていた。
「やばい、**サーシャ**! 自分で何をやらかしたんだ」と彼女は心の中で考え、全てが始まったあの頃に頭が戻っていった。
*数時間前。*
8歳の子どもにも似合わない短いエメラルドグリーンのドレス、高いハイヒール、肩にかけた金のショルダーバッグを身につけて、彼女はパルスするブラックライトクラブに入った。
ダンスフロアは、天井の回転灯から発射される青と緑のレーザービームで光っていた。 土曜日の夜だったので、クラブはDJの脈打つ音楽に合わせて踊ったり飛び跳ねたりする人でいっぱいだった。 寒さの中で群がるペンギンに似ていたが、彼らはクラックを吸っていただけだった。
「マジで最悪」**サーシャ**は友達に不機嫌そうにつぶやいた。
彼女の18歳の誕生日で、**サーシャ**が閉じこもっていた孤独の風船を破るために、友達が彼女をこのクラブに連れてきてくれたのだ。
「さあ、リトルキトゥン、パーティーよ」**シェリー**、彼女の一番の親友は、彼女の肋骨を遊び心で肘で突いて、叫んだ。
厚い翼のメイクが彼女の顔に塗られ、唇は鮮やかな赤色に塗られていた。 キャラメル色の髪は肩の長さのボブカットに新しくカットされていた。 友達と同じように、**サーシャ**も金のリングのティアラをつけ、彼女のルックを引き立てていた。
「ハッピーバースデー、**サーシャ**」友達はレイブミュージックの中で彼女の耳に叫び、彼女に彼女の手に彼女の耳を押し付けさせた。
彼らは彼女を真ん中に引っ張り、周りをぐるぐる回り、蛇のように踊った。 マジで、面白いね。 彼女ができたことは、お腹が痛くなるまで笑うことだけだった。 **サーシャ**の手を握って、**シェリー**は彼女と一緒に小さなカップルダンスを真似た、正直、それは面白い行為のようなものだった。
彼女は、この楽しさと喜びの世界で、すべての悲しみを消し去った。 彼女の過去を押し戻し、**サーシャ**は遊ぶ準備ができていたが、彼女は自分の過去が彼女と衝突し、彼女を彼女が出ようと苦労していた泡の中に押し戻すことが、どれだけ知っていたのだろうか。
しばらく踊って飛び跳ねた後、**カラ**は言った、「うわ! もう疲れた。 ドリンクを飲もう」
彼女に同意して、彼らはダンスフロアを離れた。
アルコールと煙の悪臭が彼女の肺に流れ込み、彼らはバーに向かった。 **サーシャ**は自分のためにライトビールを飲ませてくれと主張した。 今では小柄で弱い女の子なので、彼女は酒に敏感になりすぎていた。
すぐに彼女の友達はみんな男たちと一緒になり、**シェリー**だけが誰かが来るのを待っていた。
大音量の音楽とねちっこい雰囲気は、今や**サーシャ**の頭に影響を与え始めていた。
「**シェリー**、楽しんでこない? 私は家に帰りたいと思うの」と彼女はできるだけ誠実に言った。
「そして、どうやって帰るの? もう午前0時だよ、つまり公共交通機関はないってこと。 そして、私たちが持ってきた車は**ステイシー**に持って行かれちゃった。 だから、私たちができる唯一の選択肢は、私の魅力的なボーイフレンドの助けを借りること…」彼女はウィンクした、「ところで、今夜あなたのためにサプライズがあるから、ちょっと待っててね」**シェリー**の目はクラブを探し回り、誰かを探して、ついに彼を見つけたとき、彼女は叫んだ。「**ロイ**? はい!」入ってきたばかりの男に手を振って、彼女は自分の席に飛び乗った。
**ロイ**という名前の男が彼らに向かってきて、彼のガールフレンドの**シェリー**に骨が砕けるようなハグをした。 しかし、彼は一人ではなかった。彼と一緒にいたのは、**ジェーン**という名の、フェアで若い男で、彼の茶色の目は**サーシャ**の体をくまなく見て、彼女はジャケットで自分を覆いたくなるような気持ちになった。
「**シェリー**、これは僕の友達の**ジェーン**だよ。 **ジェーン**、これは僕のガールフレンドの**シェリー**で、あれが**サーシャ**かな?」**ロイ**は**サーシャ**を指差して尋ねた。
「そう。 **サーシャ**、これは私のボーイフレンドの**ロイ**で、あれが**ジェーン**。 今日のあなたのブラインドデートよ」**シェリー**は親友にウィンクして言った。 しかし、その言葉を聞いて、**サーシャ**は飲み物をむせた。
彼女の背中をなでて、**シェリー**は心配そうに尋ねた、「大丈夫?」
うなずき、**サーシャ**は身だしなみを整える前に、ティッシュで顔を拭いた。
「よし、**ジェーン**、彼女はあなたのものよ」**シェリー**は笑い、友達を前に押し出し、**サーシャ**から激しい視線を浴びた。 しかし、彼女はそれをすぐに払いのけ、腕にしがみついているデート相手と一緒にダンスフロアに向かった。
**サーシャ**がこの男と色や火花を感じなかったわけではないが、完全な見知らぬ人と一緒にいると、確かに部屋は気まずさで満たされた。
紳士のように、**ジェーン**は**サーシャ**のために椅子を引き、彼女の隣に座った。 正直なところ、彼の存在は彼女に説明できないほどの不快感をもたらした。 彼女は間違いなくこのことで**シェリー**を殺すつもりだった。
「それで、何を注文すればいいですか、プリンセス」**ジェーン**は尋ね、彼の声は偽りの甘さで覆われ、彼が**サーシャ**の膝に触れるように前に傾き、彼女はひるんだ。
「あ…ありがとう、でも実際には何もいらないし、まだ飲み物が残ってるし。 今夜はそれで十分だと思う」**サーシャ**はどもり、彼にグラスを振った。
「ああ、スイートハート! もう少ししか残ってないし、今日のは全然足りないって信じてよ。 今夜は大きな夜になる…すぐに終わらないよ」彼はニヤリと笑い、彼女にウィンクした。 彼女の目の悪意は、**サーシャ**に警告するのに十分だった。 彼女は彼からの飲み物を避ける決意をしていた。 彼は、彼女の邪悪な願望を達成するためだけにここにいるプレイボーイのようなチョコレートボーイのように思え、彼女は彼を楽しませる気分では全くなかった。
「**サイモン**」彼は、すぐに現れたバーテンダー���叫んだ。
「やあ、**ジェーン**」彼は答え、友達の隣の美しさに気づき、**サイモン**は尋ねた、「うわー! この美しい女の子は誰?」
**サイモン**にニヤリと笑って、彼は答えた、「僕のブラインドデートだよ。 だけど、彼女はあまり楽しんでないみたいだから、彼女のために特別なドリンクを作ってもらえないかな」
「本当にいらないんです」
バーテンダーは彼女を無視して、「もちろん! **ジェーン**の素晴らしいデートのために」彼はそう言って角を曲がった。
すぐに、**サイモン**は青みがかった飲み物を置いた。
彼女は何か怪しい匂いがすることを嗅ぎつけ、何が起きても、彼女はこのものを飲まないと心の中で自分に言い聞かせた。 **ジェーン**は彼女にグラスを渡し、しばらく考えてから、それを手に取り、テーブルに再び置いて、「今は飲みたくないから、たぶん後で」と言った。
**ジェーン**は今すぐに飲み物を無視するという彼女の考えが好きではなかったが、彼はうなずいてそれを手放した。 彼は、遅かれ早かれ彼女がそれを飲むことを知っていた。
「自分のことについて何か話してくれないか?」**ジェーン**は、その場を和ませ、彼女を少しスムーズにさせるために言った。
「私のこと? 私はただのシンプルな女の子で、レストランで働いてるの」彼女はそれ以上のことを自分に持っていたが、彼と交流することに全く興味がなかったので、すべてを覆い隠した。 「あなたは自分のことについて何か話さないの?」
彼は話し始め、実際には自分の人生、ルックス、力を彼女に見せびらかし、一方彼女はそこに座って、あちこちを見て、彼から逃げる方法を探していた。
その時、彼女の目は角で踊っているチョコレートブラウンの髪の背の高い人物に集中した。 彼女の心は輝いた。 彼女は彼の近くの女の子を精査した。 彼女は青いプラダのフィッシュカットドレスを着ていて、長いラプンツェルの髪はフィッシュテールの三つ編みに結ばれ、**サーシャ**が自分のダークスポットを隠すためにコンシーラーの層で覆われていたのとは異なり、彼女は最小限のナチュラルなトーンのメイクをしていた。 彼女は最もシンプルな美しさを持つゴージャスな人魚のように見えた。 彼女は、彼が彼女を去った女の子は、それだけの価値があると悟った。 槍が彼女の心を突き刺し、彼女を麻痺させた。 彼女はクラブも**ジェーン**も見えず、見えたのは**アレックス**だけだった。 彼女は彼が今彼女の前に立っていることを信じられなかった。 彼女の胸の中で、彼女の心臓は檻の中の鳥のように激しく鼓動していた。
女の子が**アレックス**の手を握って彼の腰に巻きつけ、**アレックス**に近づき、彼の首に腕を回したとき、**サーシャ**は裏切りの感情が彼女の血管に押し寄せるのを感じた。 涙が出そうになったが、彼女は制御し、泣き叫びを抑え、自分自身を沈黙させた。
彼女のデート相手がゾーンアウトしていることに気づいた**ジェーン**は、彼女を罠にかけるチャンスをつかんだ。 彼は**サーシャ**にその飲み物を渡した。**サーシャ**は最初それを避けたが、彼が**アレックス**が彼女を彼女の近くに引き寄せているのを見て、彼女は理性を失った。 彼女は**ジェーン**の手から飲み物を奪い、燃えるような液体を飲み干した。 彼女は喉が刺され、咳をし、涙が目に飛び込んできた。 彼女は燃えるような液体が喉を下るのを感じ、頭がほぼ瞬時に軽くなり始めた。 しかし、彼女は**アレックス**を頭から消すことができなかった。
彼が女の子を守り、他の男の手から彼女を保護した方法は、彼女のために記憶の波を掘り下げた。
数ヶ月前、彼女は彼を独占的に持っていて、彼によって守られ、保護され、保存されているラッキーな人だった。
彼女はまだ**アレックス**が彼女のためだけに、血が出るまで男を殴った時を覚えている。 彼らは地下鉄に乗っていたが、その日**サーシャ**はいつものようにピンクのサンドレスを着ていて、それが彼女のクリーミーな白い肌を美しく誇示していた。 男は彼らが電車に入ってからずっと彼女を見ていた。 **アレックス**は、できる限り彼女を彼のむさぼり食う視線から隠すことに熱心だった。 そして、その汚い男が**サーシャ**の後ろに立って不適切に触れようとしたとき、**アレックス**はすぐに彼らを振り返し、**サーシャ**が彼の胸に押し付けられ、彼の暖かい香りを吸い込み、一方**アレックス**は彼女の場所に立って、その男に背を向けていた。 それは彼女が自分の心に火花を感じた最初であり、彼女が**アレックス**に対する自分の関心が高まっていることに気づいたときだった。 しかし、それだけでは十分ではなく、彼らが地下鉄から出るとき、彼の何度も試みにもかかわらず、その男は**サーシャ**に小さな指一本も触れることができなかった。 なぜなら**アレックス**がいたから。 しかし、彼は**サーシャ**に一連の支離滅裂な言葉をつぶやいた。 次に何が起こったのだろうか? **アレックス**は制御を失い、その男を黒と青になるまで殴った。 地下鉄だけでなく、その日、**アレックス**はいつも**サーシャ**を過保護にしていた。 彼は愛情を込めて、人前で短いドレスを着ないように説得し、そうでなければ彼は彼女に目を向けたすべての邪悪な目を殴って通りを走るだろう。
ああ! それらの記憶は彼女の心臓へのナイフのようで、彼女はそれらを忘れること以外に何も望んでいなかった。