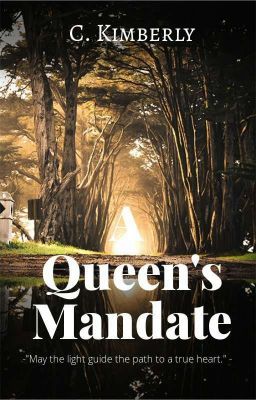復讐と救済(パート1)
メリッサ:
あたしは、みんなが全部持ってるって思ってる世界に住んでるけど、心の底では溺れてるんだ。政治とか見せかけが当たり前だけど、あたしの望みじゃない。あたしのファーザーの野望は全部を覆い隠して、あたしを重要じゃない、孤独だって感じさせる。それで、セバスチャンが現れて、あたしの世界をひっくり返した。彼は嘘を見抜いて、あたしをその見せかけから解放してくれた。でも、彼と一緒に、不確実性もやってきた。彼はドラッグみたいで、中毒性があるけど危険で、あたしは彼が自分の破滅のきっかけになるんじゃないかって恐れてる。
セバスチャン:
愛なんて、あたしの世界では神話なんだ。力こそが全ての世界ではね。ヴァンダービルト家の一員として、あたしはこの現実に縛られてる。それから、メリッサが人生に現れて、あたしの予想を全部裏切った。彼女は矛盾してるんだ、脆いのに強くて、今まで会った誰とも違う。でも、彼女とあたしのファミリーの敵とのつながりが全部を複雑にしてる。リスクを分かっていても、彼女を手放せない。それでも、彼女の安全が危機に瀕していて、彼女を守るのがあたしの義務なんだ、例え自分の血に逆らうことになっても。
--
プロローグ
彼女の目は腫れてて、涙がまつげを重くしてる。震えてて、息は荒い。こんな風な彼女を見て、あたしの心は引き裂かれた。「メリッサ、愛してる。信じてくれ」と、あたしは過去を振り返って頼んだ。
「私たちが一緒に過ごした瞬間は全部、本物だった。あなたを愛してるって、一度も嘘をついてない。もし時間を戻せるなら—」「でも、できないのよ」と彼女はさえぎって、きつい口調で言った。「それが問題なの、セバスチャン。できないのよ!」彼女の声が震えて、涙があたしの胸を叩きつけた。「大嫌い!ああ、本当に大嫌い!あなたを信じてた。あたし、あなたに心を開いたのに、あなたはまだ役を演じてたのね!ひねくれてる!」
「メリッサ、そんなことないって分かってるだろ。」あたしは優しく彼女の手首を掴んで、自分の胸に持ってきた。あたしが守ると誓った女性が、目の前で崩れていくのを見て、あたしの決意は打ち砕かれた。歯を食いしばって、自分の涙をこらえながら、彼女が嗚咽するのを見てた。あたしが原因だって分かってたし、それがあたしを引き裂いたんだ。
「あなたに会ってから毎日、ファーザーのめちゃくちゃな計画に同意したことを後悔してる。自分が嫌になる。あたしはダメ人間よ、分かってる。でも、それがあたしの育ち方なの。ファーザーはあたしに復讐心を詰め込んだ、まるでそれが自分の人生の目的だってみたいに。あなたに会うまでは。」あたしの声が途切れた。
彼女の手を握り、20年間で初めて涙を解き放った。あたしは5歳の時、マザーの葬式で泣いたのを覚えてるんだ。「
あなたはあたしをそこから解放してくれた、メリッサ。あたしを過去に縛り付けていた鎖を壊してくれたんだ。そして、愛してる。本当に、メリッサを愛してる。あなたはあたしの全てなんだ。あなたがいなかったら、あたしは道に迷うだろう。」
「信じられない」メリッサはすすり泣きながら、涙の中で息をするのに苦労してた。くそ、どうにかして彼女の痛みを和らげることができたら良かったのに。でも、あたしは完全に無力だと感じた。あたしは、あたしが何よりも愛する女性を打ち砕いたんだ。
「信じてくれなきゃだめだ」あたしはつぶやき、彼女の顎を指で優しく持ち上げ、彼女の目と視線を合わせた。「あなたを見た瞬間から、あたしはあなたを傷つけることはできないって分かってた。そして毎日、あなたはそれが正しいって証明してくれた。それからあたしがやってきたことは全部、あなたを安全に保つためだった。」
メリッサは顔をそむけ、涙を拭いて深呼吸をした。彼女の目は強烈な憎しみで暗くなった。「もし本当にあたしを守りたかったら、近づかなかったはずよ。」
「メリッサ、お願いだ…どれだけ愛してるか見せてくれ」あたしは懇願し、声が裏返った。
「いや、セバスチャン。私たちの関係はただの欲望で、愛じゃなかった。」
「そんなこと言うな。」
「でも本当のことよ。私たちは欲望を愛と勘違いしたの。」
「違う、メリッサ。こんなに強烈に感じられるのは愛だけだ。そして、こんなに苦しくて窒息しそうになるのも愛だけだ。」
「じゃあ…愛は死に至るものね」メリッサはささやき、その言葉があたしの背筋を凍らせた。恐怖が忍び寄るのを感じた。「だって、これが何であれ…あたしはオーバードーズして、死んだんだもの。」
あたしは首を横に振って、彼女の言葉があたしの心を深く切り裂いた。「そんなこと言うな。」
メリッサは軽蔑の目であたしを見て、目に涙を光らせた。「あたしから離れて」彼女は叫び、そして車に乗り込んだ。
レッドフォードは走り去り、あたしは誰もいない通りに一人立って、夜の闇に包まれた。あたしはこの地点に至ったすべての決定を疑いながら、苦痛に溺れていた。
何か後悔してるかって?もちろん。
何か変えるかって?いや。