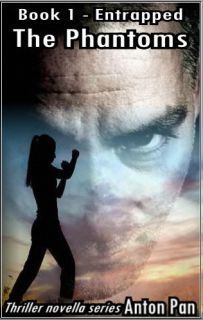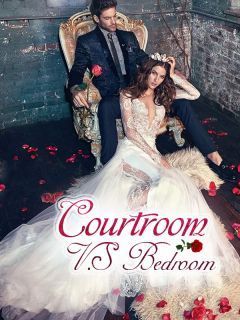紹介
目次
紹介
赤は常に愛を象徴する。しかし、ローズ・アマラにとって、それは決して愛ではなかった。それは血だった。彼女の名前にも赤が含まれている。彼女が憎む血。もし彼女が時間を巻き戻せるなら、かつて愛した男とは決して関係を持たないだろう。彼女が不要とする血が、彼女を生かし続けることができる。彼女は、愛が彼女が投げ捨てた愛を奪うためにその道を進むことになるとは知らない。彼女は、人生で一度だけ…赤が常に愛であり、ローズ・アマラが常に赤であるとは知らない。
もっと読む
すべての章
目次
チャプター1
チャプター2
チャプター3
チャプター5
チャプター6
チャプター9 パート1
チャプター9 パート2
チャプター10
チャプター11
チャプター12
チャプター13
チャプター15
チャプター17
チャプター18
チャプター19
チャプター20
チャプター20 - 2
チャプター23
チャプター25
26
27
28
29
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
57
59
60
61
62
64
67
68
71
72
73
74
75
76
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90 END
第十四章
43
77
56
第十六章
79
第八章
第二十四章
70
86
30
第四章
33
66
52
63
CHAPTER SEVEN
32
69