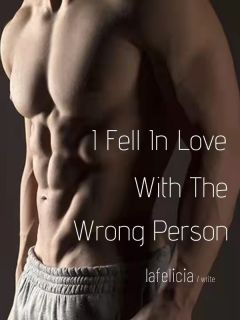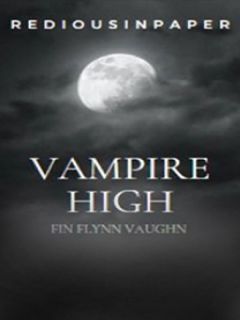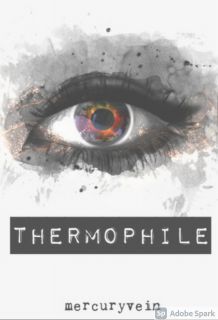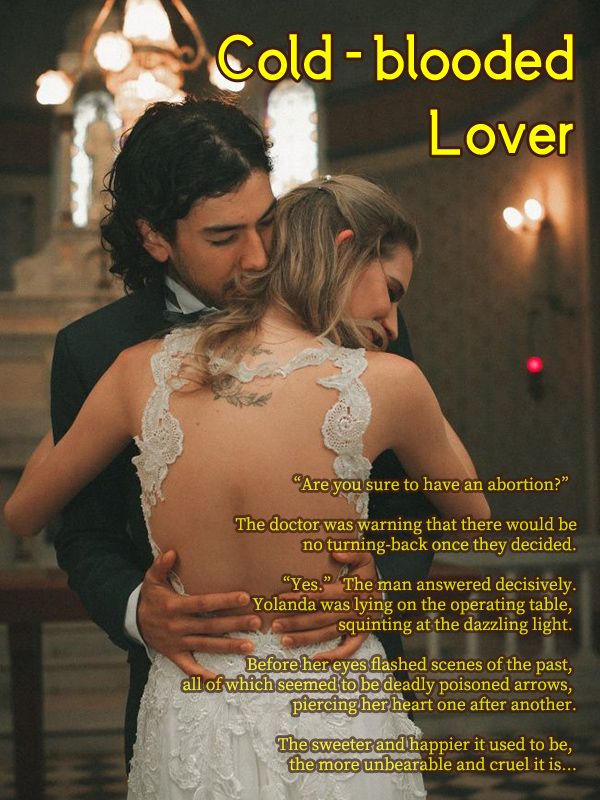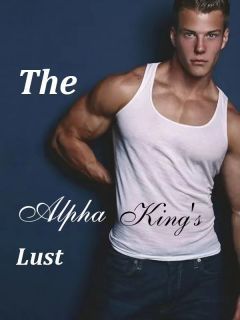ポケットに手を突っ込んで、学校から家までゆっくり歩いた。学校はいつもの日と変わらず、つまんなかった。
お父さんが死んでから、どんどん悪いことばっかりだった。友達はみんな、僕みたいな変なやつと一緒にいたくなくて、すぐにいなくなっちゃった。
自分の家まであと3軒ってところで、家の近くに引っ越しトラックが止まっているのが見えた。
誰か引っ越すのかな。
家に近づくと、トラックと同じ会社のロゴが入った制服を着た男の人たちが、うちからダンボールを運び出しているのが見えた。
残りの道を早歩きして家に入ると、ドアのところで男の人の一人とぶつかりそうになった。リビングを見たら、部屋のほとんどがダンボールで埋まっていた。
「何が起きてるの?」誰に言うでもなく、そう尋ねた。
答えを探そうと、廊下を通って、お母さんの部屋のドアをノックした。
「入ってきて」ドアの向こうから、ちょっとこもったお母さんの声が聞こえた。
「引っ越すの?」部屋に入って一番最初に尋ねた。
「あら、ライラ」お母さんは空のダンボールに自分の物を詰めながら言った。私の質問には答えようともしない。「学校はどうだった?」
「引っ越すの?」もう一度尋ねた。
「そうよ、ライラ」お母さんは作業を止めて答えた。「前に話したでしょ」
「うん、でもこんなに早くって言ってなかったじゃん」反論した。
「何が違うの?」お母さんが尋ねた。
「いっぱいあるよ、お母さん—」
「今はやめてくれない?」私が言い終わらないうちに遮られた。「後で話すから、お願いだから、自分の部屋に残ってるものを片付けてくれない?」そう頼んできた。
渋々ため息をついて、無言で部屋を出た。
「ありがとう!」ドアを閉めた後に、お母さんが叫んだ。
言われなくても、私たちが、いや、少なくともお母さんが、何から逃げようとしているのか、わかっていた。お母さんの目の下のくまを見れば一目瞭然だった。お父さんの思い出に家中の隅々まで取り憑かれているみたいだった。あの事件の後、お父さんの話はあまりしなかったけど、お母さんが必死に隠そうとしている痛みがよく見えた。全然隠せてないよ。
自分の部屋に入ると、クローゼットに残っていた服を取り出して、全部入らないほど小さいスーツケースに詰めた。その後、荷物を外に持って行って、お母さんの車のトランクに入れた。
「全部?」お母さんの声が後ろから聞こえた。
「うーん…違う」ため息をついた。「ちょっと何か取ってから、行けるよ」
そう言って、中に入って、今までずっと家と呼んでいた、今は空っぽの家をじっくり眺めた。
信じられない。引っ越すんだ。
罪悪感に襲われ、いつも抑えようとしていた思い出が、目の前で映画のように流れた。目を閉じて、その思い出を消そうとしたけど、涙が頬を伝うだけだった。
深呼吸して、気持ちを落ち着かせようと、スーツケースに入りきらなかった服が入った箱を掴んで、良い思い出も悪い思い出もたくさん詰まった家を出た。
「もう準備できたよ」箱をトランクに入れて閉めるとすぐに、そう言った。
お母さんが来て、きつく抱きしめてくれた。「心配しないで、ライラ。もっと良い場所に行くから」そう囁いた。「わかるでしょ」そう言って私を離して、車に入った。
家を数秒間見つめて、変な場所に置かれたブランコから、刈りたての芝生まで、家の隅々まで記憶に刻もうとした。
「さようなら」ため息をついて、車に向かって歩いた。
助手席に座って、シートベルトを締めた。お母さんがバックで車を出し始めて、気づいたら、私たちは新しい家に車を走らせていた。
まだ家って呼べるかな?