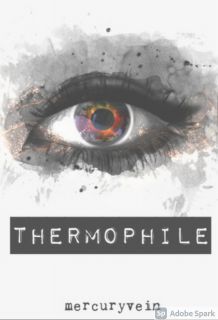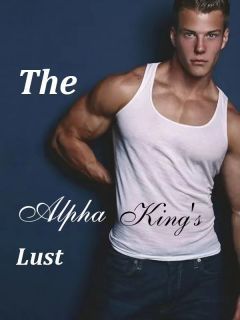紹介
目次
紹介
「私を挑発するのが楽しいのか?」彼は忙しい唇を通して言った。「初めて私のオフィスに入って以来、あなたは私の忍耐力を試すことしかしていません。そして、私たちが2度目に会ったとき、あなたは私の顔を殴りました。」
私は彼の唇を噛んで少し離れる前にくすくす笑った。彼はその行動に私の腰を締め付けた。「そうよ。」
Runner Studiosのディレクターの1人であるクルは、彼女の才能ある仕事とルールに従わないことで知られています。ナイルは、彼ら自身の家族会社のCEOです。彼はロシア、日本、アメリカの血を引いており、中性的な美しさと冷たい性格で知られています。初めて会ったとき、二人はすぐに衝突し、すぐに互いを嫌いました。しかし、ある親密な夜が二人の間で変わりました…
もっと読む
すべての章
目次
第1章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第10章
第11章
第12章
第14章
第15章
第16章
第17章
第18章
第19章
第20章
第21章
第22章
第24章
第25章
第28章
第29章
第30章
第31章
第32章
第34章
第36章
第37章
第38章
第39章
第40章
第41章
第43章
第44章
第45章
第46章
第47章
第49章
第52章
第53章
第54章
第55章
第56章
第57章
第58章
第59章
第60章
第61章
第62章
第63章
第64章
第65章
第66章
第67章
第68章
第33章
第23章
第51章
第13章
第69章
第2章
第9章
第26章
第50章
第27章
第42章
第35章
第48章