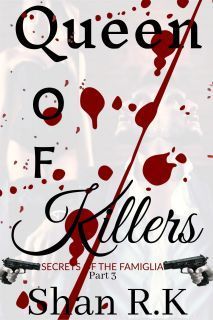なにか硬いものにぶつかって、でっかい声出しちゃった。目を開けて、ハアハア息をしながら座り込んだ。汗もかいちゃってるし、震えてるし。周りを見渡したら、夢の内容が頭にフラッシュバックしてきた。膝を抱えてぎゅって抱きしめた。
「お母さん、お父さん」って小声でつぶやいた。めっちゃ怖かったんだ。
部屋のドアが開いて、おばあちゃんが入ってきた。俺のこと見つけると、すぐそばに来て、抱きしめてくれた。俺もおばあちゃんに抱きついて、髪をなでなでしてもらいながら、落ち着く言葉を囁かれて、ゆらゆら揺られた。震えが止まって、おばあちゃんが俺をベッドまで連れてってくれて、隣に座ってくれた。おばあちゃんは、お母さんがいつも家で歌ってた、俺の大好きな歌を歌ってくれた。髪をなでられながら、目を閉じたら、すぐにまた眠っちゃった。
目が覚めたら、窓から入ってくる太陽の熱が腕とか顔に当たってるのが分かった。毛布を頭まで被って、目を閉じた。
「ハニー、起きなきゃダメだよ。寝すぎると、今夜眠れなくなっちゃうよ」っておばあちゃんが揺すってきた。
毛布をどかしたら、おばあちゃんはニッコリ笑って出て行った。バスルームに行って、鏡の前に立った。髪をくしゃくしゃってして、自分を見つめた。
~~~
俺の名前はボビー・シャウター。ゲイで、16歳。もうすぐ17歳になるんだ。誕生日は嫌い。いつも…何があったのかを思い出させられるから。友達はいない。みんな怖いから。一緒に住んでるおじいちゃんとおばあちゃん以外はね。髪は真っ黒で、目は茶色。肌はめっちゃ白い。服は黒か白しか着ないし、爪には黒いマニキュアを塗ってる。昔は自傷行為もしてたけど、今はなんとか頑張ってる。それ以外で自分を表現するなら、去年あったことのせいで、何でも怖くなっちゃった、壊れた16歳の男の子って感じかな。でも、言わないけどね。考えるのも嫌だし、話すのも嫌なんだ。
~~~
シャワーを浴びて、下に降りて、キッチンに向かって、テーブルに座った。おじいちゃんが俺の髪をわしゃわしゃして、ポンポンって叩いた。
「おはよう、坊や。昨夜はよく眠れたか?」って、お茶を飲みながら聞いてきた。
肩をすくめて「まあね」って答えた。
おばあちゃんが朝ごはんを持ってきてくれて、食べ始めた。正直、ちょっと疲れてたんだ。
「ハニー、シンディと孫が今日来るんだけど、もしよかったら、一緒に下にいる?」
俺は首を横に振った。「部屋にいる。誰にも会いたくない」って言ったら、おばあちゃんは何も言わずに頷いた。俺が人見知りだって分かってるから。
シンディとおじいちゃんとおばあちゃんは、俺が生まれる前からずっと親友なんだ。前の家で何かあってからここに引っ越してきて、彼女たちの家に近くなったんだ。1ブロックくらいで、今日彼女が孫と一緒に、うちを歓迎しに来るんだけど、俺は部屋にいるつもり。人って怖いんだよ。誰が信用できるか分からないし、悪い人かどうかは、誰かが死なないと分からないんだよ。
食べ終わって、おじいちゃんとカードゲームをしてたら、おばあちゃんがお客様のために夕食を作ってた。
「新しい学校、楽しみ?」っておじいちゃんがゲーム中に聞いてきた。
「うん、楽しみ」って嘘をついて、無理やり笑顔を作った。
学校には行きたくなかったんだ。新しい学校なんて。俺を殺しそうな人たちでいっぱいかもしれないし。初日からパニックになっちゃうだろうな。人が嫌い。怖いんだ。
ドアベルが鳴って、俺は立ち上がって、階段を駆け上がった。一段ずつ丁寧に。ドアを開けて、中に入って、ベッドに飛び乗った。そこに座って、呼吸が落ち着くまで1分くらいして、壁のテレビをつけた。アニメはいつも俺を元気づけてくれるんだ。リラックスできる。
階下で話してるのが聞こえて、テレビの音をもっと大きくして、下の音を遮断した。
**アシュトン視点**
「お母さん!お父さん!おばあちゃん!」
返事がない。マジだりい。リビングに入って、座った。立ち上がろうとしたら、おばあちゃんが入ってきた。
「あら、ハニー。何か用?」っておばあちゃんが聞いてきた。
「うん。お母さんとお父さんはどこ?今夜は帰ってくるはずなんだけど」
「ああ、帰ってこないわよ。理由は教えてくれなかったけど。準備しなさい」って言われた。
顔をしかめた。両親はほとんど家にいないんだ。本当に嫌だ。まあ、おばあちゃんがいるからいいけどね。肩をすくめて、階段を上がった。
~~~
俺の名前はアシュトン・エヴァンス。17歳。学校のアメフト部のキャプテンで、人気者。チアリーディング部のキャプテンと付き合ってるんだ。背が高くて、鍛えられた体つき。髪は茶色で、肌は日焼けしてて、目は茶色。所謂、体育会系ってやつ。チャラいって言う人もいるけど、自分ではそう思ってない。
~~~
「アッシー、準備できた?」っておばあちゃんが階下から呼んだ。
おばあちゃんは、昔からの友達に会いに連れて行ってくれるんだ。彼女たちは、1ブロック先に引っ越してきたばっかりなんだ。おばあちゃんと一緒にお出かけするのは楽しいんだよね。
「うん、行くよ!」って返事して、イヤホンを拾って、部屋から出て、ドアを閉めた。
階段を降りて、おばあちゃんの車に乗った。
「おばあちゃん、歩いても行けたんじゃない?」って、家の前で車を発進させながら言った。
「あんた若いんだから、歩きなさいよ」って言われた。
ため息をついて、道に目を向けた。5分も経たないうちに、おばあちゃんが家を指さした。家を見てみた。デカくて、お金持ちっぽい感じ。車から降りて、おばあちゃんが来るのを家の前で待ってた。おばあちゃんが来て、一緒にドアに向かった。おばあちゃんがドアベルを押して、待ってた。おばあちゃんの年の女性がドアを開けて、お互い笑顔で抱き合った。
「シンディ、元気?」ってその女性が聞いた。
「元気よ、マリッサ。ボビーは最近どう?」っておばあちゃんが聞いた。
「あんまりよくないのよ。ドアベルが鳴ったら、すぐ2階に走って行っちゃったわ」って女性は顔をしかめた。
「あら、それは残念ね。すぐ良くなるわよ」ってその女性は微笑んで、俺の方を向いた。
「それで、あなたがアッシーね」ってその女性は俺に微笑んだ。
「アシュトンです」って俺は訂正した。「はじめまして」
「マリッサよ。私もよ。入って、二人とも。夕食はできてるわ」
彼女は歩いて行って、俺たちは後に続いて、家の中を見回しながら行った。やっぱり、金持ちの家だ。ダイニングルームに着くと、おじいさんが顔を上げて、俺たちに微笑んだ。
「やあ、シンディ、調子はどうだい?って、そのおじいさんは椅子の上で姿勢を変えながら言った。
「まあね、テッド。あなたは?」って、おばあちゃんが聞いた。
「歳をとるばかりだよ」って、おじいさんは言って、背中を鳴らした。俺はクスクス笑った。
「で、この反抗的な子供は誰だ?」って聞いた。
「ああ、これはアシュトンよ、私の孫なの」
おばあちゃんが言った。
「こんにちは」って俺は言った。
「マリッサよ。あなたもね。どうぞ座って。食事の時間よ」
マリッサがやってきて、大きなダイヤモンドのテーブルに料理を並べた。
「ボビーは一緒に食べないのかしら」っておばあちゃんがまた聞いた。
「いいえ、まだ自分の世界にいるわ」ってテッドが囁いた。
「あら」って、おばあちゃんは言って、俺たちは食べ始めた。3人は深い会話に入り込んだ。30分くらいで食べ終わって、俺はただ面白がって見てた。階段から音が聞こえてきた。ボビーって子だと思う。テッドはまだ自分の世界にいるって言ってたな。どういう意味なんだろう。
1時間くらい経って、退屈してきた。
「トイレ、借りてもいいですか?」って、会話を中断して言った。
「ええ、もちろん」ってマリッサが俺に微笑んだ。俺も微笑んで、立ち上がった。
階段を上がって、家の中を調べながら行った。マリッサにトイレの場所を聞くのを忘れちゃったな。全部のドアを開けてたら、時間がかかりすぎる。廊下の奥のドアから音が聞こえてきた。もしかしたらボビーかもしれない。彼にトイレの場所を聞いて、ボビーに会えるかもしれない。
**ボビー視点**
まだテレビを見てた。お客さんたちはまだ下にいるみたい。彼らの声が聞こえてた。リンゴが食べたかったけど、彼らが帰るまで出ていきたくなかった。
トイレに行こうと立ち上がったら、ノックの音がした。飛び上がって、動きを止めた。おばあちゃんかおじいちゃんだろう。
「入って」って言うと、ドアノブが回って、男の人が入ってきた。笑顔で。
恐怖が体に走った。叫び声をあげた。彼は後ずさった。
もう一度叫んで、ベッドの近くの隅にしゃがみ込んだ。
「お願い…行って」
「すみません。怖がらせるつもりはなかったんです。ただ…」
「私を放っておいて!」ってまた叫んだ。もうめっちゃ怖かったんだ。人が嫌い。知らない人なんて大嫌いなんだ。
「ああ、アシュトン、何をしたの?」って女性が入ってきた。
見覚えがあった。おばあちゃんの友達の1人だ。昔一度会ったことがある。関係ない。まだ怖いんだ。頭の中にあるのは、彼らが俺を傷つけようとしてるってことだけだった。隅にもっと近づいて、泣き始めた。
「行って、行って、行って」って泣き叫んだ。
「知らない!入ってきたら、俺のこと見て、パニックになって…」って、アシュトンってやつは言ったんだと思う。
「ボビー?」っておばあちゃんが入ってきて、おじいちゃんが後ろにいた。立ち上がって、おじいちゃんの腕に飛びついて、強くしがみついた。
「すみません、何かしましたか?本当にすみません」ってアシュトンが言った。
「大丈夫よ、何にもしてないわよ。ただ、怖がりなだけなのよ」っておばあちゃんが言った。
「分かった。すみません、下にいきます。マリッサ、アシュトン」っておじいちゃんの友達が、その男を部屋から連れ出した。
おじいちゃんが俺をベッドまで連れてきて、座ってくれた。
「大丈夫だよ、坊や。もういないよ。大丈夫だよ」って言って、背中をさすってくれた。
「下に行くから、ボビー、落ち着いて深呼吸してね」っておばあちゃんがドアに向かって言った。
頷いて、おばあちゃんはドアを閉めた。すぐに落ち着いてきて、おじいちゃんが俺を離して、立ち上がった。
「もう大丈夫か、ボビー?」って聞いた。
頷くと、出て行って、俺はすぐに立ち上がって、ドアを閉めて、鍵をかけた。ベッドに後ずさりして、座った。膝を抱えて、体を前後に揺らした。学校に戻る準備はできてなかった。どうしても無理なんだ。こんなに怖かったのは、この家を出た時以来だった。もうずっと、長い間だ。2ヶ月間、家を出てない。夏休みと、前の家。あの事件が起きてから、出てないんだ。
人って怖い。少し前のことに頭が戻った。めちゃくちゃ怖くて、おしっこが出そうだった。アシュトンってやつ。声はすごく優しかったのに、怖かった。誰でもそうだ。