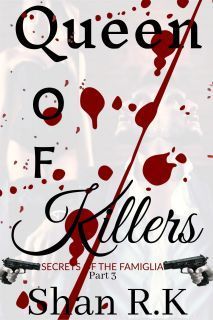アリヤーナ・カペッロ・カテッリ
現代
楽園への道は地獄から始まる
ダンテ・アリギエーリ
「サルヴァトーレ、お願い、サルヴァトーレ」空っぽの教会で叫ぶ。ヒールが木製の床をコツコツと鳴らし、荒い呼吸が私の狂気を空気で伝える。頭がぐるぐる回り、私は通路を駆け下りる。
「サルヴァトーレ、中にいるんでしょ」大声で叫ぶ。奥のドアから彼の高い姿が現れる。黒いズボンと聖職者のカラーが付いた黒いシャツ、これまでのこと全てを痛烈に思い出させる。指のリングが重く感じられ、何年も私に仕え、彼が守ることを選んだ悪魔を知らなかった男と対峙する。彼の傷跡が目立ち、私の前に立ち止まり、指をきつく絡ませる。
「アリヤーナ、あれからもうすぐ一年だ。何をしたんだ?」
私はひざまずき、「何をしなかったかよ。父よ、罪を許してください」と、長年苦しんでいた身体の緊張を解き放ちながら言う。
「ああ、アリヤーナ、一体何をしたんだい?」かつて忠実な兵士として私に仕え、自由を得たセント・アンソニー教会の神父を見上げる。
涙が私を裏切り、数年前のように、彼の厳しく、容赦のない視線を見つめる。あの時は、父の毒と王の残酷さに触れた少女だった。今は女王、地獄のローブに包まれ、罪のない人々の血にまみれ、ヴェノムの王に所有されている。私はどこまで地獄に落ちたのだろうか?
「アリヤーナ、話してくれ」サルヴァトーレは、彼が何を求めているのか知らないまま、その言葉を発する。しかし、私は罪のない神父を見上げる。
「全部殺した」
人生には、たとえ地獄に落ちた者でさえ、真実を認めなければならない時が来る。全てから逃れられる瞬間がある。あなたがそこに立っていて、全てがあなたに襲いかかる、あの特別な瞬間。全ての嘘、あなたが紡いだ物語、あなたが傷つけた人々。あなたが裏切り、全く意味もなく台無しにした人々、ただそうすることで心の痛みが和らぎ、明日が明るい日になるかもしれないという希望のためだけに。でも、そうではない。私は生きて、愛し、彼らが私に禁じた全ての感情を感じた。
この地球での29年間で、私はまともな人なら想像もできないようなことをしてきた。私の物語は、一人の男への愛で満たされているのではなく、多くの男への愛で満たされている。私にとっていつも最高を願ってくれた父への愛、たとえ彼のやり方が間違っていたとしても。彼の全てを愛した。彼の深い魂に宿るほんの少しの善さも、多くの人をあの世に送った権力への渇望も。彼への愛は…永遠だった、たとえ彼が私を誘惑に導いた蛇だったとしても。
そして、シカゴで私と一緒に育った4人の少年たちへの愛があった。自分の血や性別によって定義されない何かに属する感覚を教えてくれるまで、自分が欲していることさえ知らなかった兄弟たち。ロメロ、ミシェル、ガブリエル、ロレンツォは兄弟であり、私の一部となった。そのうちの一人が倒れ、そのうちの一人が私たちを裏切るまでは。
最後に、二人の男への愛があった。二人ともシャドウに属していた。一人は最も強力な悪者になることを決意し、もう一人はただ私と一緒にいたいと願った。しかし、嫉妬、憎しみ、復讐、名誉が全ての良さをねじ曲げ、私の物語は、敵と恋に落ち、守ることを誓った人への約束を守るという、ほろ苦い物語になった。私の物語は悲劇でもなければ、ハッピーエンドでもない。しかし、それは私のものであり、ここに私はまだ生きている。だから、ついにそれを語ることができる。
「サルヴァトーレ、告白します」ひざまずいたまま、彼の指がほどけ、荒れた指が私のあごをつかむ。私は顔を上げる。
「聞こう。正直に告白し、真実だけを話すと約束してくれるか?」彼は、何年も前に私に尋ねた質問をする。あの時、私は彼から背を向け、自分が傷つけた全てのことを恥じていた。今は、過去の決断に悩まされることはない、私は贖罪の準備ができている。
「はい、全て話します。私の告白は13年前、シカゴを乗っ取る協定を結び、エリーザ・ルッソが囮になることになった時に始まりました。」
「あの頃の何がそんなに悪かったんだ?」
サルヴァトーレの神父姿を見る。かつて神の御加護から落ちそうになった聖なる男。
私は微笑むが、私の顔に浮かぶのは幸福ではなく、恥ずかしさ、当惑、罪悪感のようなものだ。
「嘘をついた」
-----
パートI
過去、痛み、そして認識
アリヤーナ
13年前
過去は決して現在に作られるべきではない
そして、現在が未来に霞をかけてはいけない。
嘘とは、意図的に欺くために作られた虚偽の陳述、意図的な不真実、虚偽のこと。
「一体何やってんだ、お前ら悪魔は?」ガブリエルが、カーペット敷きの床に座っているメロの隣に座りながら尋ねる。シアトルに戻ってきて、本当に気分がいい。ついにシカゴを後ろにできる日が来るまで、そう長くはなさそうだ。
シカゴは、私たち5人のために特別に作られた刑務所のようなものだと表現したい。私たちは明日の朝一番に飛行機をチャーターすることになっていた。しかし、私は、まるでネズミのように扱われる都市で、もう一晩も耐えられなかった。私たちがその都市にいるのを魅力的にしなかったのは、私たちを囲む大人たちではなく、いつかそれを支配するティーンエイジャーたちだった。私は父に話すことを知っていたし、ガブリエル、メロ、ミシェル、そしてレンもそうだった。カポ・スタジオ・ルッソが、ティーンエイジャーの問題はティーンエイジャーの問題だと言ったとき。彼の言葉は単なる言葉ではなく、彼のテリトリーで起こったことは静かにしておきなさいという警告だった。
夏休みで、パパは明日の朝、東アフリカからの旅行から帰ってくる。そのため、私たちの早着は、この数ヶ月間閉じ込めていた緊張をようやく解き放つ完璧なタイミングになった。今、多くのことが起こっており、ガブリエルとレンは二人とも、ルッソの血を本気で求めていた。彼らはシカゴで最高の犯罪一家であり、また、私たちが高校を卒業するまで主に私たちの保護者でもあった。
第5州では、少年たちのグループを同盟国のテリトリーに送ることがルールだった。それは誠意を示すためのものだった。しかし、父は私に女の子をシカゴと私たちのファミリーに送った。カテッリ家は、私たちに同じ敬意を払うことを主張し、ルッソ家はエリーザを送った。彼らの貢物になるはずだったが、実は父の娘だった。めちゃくちゃな家族だ。そして、私のもすぐに上だった。
エリーザだけでなく、私らしくないアリスという女の子もいた。彼女はすでに大人で、ルッソ家の嫌われ者、マッテオ・ディ・サルヴォの妹だった。正直に言えば、言い換えれば、私はマッテオ・ディ・サルヴォを最も嫌っていた。他の人は彼を嫌っていたのではなく、彼が代表すると推測していたものを単に嫌っていただけだった。
「どこに急いで行ったんだ?おじさんのところに行っていい子ぶってるのか、それとも特定の赤毛の家に向かうことにしたのか?」ミシェルがガブリエルに尋ねる。ミシェルは私の白い掛け布団の下で落ち着いて、空港からの帰り道で買ったポケットナイフをいじっている。レンと私はベッドの左上を取り、私のベッドの半分に散らばった何百枚もの写真を見ていた。
いつもそうするように、どの写真が両親に見せるのに一番良いか決めていた。私たちは、戦争を始めないために、幸せな子供たちの外観を保とうとした。そして、氷でできていないようにするためにも。父は、選ばれた男は火の中を歩いても燃える必要はないと言った。私は、火が燃えるはずの時に、どうすれば燃えないのか確信がなかった。
私たちはすでに何度も火の中で焼かれていた。唯一の違いは、私たちの傷跡は内側にあり、私たちの目である窓は小さすぎて気づかないということだった。
実際、私たちはアレックとその仲間たちが私たちを排除しようと考案したいじめや陰謀に慣れていた。しかし、ガブリエルの車のブレーキを切ったことが記録された。彼らは危険なゲームをしていたが、ほとんどの場合、私たちは彼らより賢かったが、私たちの時計が刻々と進んでいることを知っていた。
「このクソをどれくらい続けられると思う?」レンが私たちに質問し、5人でピッツェリアにいる写真を持ち上げる。
「俺は立ち向かうべきだと言うよ、来年、あのクソったれ穴から出ていく。ルッソにレッスンをするのに完璧なタイミングになるだろう」ガブリエルが床から言う。彼の青い目は見開き、復讐への彼の期待と飢えが部屋中に響き渡るように、レンに集中している。
「アレックがシカゴを支配するとは思わない。彼は全面戦争を引起こすだろうし、カポ・デイ・カピは最終的に介入しなければならないだろう。カッシオとキャメリッドは手下だ。どちらもカポを叫んでいないし、どちらもきちんと歯を磨ける脳みそがあるとは思えない。マッテオはしかし…」メロは、私たちが皆考えているのと同じことを声に出す。ルッソ家の男たちはどちらも、シカゴのような大きくて危険な都市を扱うのに適していなかった。
「マッテオはディ・サルヴォのカポになるだろう、彼の家族はイギリスのモレッティと親しく、ディ・サルヴォは常にガロ一族と共にL.Aを運営してきた。彼はルッソでいっぱいの場所を支配したいとは思わないだろう。シカゴは彼にとって何でもない、彼の父が彼を降ろした場所でしかない」ミシェルは、地面から立ち上がり、彼の細い体を伸ばしながら言う。彼は10代後半で筋肉質になっていた。彼の運動能力のある脚の約束が、彼が現在身につけているダークウォッシュのジーンズを通して見えた。まるで彼の体のあらゆる部分にフィットするように作られたように。