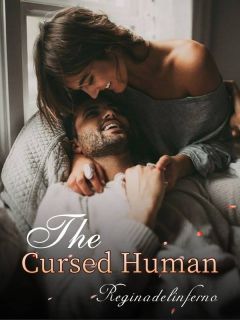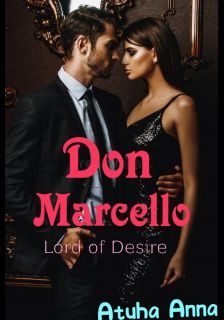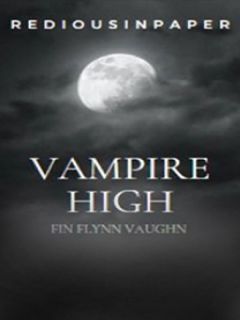夜がピークを迎え、心を惹きつけ合うような魅力的な闇が広がっていた。そこには、誰よりも素敵な顔立ちをした男がいた。サファイアよりも青い瞳をきらめかせ、クラブにいたんだ。
正確に言うと、彼自身のクラブ。
彼の柔らかいカラス色の髪は、男らしい体格と相まって少し乱れていて、グラスを握る指には、失望の色が滲んでいた。彼の低く響く声には、そんな感情が込められていたんだ。
「ああ…なんて魅力的で、寂しい夜なんだろうな」
彼は長い溜息をつき、唇からはニヤリとした笑みが消えない。
彼からはいつも、人を惹きつけるオーラが漂っている。分厚い唇には悪賢い笑みが浮かび、彼は喜びの源を求めて、クラブの中を見回した。
あの悪名高いプレイボーイ。
ロイ・レイン。
25歳の独身男。女たちの心を掴み言葉を操る、あのチャームマンだ。
魅力的な性格で成功を収めたビジネスマンとして有名で、いつも注目の的だった。
その魅力的な容姿もあって、女性に声をかけられるのは日常茶飯事だった。ある女性が近づいてきて、彼の肩に手を置こうとしたときもそうだった。
「ねえ、イケメン」
彼の笑みはさらに深くなり、彼女の手首を掴み、危険なほど青い瞳を彼女の瞳に合わせた。
「君じゃない、ダーリン」
彼女が眉をひそめると、彼は彼女を膝の上に座らせた。荒い息を吐きながら、彼女の耳元で囁き、もう片方の手は彼女の脚を滑るように撫でた。
でも──「君はもっと価値があるんだ、ベイビー。ずっとずっと」
彼は彼女に近づき、彼女の耳たぶを噛みながら、官能的な囁きで彼女は顔を赤くした。
「ほんの一夜や、ほんの少しの時間なんかじゃ足りない。いつでもいいんだよ」
彼は、どんな「獲物」も逃がすことなんてできるわけがないんだ。
彼の魔法に彼女を幻惑させ、ニヤリと笑って、彼は彼女に自分のカードを渡した。彼女は恥ずかしそうに去り、彼は彼女の指の関節にキスをしてウィンクした。
「またね」
手を振って見送ったあと、彼女が視界から消えるやいなや、彼は鼻で笑い、目を転がした。
「ちっ、邪魔だな」
彼は、いつものワンナイトスタンドだけでは物足りない、もっと強烈で止められないものが欲しかった。そして、彼は自分の獲物を見つけたんだ。
彼の視線は、今夜のメインアトラクションに釘付けになった。
ガーネット・ベス。
自分の美しさに気づかない23歳の女性。エメラルドの瞳を持つ彼女は、親友のレスリーと一緒に不安げな様子でクラブに入ってきた。
「レスリー、本当にやめた方がいいと思う。月曜日には就職面接があるんだから」
彼女は茶色の髪を整えながら、唇を固く結んだ。孤児院を出た日に、友達に無理やりパーティーに連れてこられたことに、彼女は不満げだったんだ。
「大丈夫だよ、ガーネット。そんなに気にしちゃだめだって。やっと孤児院を出られたんだから。これはお祝いの時よ!」
レスリーはくすくす笑いながら、彼女をカウンターに押しやり、飲み物を注文した。
「まあ、なんて純粋なんだ」
チャームマンは、自分の飲み物を一気に飲み干し、遠慮がちな女性をじっと見ていた。初めて来たのかな、と思ったんだ。
大音量の音楽と煙が、ガーネットを歓迎した。彼女は匂いを吸い込み、レスリーの方に顔を向けた。そして、その雰囲気に合わせてゆっくりと体を揺らした。
「ノスタルジックだね」
彼女は息を吐き出し、自分を抱きしめ、モクテルのグラスを傾けた。クラブに見慣れているかのように、あたりを見回していたんだ。
「いつも幸せでいてね。私がいるから、あなたの未来は待っているよ、ガーネット」
レスリーはにっこり笑いながら、テキーラを飲み干し、彼女の気分を高めた。
「私の未来、ね?確かにそうだね」
彼女は優雅に笑い、髪の毛を耳にかけながら、2人の会話は聞こえなくても、彼女の優しさを感じ取って魅了された男を惹きつけた。
奇妙な感情が込み上げてくる。
(どうして俺の陽気なクラブで、そんな顔をしてるんだ、女は?)彼は興味を持ち、彼女の動きを目で追ったんだ。
友達はダンスフロアに行き、胸の重りを軽くするために、ガーネットは気分転換することにした。
彼女は手を空に掲げ、ビートに合わせて踊り始めた。軽快に踊り、リズムに合わせていたんだ。
彼女の唇には笑顔が浮かび、目じりには涙が光った。彼女はとても魅力的だと感じた。自由だと感じたんだ。
(レスリーの言う通り、これが私の新しい人生の始まり。楽しむべきだわ)
でも彼女はそれを心にしまいこみ、涙を流しながら踊り続けた。唇は少し震え、過去のあまり輝かしい思い出を必死に心から追い払っていたんだ。
彼女は決意を胸に、涙を頬に光らせながら踊り続けた。
(そうよ、もう誰にも、この人生を奪わせない)
彼は獲物を見つけて、不敵な笑みを浮かべた。しかし、彼女の震える唇を見て、美しい瞳が細められた。
「ん?苦悩?俺のクラブで?」
彼は飲み物を飲み干し、少し酔っていたが、熱狂的な場所で、なぜ誰かが悲しそうにしているのか知りたかったんだ。
彼女に近づくと、彼女の頬に涙が光っているのが見えたんだ。
(やっぱり、俺の気のせいじゃなかった、涙だったんだな)
彼女の姿だけでなく、彼女から発せられる深い悲しみと解放感というオーラにも心を奪われていた。
好奇心から、彼は距離を縮め、近づき、近づき、近づいた。彼女を見下ろすと、彼女は彼に比べて小さく見えたんだ。
(なんて美しい涙なんだろう)
心からそう思い、彼女の頬に手を伸ばし、涙を拭い、彼の美しい低音の声で話しかけた。
「何が君をそんな悲しみに沈ませているんだい?」
彼女は踊るのをやめ、彼を見た。彼女は彼に向かって眉をひそめたんだ。
「え?」
彼女は、自分が泣いていたことに気づき、彼の手が自分の涙を拭いていることに気づいたんだ。彼女は彼の手を振り払い、一歩後ずさった。
「あなたには関係ないわ」
怒ってヒステリックに言いながら、彼女は去ろうとした。しかし、彼の体は自分の意思で反応し、彼女の腕を掴んで彼女を自分の近くに引き寄せたんだ。
彼女は足を止め、彼を睨みつけ、近づかないように警告した。もう彼女は理性を失っていたんだ。
彼女の夜は、すでに思い出によって台無しになっていた。
「構わないで」彼女はつぶやき、視線をそらした。
彼女の腕をひねると、彼女の体は彼の引き締まった胸に突然倒れ込み、彼は彼女の腰をしっかりと抱きしめ、彼女の頬を優しく撫でたので、彼女は息を呑んだ。
「どうして?ベイビー」
「まるで見たことのない、珍しいクリスタルを見たみたいで、興味を持っただけなんだ」彼はいたずらっぽくからかい、挑発的に眉をひそめたんだ。
彼の視線は彼女の唇に止まり、ゾクゾクとしたものが彼女の背筋を走り、2人の呼吸が混ざり合うのを感じた。
彼は、自分が何に魅了されているのか分からなかった。彼女に魅せられていることに気づいたんだ。
「いいえ。私のことには関わらないで」
彼女の柔らかい声と息遣いが、大音量の音楽の中でも聞こえるほど顔を近づけた。
彼女は無意識のうちに彼の黒いシャツを掴み、彼女の大きなエメラルドの瞳は無邪気に揺れ、彼女の心臓は激しく鼓動し、喉が渇いた。
彼の手が彼女の頬に触れたとき、彼女の体は少し緊張し、彼の口元が彼女の耳元に止まったとき、彼女はゴクリと唾を飲み込んだんだ。
彼は挑発的に囁いた。「君が許してくれるなら、それ以上だってできる」
彼の声の低さに、彼女の体は弱り、頭は真っ白になった。
彼が夢中になったのは、彼女が隠している秘密だけだった。
なぜ彼のクラブで涙を流すのか?なぜ彼の前で悲しむのか?なぜそんなに抵抗するのか?
「どうしたの?大丈夫?」
彼女が顔をそむけたので、彼は彼女の顔に近づいたんだ。
「あっちに行って」彼女は弱々しく言った。
彼の視線が彼女の手元に下り、震えが走るのを見て、彼のシャツへの彼女のグリップは強まり、彼女は理性を失いそうになったんだ。
分厚い唇に笑みを浮かべ、彼女の態度、混乱、そして心配が面白かったんだ。
彼から顔を背けて、彼女に近づき、彼女の体に体を押し付けたんだ。
「もしそうじゃなかったら?そんなに多くを求めているわけじゃないよ、ベイビー。少し言葉を交わすくらいで、君の心も軽くなるよ」
タバコの強い匂いがガーネットに届き、彼女は歯を食いしばり、なぜか勇気を感じたんだ。
「言ったでしょ。私がそうする前に、あっちに行って」彼女は息を吐いた。
「好奇心を満たさせてくれ。そんなに多くを求めてるわけじゃないんだ。それに、ここは俺のテリトリーなんだから、オーナーとして、誰かが悲しい顔で帰るのを見過ごすわけにはいかないんだ」
彼は肩をすくめ、後ろに退かず、安心させるために唇をカールさせたが、彼女は今はどんな接触もしたくなかったんだ。
「このクソ野郎から出て行け」
ガーネットは唸り、彼を突き放そうとした。彼は少しもひるまず、ニヤリとした笑みを浮かべ、笑顔に変わったんだ。
支配的な笑みだった。
今夜の彼女は彼の魅力そのもの、つまり、彼女は彼のものになるんだ。
しかし、彼女が強く抵抗しているのを見て、彼はもうどうしようもないことに気づいたんだ。
彼女の試みにため息をつき、ロイは去ろうとしたんだ。もちろん、無理強いはできない。
(なんてがっかりなんだ)彼はそう思い、渋々彼女から手を離そうとしたんだ。
「ふっ、もー」
そして、後で彼女を手に入れる別の手段を見つけるため、彼女が欲しかったし、手に入れるためには何でもするだろうから。
しかし、ガーネットは我慢できなくなり、見知らぬ人を邪魔させないために、彼女がすべきことをしたんだ。
彼女は彼を叩き、彼を遠ざけた。
「消えろ、クソ野郎!」
叫び声を上げると、かなりの注目を集めた。彼は驚いた顔で立ち尽くし、口は開いたままだったんだ。
彼女は彼を睨みつけた。そして、誰もが有名な人が、ただの女の子に平手打ちをされたのを見るために、彼らに注目したんだ。
「すべての女が、あなたに親密さを求めるためのおもちゃだと思ってるんじゃないわ!いったい、自分は何様なのよ!? 地獄に落ちろ、このクズ!」
彼女は叫び、見下すように彼に中指を立てて、彼は呆然と立ち尽くしたんだ。
「あなたみたいなくだらない男に、時間を無駄にするつもりはないわ」彼女は唸り、彼と周りの人たちを驚かせたんだ。
「聞いた?彼女は彼をくだらないって言ったんだよ」
「彼女はこれ、注目を集めるためにやってるの?」
「どうして彼女が彼を叩けるの?」
ささやき声が響き渡り、音楽が止まり、誰もがこの光景をもっと見たがったんだ。
彼女は地面を踏みつけ、怒りながらクラブを後にした。
ロイは、何が起こったのかをまったく理解できず、女性が彼に抵抗することができ、それだけでなく──
彼を平手打ちしたことに、完全に驚いて立っていたんだ。
彼は自分の頬に触れ、彼女の平手打ちの痛みが、彼の脆い男性的なエゴを焼き、皆の前で侮辱された復讐心を掻き立てたんだ。
「よくもまあ…」
彼は息を呑み、誰もがこの平手打ちの復讐を求める強い願望を持って出て行ったんだ。彼は侮辱されたんだから。
復讐ゲームの始まりだ。