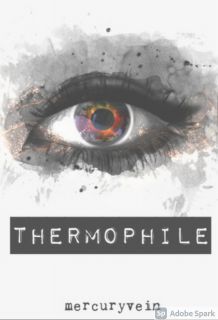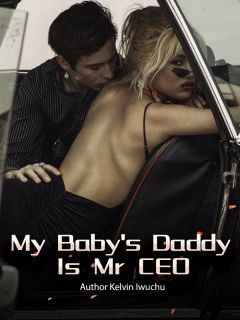電話が来て起きたんだけど、誰からかなって見たら、相手はフェイスだった。フェイスは、私の大大親友。
「おっはー、イザベラ・ソフィア・モーセル!今日はお前の誕生日だよ!」 フェイスが叫んだ。
「うわー、声!まだ早いよ!学校は7時なのに、今はまだ5時46分だよ」 眠そうな声で言った。
「あー、ごめんごめん。でも、ただ誕生日おめでとうって言いたかっただけなんだ。学校でね!大好き!」 そう言って、電話を切られた。あのコ、ちょっと可愛いところあるんだよね。それに、おかげで全然眠れなくなっちゃったから、起きてベッドを整えて、部屋を出た。
「おはよ、お母さん、お父さん!」 二人を見つけたとき、そう言った。
「おはよう、可愛い娘。よく眠れたかい?」 お父さんが尋ねた。「ジョージ、ハニー?」 お母さんが言った。「なんだい、ハニー?」 お父さんが答えた。「今、会議あるの?それとも後から?」 お母さんが尋ねた。「あるよ。君は?」 お父さんが言った。お母さんは頷いた。
二人は私の誕生日を覚えてないみたいで、悲しい気持ちで学校の準備をするためにバスルームに向かった。お風呂から上がって、制服を着た。「お母さん、学校に行ってくるね。運転手のことは気にしないで。バイクで行くから」 そう言って、二人にキスをした。「バイバイ」 二人とも言った。あーあ、誕生日のこと覚えてないんだ。もう慣れちゃったけど。お父さんは会社経営してるから、いつも仕事だし。でも、心から愛してる。私を育ててくれて、優しくて親切な人になるように教えてくれて、私の心を満たしてくれた。兄弟はいないけど、二人の愛情を半分もらえてる気がする。仕事のせいでね。
「ねー、フェイス、学校行ってくるね。またねー」 自分の声を録音して、フェイスに送った。学校に着いて、バイクから降りた途端、私を見た男の子たちがみんな「誕生日おめでとう!」って言って、プレゼントをくれた。優しくしてくれて、誕生日にプレゼントまでくれて、ありがとうって言った。何人かの女の子たちは、二つの眉毛を真ん中に寄せて、私を睨みつけてたけど。でも、どうしようもないよね。小学校の頃からずっとそうなんだから。男の子たちは私に夢中で、女の子たちは嫉妬してるんだよね。でも、フェイスがいつもそばにいてくれるから、その問題は心配してない。
男の子たちがプレゼントを渡し終わったとき、みんなにありがとうって言ったんだけど、フェイスが私に手を振ってるのが見えた。彼女の方に走って行ったんだけど、誰かがわざと私にぶつかってきた。ヒラリーだった。私に対して意地悪な女の子の一人。ヒラリーは私に嫉妬してるだけだって言われてるけど。でも、全然気にしてない。ヒラリーは私を殺すように睨みつけてたけど、フェイスが私を掴んで、そこから連れ出してくれた。
「あー!あのビッチ、大嫌い」 彼女は怒って言った。
私は彼女を落ち着かせて、あのコのことは心配しなくていいって言った。ヒラリーなら私が何とかできるから。彼女は頷いて、一緒に教室に向かって歩き始めた。「ねえ、ソフィア?」後ろから誰かが私に声をかけた。びっくりした。ジョシュだった。私は密かに彼に片思いしてたんだ。彼はあまり話さないんだけど、学校の憧れの的。いつもトップクラスで1位なんだ。今まで話したことなかったのに、人も変わるもんだね。
私は振り返って、フェイスには教室で待っててって言った。
「あ、ジョシュ、どうしたの?」 私は恥ずかしそうに言った。
「あー、ただ誕生日おめでとうって言いたかっただけ。これ、あげるよ」 そう言って、小さな箱を渡された。
「うわー、ありがとう、ジョシュ!」 私は言った。
「どういたしまして。じゃ、また」 そう言って、彼は歩き始めた。彼が去るのを見てたら、私の方をチラッと見て、ウインクしたんだ。そしたら、近くにいた女の子たちが、幽霊でも見たみたいに叫んだ。ほとんどの女の子がジョシュに片思いしてるから、私もその一人。彼は優しくて、ジェントルマンなんだ。そして、他のイケメンみたいに嫌なやつじゃないんだよね。
私は教室を出て、自分たちの教室に向かった。席に座ったら、フェイスが隣に座った。
「それで、ソフィア?お母さんとお父さんは何か計画してるの?盛大なパーティーとか?」 フェイスは私に大きく微笑んだ。彼女の笑顔は知ってるよ。彼女は食べることが大好きだけど、全然太らないんだよね。
「あー、知ってるでしょ、フェイス。私の両親は忙しいから、誕生日でもね」 私は悲しそうに言った。
「でも、おじさんとおばさんはソフィアのこと大好きだよ!」 彼女はそう言って、私は笑顔になったけど、作り笑いだった。どう反応すればいいのか分からないんだよね。誕生日のたびに、豪華なプレゼントはくれるんだけど、私のそばにはいないんだ。いつもメイドさんや運転手さんと一緒に過ごしてる。それはそれで嫌いじゃないけど、誕生日に私と過ごす時間も欲しかったりするんだよね。
「分かった。先生が来たら起こしてね」 私はそう言って、イヤホンをつけた。まだ眠くて、椅子の机に頭をコツンってぶつけちゃった。両親が私を愛してくれてるのか、それとも考えすぎなのか、考えずにはいられなかった。寝ようと目を閉じたけど、先生はもう来てた。
「誕生日の人は誰?」 彼女はそう言ったけど、自分で答えた。「みんな、イザベラ、16歳のお誕生日おめでとう!」 そう言った。何人かの先生は私に親切なんだよね。なんでだろう?お父さんが株主の一人だから?それとも寄付金が一番多いから?それとも、私がいつもトップだから?両親のお金のおかげじゃなくて、成績が良いからだけど。
みんなが私に誕生日おめでとうって言ってくれて、歌を歌ってくれた。私は立ち上がって、みんなが歌い終わったときにお礼を言った。「あなたは女王様よ」 先生が教え始めたとき、フェイスが私に囁いた。私の人生は、まあまあ楽しいけど、両親ともっと一緒に過ごせたらいいのにな。
ガルシア先生は私たちの担任で、平等に接してくれるんだ。今までで一番いい先生。前に、お金が欲しくて私を助けてくれる先生もいたから。でも、お父さんはそういう人じゃないから、教えてもらって何も得られないと、成績を下げられたり、学校から追放されたりするんだよね。お父さんの力で。何人かの子供たちは私を褒めてくれるけど、嬉しくないんだ。彼らは自分たちのことを見下してるけど、私に対してはすごく高い評価をしてくるから、空しか見えないんだよね。みんな親切だけど、意地悪な人もいる。
先生が何を言おうとしてるのか、ちゃんと聞こうとした。科目はちょっと難しいけど、面白いんだよね。科学の授業で、子供の頃は科学と数学が一番嫌いだった。いつも頭痛がしてた。宿題を投げたのを覚えてるんだ。ちゃんと解けなかったから。それに、実験のせいで家を燃やしそうにもなったし。子供の頃のことを思い出して、くすくす笑っちゃった。遊んでばかりで、頑固だったんだよね。笑っちゃったから、みんなが私を見た。
「ごめんなさい、ガルシア先生」 私は言って、頭を下げた。
「集中しなさい、モーセルさん」 彼女はそう言って、科学の話を続けた。
ガルシア先生の話題は、生命の起源についての評価だった。少しは知ってるんだけど、ちゃんと聞いた。科学の時間は終わって、休憩時間の前にもう一つ科目があるんだよね。お腹すいたし、聞くのに集中できない。
数分後、時間になった。私は立ち上がって、フェイスの手を掴んだ。
「痛い」 彼女はそう言って、泣き真似し始めた。
私は彼女を笑って、彼女は私にニヤリとした。「ねえ、ソフィア、やめて」 彼女は言ったけど、私は振り返らなかった。ただ列に並んで、カフェテリアで注文した。彼女も絶対ついてくるから。食べ物を手に入れて、おやつも買った。何人かのカフェテリアのスタッフが、私に誕生日おめでとうって言ってくれた。
彼女たちは、私のすごくいい友達なんだ。私を人間として扱ってくれるんだ。お金のために近づいてくるんじゃなくて、他の人たちと同じようにね。列から出て、フェイスを待った。彼女が私を怒ったように見ているのが見えた。あーもう、大丈夫。これが私たちなりの絆の形なんだ。お互いを愛し合うんじゃなくて、からかい合うんだよね。そして、それが私がフェイスの好きなところなんだ。
食べ終わった後、ゴミをゴミ箱に捨てて、カフェテリアを出た。「ねえ、あそこに猫がいるよ」 フェイスが言って、猫を指差した。ああ、ヴィーナス様、あの猫、めっちゃ可愛いじゃん。欲しい。私たちは猫の方に歩いて行って、持ってた食べ物をあげた。メスかな?「おいで、可愛い子ちゃん、ママのとこにおいで」 私は優しく言った。そしたら、私のところにやってきて、私の頭をスリスリしてきた。あーもう、なんて可愛い猫なんだ。「フェイス」 私はフェイスを呼んで、彼女が誰かを見てるのを見た。誰だか分からないんだけど。
「知ってるよ。あの猫を家に来させたいんでしょ?」 彼女はそう言って、私に微笑んだ。うん、彼女は私を私以上に知ってるんだよね。私は彼女を笑って、彼女も笑った。チャイムが鳴った。「ランチ休憩は終わり」 フェイスはそう言って、私の手を掴んだ。「また来るからね、ちっちゃい猫ちゃん。ママを待っててね、いい子?」 私は猫に悲しそうに言った。フェイスは私のシャツを掴んで引っ張ってきた。その猫は白くて、ちょっと汚れてた。多分、誰も世話をしてないんだろうね。それに、目のところにハートの形があって、それがまた可愛いんだ。
授業が続いて、私が一番嫌いな先生もいたけど、すごく綺麗なんだよね。彼女の名前はパク・キム・ヒョン。彼女はハーフ韓国人で、怒ってると何言ってるか分からない時があるんだよね。それに、私が間違ってないのに間違ってるって言われるんだ。「ねえ、ソフィア、鉛筆借りてくれる?」 フェイスが囁いたけど、パク先生は聞いてて、フェイスが私に話しかけてるのに気づいた。「サンドラ・フェイス・サクソンさん、イザベラ・ソフィア・モーセルさん。私が教えてるの見てなかった?後ろに立ってなさい、行きなさい!」 彼女はそう言って、眉毛を寄せた。私は立って、フェイスも立った。「信じられないわ、あーもう!」 フェイスは言った。二人で笑った。「ねえ、二人とも腕を上げてて、私が先生じゃなくなるまで下げないで」 彼女はそう言って、クラスメートに教え続けた。「ねえ、二人とも腕上げてて、ねー、ねー」 フェイスが真似して、二人でくすくす笑ったから、他の人には聞こえなかった。
何分も経って、終わった。あーもう、腕が死ぬ。もう腕がないみたい。フェイスも腕のことを文句言って、椅子に座った。「ねえ、おじさんとおばさんは何も計画してないって言ってたよね?」 彼女は尋ねて、私は悲しそうに頷いた。「じゃあ、ショッピングモールに行こう。今回は私が奢るから」 彼女は言って、私は彼女に大きく微笑んだ。
「急いで!」 フェイスは、家に帰るようにチャイムが鳴ったときに言った。帰り道で、私はベルを探してたんだ。前に見た猫のこと、私はその猫に名前をつけた。「何を探してるの?」 彼女は私に尋ねた。猫がいなくなっちゃったって言った。探してみたけど、何も見つからなかった。「ソフィア、また明日見れるかもしれないよ」 彼女はそう言って、私を納得させた。そして、駐車場に向かって歩いた。フェイスは車を持ってるんだけど、私が彼女のバイクで送ってあげるって提案してくれた。私は承諾して、彼女は運転手に話した。多分、彼女の車を家に持って帰ってって頼んだんだろうね。私は免許持ってないんだけど、それでもバイクを運転してるんだ。お母さんにはやめろって言われてるのに。「何時?」 フェイスが尋ねた。私は時計を見て、時間を言った。「もう4時だよ」 私は言った。「よし、行こう!」 彼女はそう言って、私のバイクに飛び乗った。私は彼女の後ろについていった。彼女はすごく興奮してた。
「行こー!食べよー!お腹すいたー」 彼女はそう言って、ショッピングモールに着いた。「うっさい、いつもお腹すいてるんだから」 私は言って、彼女はぷーってした。「分かった、奢りなんだからね?」 私はそう言って、彼女は頷いた。彼女は私をバーガーの店に引っ張って、二人分のを買った。それに、ドリンクにも引っ張って、私たちがさっき見たミルキーティーを買おうって言って、私はイエスって言った。私たちは食べてる間、ショッピングモールをぶらぶらしてたら、近くにフォトブースがあった。「写真撮ろう!」 彼女は嬉しそうに言った。私は彼女について行って、中に入った。私たちはポーズ、ポーズ、ポーズして、すごく楽しかった。両親が私の誕生日を覚えてないことなんて、ほとんど忘れちゃってた。こんな最高の親友がいて、本当に感謝してるんだ。だから、彼女をぎゅっと抱きしめて、それが私たちが撮った最後の写真になった。すごく綺麗だった。
「ショッピング行こ」 彼女はそう言って、ブースから出た。「先に食べな。持ってる食べ物と一緒に買い物には行けないから」 私は言った。彼女はまるでフラッシュみたいに、1分で食べ終わっちゃった。「行こ!」 彼女は言って、また私を引っ張った。あーもう、これがフェイスの嫌いなところなんだよね。いつも私を引っ張ったり、連れて行ったり、掴んだり。
「好きなのを選んで。私が払うから」 彼女は言った。「あなたは天使ね」 私は言って、彼女の頬を抓った。彼女が痛がってるのが見えたから、彼女の頬を擦ってた。「あ、ごめん」 私は言って、彼女から逃げ出した。「誕生日だから感謝しなさい」 彼女は言って、自分の服を選び始めた。
私は綺麗だと思ったもの、シンプルで安いものを選んでる。フェイスは金持ちなのに。何にしようか考えてたら、フェイスがまた私を掴んだ。
「これ見て。私たち、相棒!」 彼女は言って、私にクロップド丈のTシャツを渡した。同じ絵柄なんだ。デザインは、親友同士が抱き合ってるやつだった。
「買う?」 彼女はそう言って、私が話す前に、レジに行って買っちゃった。私はフェイスを待ってる間、携帯がポケットで震えた。画面を開いたら、お父さんからのメールが来てた。
「誕生日おめでとう、可愛いね。誕生日のこと忘れてないよ。家に帰って、今夜は一緒にご飯食べよう」 お父さんからのメッセージだった。
「フェイス、行こ?」 私は言った。「どこに?」 彼女は尋ねた。「家に帰ろう。お父さんが、一緒にご飯食べるって。もしよかったらだけど、送っていくよ」 私は言った。彼女は頷いた。
私は携帯を取り出して、お父さんに返信した。「家に帰るよ」 そう返信した。
フェイスを家に送った。「今日はありがとう!」 私は言って、彼女を抱きしめた。「幸せにしてくれた。愛してる!」 私は言った。「ドラマクイーンはお前に似合う!」 彼女は言って、私を置いて行った。あーもう、あのコったら。
私はバイクに飛び乗って、運転し始めた。フェイスの家と私の家はすぐ近くだから、すぐだった。「お母さん、お父さん、ただいま!」 私は叫んだ。「誕生日おめでとう、可愛いね」 お母さんが言って、私を抱きしめた。「誕生日おめでとう、お姫様。もう大きくなったね」 お父さんが言って、お母さんは笑った。お父さんが泣きそうな演技をしてたから。
「やったー!」 私は言って、二人を抱きしめた。「え?」 二人は私を見て、困惑した顔をしてた。「誕生日のたびに、あなたは時間がなかった。いつも仕事してた。疲れてても」 私は言って、私の目からゆっくりと涙がこぼれ落ちた。「今、世界で一番幸せだよ」 私は言った。「ところで、メイドさんと運転手さんは?」 私は尋ねて、二人はお互いを見て、微笑んだ。「私たちは、今日は休みにして、あなたと一緒にいることにしたのよ」 お母さんが説明した。私は衝撃を受けた。
「ありがとう、二人とも、愛してる!」 私は言って、もうすぐ涙があふれ出しそうな気がした。悲しいからじゃなくて。
「着替えてきて。今日はレストランで夕食だから」 お父さんが言った。お父さんはレストランも経営してて、私の名前がついてるんだ。
(イザベラのダイニング)
私はシンプルな赤いドレスを着た。お母さんとお父さんが私に近づいてきて、褒めてくれた。「すごく綺麗だ」 お父さんがお母さんに言った。「うん、そうだね」 お母さんが答えた。「さあ、お姫様、行こうか?」 お父さんが私に尋ねて、腕を差し出した。私はそれを掴んで、お父さんはお母さんのところに行った。「さあ、女王様、行こうか?」 彼はそう言って、私にしたのと同じことをした。
いつもこうだったらいいのに。お母さんとお父さんがいつも私のそばにいてくれるように。
お父さんは車を取りに行って、私たちを乗せてくれた。お母さんは助手席に座って、私は後ろに座った。「ありがとう」 私は言って、二人は微笑んだだけだった。
携帯を開いたら、インスタグラムにたくさんのお祝いメッセージが来てた。フェイスにDMを送って、もう一度ありがとうって言った。そしたら彼女は、「気をつけてね」 って返信してくれた。彼女はツンデレだけど、時々ムラっ気もあるから、私は彼女を操れる。
「着いたよ」 お父さんが言って、私とお母さんのためにドアを開けてくれた。私たちが中に入ると、スタッフのみんなが私とお父さんに挨拶してくれた。私たちは食べたいものを注文した。食事について話してる間、お父さんとお母さんはお互いに囁き合ってた。
「イザベラ」 お父さんが言った。
「はい、お父さん?」 私は言って、困惑して彼を見た。
「そろそろ真実を知る時だよ」 お母さんは言って、またお互いを見つめ合った。何がどうなってるの?すごく混乱してるんだけど。
「何なの、お母さん?」 私は言った。
「あなたは、まだ子供だったとき、私たちの家のドアに置いていかれたの。あなたが今つけてるネックレス、あのネックレスは、あなたを置いていった人からのもので、狼の形をしてて、イザベラ・ソフィアってあなたの名前が書いてあるの。私たちはあなたを育てて、あなたを置いていった人が戻ってくるのを待ってた。でも、誰も来なかった。私たちはあなたを自分の子供として愛してる。私たちはあなたにすべてを与えた。神様が私たちを祝福してくれたんだと思う。子供が欲しいってずっと祈ってたから」 お母さんは言った。
「お母さん、手短に話して、お願い。何言ってるのか分からないわ」 私はゆっくりと言った。心臓がドキドキして、呼吸が苦しくなってきたから。
「あなたは養子なんだ」 お父さんが言った。「私たちは、あなたの本当の両親じゃない」 彼はそう言って、彼の目から涙が流れてるのが見えた。でも、私は自分が知ったことを信じられないんだ。
息ができない。私は走り出して、お父さんが私を追いかけてくるのが見えた。「やめて、お願いだから」 私は言って、彼から逃げた。