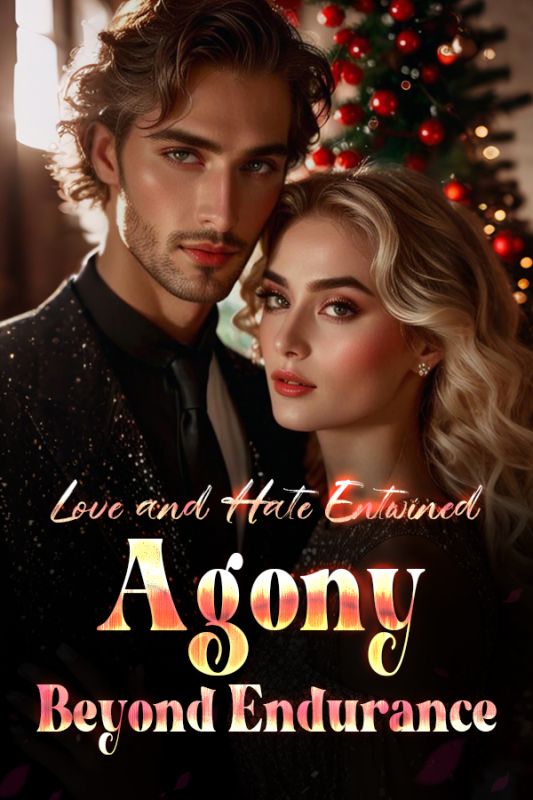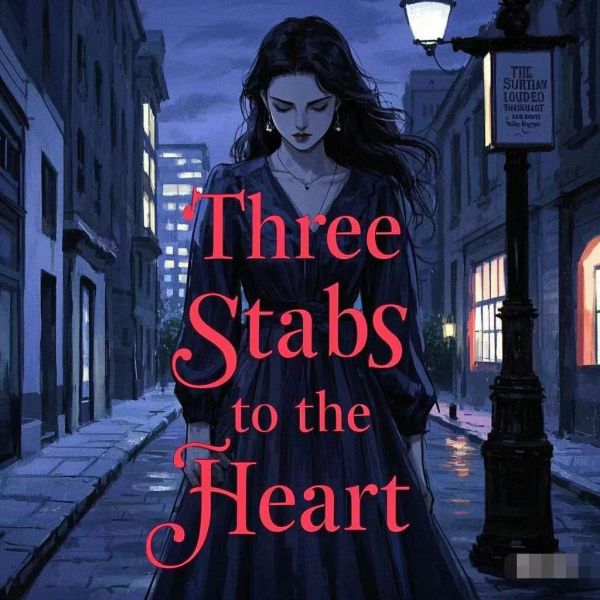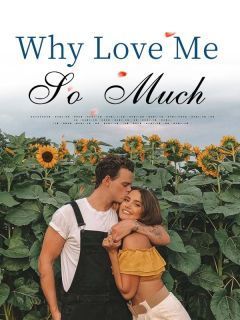「まだ、お腹に赤ちゃんできないの?」
夜が深まる中、ウィルソンは一本線の妊娠検査薬をちらりと見て、顔を険しくした。
「あの…」アンは顔を青ざめさせ、目の前の男を見つめ、澄んだ瞳には懇願の色が浮かんでいた。「もう少しだけ時間をください。きっと、妊娠できると信じています…」
声は悲しみに沈んでいた。
潤んだ瞳が弱々しく彼を見つめ、その中のパニックと懇願がウィルソンをさらに苛立たせた。
彼は妊娠検査薬を投げ捨て、冷笑した。「だったら、今すぐ俺に奉仕しろよ!」
声は冷たく、彼女の骨の髄まで冷気が突き刺さった。
アンは唇を噛み締め、目に浮かぶ悲しみを必死に抑え、「わかりました」と答えた。
彼女は一歩一歩、彼のそばに歩み寄った。
「跪いて、俺のものを吸え!」ウィルソンは彼女を見下ろし、その目に嘲りと嫌悪感を込めた。
彼を怒らせることは、さらなる苦しみをもたらすだけだと知りながら、アンは拳を握りしめ、屈辱に耐えながら震え、彼のベルトの革紐をゆっくりと外した。
そして、ゆっくりと彼のズボンを下ろした。
血色のない唇が震え、やがて目を閉じ、彼に唇を重ねた。
喜びのうめき声が、彼の唇と歯の間から漏れた。
ウィルソンは、深く鋭い眼差しで目の前の女性を嫌悪感で見て、冷たく、温かみのない声で言った。「アン、お前がどれだけセックスに飢えているか、ホール家の娘がいかに恥知らずか、みんなに見せてやれ!」
そう言うと、彼はアンに反応する時間を与えなかった。ウィルソンは彼女を力強く持ち上げ、隣のソファに押し倒した。そして、彼の大きな体が彼女を覆いかぶさった。
彼の情熱的で支配的なキスが彼女に降り注いだ。
「やだ…」アンの目に涙が光り、本能的に抵抗した。
「やだ?妊娠したくないのか?」ウィルソンは冷笑し、彼の目の嫌悪感と嘲笑が彼女の心を突き刺した。
アンは唇を噛み締め、伸ばそうとした手は、力なく横に落ちた。
そう、彼女は妊娠しなければならない。妊娠してこそ、父親の医療費を確保できるのだから…
「ふん、偽善的な女め!」
ウィルソンは冷笑し、そして彼女の体を無慈悲に、強引に貫いた。
アンは天井をぼうっと見つめ、涙が目にたまり、渦巻いているが、頑なに落ちることを拒否した。
10年前、彼女の父親はビジネス戦争でホワイトグループを乗っ取り、ホワイト家を破滅させた。
10年後、無邪気でナイーブな彼女はウィルソンと恋に落ちたが、家に狼を招き入れていたとは予想もしていなかった。結婚3ヶ月後には、ウィルソンはホール家の会社の経営秘密を完全に把握し、電光石火の速さでホール家を破滅させたのだ。
彼女の父親は心臓病が再発し、昏睡状態のまま入院した。
そして、彼女に離婚同意書にサインするよう強要した後、ウィルソンはジェニファーを抱きしめ、去ろうとした。
ホール家は破滅し、愛した恋人に裏切られ、彼女はすべてを失い、バーに悲しみを癒しに行ったが、酔っぱらった後、偶然ジェニファーの車にぶつかり、妊娠3ヶ月だったジェニファーは流産し、彼女は二度と妊娠できなくなった。
ウィルソンはジェニファーを深く愛しており、それはニューヨーク中の誰もが知っていた。
だから、彼女を罰するために、彼は彼女を自分の側に監禁し、昼夜を問わず拷問した。
彼は、彼女がジェニファーの子供を殺したのだから、ジェニファーのために子供を産んで償ってほしいと言った。
そのため、彼は彼女に妊娠合意書にサインするよう強要した。
妊娠すれば、父親の医療費が確保される。この子供を産めば、彼女は去って自由を取り戻せる。
アンは歯を食いしばり、彼の突きに耐えながら、爪を手のひらに食い込ませた。その過程全体は快楽とは程遠く、ただの鈍い痛み、持続する拷問のようだった…
しかし、どんなに痛くても、彼女の心の痛みには及ばなかった…
その後、ウィルソンは服を着て、彼女を振り返ることなく去った。
彼の去りゆく背中をぼうっと見つめながら、アンは体を小さなボールのように丸め、涙がぽたぽたとこぼれ落ちた…
朝。
まるで車の車輪に轢かれたような体で、アンは体を支えながら、一つ一つ服を着ていった。
身支度を済ませた後、アンはキッチンに行き、コーヒーを入れ、卵サンドイッチを作った。
湯気の立つコーヒーを運びながら、アンはそれを食卓に置こうとしていた。その瞬間、「ドーン」という音とともにドアが蹴破られ、ジェニファーが急いでキッチンに入ってきた。
「ジェニファー?」アンは驚いた。
「あら、やっぱりいたのね」ジェニファーは冷笑し、その目に冷たい光がちらついた。
それから、彼女が反応する前に、ジェニファーは彼女の手から熱いコーヒーを無理やり奪い取り、頭に叩きつけた。
「バシャーン—」
「ヒィー—」
沸騰した熱いコーヒーがアンの長い髪に降り注ぎ、髪の毛、顔、さらには襟にまで流れ込み、彼女をひどく汚くした。
焼けるような温度はアンの磁器のように白い顔を赤く腫れさせ、すぐに水ぶくれが皮膚の多くにできた。
「何なの、あなた、気が狂ったの!?」アンは痛みに耐えながら、声が震えた。
そう言いながら、彼女は急いで服を整えたが、顔にはコーヒーがたくさん付いており、少しでも目を開けると、コーヒーが目に入り、目を閉じて盲目的に手探りするしかなかった。
「私が狂ったの?」ジェニファーは冷笑した。「あんたこそ、私を狂わせた女よ!」
「私の子供を殺し、私の妊娠能力を一生奪った。今、ここで快適に暮らして、私の男を誘惑する気!?」ジェニファーは彼女の襟を掴み、汚い顔に近づけ、歯を食いしばって叫んだ。「アン、あんたって、本当にビッチね!」
「違うわ!」アンは震える声で言い、顔の汚れを拭い、目が赤くなった。「ウィルソンは私を無理やり自分の側に縛り付けて、私に代理出産を強要したの!私があなたの家族を破滅させた男と一緒に暮らしたいとでも思ってるの!?」
彼女は深呼吸をして続けた。「ジェニファー、信じられないかもしれないけど、3ヶ月前の車の事故は私がやったんじゃないの」
あの時、彼女は飲みすぎてタクシーに乗ってしまった。その後何が起こったのか覚えていない。
彼女は、事故現場で、タクシーの残骸の中で目を覚ましたことだけを覚えている。
その後、ジェニファーの子供が流産した…
その時、誰もが、彼女がウィルソンへの報復としてジェニファーを殺すために誰かを雇ったのだと思った。
でも、彼女は…
本当に…
アンがそう言い終えた瞬間、「パーン!」—
激しい平手打ちが彼女の小さな顔に強烈に食い込み、アンは星が見え、口角から血がにじんだ。
「このビッチめ、面と向かって嘘をつくなんて!今日こそお前の口を裂いてやる!」ジェニファーの目は血走り、表情は険しく、肩甲骨がわずかに震えていた—アンは、彼女が発作を起こしていることを知っていた。
車の事故以来、ジェニファーは精神的に刺激を受け、時々精神的な崩壊を起こしていた。
彼女の病気が、彼女にアンを無慈悲に傷つける理由を与えていた。
そして、ウィルソンは決して干渉したり、尋ねたりしなかった。
ジェニファーのほとんど狂気に近い様子を見て、アンの心は激しく震えた。ジェニファーが果物ナイフで彼女を刺そうとしたまさにその時—
「やめろ!」
冷たく、不吉な男の声がジェニファーの後ろから聞こえ、革靴が地面を歩く音が遠くから近づいてきた。
アンは顔を上げ、それがウィルソンだと気づいた!
彼はジェニファーにやめろと言ったのか!?
良心を取り戻したのか?
ほんの少しの喜びと期待がアンの心に広がった。
しかし、彼の次の言葉は、彼女の唯一の希望を完全に打ち砕いた。
「ジェニファー、こんなやつで手を汚すな」ウィルソンはジェニファーを抱きしめ、優しく語りかけた。
彼女の心はゴーンと深淵に落ちた。
アンは自分の心臓が血を流す音さえ聞こえた。
とても痛い。
もちろん、彼は彼女を深く憎んでおり、決して彼女を助けようとはしないだろう。
すべては彼女の願望に過ぎなかった。
アンの落胆と苦しみに満ちた表情を見て、ウィルソンは、期待していた復讐の満足感を感じなかった。代わりに、胸に何か詰まっているような気がして、息苦しくなった。
「ウィルソン」ウィルソンの胸に寄りかかりながら、ジェニファーの感情は少し落ち着いた。美しい目から涙が流れ、まるで雨の中の繊細な花のように見えた。「ウィルソン、彼女に代理出産させるのはやめて、いい?私の子供は彼女に殺されたの、私は彼女が嫌なの…」
彼女の声は優しく繊細で、子供のような言葉とあの無力で美しい顔が合わさって、ウィルソンの心を少し痛めた。
「どうして泣いているんだ?」彼は優しく語りかけ、荒い指先でジェニファーの顔の涙を優しく拭い、その目は優しさで満たされていた。「君が彼女を嫌なら、彼女に産ませない。子供のことなら、養子をもらえばいい」
そんな優しい口調、そんな優しい表情、そんな甘やかすような行動は、アンの目を焼き尽くしそうだった。
かつて、彼は彼女にも同じように優しかったのに。
ああ、すべてはまやかしだった。彼の偽善的な優しさは、彼女を偽りの愛情の罠に誘い込み、彼女からより多くの情報を得るための仕掛けに過ぎなかったのだ。
実際、彼女は本当に尋ねたかった。「ウィルソン、あなたは私に対して、ほんの少しでも気持ちがあったりしたの?」
しかし、彼女は自分を辱めたくなかった。答えはすでに明らかだった。
アンが考えにふけっていると、突然、ウィルソンに邪魔され、彼女の足元に書類を投げつけ、冷たく命じた。「サインして、ここから出て行け、今すぐ!」
アンは凍りつき、それからゆっくりとしゃがみこみ、比較的きれいな手でその書類を拾い上げた。その内容を読むと、彼女の心はひどく傷んだ。
彼女は自由のために彼に必死に懇願したが、無駄だった。
しかし今、ジェニファーの一言のおかげで、彼は彼女を手放すことをいとわない。
自由になった今、彼女は笑いたかったが、できなかった。泣きたかったが、目は乾いており、涙一つ見られなかった。
「心配するな、お前はここ数日、よくやった。この100万ドルを慈善事業だと思ってくれ」ウィルソンは冷酷な笑顔で言った。
アンは唇を噛み締め、ゆっくりと目を上げて、かつて深く愛した男を見た。「もし、今サインしたら、私たちは永遠に他人になるのよね?」
これを聞いて、ウィルソンの深い目に2つの炎が燃え上がるように見えた。
彼女は本当にそんなに彼から離れたいのだろうか?
ウィルソンのオーラに冷たさを感じ、ジェニファーは急いで彼の袖を引っ張り、無力な口調で懇願した。「ウィルソン、彼女を行かせてあげて、いい?彼女を見ると頭が痛くなるの…」