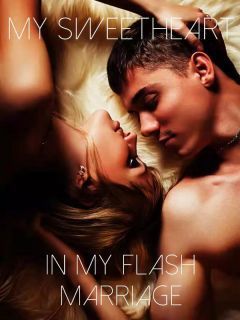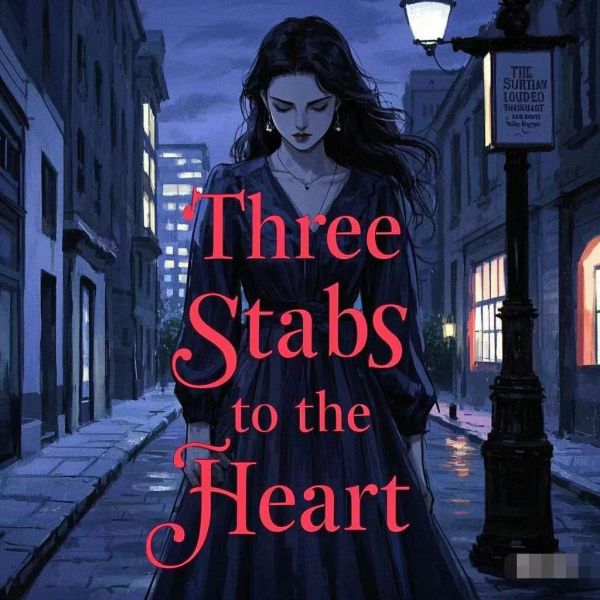私、フックにエプロンをかけて、レストランの中心部で大喧嘩が始まった。ガラスが割れる音と叫び声が空気を満たしている。中に入ろうとすると、ドアにたどり着く前に止まって、何が起きているのか考えた。助けに行くべきだけど、ちょうどタイムカードを切ったところで、つまり、これは、厳密に言うと、今は私の問題じゃない。そんなドラマはもういらないって決めて、肩をすくめて、ロッカーに向かい、バッグを取り出した。すぐにドアが開き、友達のピーターが走って入ってきた。ドアを閉めると、また開くかのように背中を押し当てていた。
「大丈夫?」と私は少し笑いながら尋ねると、彼は私を見上げて胸に手を当てた。息も切らしているみたい!
「あの男が言ったことについて、ある女性はご不満だったってことにしておこう。」彼は、エプロンを脱いで私の隣にかけながら言った。うーん、それだけじゃ全然わかんない。「でも、あいつはすごいよ。子供ができる前に逃げたんだから。」彼はため息をつき、やっと何か教えてくれた。あー、彼氏と別れたんだ、彼女はうまくいかなかったんだな。ここでそんなこと、何度も起こるんだから信じられないよね。
「まあ、全部めちゃくちゃになる前に出てきてよかった。」と私は笑い、ロッカーを閉めた。彼は笑顔で首を振りながら、自分のロッカーを開けた。
私は一人で裏口に向かって歩き始めたけど、すぐに彼がロッカーを閉める音が聞こえ、私と一緒に歩くために走ってきた。彼が私のためにドアを開けてくれたので、私は彼に笑った。
「ジェスが今夜パーティーするんだけど、一緒に行かない?」レストランの裏口を出ると、彼は尋ねた。駐車場に着いたときには、太陽が沈み始めていた。
「わかんないな。だって、まだ週の真ん中だし。」私はため息をつき、まるで老女みたいだってわかってるけど、長い一日だったんだ。一人でシラフで、誰かが変なことをしないように見張っている気にはなれないんだよ、いつもみたいにさ。
「頼むよ、楽しいよ。それに、行かなかったら、すごくダサくない?」彼は笑顔で、自分の車に向かって歩きながら言った。私は自分の車に向かおうとしたが、彼の得意げな顔を見て止まってしまった。
「私に聞くことすらせずに、もう行くって言ったの?」私は自分の車をアンロックして叫んだ。彼は笑い、自分の車のドアを開けた。私は地面を見て、これから口から出る言葉を後悔することになるだろうとわかっていた。「わかったよ。でも、1時間か2時間くらいしかいないから。」私は降参し、鍵で彼を指さした。彼は笑い、バッグを後ろに投げ入れ、自分が勝ったことを知っていた。
「いつもそう言うんだよ!9時に家に行くから!」彼は車に乗り込みながら叫んだ。私は目を回し、彼と職場の迷惑なやつらの仲間入りに同意したことをすぐに後悔した。
どうして簡単に彼に負けちゃうんだろう?ノーって言えたはずなのに!私は優しすぎるんだ、それが時々本当に嫌なんだ。ピーターと私は何年も友達なんだ。卒業した年に、二人とも適当な卒業パーティーに行ったんだけど、その頃はパーティーって本当に楽しかったんだよね。すぐに意気投合して、あとは歴史通り。私はすぐに自分の車を運転して家に帰ったけど、まだこのパーティーの話でイライラしていた。
家に帰ると、お父さんがキッチンで歌っているのが聞こえた。私は笑顔で自分の物を置き、中に入ると、彼はオーブンで食べ物をかき混ぜていた。私はもっと早く引っ越していたかもしれないけど、そうしたら、この大きな家に一人でいることになっちゃうから。お母さんは、あちこち旅行する弁護士で、ほとんど家にいないんだ。彼女は、私の人生の23年間で、多分30回くらいしか家に帰ってない。何年も、お父さんと私だけだったから、彼女が家にいると、すごく変な感じがするんだ。私は近づいて、彼の頬にキスをして、彼が何を作っているのか見下ろした。シチューとかそんな感じだった。
「食べる?」彼は私を見て、彼の作品を少し持ち上げて尋ねると、私は首を振って冷蔵庫に水を取りに行った。
彼は料理上手だし、何を作ってもすごいと思うんだけど、今夜はシチューって気分じゃないんだ。特に、あの迷惑なパーティーに行かなきゃならない前にね、そう、まだ引きずってるんだ。
「いいよ、構わないよ。すごく美味しい材料をいくつか入れたから、伝説になるよ。そろそろ売り始めて、金持ちになろうかな。」彼は奇妙な動きで冗談を言ったので、私はカウンターに座って彼と彼の奇妙な行動を見て笑った。
「まあ、そうなら、絶対に試してみるよ。今夜はいないから、ピーターがどうしてもって、すごく行きたくないパーティーに連れて行かれるんだ。」私はため息をつき、水を一口飲みながら、お父さんがハーブの棚を見ていると、もうシチューに十分なハーブが入っている匂いがした。
「どうしてたまには、あの男にノーって言えないのかわからないけど、まあ、自分の人生を生きてるんだろう。」彼は肩をすくめて、奇妙な緑色のハーブを手に取り、鍋に投げ入れた。彼は、自分が何を入れているのかわかってるのかな?
「うん、まあね。着替えて、降りてきたら、あなたの伝説のシチューを試してみるよ。」私は笑顔で立ち上がり、階段に向かって歩き始めたが、彼がまた歌っているのを見て、笑顔になった。彼はただ音楽なしで楽しそうに踊っていた。
私は首を振り、階段を上って自分の部屋に入り、ドアを閉た。着替えるのに時間はかからず、ジーンズとトップスを着て、部屋のドアを開けると、濃い黒い煙が廊下に充満した。彼は家を燃やしたいのか?
階段に向かうと、外で騒ぎ声が聞こえた、ほとんどが叫び声。隣人たちはいつも喧嘩しているので、あまり気にしなかった。
階段を下りていくと、さらに煙が部屋に充満してきた。なぜ彼はドアや窓を開けようとしなかったんだろう?キッチンの入り口に行くと、彼が作っていたシチューはまだコンロの上にあったが、ほとんど燃えていて、彼はそこにいなかった。私は熱い鍋をつかんで、シンクに投げ込んだ。
「お父さん、家を燃やそうとしてるの?」私は尋ね、蛇口をひねると、鍋がジュージューと音を立て、煙が出た。まあ、それは最良のアイデアではなかったかもしれない。「お父さん、どこにいるの?」私は、皿布を取って火災報知器から煙を払いながら尋ねたが、彼からはまだ返事がなかった。
「お父さん、どこにいるの?伝説のシチューを燃やしてしまったのは知ってるけど、隠れる必要はないよ。ピザでも頼もうよ。」私はキッチンからリビングルームに出てみたが、まだ何もなかった。
キッチンに戻ると、スライドドアが少し開いているのが見えた。お父さんはいつも、あのドアを閉めておくことに妙にこだわっていたから、すぐに私の注意を引いた。
ドアを全部開けて裏庭に出ると、裏門も大きく開いていた。絶対に彼はそんなことはしないはず。裏庭を見回したが、彼の姿はなかった。パニックが私を襲い、彼の名前を呼び始めた。家に戻って自分の部屋に行き、携帯電話を取った。何かおかしい、お父さんはこんなことはしないはずだ。
「お父さん、隠れているところから出てくるのに10秒あげるよ。さもないとお母さんに電話するよ。彼女は緊急事態のときだけ電話しろって言ってたでしょ!」私は叫びながら家の中を歩き回り、見逃したものは何もないか確認したが、スライドドアに戻り、お父さんの姿はなかった。私はお母さんの名前をクリックして、携帯電話を耳に当てた。
「鳴ってる!」私は、彼がクローゼットとかから出てくることを願って叫んだが、彼は出てこなかった。電話が鳴り続ける。
「もしもし。」お母さんの声が電話から聞こえ、私は固まってしまった。まるで、何年も聞いていないような声だ。「アリー、もしもし。」彼女は繰り返すと、やっと私は我に返った。私は家の中を走り回り、彼を探し続けた。
「お父さんがいなくなった。本当に消えちゃったの。ほんの一瞬前にいたのに、もういないの。全部探したけど、見つけられないの。」私は、上着をつかみながら、スライドドアから出て、まだ隠れていないか確認しながら、早口で説明した。でも、心の奥底では、彼は冗談をこんなに長く続けるとは思えなかった。
「どういうこと?お父さんがいなくなったって?」私が裏門に着くと、彼女は尋ねたが、そこにはいなかった。私はパニックになっていて、彼女がそうでないのがむかついた。
「お父さんが階下で夕食を作ってたの。着替えに上がって、降りてきたら、夕食はほとんど燃えてて、彼はいなくて、彼の車はまだ家の後ろに止まってるんだけど、ドアも裏門も開いてたの。」私はさらに説明しながら、門から出て、周りを見回した。彼が私が見える場所にいるわけない。「聞いて、お母さん、彼がいなくなったの。お父さんはこんな人じゃないの。嫌な予感がする。」私はそう言ってると、道路の端でヘッドライトが光り、タイヤの音が聞こえ、数秒で車が私に向かってきた。私は叫んでよけ、地面に倒れた。
「アリー!アリー!アリー!」お母さんが電話から叫んでいるのが聞こえ、私は数フィート先の草の上に横たわっている電話を見上げたが、すべてが暗くなった。
痛みに目覚め、周りを見回すと、ぼやけていたけど、まだ草の上に横たわっているのはわかった。車のヘッドライトが私を眩ませ、数秒後には、人生で一度も会ったことのない人が私のそばにいた。
「アリー、あなたのお母さんと仕事をしてるんだ。あなたを迎えに来るようにって言われたんだ。」彼は説明し始め、私が彼を見上げると、彼は私を立たせようとしたが、うまくできず、彼は私が歩くのを手伝おうとしたが、私はどうしてもできなかった。足がゼリーみたいだった。
彼は私を抱き上げて車に走り、別の人がドアを開け、気がつくと私は後ろに置かれていた。そして、私たちは道路を走っていた。私は見上げると、私の頭は誰かの膝の上にあった。
「お母さん?」私は尋ねると、世界が再び暗くなり始め、気がつくと二度目の気絶をした。