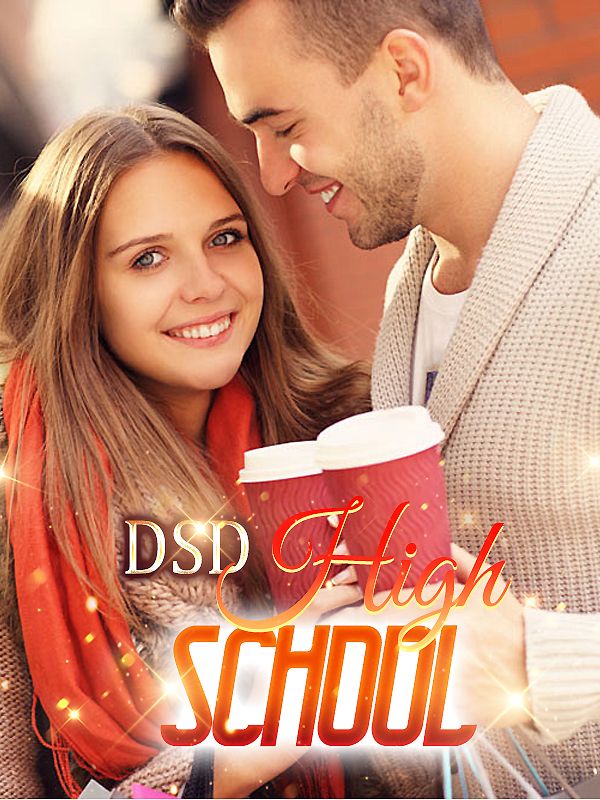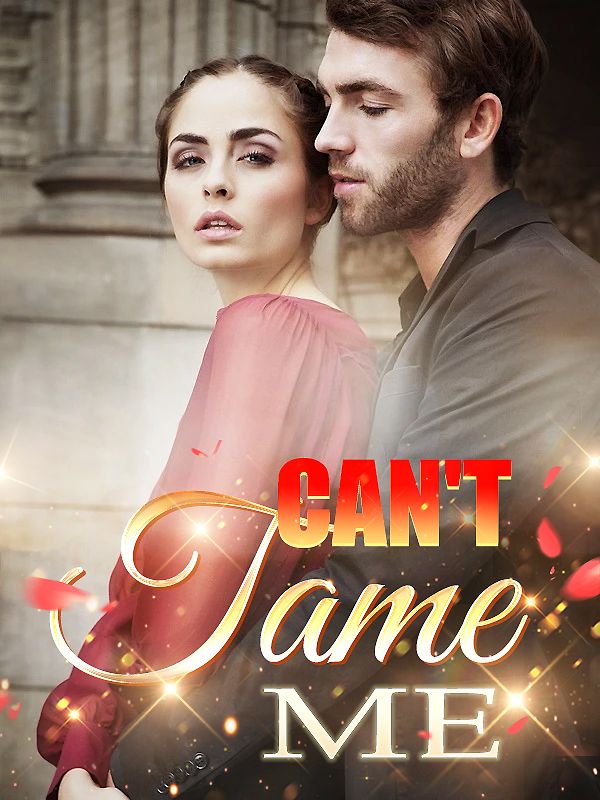レオナルドは生徒たちが静まり返る中、ホワイトボードに何かを書き込んでいた。期末試験が近づき、生徒たちは皆、残りの課題を学ぶことに必死になっていたんだ。最後の大きな見出しの下に、レオナルドは教室を振り返り、熱心な眼差しが彼を見つめているのを見た。
「Si(はい)、何か問題ある?」レオナルドは顔の笑みを隠しながら、生徒たちに尋ねた。期末試験前に、生徒たちがやるべきことがたくさんあることを知っていたからね。ホワイトボードに寄りかかり、腕を組んだ。
生徒たちが何か質問するのを辛抱強く待ったが、いつも通り、彼らは緊張していたので、誰も手を挙げなかった。レオナルドはボードから離れ、自分の席まで歩いて行って座った。
「まあ、みんな理解したみたいだね。僕はみんなに100パーセントを期待しているよ」教室は大騒ぎになり、レオナルドは求めていた笑顔を見せた。
何年も前に、レオナルドは教師になる決意をした。それは、何年も前に父親が彼に望んでいたこととは正反対のことだった。今、高校の生徒たちが、試験問題に何が含まれるかを議論しているのを見て、彼は微笑んだ。恵まれない子供たちの人生に違いをもたらすことができて嬉しいからだ。
椅子から立ち上がって、レオナルドはまだ言い争っているクラスを見回した。
「Per favore(お願い)、座って」彼は彼らに頼むと、指を鳴らすだけで、全員が席に着いた。
「よし、最初から始めよう。質問ある?」レオナルドは生徒たちに尋ねた。彼のアクセントは、彼が育った重厚なイタリア訛りとはかけ離れていた。
教室の隅で小さな手が挙がった。彼女の小さな姿は、彼女の前の席の少年の巨大な体格に埋もれていた。
「はい、ナッティ」レオナルドはナターシャをからかった。ナターシャは顔を覆い、彼がそうするのを見てクスクス笑った。
「ロマーノ先生、私の名前はナターシャです」彼女は彼に思い出させ、レオナルドは彼女に微笑み返した。困難な環境から来た生徒たちの笑顔を見ることは、彼に必要なすべての報酬だったんだ。
手を叩き合わせ、レオナルドはナターシャのテーブルに向かい、彼女の前に立った。レオナルドの背の高い体格はそびえ立ち、すでに緊張しているナターシャを見下ろした。彼は彼女に微笑みかけ、彼女もまた微笑み返した。
「ナッティって呼ぶのはやめるよ。君も僕をロマーノ先生って呼ぶのはやめてくれないか。まるで老いぼれみたいだから」レオナルドは冗談を言った。ナターシャが同意してうなずき、微笑んでいるのを見るだけで十分だった。
「Si(はい)、レオナルド先生」ナターシャは彼の母国語で答えた。これは、生徒たちが彼の母国語であるスペイン語でコミュニケーションをとろうとしていることに、レオナルドを驚かせた。
「何か質問は?」
「先生、次の試験には代数が入りますか?」ナターシャが尋ね、その質問はレオナルドの顔に笑顔をもたらした。彼はゆっくりと踵を返し、自分の席に戻った。
「これまで私たちが取り組んできたことすべてだよ。残念ながら、今回はネタバレはなし」彼は落胆した生徒たちに知らせ、彼らは不平を言った。
「さて、他に質問は?」彼は尋ねると、もう一人の生徒、ジャレッドが手を挙げた。「はい、ジャレッド、私に何を聞きたい?」
「はい、先生、いつロマーノ夫人を見せてくれるんですか?」ジャレッドが尋ねた。他の生徒たちは大笑いし、レオナルドもそうだった。過去数年間、彼が担当したすべてのクラスは、彼を家族の女性と引き合わせたいことを目標としていたんだ。
「その質問をしてくれてありがとう、ジャレッド。数学や次の試験とは関係ないけどね。まあ、僕もロマーノ夫人を探しているところだよ。君の叔母さんがどこかにいるんじゃないかな?」レオナルドはからかい、生徒たちは歓声を上げた。歓声は、学校のベルが鳴り、帰宅時間であることを知らせる音で止まった。
予告もなく、彼らは皆、学校での長い一日の後、家に帰るために急いでカバンを詰め始めた。
「みんな、勉強を忘れないでね。試験は3日後だよ」レオナルドは、全員が走り去るのを呼び止めて、教室の真ん中で立ち止まり、散らばったすべてのページを拾い上げ、微笑んだ。すぐに立ち上がると、レオナルドは凍りつき、微笑んだ。
「こんにちは、レオナルド。そう呼んでもいいですか?」隣の理科の教師、レアが彼に尋ねた。
「大丈夫だよ。実は、ロマーノ先生よりレオナルドって呼ばれるほうが好きなんだ」レオナルドはレアを励まし、彼女は微笑んだ。彼女は彼に向かって歩き、硬いタイルの床にヒールをカツカツ鳴らし、彼の前で止まった。
「あなたは自分の仕事が好きなんですね」レアは彼を褒め、レオナルドは笑顔で答えた。彼はレアを通り過ぎ、床から拾った書類を自分の机に置いた。
「これは仕事とは考えていないんだ。どちらかというと情熱だね。そう!僕は生徒たちに情熱を注いでいるんだ」レオナルドは説明し、レアが彼に近づくのを思いとどまらせたいと思っていた。彼女は、レオナルドが子供たちを教えるのがどれほど好きかをまくしたてるのを見て微笑んだ。
「生徒の話はもういいです。今夜、夕食をご一緒しませんか?」レアはレオナルドに尋ねた。レオナルドは彼女がそう尋ねるだろうと知っていたかのように、優しく微笑んだ。
「申し訳ないけど、お断りしないといけないんだ。残念ながら、家族の集まりに出席しないといけないんだ。週末は家族と過ごすんだよ」レオナルドは残念そうに伝え、レアは落胆したように見えたが、笑顔を浮かべた。
「あら、そう。じゃあ、また今度」彼女は彼の返事を待たずに教室を出て行った。レオナルドは再びため息をついた。彼はレアの形で弾を避けたんだ。彼女は、彼の心をロマンスで奪おうと最善を尽くしていたんだ。
レオナルドはそれを考えて微笑んだ。彼は自分の仕事と生徒のために生きており、その範囲外のことは気にしないんだ。
**
レオナルドはステアリングホイールを握りしめ、「ダラス・テキサスへようこそ」という標識を通り過ぎると、不安感が全身を駆け巡った。家族を愛しているけれど、週末に4時間かけて家族を訪ねることは、レオナルドが後悔していることの一つだった。
両親のダラスに向かう途中、レオナルドは、自分の家族がイタリアとテキサスの両方でどれほど影響力を持っているかを思い出していた。彼の家族は、ほぼすべての店、レストラン、バーを所有しており、彼はそれには一切関わりたくなかったんだ。
レオナルドは育つ上で何も不足することはなかったが、ある日、もっと目的のある人生、一生懸命働き、すべてのお金を稼ぐ人生を求めた。何世代にもわたる家族の富に頼って生きても、彼は何の慰めも感じなかった。
イニシャル「R」が刻まれた黒いビクトリア朝風の鋳鉄製の門の前で車を止め、彼はついに家に帰ってきたのだと悟った。もう後戻りはできない。
時計仕掛けのように、門が開き、レオナルドは大きな鋳鉄製の門を通り抜けた。レオナルドは両親の家に続く長い砂利道を車で走り、両親のトスカーナ風の邸宅の目の前で車を止めた。そして、彼の心は胃の中に沈んだ。車から降りると、この夕食が父親が主催した他のすべての家族の夕食のように、ただの災難になるだろうとわかっていた。
レオナルドは入り口に向かって歩き、ドアをノックする前に、それが開いた。レオナルドは拳を握りしめた。この家のすべてが時計仕掛けのように、計画通りに動いていたんだ。
「こんにちは、ロマーノ様—」
「トニーさん、そんな風に形式ばった名前で呼ばなくてもいいよ。レオナルドで十分だから」彼は執事に割り込み、執事は彼に微笑んだ。
「かしこまりました、レオナルド様。どうぞお入りください」レオナルドは邸宅に入り、いつものように、両親の家の豊かさがすべてを物語っていた。クリスタルシャンデリア、イタリア製のマーブルタイル、オーク材の木製階段から。
「お母様は、夕食はまもなくなので、食堂に向かうようにとおっしゃっていました」トニーがレオナルドに伝えると、彼はうなずいた。何も変わっていないんだ。彼の母親は相変わらず、皆を一つにし、家族の伝統を守りたい伝統的なイタリア人女性だったんだ。
トニーにうなずき、レオナルドは食堂に向かい、一歩踏み出すごとに、家族のメンバーに対処するための勇気を心の中で求めた。
「Mio figlio(私の息子)!」レオナルドの母親が彼に呼びかけ、夕食台を周り、彼に向かって歩いてきて抱きしめた。彼女の短い手はレオナルドの腰を完全に包み込むことができず、つま先立ちになり、彼の頬にキスをした。
「こんにちは、お母さん」レオナルドは母親に挨拶し、彼もまた彼女を抱きしめ、目を閉じた。まるで、先ほど彼がしたように、最後に母親を抱きしめたことを思い出せなかった。
彼の母親は彼を離し、レオナルドの目を見つめると、彼女の目の輝きは、彼が彼女を恋しく思っているのと同じくらい、母親も彼を恋しく思っていることを知るのに十分だったんだ。
「あなたがいなくて寂しかったわ」母親は彼に告げ、その過程で声が震えた。
「僕もだよ、マドレ。でも、今ここにいるよ」彼は母親を安心させ、母親は彼を席に案内した。レオナルドは食堂の椅子に座った。それは、彼の家にある椅子とは全く違うものに感じられたんだ。
両親の家の豊かさは、一般の人々が壮大だと考えるものだったが、レオナルドにとっては、彼の四肢に巻かれた手かせのようなものだった。
「お父さんは?」彼は尋ねた。彼の母親は料理を盛り付けるのをやめ、一瞬立ち止まり、笑顔を浮かべた。
「あなたのお父さんは、ビジネスの話でとても忙しいのよ」彼の母親は彼に答え、すぐにレオナルドに食事を運んだ。
「昨日、ここに来るように電話してきたんだ」レオナルドは母親に言った。
「それで、あなたは父親に頼まれたから来たのであって、ここにいたかったから来たのではないってこと?」彼の母親は彼に尋ね、落胆が彼女の声に満ちた。レオナルドは、自分が母親を動揺させてしまったことに気づき、テーブルの横にカトラリーを落とした。
「お母さん、そう言いたかったんじゃないんだ」彼は説明しようとしたが、彼の母親は彼の方を向こうとせず、一人っ子であることは、母親の幸せが彼に依存していることを意味していたんだ。
「素晴らしい、私の息子が来た!」オナルドは目を閉じ、フォークを握りしめた。父親の声は、彼があまり聞きたい声ではなかったが、母親のために、彼は目を開き、微笑んだ。
「Buon pomeriggio(こんにちは)、パパ」彼は父親に挨拶し、食事を続けた。レオナルドは、父親が椅子を引っ張り出すのを横目で見ると、すぐに彼の食事が運ばれてきた。
彼ら3人は、まるで普通の家族であるかのように、無言で食事をした。完璧な家族像はレオナルドの神経を逆なでし、彼は再びテーブルにカトラリーを置いた。
「父さん、あなたはさっき何か話したいことがあるって電話してきたから、その話を今したいんだ」レオナルドは父親に伝え、彼の声は強く、父親の目をまっすぐに見つめたんだ。