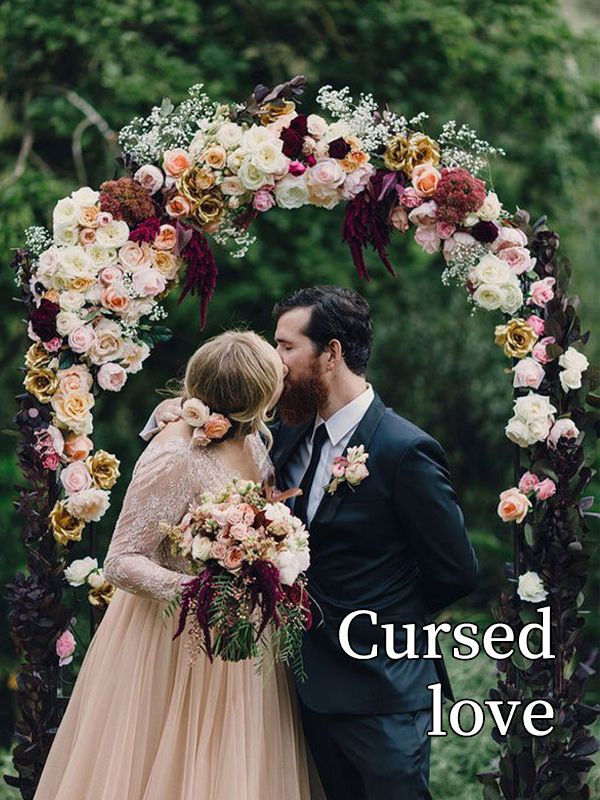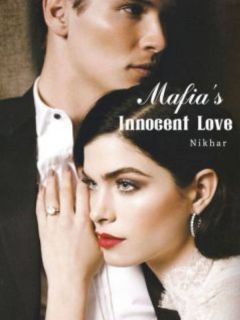あたしの婚約の直前、あたしは超有名なアルファキング、ジャマルをフッて、別の男と逃げたんだよね。
あたしは、彼が記憶をなくしたことをずーっと自分を責めてた。ディープフォレストで彼に殺されそうになるまでは。
ジャマルの記憶喪失が嘘だって分かってから、彼はマジでパニクってた。
あたしに、別の女とイチャイチャするところを見せつけられたし。
あたしは体調悪くて、セキュリティに追い出されたんだよね。
「やめろよ、ヘブン。記憶喪失ごっこはあたしが考えた最後のトリックだよ。」
あたしは彼の前で気絶するまで。
彼があたしの別れの真相を知るまで。
1
空港の入り口で、エジソンとあたしは入ろうとしてた。
赤いポルシェ911が急ブレーキかけた。男が出てくる前に、匂いで誰か分かった。あたしの元婚約者のジャマルだった。
自分で運転してるし、明らかに、このことを知って慌てて来たんだ。
「ヘブン、今なら引き返せば、あたしはなかったことにする!」
あたしも行きたくなかったけど、行かなきゃいけなかったんだ。
あたしが返事をしないのを見て、いつも余裕な顔してたアルファキングが、ついに焦り出した。
そして考えなしに話し始めた。
「もし今日、あいつと一緒に行くなら、二度とアパックには戻れない。お前ら二人に追放を言い渡す!」
あたしは涙をこらえた。
「ジャマル、家に帰って。」
あたしは、行こうと背を向けた。
でも、ジャマルがあたしがあげた香りのネックレス、あたしの匂いがするガラスビーズをちぎった瞬間、あたしの足元に転がって、あたしを引き止めるように見えた。あたし達がかつて持っていた気持ちと一緒に。
彼は顔を赤くして、気づいたら涙が溢れてた。
「ヘブン、最後にもう一度だけチャンスをやる。戻ってこい!」
震える声のトーンからも、彼がすごく怒ってるのが分かった、めっちゃ怒ってる。
あたしは彼に背を向け、二人の間に空気が流れて、彼は冷たく鼻で笑った。
「今日から、お前のことなんか知らなかったことにする!」
2
あたしは、自分の痛みに浸らないように、飛行機から降りてすぐに、おばあちゃんに会いに行くために病院に行った。
エジソンがあたしを掴んで慰めてくれた。「おばあちゃんは大丈夫だよ、心配しないで、ヘブン。」
あたしは彼の手を振り払って、悲しみを怒りに変えたんだ。
「もちろん大丈夫でしょ!」
「もしおばあちゃんに何かあったら、次はアンタが困ることになるわよ!」
エジソンは全部お見通しみたいだった。
「ジャマルがどれだけお前を愛してるか、見てれば分かるよ。」
「彼は、お前を待つかな?」
おばあちゃんの手術は無事終わった。あたしが本当に疲れてたとき、おばあちゃんの世話をしてくれたのはエジソンだった。
同時に、彼はすごく優しくあたしのことも気遣ってくれた。
あたしをジャマルから引き離そうとしたこと以外は、本当に悪いとこなんてないんだよね。
おばあちゃんは順調に回復してて、生活も落ち着いてきた。
あたしがまたジャマルのことを聞くまで。
3
話をしてるうちに、親友がポロっと言っちゃったんだよね。
あたしが海外に行った日に、ジャマルが車の事故にあったって。
空港から家に帰る途中で。
あんなに強いアルファキングでも、車の衝撃には勝てなくて、回復には時間がかかる。
己嫌悪は、深海にできた巨大な渦みたいに、あたしを中に引きずり込んだ。
ジャマルは記憶を失くした。
足に酷い怪我をしてて、立つためのリハビリは、普通のウェアウルフの医者にはほぼ不可能なくらい難しい任務だったんだ。
そのことを知った日、あたしは長い間、ずーっと泣いてた。
結局あたしは、戻ってジャマルと一緒にリハビリのトレーニングをすることにしたんだ。
それは、パックで一番医療スキルが高いあたしの使命だったから。だって、彼はあたしたちの最高のアルファだし、あたしは公私ともに彼の為に戻るべきだと思った。
彼の人生を台無しになんかできない。
あたしは彼を治して、それからきちんと謝って、彼に借りがあるものを返さなきゃ。
エジソンは、あたしを引き止めようとしたけど、最終的には承諾してくれた。
「お前を引き止めることできないのは分かってる。おばあちゃんの世話はあたしがするよ。」
「あたしは、ずっとここで待ってるからな。」
家に戻った日に、あたしは思ってたより事態は単純じゃないって気づいたんだ。
4
あたしの医療スキルは、おばあちゃんから受け継いだものなんだ。
才能って言ってもいいかも。あたしにはこの能力があるし、ジャマルを回復させなきゃ。
月の女神に心の中で誓った。
全部あたしが彼に借りがあるんだ。
ただ、あたしは彼が今のあたしのことを覚えてないってことを忘れてた。
彼のママが、あたしを彼の部屋のドアまで案内してくれた。
去る前に、優しくあたしを慰めてくれた。「ヘブン、彼は記憶喪失だからああなってるの。悲しまないで。」
「でも、あたしはあなたが彼を治せるって信じてるし、きっとうまくいくわ。」
あたしは、ドアを開けて中に入るまで、彼女の言ってる意味が分からなかった。
スタイル抜群の女が、片膝ついて、ジャマルを車椅子に抱きしめてた。
ジャマルの顔には、彼女の口紅の跡。
そこでようやく、あたしはもう彼の婚約者じゃないってことに気づいたんだ。
代わりに、あたしはパックの中で医療スキルが凄い、ちょっと変わったウェアウルフの医者になったんだ。
部屋にいる二人の視線が、あたしに向けられた。
軽く微笑んで、自己紹介するべきだったんだと思う。
あたしは心の痛みを抑えた。
「初めまして、あたしは新しい医者のヘブンです。」
「ジャマルの…」
そう呼ぶのは違うなって思った。「アルファキングのリハビリを担当します。」
車椅子の二人が離れて、彼はあたしに嫌そうな顔をした。
あたしを上から下まで見て。
最後に、ゆっくりとこう言ったんだ。「なんでお前って、こんなにムカつくんだ?」
「お前の口紅の色も、あたしが一番嫌いなやつだ。」
ありえない。
これ、明らかにアンタがあたしにあげた口紅じゃん。
「あはは、アルファ様、冗談ですよね。」
あたしは自分をなだめたんだ。
「誰がお前に冗談を言ってるんだ?」
彼は真剣な顔で、笑いもしない。
「客間は1階にあるから、他に用がなかったら、もう行ってくれ。」
あたりは静まり返った。
あたしがあげた香水は、彼のベッドのところに静かに置かれてた。
部屋の中でも、その香水の奥のほうの蘭の香りがかすかにする。
ただ、彼はもう、それを誰からもらったのか知らないんだと思う。
見慣れた家、見慣れない部屋。
辛い夜だった。
次の日あたしを起こしたのは、目覚まし時計じゃなくて、ジャマルだったんだ。
5
鋭い痛みが、あたしを叩き起こした。
痛みで、あたしは急いでベッドから飛び降りて、痛みの元、あたしの手の甲を見たんだ。
「やっと寝れたか?」
「あたしがお前を寝かせるために雇ったのか?リハビリを手伝ってやろうか?」
あたしたちはウェアウルフだから、すぐに治る能力があるけど、痛みは一緒だ。
つまり、あたしは痛いってことで、それは誰よりもジャマルが知ってることだ。
あたしは、ジャマルがあんなに攻撃的で冷酷な人間だって、今まで知らなかった。
あたしは彼に薬を渡したけど、彼はそれをあたしの足元に、ガラスごと投げつけたんだ。
粉々になったガラスの破片が、今度はあたしの足を狙った。
血が流れ出して、床を赤く染めた。
あたしは痛くて泣き始めた。
ジャマルはただこう言った。「すぐ治るだろ。何泣いてるんだか。」
彼は、今までならこんなことしなかった。
自分の傷を少し手当てしてから、あたしは彼の言うリハビリを手伝い始めたんだ。
最初は、彼はキレてた。
「なんだよ、このクソみたいなトレーニングはよ?やるわけねーだろ!」
「出てけ!」
彼は車椅子に座ったままで、また立ち上がる気はなさそうだった。
あたしはしゃがんで、彼に囁いた。「アルファキング様、最初は何でも難しいものです。もう一度やってみませんか?」
彼は怒ってあたしを突き飛ばして、あたしはバランスを崩してまた膝を打った。
痛い。
「出て行けって言ってるんだよ、分かんねーのか?」
ジャマルは、少しも謝罪せずにあたしを睨みつけた。
あたしはゆっくり立ち上がって、また彼のそばにしゃがんだんだ。
「偉大なるアルファキング様、自分の部下たちに、車椅子でパックを統治するところを見せたいですか?アパックを笑い者にしないでください。」
「生意気にも、あたしにそんなこと言うとは、なんだ、ちょっとした部族の医者か?」
そう、あたしはちょっとした部族の医者なんだ。
「J〜」
優しくて、甘い女の声が耳に届いた。
J?あたしだけだよ、彼をそう呼んでたのは、あたしたちが付き合ってた頃は。
昨日の女だった。
ジャマルは突然笑った。「ネヴァー、また会いに来たのか。」
嬉しすぎて言葉にならないって感じ。
「来なかったら、アンタがちゃんとトレーニングしてるか、分かんないでしょ?」
彼女はそう言って、彼は笑った。
二人は、甘いドラマの中で恋人同士みたいで、あたしは一人、舞台の観客だった。
ネヴァーは彼の前で甘えてた。「ジャマル、医者の言うこと聞いて、もう一回やってみて〜」
「あたしのために。」
彼はすぐに承諾した。
あたしがやったほど大変じゃない。
まだ2日目なのに、全身が痛い。
彼女は、彼の心の中でめっちゃ大事なんだろうな。
ネヴァーが一緒だと、トレーニングはついにスムーズに進んだ。
ただ、彼は疲れたら彼女に抱きしめてもらって、喉が渇いたら彼女に食べさせてもらって、痛かったら彼女に慰めてもらいたい。
いつも、一緒なんだ。
あたしは見てるしかできなかった、ただ見てるだけ。
あの時、あたしは記憶喪失が彼の変装だって知らなかったんだ。
小さな山村から落胆して帰ってくるまで、ついに理解できなかったんだ。