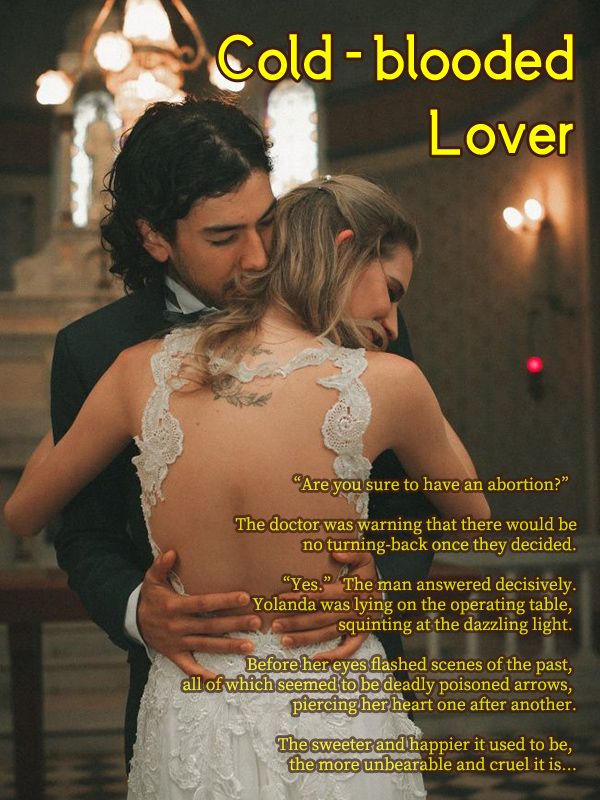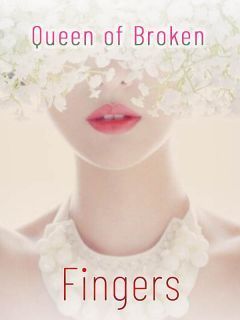「マジかよ」 紳士服を着た男は、向きを変えて、目の前に座る涙を流す女性をじっと見つめた。「31年間も、間違った人を父親だと思ってたなんて」
「クリストファーは、それでもあなたのパパよ。あなたを受け入れて、自分の子供のように愛してくれたわ」 女性はそう言って、声が震えていた。彼女の明らかに高価なシルクのスカーフは、メイクが崩れないように涙を拭くのに役立っていた。
「知ってたのか?」 チャールズは母親に確認され、鼻で笑った。妙なことにいつも座る革張りのソファに座り、髪を後ろに撫でつけた。乾燥が少し気になった。「信じられないよ、隠してたなんて」
「チャールズ」 年齢を感じさせない、豪華な服を着た女性が優しく言った。「正直言うと、できれば、あなたに知られたくなかったの。ロドリゴは、ちょっと、チャールズには悪いけど、ろくでなしなのよ」
「何年も知らずに、ろくでなしだったんだな、ママ」
母親の優しい表情は一瞬で曇った。「そんなこと、自分のことについて言わないで、チャールズ。あなたは素晴らしいお父さんに育てられたのよ。最高のお父さんに」
彼はため息をついた。
彼も、パパと呼んだ男性を愛していた。チャールズは、彼がしてくれたすべてのことに感謝していた。でも、辛かった。長年、間違った人を父親と呼んでいたと知るのは辛かった。
「じゃあ、この手紙が来なかったら、知らなかったってことか」
「本当に来なければよかったのに」 オックスフォード夫人は、まるでそこにいる主の顔のように冷たい表情をしたオフィスでささやいた。
沈黙が支配した。母親は息子の鋭い視線を避けた。息子は、そのごつごつした顔の奥に怒りを隠そうとしているのを知っていたのだろう。チャールズはもう一度母親を見て、決意を込めた。「ロドリゴ・オルディナスに会わなければならない」
母親の頭の変な帽子が、彼の言葉に反応して揺れた。首を振り、目に涙を浮かべながら、彼女は懇願した。「お願い、息子よ、やめて。彼の要求を呑まないで」
「死ぬ前に、本当の父親に会うべきだ」 彼は母親が泣くのを見ることはめったになかったので、彼女の訴えがどれほど真剣なのかわかった。しかし、彼の心は決まっていた。
「でも、彼に会いたいのなら、彼の要求を呑まなければならないのよ」
チャールズは軽く肩をすくめた。「結婚しなきゃいけないんだ、そんなに大変かな?」
「誰とでも結婚できるわけじゃないのよ、それは男にとって最悪のことよ」
「誰かと結婚するって?ママ」 彼は顎の下に手を置いた。「俺は、物事に対して正確な選択をする男だ。妻を選ぶことに関しても、例外は作らない」
「お金のこと?ロドリゴのお金のこと?そんなことしなくてもいいのよ、息子よ。あなたのお父様の帝国は十分すぎるほどよ」
「金のことなんかどうでもいい。ただ、本当の父親に会いたいんだよ、クソ!」 母親がひるむのを見るのは嫌だったが、彼女は感情に目が眩んでいて、それが彼にとってどれほど重要なのか理解できなかった。くそ! 彼は、本当の父親と… 兄弟に会うためなら、千回でも結婚するだろう。
「兄弟もいるんだ。会う権利くらいあるだろ?」
「言いたいのは、彼の要求を呑む必要はないってこと。他の方法もあるから…」
「ママ、あなたは言ったじゃないか。ロドリゴ・オルディナスは、奇妙だけど計算高く、非常に操り上手な男だって。彼が、俺に会うための他のルートをすべて断っているに違いないよ。頼むから、ママ、これ以上難しくしないでくれ。俺は決めたんだ」
「それで、結婚するのね」 子供が結婚すると言ったとき、母親がいつも見せる過剰な笑顔とは対照的に、そのフォーマルな中年女性は顔を曇らせた。
「そうみたいだね」
「気をつけて、チャールズ」 そして彼女は立ち上がり、彼を自分の考えと、寂しげなオフィスに残した。
最近の彼の決断は、彼の計画に変化をもたらした。妻になってくれる女性を探すこととは別に(これはちょっと大変だろう)、本当の父親が長年住んでいるアメリカに引っ越す必要があった。チャールズは、最近発見された家族にもっと近づく必要があった。
ロドリゴ・オルドニズに会うという彼の意図は、母親のように、一部の人々には不必要に見えるかもしれない。しかし、彼は両親がイギリス人なのに、なぜ自分がブラジル人の特徴を持っているのか疑問に思って育った。彼は間違いなく、自分の疑問に対する完全な答えを見つける機会を逃すつもりはなかった。
しかし、条件が付きまとった。結婚するのに十分信頼できる女性を、どこで見つければいいのだろうか?
もし、あの頃に結婚してくれていたら、こんな問題はなかったのに。彼はまだ彼女のことを忘れていなかった。彼女のような顔を持つ女性を忘れるのは難しかった。声はとても魅力的で、すぐに反応してしまう。彼女の体は、正しい場所に完璧な曲線を描いていて、チャールズは彼女の柔らかな肌を撫でているのがほぼ見えた。
しかし、彼女をまだ忘れていないことが、彼を悩ませた。
一体何なんだ、彼女は彼を祭壇で待たせたまま、手紙もなく、跡形もなく姿を消した。彼女は彼を失恋させ、確かに失恋だった、なぜなら彼は彼女を愛していて、彼女もそう思っているはずだと信じる理由がすべてあったからだ。
「チャールズ様?」 秘書の声が彼の思考から彼を引き戻した。
「ケインさん、どうしたんですか?」
「ファイルがテーブルにあります、旦那様」 彼女のシャツのボタンがいくつか外れており、それは彼女が母親の到着を知らせに来たときとは明らかに違っていた。
「契約は…?」 彼は喉を鳴らした。彼女は彼に水を注ごうとした。「ジュビリ・リミテッドとの契約は?」
チャールズは、彼女が挑発的なポーズをとるために体を傾けたとき、彼女の胸のふくらみが見えた。彼はそれを認めざるを得なかった、彼女は自分のゲームを知っていた。ケインさんは間違いなく魅力的で、彼女は決して自慢することを怠らない金色の絹のような髪を持っていた。そして、彼女がいつも自分の体の形を引き出すためにぴったりと着ているオフィスの服。しかし、彼は従業員とのセックスをしないという厳しい方針を持っており、それを破るつもりはなかった。
「はい、旦那様」 彼女の指先が彼の手の甲に触れた。「彼らは、署名済みの契約書のコピーを送ってきました」
「プライベートジェットの準備をしておいてくれ。来週の月曜日には、アメリカに出発する」
「承知いたしました、旦那様」 彼女は非常に有能で、彼は彼女と夜の快楽に浸ることで、それを汚したくなかった。
「それで、まだ署名されていない残りの書類を送ってください。そして、今週中に会議を詰め込むようにしてください。万が一、次の週に会議が入る場合は、アメリカで開催される会議にしてください」
「わかりました、旦那様。以上でよろしいでしょうか?」 彼は秘書を落胆させるように、ぶっきらぼうにうなずいたが、それに気づかなかった。彼は、先に考えていた女性の美しさを再び楽しんでいた。
チャールズはそれをしているのが嫌だったが、まるでイザベラがまだ彼の人生にいて、すぐに部屋に入ってくるかのように、彼女の目には彼への渇望が光っていたため、彼の一部は喜んでいるように感じた。