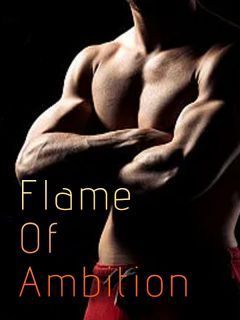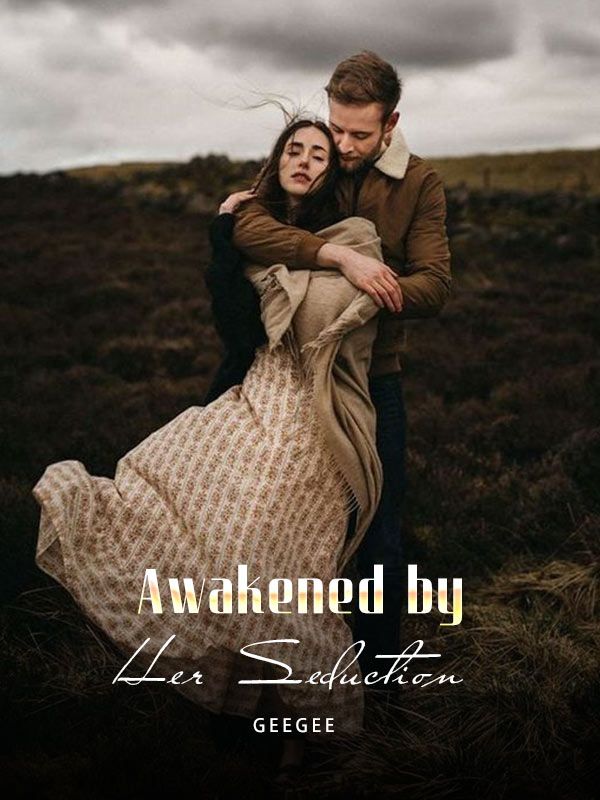プロローグ
4年前
「行かない」
アガタは腕を組んで、友達をきっぱりと見た。彼らは何でも言いたいことを言える。でも、どんな言い合いも彼女を揺るがすことはない。彼女はここに残るんだ—彼らと一緒に。
家族。
「は?ここに残って、デイティに次の妻にされる気?それがお前の望みか?」アロンが尋ねた。
彼女は震えた。誕生日の次の日に、デイティが彼女をオフィスに呼び、大きな発表をしたことを思い出したからだ。彼の彼女を見る視線。飢えの目で。所有欲をむき出しにして。彼女はまだ彼の腕が彼女を掴んだ感触を覚えている。
彼女は自分の腕をちらりと見た。痣ができているような気がしたが、彼の触れ方は彼女の未来を厳しく明らかにしただけで、罰を与えるものではなかった。
「アロン!」ローシンが叱った。彼女は彼とルノーの間に木製の床に座っていた。彼らはみんなツリーハウスに詰め込まれていた。そこは彼らにとって安全な場所だった。
ママがなぜ彼らをここに連れてきたのか、彼女には理解できなかった。でも、アガタが尋ねるたびに、ママは恐ろしい顔をして、この場所は安全だとアガタに言った。
または、デイティがアガタを次の妻にすると発表するまでは。5番目の妻。
吐き気が彼女の胃の中で泡立ち、彼女はそれに手を当てた。デイティとの結婚から抜け出す方法は二つしかない。
去るか、死ぬか。
そして、彼女はどちらもやりたくなかった。
「本当のことだよ、ローシン」アロンは不機嫌そうに言った。彼はいつも真面目で、他の皆を保護している。でも、アガタが16歳になった今、彼はさらにそうだった。
神の子どもたちのすべてが結婚することになっている年齢。
幸運なことに、彼女はカルトのリーダーと結婚することになった。彼らの中で最もイライラする、最も嫌なやつ。
アガタは大きくつばを飲み込んだ。
「行かなきゃ、アガタ」アーニャは優しい声で言った。彼女はルノーとハイメの間に挟まっていて、彼女の小さな体は彼らよりも小さかった。
ローシンが16歳になったらどうなるんだろう?そしてアーニャ?彼は誰をあげるんだろう?アロンとルノーのパパ?アイザックのパパ?
気持ち悪い。
間違ってる。
そして、彼女は彼らを助けなければならない。
「彼と結婚しちゃダメだよ、アガタ」アイザックは静かに言った。彼の目は取り憑かれたように見えた。彼は壁に寄りかかり、落ち着かなく足を叩いていた。「彼はあなたを傷つけるよ」
アガタは大きくつばを飲み込んだ。彼女は彼と結婚したくなかった。でも、彼女は6人全員を置いていくことも嫌だった。
「わかった、行くよ。でも、みんなのために戻ってくるから」彼女は激しく約束した。それが彼女が行く唯一の理由だった。
なぜなら、それが彼ら全員を救う唯一の方法かもしれないから。
「いいね」アロンはきびきびと言った。彼はポケットに手を入れ、いくらかの現金を取り出した。「ほら、みんなで出し合ったんだ」彼はそのお金を渡そうとした。
「え?いや。受け取れないわ」現金は乏しく、キャンプでは手に入れるのが難しかった。彼らが稼いだものはすべてデイティに渡され、彼はそれを使って彼らを世話することになっていた。彼の理由は、彼らを経済的負担から解放し、神を崇拝する時間を増やすということだった。
でも、アガタは、キャンプに住んでいるほとんどの人が必死に働いていて、ほとんど何も持っていないことを知っていた。彼らは食べ物と衣服を与えられたが、それだけだった。
しかし、階級が上の人たちは、より良い特典を得ているようだった。アロンとルノーのパパはセンチネルだったので、彼らは他のほとんどの人たちのような小屋ではなく、実際には家で暮らしていた。
アガタのママはカルトに入ったときもっと年上で、彼女はもう良い子孫とは見なされなかったので、男の一人と結婚する必要はなかった。もちろん、それは、彼らが非常に低い階級にいたことを意味していた。
彼らが住んでいる場所は、ずっと前に非難されるべきだった。
「受け取れるし、受け取るんだ」アロンは命令した。彼はとても横柄だった。
アガタは彼をにらんだ。もし彼女が恋に落ちたら、彼女は気楽な男と恋をするだろう。彼女に何をすべきか言おうとしない男。
彼女が望むときに、彼女が望むことを何でもさせてくれる男。
「それが必要になるよ、アガタ」ルノーは真剣に彼女に言った。彼は疲れているように見えた。まるで世界の重荷が彼の肩にかかっているかのように。これは本当に不公平だった。彼らはティーンエイジャーだった。なぜ彼らはこんなくだらないことを心配しなければならないんだ?
「ここから遠く離れるために使えるんだよ。お母さんは友達がいて、みんなと一緒に泊まれるんだよね?」ローシンが尋ねた。彼女は自分の親指の爪を噛んだ。
「そう。彼女はそう言った。でも、どうやって逃げるの?」彼女は尋ねた。
キャンプは孤立していた。彼らは町まで歩いて行けるかもしれないが、彼らがいないことに人々が気づき始めるまで、どのくらいかかるだろうか?
「心配しないで」アイザックが彼女に言った。「真夜中に気をそらす計画があるんだ。みんなはこっそり逃げる準備をしていて。セントアイブスに行って、そこからバスに乗って逃げよう」
アガタはうなずいた。「まだ戻ってくるよ。みんなを連れ出すつもりだ」
彼らはみんな、希望と悲しみのさまざまな表情で彼女を見つめた。彼女は理解していた。彼らはこの場所での希望を失いつつあった。
でも、彼らが覚えておくべきことは、アガタはヤギよりも頑固だということだった。そして、彼女は決して家族を置き去りにしないということだった。
家族第一。
いつも。
5ヶ月後
「キャンプを襲撃するとき、そこにいる必要があるわ、ママ」アガタは、小さなモーテル部屋を歩き回りながら言い張った。
彼らはキャンプから車でわずか20分だった。彼女はとても近かったが、FBIと一緒に行くことは許可されていなかった。
嫌なやつら。
「エージェント・ゴードンが言ったことを知っているわ、ミハ」彼女の母親は答えた。「私たちは邪魔にならないように、ここにいなければならないの。私たちが行くのは安全じゃない」
アガタは鼻で笑った。「私たちが彼らに場所を襲撃するために必要な情報を提供したのよ。私たちがそうじゃなかったら、彼らはまだ自分たちの尻を追いかけていたでしょう」
「ミハ」ママは警告した。
「何?本当のことよ!そして、みんなは私を必要としているかもしれない。彼らは怖がっているでしょう。ローシンの誕生日まであと数週間よ…もし…もし彼が私を彼女と交換することに決めたら?」
その心配は彼女を夜に眠らせなかった。ローシンは16歳になるのがとても近かった。もしあの嫌なやつが彼女を妻にしたら…