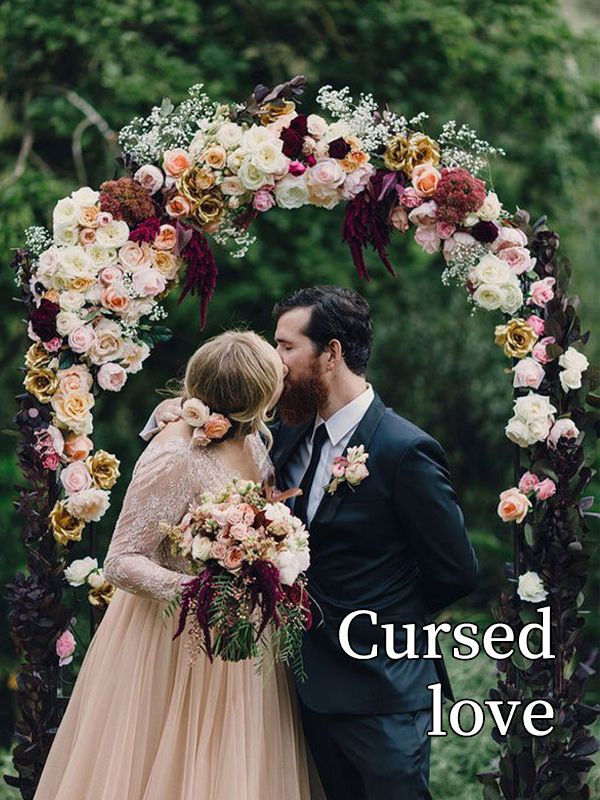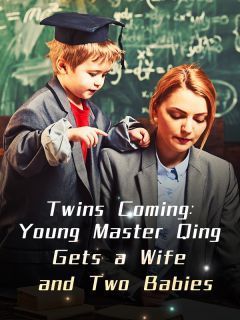紹介
目次
紹介
普通の女の子、ペイトンは、ようやく大人としての生活に慣れてきた。ボーイフレンドとの素敵なアパート、そしてボーイフレンドの厄介な親友。安定した高収入の仕事、すべてがまともな人々の夢。それが、ボーイフレンドが出張に行ってしまい、彼の親友が彼女に助けを求めてくるまでは。
それはそれほど難しいことではなく、上司に良い印象を与えるために、彼のガールフレンドのフリをするだけだった。しかし、彼は、その上司が周囲で最も大きなギャングの一人であるという部分を言い忘れていた。彼女はサメの中に投げ込まれ、このまともな女の子の普通の生活は、普通ではなくなる。
彼女はすべての犯罪の紆余曲折を乗り越えなければならず、自分の居場所がわからなくなる。さらに悪いことに、彼女のふりのボーイフレンドが彼女への自分の気持ちを告白した!
警察、殺人、そして人間関係が彼女の人生をひっくり返す。彼女の物語を追い、恋の代役が本当に何を意味するのかを見つけよう。
もっと読む
すべての章
目次
チャプター2
チャプター3
チャプター4
チャプター5
チャプター6
チャプター7
チャプター8
チャプター9
チャプター11
チャプター12
チャプター15
チャプター16
チャプター17
チャプター18
チャプター19
チャプター20
チャプター22
チャプター24
チャプター25
チャプター26
チャプター27
チャプター28
チャプター29
チャプター31
チャプター33
チャプター34
チャプター35
チャプター37
チャプター40
チャプター41
チャプター43
チャプター44
チャプター45
チャプター46
チャプター47
チャプター48
チャプター50
チャプター51
チャプター52
チャプター53
第54章
第55章
第56章
第59章
第60章
第61章
第63章
第64章
最終章
第21章
第49章
第10章
第39章
第1章
第62章
第58章
第23章
第14章
第30章
第36章
第三十二章
第十三章
第三十八章